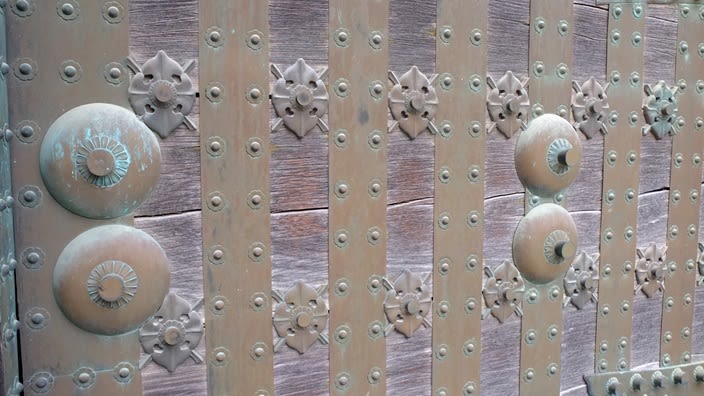土佐 といえば…
鰹 と 千代
土佐の戦国武将と言えば…長曾我部元親
旦那はどーした?
旦那がなんだ
反対から読んだら
やまのうちかずとよ
と 習ったのですが
今は
やまうちかずとよ
武者小路実篤も 自分では 「むしゃこうじ」言ってたようです
そもそも
高知 と言うのが なんで?
明治からよね?
石段を 上がって 右の方にきた所が
杉の段
千代の前から 振り返りますと
三之丸石垣

⇧ ロックオン
かなりの高石垣 色がやけに黒いので
重厚に見えます
ここには 櫓はなかったようで
矢狭間塀がつながってたようです
ここ 平成に 修復
積み直されたという
ちょっと見た目では
気が付きませんでした
同じ位置から

人の居る所から
⇦ 上がってきた石段 三の丸 ⇨
ど~~ん!

⇧ これ どうなんでしょう…
折れちゃったんでしょうが…

危なくないですかね

逆光気味なんで ちょっと補正
あ~ しなくてよかったか…
熊本城風に撮ってみた

のですが…
ダメだこりゃ

うん
いい勾配だ

出角 になっていてるが 櫓台ではなく
横矢掛け のためのようだ
ここから 北 の方になるのかな

三之丸石垣
立派だ
ぐるっと行った所に 🐂🐅櫓跡 ⇨
⇦ 三之丸に上がる 門の方に 行ってみましょ

ここは 算木積み

見事な 角 です
⇩ 三の丸へ上がる 門 石垣の上から 総攻撃される

門の天守側は 何段にもなってる ここからも
総攻撃

新緑が きれいですが
石段が わかりづらい
それでも 見学ルートは整備されていて
🐍
心配は要らない

絶妙に曲がる石段 いいね~
この石段から 見上げる

ここの石段は 守りの要を感じます
絶対 通さない 意気込みの 石垣
その意気込みでも 排水も 手抜かりなし

ほぼ真下 と言うくらいの 段状の 石垣

え~っと まだ 子卯午酉 把握できてません
逆光…東?
ここは 午前攻めが 良かったのか…

さて 門

土台 切り込みです
部材も大きい

門の前は
折坂
門内は
枡形食違虎口折坂
門を目指して攻めてると
後ろは

何でもなさそうだけど
向こうから 鉄砲隊が 今にも出てきそう

不当ピッチ & 躓き段
足元見ずして上り下りはムリです

ここ 何回も
上がったり… 登ったり…