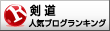四條畷市立四條畷西中学校の体育館。
20時から21時25分まで。今年38回目。参加人数22名。
最初に11月16日、七段を合格されたS山さん(女性)のお話。
まとめれば「自分のペースを崩さず攻め続けた」ということ。
木曜会に稽古に来られて3年か4年だと思うが、
最初の頃は相手を引き入れて打ち取る剣風だったと記憶している。
いまは自分から攻め入って打つ、返す剣風になっている。
気迫がすごいのも良い。剣道に対する取り組み方など見習う点は多い。
小柄な女性で七段合格は素晴らしい。木曜会の指導の成果である。
-----------------
素振り。面着用後、3人組交代で切返し、本日は切返しを多め。
あと、1歩入りの正面打ち、2歩入りの正面打ち、小手打ち。
出頭面の稽古のあと1分半の回り稽古。切返しで終了。
※回り稽古は、イ~チ、イチニの入りを意識した稽古であること。
-----------------
以下、指導の中での留意点のみ書きとめる。
---素振り---
背中が丸まっていては駄目。背中の筋肉を使って素振りをすること。
前半身で降らないように。あごが出ないように。前傾しないように。
竹刀を上げる時は「左手を上げる」感じで振り上げる。
先に剣先を上げるのは無く左手の小指を押し上げる感じで。
---基本稽古---
切返しで、当るか当らないかで竹刀は戻さないこと。
切返しはしっかり打ちきること。(打ちきるが右手で止めない)
切返しは準備運動では無い。
女性は怖さがあるから「自分の間合まで入れない」ことが多い。
女性は気迫気勢がどうしても不足勝ちになる。
これには、一つ攻め、二つ攻め、場合によっては三つ攻め。
一つ目のスイッチは遠間では無い。一足一刀の間である。
遠いと手と足の動きが合わない。前半身で打ってはいけない。
後ろ半身(背中)で打つこと。攻めるが戻れる体勢であること。
スイッチは、早く入れるのか、ゆっくり入れるのか、どう入れるのかは、
相手を良く見て変える必要がある。いろいろ試してみること。
---終礼でのお話---
七段を取った瞬間から七段の剣道になってしまうものだ。
今までやってきた事を信じて挑戦することが大切である。
審査では「落ちることに慣れない事」も大事。
一人目で良かったのに、気が抜けたり、パニくったりしないこと。
合格した時のイメージを持って審査に挑むこと。
「落ちるかも知れないなあ・・」と思っていたら受からない。

(稽古終了)
【感想・反省点】
基本の稽古で「遠くから打ちたい」と「速く打ちたい」が出て、
師匠から「前半身で打ってるよ」と注意された。
これは大反省で、普段の稽古でも夢中になると出てしまう悪いクセである。
スピードは出て当る確立も高いので「それで良し」とクセが固まってしまう。
背筋を使った、より強度と冴えのある打ちを目指すならこれではいけないのだ。
(ふと、尾鷲の岡田さんの背中の筋肉が鍛え抜かれているのを思い出した)