今週末の3月21日(土)、電動車椅子サッカーの大会が神奈川県平塚市で開催されます。国際ルールの10kmで行われる大会には全国から選抜された6つのクラブチームが参加し、例年迫力あるハイレベルな試合が繰り広げられています。面白い試合の連続になることは間違ありません。
(日本の電動車椅子サッカーは、プレー中の電動車椅子の制限速度が10kmと6kmのものがある。10kmは国際ルールに準じており、6kmは国内ローカルルールである)
会場は神奈川県の平塚総合体育館 。
キックオフ時間は12時半~、13時20分~、14時10分~、15時~、決勝は16時~。
お時間のある方は是非どうぞ。
観客席もちゃんとあります。
と書いてはみたものの、もし初めて電動車椅子サッカーを観戦した人はどういったことを思うのでしょうか?
初めて観た人の感想を聞くと、回転キック凄い!ぶつかり合いが迫力ある!みたいなことだったりします。特殊なルールもあってわかりにくい面もありますが、サッカーを含むゴール型のスポーツを見慣れている人であれば入っていけると思います。ボール保持者に対して2名でディフェンスにいってはいけないという2on1(ツーオンワン)というルールがありますが、「なんかそれらしきルールがあるようだ」ということには気が付くと思います。私自身もそうでした。ただセットプレー時のビブスの選手を含めた守り方などはよくわかりませんでしたが。
以前ブログにも書きましたが、私が初めて電動車椅子サッカーを初めて観たのは2006年10月富山での全国大会。その当時は巨大なボールを使用していて速度も6kmのみ。パスと呼べるものはほとんどなく、ラグビーのスクラムかおしくらまんじゅうのようでもあり、はっきり言って“観るスポーツ”としては全然面白くありませんでした。もちろん興行ではありませんし、プレーヤーが楽しければそれでいいわけなんですが。
また“サッカー”ともあまり思えませんでした。
その後20011年7月に久しぶりに観戦する機会があり、まったく別のスポーツかと思えるほど変化していることに驚きました。ボールも小さくなっていて、ルールも変わってパスも回り、まさしくサッカーのように感じました。電動車椅子の速度もその試合は10kmと、スピーディーになっていました。選手で印象に残ったのは「負けてたまるか!」という気持ちが炎のように燃え盛っている(ように見えた)女子選手と、柔らかなボールタッチでサッカー的インテリジェンスを感じさせた鹿児島の選手。しかし電動車椅子サッカーのルールや戦術を把握できていなかったため、例えば東京の選手の良さなどはその時は理解できませんでした。
現在は電動車椅子サッカー専用マシーンとでも呼ぶべきアメリカ製のパワーマシーン“ストライクフォース”が登場しボールスピードも格段に速くなり、トップレベルでプレーするための必需品と化しつつあります。もちろん誰もがストライクフォースを手にすることは出来ないわけで、2極化は避けられない状況となっています。
(2極化というより3極化してもいいのではないかと思っています。10kmと6km、さらにソフトなボールを使い簡易電動車椅子でもできそうな競技の3つです。もちろんステップアップしてもいいし、しなくてもいいと思います)
普及と言う意味で電動車椅子サッカーの裾野の部分はとても重要ですが、第三者に観せる観てもらうものとしてはやはりトップレベルの試合になるでしょう。(この点に関しては他の競技も同様かと思います)。そういった意味ではドリームカップはうってつけですが、やはり電動車椅子サッカーの特殊性を理解するのには多少時間がかかります。私自身もかなり時間を要しました。
「適切なガイド役が最初からいれば理解は早いのに」と思ったりもします。
自分自身が当初わかりにくかった点は、なんといっていいか皮膚感覚とでもいいましょうかプレーヤー感覚がないためにプレーがうまく理解できないといったことでした。例えば11人制サッカーであれば、下手な草サッカー体験をもとにプロサッカー選手のプレーを理解することもできます(理解を超える超絶プレーもありますが)。シュートコースがなかったから切り返してシュートしようとしたなど。
電動車椅子サッカーの場合、そういったプレーヤー感覚が掴めなくてうまく入り込めませんでした。その点は電動車椅子に乗ったり、選手の話を聞いたりすることによって徐々につかめてきました。戦術的なことに関して言うと、選手によって使用している用語がまちまちで、その点はとても分かりにくかったです。ただその点は内部的にも問題があったようで解消されつつあります。
自分の場合は撮影している場合が多く、撮影と競技への理解がなかなか両立できませんでしたが、観戦に徹していれば理解は早いような気もします。
またレベルが上がってくると各々の選手の動きに意図があるわけで、それを観るだけでもワクワクさせてくれる選手もいます。その選手の意図を周りが感じ取れなかったりということもありますが。そのあたりは11人制サッカーも同じですね。
(後半へと続く)

















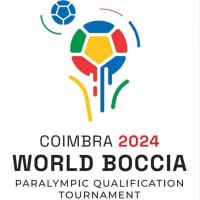

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます