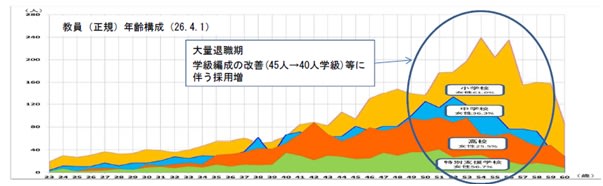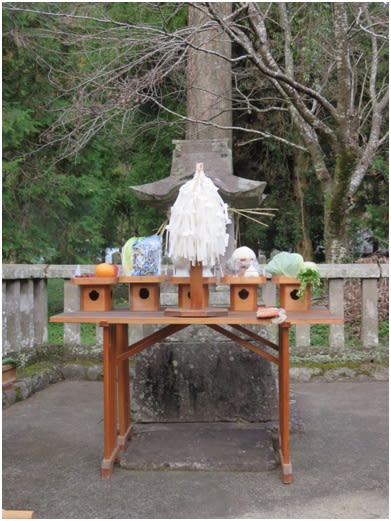今日は、欲のない?銀行員が昼休みやってきました。地域のたくさんの行事に参加しながら、地域になじんでいますが・・・。でもとてもなかよくさせてもらっています。

若いけれど、人とつながりをもてるというところから、学ぶところも多いです。
話は変わりますが、中学校で野球部を担当しているときに、プロ野球の試合観戦に北九州市民球場に部員たちと列車に乗って行きました。その時に、ジャイアンツに中津出身のピッチャーがいました。
そのピッチャーが小野選手でした。
生徒たちは、しきりにグランドを走ったりブルペンで投げている小野選手に声援を送っていました。昨日のことのような思い出ですが、月日が経っています。
その後、小野選手は、引退しました。出身の大学の大学院で経済学を学び会社を立ち上げ、現在に至っています。
震災の被害地である福島県とも関わりを持ち、福島県で初めてのプロ球団「福島ホープス」のゼネラルマネージャーを務めています。多角的に活躍をしている方です。

当時小野投手、つまり小野剛さんの講演会が昨日の夜、「第8回中津教師義塾」の中で行われました。
この会のためだけに帰郷してくれています。
現在、ソフトバンクホークスの監督をしている工藤公康さんとの関わりについて、話を切り出していきました。工藤さんの選手時代、一緒に練習をしたとき驚いたことについてです。工藤さんは、いろんな科学的な練習法を取り入れています。

しかし、一緒に練習をしてもそれを手取り足取り教えるわけでもなく、背中を見れと言わんばかりに、練習を進めていきます。関係性ができてからは、厳しい指摘などがあったそうです。
怒ることで嫌われることを気にしない工藤さん。
しかし、相手を思いやり、相手をレベルアップさせていこうとするとき、時として怒ることも大切ではないかと言います。そこには、情熱、愛情をもって怒ってあげることで、いつかは、相手が感じる時がやってくることを伝えていきました。
小野さんも工藤さんの思いを、教える立場になって感じたそうです。
中津の中学校の軟式野球部という部活動から、日本の中で指折りの強豪校でもある神奈川県の高校に入ります。上には上がいることを痛感します。挫折をしながらも大学に進学。
そして読売ジャイアンツ。会社経営と続きます。

波瀾万丈な人生の中で、自分自身を保ち、活躍をしていることの理由は次のように話しています。
「極端なプラス思考です。失敗しても取り返せばいい。なんとかなる。とにかく有言実行です。」
そのくらいの思いがなければ、小野さんの今はなかったでしょう。
「念ずれば花開く」
「人間は自分が考えているような人間になる」
それを言い続け、自分自身を洗脳してきたそうです。

最後に
「あきらめないことが負けないことにつながる」
「一流になるための一万時間の法則」
を話して終わりました。これで、今年度の8回予定された中津教師義塾が終了。たくさんの方の話や実践を聞くことができ、自分の考えなどを広げる機会をいただきました。感謝の時間となりました。

若いけれど、人とつながりをもてるというところから、学ぶところも多いです。
話は変わりますが、中学校で野球部を担当しているときに、プロ野球の試合観戦に北九州市民球場に部員たちと列車に乗って行きました。その時に、ジャイアンツに中津出身のピッチャーがいました。
そのピッチャーが小野選手でした。
生徒たちは、しきりにグランドを走ったりブルペンで投げている小野選手に声援を送っていました。昨日のことのような思い出ですが、月日が経っています。
その後、小野選手は、引退しました。出身の大学の大学院で経済学を学び会社を立ち上げ、現在に至っています。
震災の被害地である福島県とも関わりを持ち、福島県で初めてのプロ球団「福島ホープス」のゼネラルマネージャーを務めています。多角的に活躍をしている方です。

当時小野投手、つまり小野剛さんの講演会が昨日の夜、「第8回中津教師義塾」の中で行われました。
この会のためだけに帰郷してくれています。
現在、ソフトバンクホークスの監督をしている工藤公康さんとの関わりについて、話を切り出していきました。工藤さんの選手時代、一緒に練習をしたとき驚いたことについてです。工藤さんは、いろんな科学的な練習法を取り入れています。

しかし、一緒に練習をしてもそれを手取り足取り教えるわけでもなく、背中を見れと言わんばかりに、練習を進めていきます。関係性ができてからは、厳しい指摘などがあったそうです。
怒ることで嫌われることを気にしない工藤さん。
しかし、相手を思いやり、相手をレベルアップさせていこうとするとき、時として怒ることも大切ではないかと言います。そこには、情熱、愛情をもって怒ってあげることで、いつかは、相手が感じる時がやってくることを伝えていきました。
小野さんも工藤さんの思いを、教える立場になって感じたそうです。
中津の中学校の軟式野球部という部活動から、日本の中で指折りの強豪校でもある神奈川県の高校に入ります。上には上がいることを痛感します。挫折をしながらも大学に進学。
そして読売ジャイアンツ。会社経営と続きます。

波瀾万丈な人生の中で、自分自身を保ち、活躍をしていることの理由は次のように話しています。
「極端なプラス思考です。失敗しても取り返せばいい。なんとかなる。とにかく有言実行です。」
そのくらいの思いがなければ、小野さんの今はなかったでしょう。
「念ずれば花開く」
「人間は自分が考えているような人間になる」
それを言い続け、自分自身を洗脳してきたそうです。

最後に
「あきらめないことが負けないことにつながる」
「一流になるための一万時間の法則」
を話して終わりました。これで、今年度の8回予定された中津教師義塾が終了。たくさんの方の話や実践を聞くことができ、自分の考えなどを広げる機会をいただきました。感謝の時間となりました。