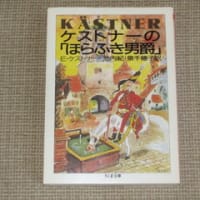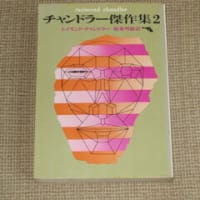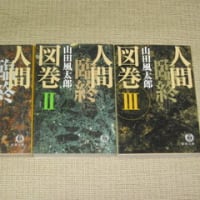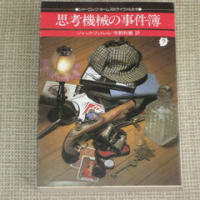丸谷才一 一九八七年 福武書店
これは去年9月の古本まつりで買ったもの、この単行本買ったすぐあとに、文庫本あるのを見つけて、しまった文庫でよかったのに(置くとこないから)と思ったんだが。
評論集ですが、「あとがき」に、
>どうやらわたしは、一方ではわが近代文学が文学を純粋な文学性の枠のなかに入れてゐる慣行に疑惑を感じながら、他方、その延長として、日本文学に限らず文学一般に、古代的なものが意外にまつはりついてゐるのではないかと疑つてゐるらしい。つまり文学だけを相手どつてゐるのでは文学はわからないといふ厄介な消息に逢着してしまつた。
とあるように、そういう文学研究の話であって、「『忠臣藏とは何か』に対する長い長い注のやうな本」と言ってるんで、そっち先に読んだことあってよかったと思った。
本書の第 II 章は、その『忠臣藏とは何か』に対して、浄瑠璃と歌舞伎が専門の国文学者から批判があったので、それに反論したものだったりする。
私はその批判のほう読んでないんだけど、丸谷さんは、「この人は文章を読めないし書けもしないのだなと思ふしかない」とか「知見が足りないだけでなく、物事をいちいち窮屈に考へるといふ癖もわざはひしてゐるらしい」とか、理解に苦しむというかあきれてる感じ。
んー、丸谷さんは、忠臣藏は御霊信仰だとか、悪王綱吉の世で政治的呪術性があったとかって論を張ってんだけど、どうも、どこにそんなこと書いたものあるんだ、みたいに批判してきたんで、そんなこと書いたものあるわけないぢゃない、って答えることになる。
>いはゆる定説なるものは、ここからさきへ行つてはいけないといふ禁止の信号ではなく、われわれはここまで達した、もつとさきへ進んでくれと促したり励ましたりする合図だとわたしは思つてゐる。(p.80)
とか、
>そのときわたしは、解釈力と想像力と思考力を用ゐた。それが文学研究の大道だからである。言ふまでもないことだが、一般に文学研究には想像力が不可欠だし、文献の乏しさによつて制約されてゐる場合にはなほさらだらう。それなのに今の日本では、想像力と仮説とを排撃する風潮が支配的で、しかもそれは、研究者たちの怠慢を正当化する口実に使はれてゐるのである。(p.111)
とかっていうのを読むと、やっぱ私は丸谷さんのほうを支持したくなる。
第I章では、「太平記」と楠木正成の人気の理由の考察から始まって、江戸時代に講釈として人気だったのは、江戸時代は忠を重んじた時代だったからとか、明治になって人気だったのは、王政復古の立役者が明治維新政府にとっても好ましい存在だったからとかってあたりに触れるんだが、話はそんなとこでとどまらず、やっぱ御霊信仰がでてくる。
御霊信仰ってのは、怨みをいだいて死んだ人の霊はたたる、それで災厄をもたらすんだが、その霊を慰めると、霊は機嫌を直して、たたらなくなるどころか、人々を守る存在になる、っていう古くからの信仰。
そんで、
>(略)明治天皇は北朝の血を引いてゐる。北朝の子孫はこれまで、武家によつて政権を奪はれてゐたから、南朝方の亡霊にたたられなくてすんだ。が、今度は違ふ。もう政権を握つたのだから、南朝方はさだめし羨み、かつ怨んでゐるに相違ない。たたりを受ける見込みはかなりある。ここは一つ早手まはしに、彼らの機嫌を取つて置かなければならない。(p.33)
という心理で、明治維新後に、楠木正成とか新田義貞とかに位が遺贈されて、祀る神社が創建された、ってことらしい。
そんな南北朝時代の話だけぢゃなくて、西郷隆盛だってそうだという、反政府だけど反・忠君愛国ぢゃなかったとして人気あって、後年に大赦で位を贈られたのは、やっぱ御霊神扱いなんだと。
>興味深いのは、この年、西郷の銅像が上野公園に、翌々年、正成のそれが馬場先門に建てられたことです。言ふまでもなく、表面は西欧の文物の採用で、次の層には忠臣の顕揚があり、しかし内実は、死霊によつて首都を守護してもらはうといふ信仰であります。(p.38)
ということらしいんだけど、渋谷の忠犬ハチ公の銅像も御霊信仰で、「表面は動物愛護みたいですが、次の層は忠義の鼓吹で、その下には怨霊慰撫があります」(同)とまで言われちゃうと、ホントかいなという気にはなる。
そして、話は文学の研究だけにとどまらなくなるわけで、
>近代日本精神史の特色の一つは、御霊信仰と忠義とが非常に密接に結びついたことでした。
>銅像くらゐだつたら、別に害はありません。社会を乱すことはない。しかし御霊信仰と忠義との結合が妙な具合に昂じると、その感傷的な情感、非合理な思考が、社会を騒がし、文明をさまたげ、国家の運命を誤ることになりました。(p.39)
という具合に、話が大きくなってくる。
>しかし忠君愛国的な御霊信仰は、もつと具体的な面でも国運を誤りました。戦死者を護国の鬼と呼ぶ語法は、近代日本ではごくありふれたものですが、改めてこれを見れば、戦争の犠牲者の霊によつて国を護つてもらふといふ、民俗的信仰の表現であることがわかります。(p.41)
とか、
>日露戦争の戦死者の霊の手前、外国に侵略しなければならないといふ論法ですね。さういふ思考のパターンが透けて見えます。(略)侵略が供物になつてしまつた。これは御霊信仰と帝国主義との合体あるいは癒着でした。(p.42)
とか、言われると、なんだなんだと思うんだが、
>京極純一氏は、昭和十六年(一九四一)の日米交渉の際、その条件の一つである中国大陸からの撤兵について、撤兵しては英霊に申しわけないといふ理由で陸軍が拒否したことに注目してゐますが、これは一国の運命が宗教的感情、あるいはすくなくとも伝統的宗教感情の型へのよりかかりによつて決せられた、重要な一例でした。つまり、日米開戦は御霊信仰のせいだつたのだ、と言つても誤りではないでせう。(p.43)
と、とうとうそんなとこまでたどり着いてしまう、丸谷さんの軍隊嫌いは承知してるけど、軍隊のトップがバカだったとかだけ言うんぢゃなくて、古代の信仰が近現代におよんでるって論を張るのは、読んでおもしろかった。
第 III 章のそれぞれも、読んでると丸谷さんらしい主張があちこちあって、なるほどねえと思わされること多い。
大岡昇平の『事件』は、理想主義的な裁判小説だといって、理想主義ってのは何かっていうと、石川淳に『梅ごよみ』がそうだと教えられたとして、
>あれはつまり徳川時代における理想の生活を描いた長篇小説であつた。もし『梅ごよみ』のさういふ性格が異様に見えるならば、それはわれわれが明治末年以後のリアリズム小説に慣れすぎて、この手の小説の書き方と読み方を忘れてゐるからにすぎない。(p.129)
っていうんだけど、このあたり、深刻ぶってばかりいるのが小説ぢゃないよ、みたいな、いつもの指摘と関連してると思う。
岡野弘彦の新歌集『海のまほろば』について語るとこでも、王朝和歌にくらべて現代短歌にはおおいに不満があって、
>(略)われわれの生きる社会では、西洋十九世紀ふうの写実主義的散文の理念が、おそらく西洋十九世紀に倍するくらゐはびこつてゐるのである。さらに、このことと密接な関係があるが、われわれは西洋十九世紀の圧倒的な影響を受けて、遊戯的なものを否定するやうになつてゐる。この鹿爪らしさの支配、遊び心の欠如は、掛け詞の採用に対し、ほとんど決定的な障壁になつてゐるだらう。(p.178-179)
みたいに言うんだけど、このへんも、これまでに何かで(どこだ?)読んできたことあったような気がする、文学ってのは写実だけが目的ぢゃないのよと。
(十九世紀ころの文学が、真実の追求を主眼にして、祝祭性がうすれちゃった、って話は『闊歩する漱石』のなかか。)
あと、探偵小説について、探偵やスパイに対する嫌悪や軽蔑が基本的にあってこそ、探偵小説が成立するんだって話の前段として、
>近代小説の大事な仕事の一つは、作中人物の魂の底に降りてゆくことによつての人間の研究だが、その場合、嘲笑や憫笑の対象でしかない者の内部に実は一つの宇宙が存在してゐることを示せば、読者の感銘はことのほか深いはずである。それは、読者が漠然として尊敬してゐる作中人物の魂のなかに小宇宙を発見したときよりも、遥かに印象が強いにちがひない。そして近代の作家がしたのはおほむねこの系列のことで、彼らは偉人伝や立志伝の著者ではなく、市井の凡夫凡婦、あるいはいつそ淫夫淫婦の行状記を書きつづけた。(p.194-195)
なんてことを教えてくれるのも、刺激的だったりする。
文学史みたいなことは、こういうことを解説してほしいよね、読んでもつまらんかったで終わらずに、いや結構こういうの書いたのは重要なことだったのよと、気づかせてほしいというか。
ちなみに、この「茨の冠」という一篇は、どっかで読んだことあったような気がすると思ったら、『探偵たちよスパイたちよ』に入ってましたね。
本書のコンテンツは以下のとおり。
I
楠木正成と近代史 (昭和62)
II
お軽と勘平のために (昭和60)
文学の研究とは何か (昭和60)
III
ある裁判小説の読後に (昭和53)
鷗外の狂詩のことなど (昭和53)
白い鳥 (昭和53)
茨の冠 (昭和54)
荻生徂徠と徳川綱吉 (昭和60)

これは去年9月の古本まつりで買ったもの、この単行本買ったすぐあとに、文庫本あるのを見つけて、しまった文庫でよかったのに(置くとこないから)と思ったんだが。
評論集ですが、「あとがき」に、
>どうやらわたしは、一方ではわが近代文学が文学を純粋な文学性の枠のなかに入れてゐる慣行に疑惑を感じながら、他方、その延長として、日本文学に限らず文学一般に、古代的なものが意外にまつはりついてゐるのではないかと疑つてゐるらしい。つまり文学だけを相手どつてゐるのでは文学はわからないといふ厄介な消息に逢着してしまつた。
とあるように、そういう文学研究の話であって、「『忠臣藏とは何か』に対する長い長い注のやうな本」と言ってるんで、そっち先に読んだことあってよかったと思った。
本書の第 II 章は、その『忠臣藏とは何か』に対して、浄瑠璃と歌舞伎が専門の国文学者から批判があったので、それに反論したものだったりする。
私はその批判のほう読んでないんだけど、丸谷さんは、「この人は文章を読めないし書けもしないのだなと思ふしかない」とか「知見が足りないだけでなく、物事をいちいち窮屈に考へるといふ癖もわざはひしてゐるらしい」とか、理解に苦しむというかあきれてる感じ。
んー、丸谷さんは、忠臣藏は御霊信仰だとか、悪王綱吉の世で政治的呪術性があったとかって論を張ってんだけど、どうも、どこにそんなこと書いたものあるんだ、みたいに批判してきたんで、そんなこと書いたものあるわけないぢゃない、って答えることになる。
>いはゆる定説なるものは、ここからさきへ行つてはいけないといふ禁止の信号ではなく、われわれはここまで達した、もつとさきへ進んでくれと促したり励ましたりする合図だとわたしは思つてゐる。(p.80)
とか、
>そのときわたしは、解釈力と想像力と思考力を用ゐた。それが文学研究の大道だからである。言ふまでもないことだが、一般に文学研究には想像力が不可欠だし、文献の乏しさによつて制約されてゐる場合にはなほさらだらう。それなのに今の日本では、想像力と仮説とを排撃する風潮が支配的で、しかもそれは、研究者たちの怠慢を正当化する口実に使はれてゐるのである。(p.111)
とかっていうのを読むと、やっぱ私は丸谷さんのほうを支持したくなる。
第I章では、「太平記」と楠木正成の人気の理由の考察から始まって、江戸時代に講釈として人気だったのは、江戸時代は忠を重んじた時代だったからとか、明治になって人気だったのは、王政復古の立役者が明治維新政府にとっても好ましい存在だったからとかってあたりに触れるんだが、話はそんなとこでとどまらず、やっぱ御霊信仰がでてくる。
御霊信仰ってのは、怨みをいだいて死んだ人の霊はたたる、それで災厄をもたらすんだが、その霊を慰めると、霊は機嫌を直して、たたらなくなるどころか、人々を守る存在になる、っていう古くからの信仰。
そんで、
>(略)明治天皇は北朝の血を引いてゐる。北朝の子孫はこれまで、武家によつて政権を奪はれてゐたから、南朝方の亡霊にたたられなくてすんだ。が、今度は違ふ。もう政権を握つたのだから、南朝方はさだめし羨み、かつ怨んでゐるに相違ない。たたりを受ける見込みはかなりある。ここは一つ早手まはしに、彼らの機嫌を取つて置かなければならない。(p.33)
という心理で、明治維新後に、楠木正成とか新田義貞とかに位が遺贈されて、祀る神社が創建された、ってことらしい。
そんな南北朝時代の話だけぢゃなくて、西郷隆盛だってそうだという、反政府だけど反・忠君愛国ぢゃなかったとして人気あって、後年に大赦で位を贈られたのは、やっぱ御霊神扱いなんだと。
>興味深いのは、この年、西郷の銅像が上野公園に、翌々年、正成のそれが馬場先門に建てられたことです。言ふまでもなく、表面は西欧の文物の採用で、次の層には忠臣の顕揚があり、しかし内実は、死霊によつて首都を守護してもらはうといふ信仰であります。(p.38)
ということらしいんだけど、渋谷の忠犬ハチ公の銅像も御霊信仰で、「表面は動物愛護みたいですが、次の層は忠義の鼓吹で、その下には怨霊慰撫があります」(同)とまで言われちゃうと、ホントかいなという気にはなる。
そして、話は文学の研究だけにとどまらなくなるわけで、
>近代日本精神史の特色の一つは、御霊信仰と忠義とが非常に密接に結びついたことでした。
>銅像くらゐだつたら、別に害はありません。社会を乱すことはない。しかし御霊信仰と忠義との結合が妙な具合に昂じると、その感傷的な情感、非合理な思考が、社会を騒がし、文明をさまたげ、国家の運命を誤ることになりました。(p.39)
という具合に、話が大きくなってくる。
>しかし忠君愛国的な御霊信仰は、もつと具体的な面でも国運を誤りました。戦死者を護国の鬼と呼ぶ語法は、近代日本ではごくありふれたものですが、改めてこれを見れば、戦争の犠牲者の霊によつて国を護つてもらふといふ、民俗的信仰の表現であることがわかります。(p.41)
とか、
>日露戦争の戦死者の霊の手前、外国に侵略しなければならないといふ論法ですね。さういふ思考のパターンが透けて見えます。(略)侵略が供物になつてしまつた。これは御霊信仰と帝国主義との合体あるいは癒着でした。(p.42)
とか、言われると、なんだなんだと思うんだが、
>京極純一氏は、昭和十六年(一九四一)の日米交渉の際、その条件の一つである中国大陸からの撤兵について、撤兵しては英霊に申しわけないといふ理由で陸軍が拒否したことに注目してゐますが、これは一国の運命が宗教的感情、あるいはすくなくとも伝統的宗教感情の型へのよりかかりによつて決せられた、重要な一例でした。つまり、日米開戦は御霊信仰のせいだつたのだ、と言つても誤りではないでせう。(p.43)
と、とうとうそんなとこまでたどり着いてしまう、丸谷さんの軍隊嫌いは承知してるけど、軍隊のトップがバカだったとかだけ言うんぢゃなくて、古代の信仰が近現代におよんでるって論を張るのは、読んでおもしろかった。
第 III 章のそれぞれも、読んでると丸谷さんらしい主張があちこちあって、なるほどねえと思わされること多い。
大岡昇平の『事件』は、理想主義的な裁判小説だといって、理想主義ってのは何かっていうと、石川淳に『梅ごよみ』がそうだと教えられたとして、
>あれはつまり徳川時代における理想の生活を描いた長篇小説であつた。もし『梅ごよみ』のさういふ性格が異様に見えるならば、それはわれわれが明治末年以後のリアリズム小説に慣れすぎて、この手の小説の書き方と読み方を忘れてゐるからにすぎない。(p.129)
っていうんだけど、このあたり、深刻ぶってばかりいるのが小説ぢゃないよ、みたいな、いつもの指摘と関連してると思う。
岡野弘彦の新歌集『海のまほろば』について語るとこでも、王朝和歌にくらべて現代短歌にはおおいに不満があって、
>(略)われわれの生きる社会では、西洋十九世紀ふうの写実主義的散文の理念が、おそらく西洋十九世紀に倍するくらゐはびこつてゐるのである。さらに、このことと密接な関係があるが、われわれは西洋十九世紀の圧倒的な影響を受けて、遊戯的なものを否定するやうになつてゐる。この鹿爪らしさの支配、遊び心の欠如は、掛け詞の採用に対し、ほとんど決定的な障壁になつてゐるだらう。(p.178-179)
みたいに言うんだけど、このへんも、これまでに何かで(どこだ?)読んできたことあったような気がする、文学ってのは写実だけが目的ぢゃないのよと。
(十九世紀ころの文学が、真実の追求を主眼にして、祝祭性がうすれちゃった、って話は『闊歩する漱石』のなかか。)
あと、探偵小説について、探偵やスパイに対する嫌悪や軽蔑が基本的にあってこそ、探偵小説が成立するんだって話の前段として、
>近代小説の大事な仕事の一つは、作中人物の魂の底に降りてゆくことによつての人間の研究だが、その場合、嘲笑や憫笑の対象でしかない者の内部に実は一つの宇宙が存在してゐることを示せば、読者の感銘はことのほか深いはずである。それは、読者が漠然として尊敬してゐる作中人物の魂のなかに小宇宙を発見したときよりも、遥かに印象が強いにちがひない。そして近代の作家がしたのはおほむねこの系列のことで、彼らは偉人伝や立志伝の著者ではなく、市井の凡夫凡婦、あるいはいつそ淫夫淫婦の行状記を書きつづけた。(p.194-195)
なんてことを教えてくれるのも、刺激的だったりする。
文学史みたいなことは、こういうことを解説してほしいよね、読んでもつまらんかったで終わらずに、いや結構こういうの書いたのは重要なことだったのよと、気づかせてほしいというか。
ちなみに、この「茨の冠」という一篇は、どっかで読んだことあったような気がすると思ったら、『探偵たちよスパイたちよ』に入ってましたね。
本書のコンテンツは以下のとおり。
I
楠木正成と近代史 (昭和62)
II
お軽と勘平のために (昭和60)
文学の研究とは何か (昭和60)
III
ある裁判小説の読後に (昭和53)
鷗外の狂詩のことなど (昭和53)
白い鳥 (昭和53)
茨の冠 (昭和54)
荻生徂徠と徳川綱吉 (昭和60)