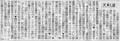昨年、メインのPCがダウンして、バックアップしなかった資料が無くなりました。
その一つが、肺と声帯の模型の動画です。肺から空気を送り、声帯を振動させるデモです。声帯は、ゴム風船を切り出し、声帯の長さくらいの2枚を突き合わせます。肺は2つの円筒の間の空気を、一定の圧力で送り出します。水圧で10センチくらいの圧力で、音が出ます。声をだすときの、肺の圧力と大体同じです。
世界で、似たような模型を作った人はいません。教育に使いましたが、現役を退くときに、音響学会のポスターセッションで発表しました。
その結果、ポスター賞を受賞しました。普通、この賞は若手がもらうのですが・・
10何年ぶりに、声帯を張り直して動画を撮りました。動画は、https://www.facebook.com/suzuki.jouji にあります。