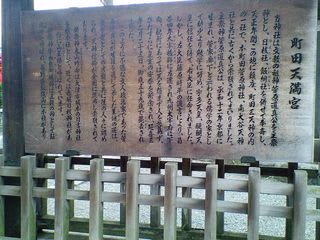1月30日、惣善寺の次は、数分で、勝行院です。
惣善寺から脇に行くと勝行院の三重の塔が見えて、ここかと思うと入り口が見つからないで一苦労。

山の下側に入るところはありました。
巽門です。これで、中に入れると安心。

山門です。額を見ると三福山の山号があります。

工事中が残念。
本堂です。

本堂右脇には釈迦堂があります。この釈迦堂は1520年に建てられたそうです。先の惣善寺は、この辺で下の寺、こちらは中の寺と呼ばれているそうです。

三重の塔です。1988年建立です。

三重の塔は境内左奥。そして右側からの出入りは乾門です。

こちらのお寺は真言宗。広い境内に様々な建物が並ぶ古刹です。新しい建物が多くとも、信仰の雰囲気があります。
惣善寺から脇に行くと勝行院の三重の塔が見えて、ここかと思うと入り口が見つからないで一苦労。

山の下側に入るところはありました。
巽門です。これで、中に入れると安心。

山門です。額を見ると三福山の山号があります。

工事中が残念。
本堂です。

本堂右脇には釈迦堂があります。この釈迦堂は1520年に建てられたそうです。先の惣善寺は、この辺で下の寺、こちらは中の寺と呼ばれているそうです。

三重の塔です。1988年建立です。

三重の塔は境内左奥。そして右側からの出入りは乾門です。

こちらのお寺は真言宗。広い境内に様々な建物が並ぶ古刹です。新しい建物が多くとも、信仰の雰囲気があります。