
先日のお稽古の中で、茶杓の銘に「げげ」とおっしゃった方が
「げげ」って何でしょうとお聞きすると
茶道手帳に『解夏』(げげ)とありましたと、
夏が解けるとは、素敵な比喩ですが、
音で聞くと「げげ」とはなんか耳ざわり
でも『夏解ける』っていいですね。
夏の暑さから解放されるという事ですかね。

そこで『解夏』とは何ぞやと調べてみますと
仏教の僧が夏に行う安居という修行が終わる時をいう。
対語は結夏(修行が始まる時)。
因みに『解夏』(げげ)は、2002年に刊行されたさだまさし著の
短編小説集、またその表題作でもありました。
表題作「解夏」は2004年に映画化、テレビドラマ化もされており、
その中で失明を告知をされた主人公が、故郷で出会った老人から
「解夏とは、失明する恐怖と闘うあなたにとって、
失明すると同時にその恐怖から解放される日」
であると言葉をもらい・・・・心の自由を得る?
ウイキペディアからの一部引用でありますが
『解夏』にはこんなに深い意味がありましたね。
茶杓の銘として『解夏』を選びお勉強してくださった○○さんに
感謝、呉音の『げげ』という響きも好きになりました。
このお菓子の銘は『解夏』にいたしましょう。



















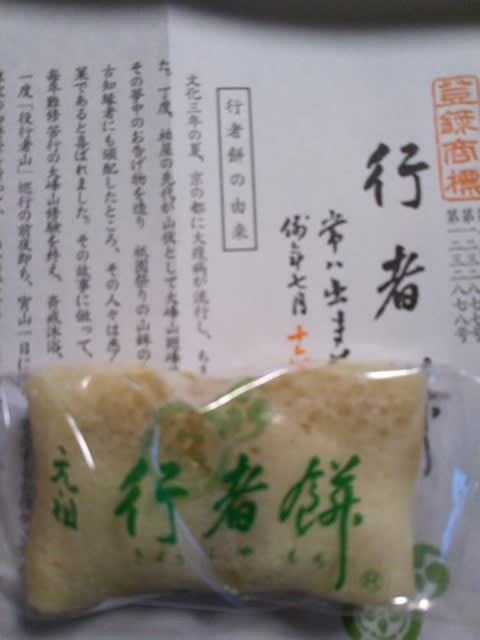










 今日は、五月晴れ、嘉祥の日(和菓子の日)です。
今日は、五月晴れ、嘉祥の日(和菓子の日)です。










