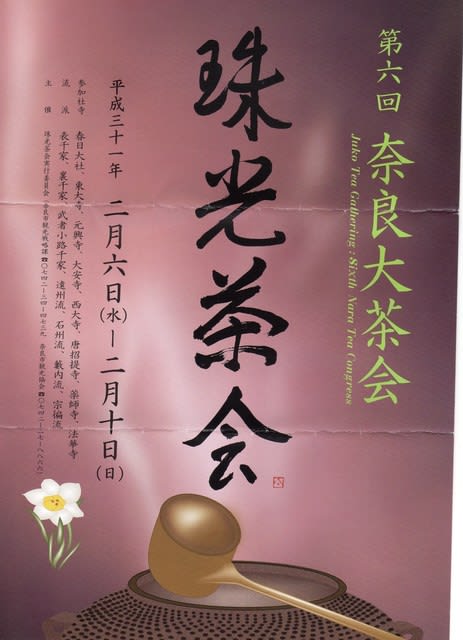今年の四月は、桜が咲き始めてから寒い日が続き
花見はゆっくり楽しめていいなと思いきや
雷、雨、風、霰、所によっては雹まで降り
大荒れの日が終わったと思ったら
最高29℃と夏のような日もあり
椿、利休梅はあっという間に終わり、藤は満開、シャガも咲きだし
黒ロウバイ、タツナミ草も蕾をつけ いっぺんに開花です
そんな四月に七年ぶりに
茶飯釜の茶事ができました。
昨日からの雨が上がり
暑くもなく寒くもないさわやかな
世間はお花見で大賑わいの日に・・・
お客様が揃えば下火6本(丸ぎっちょ3本、割ぎっちょ3本)
米3合分の水を入れたヌレ釜をかけ
(ご飯が吹きこぼれて炉中を汚してはいけませんので3合までに)

汲み出しは桜湯「お白湯お召し上がりの上腰掛待合へ」

迎えつけ、席入り ご挨拶と進み
茶飯釜では席中では香をたかず、床は香合荘りに

初炭が始まります
いつもの炭との違いは半ぎっちょ2本点炭2本と余分に
炭斗にいれ、丸管、割管、枝炭は炉につぎません


いよいよ洗い米投入

洗い米を入れた釜をかけ
火吹き竹でお客様にも助けてもらって
美味しいご飯が炊けますようにと
めいいっぱい火を熾します

炭の具合が落ち着いてきましたら
香合の拝見、香合は「釣り鐘」
道成寺の釣り鐘、春爛漫『入相桜』を
想像していただければと

お膳を運び 「どうぞお箸のお取り上げを」
飯椀は蓋だけ、汁椀にはからしを落とし
ご飯が炊けるまで、まずは向付で一献

煮物椀(利休卵豆腐にこごみと人参の桜を散らして)も出して
杯を進めながらごはんの炊けるのを待ちます

ご飯のいい香りが

ご飯が炊けたら 釜を上げて、金色(汁)をかけ

まずは炊き立てのご飯を頂いてもらいましょう

汁も温まればまわします
金色を上げたら炊き合わせの鍋を
汁は蓬麩、桜麩、湯葉
炊き合わせは筍、ワラビ、蕗、わかめ、木の芽

おひつに取った蒸らしたごはんをまわし
焼き物は剣先いか

預け鉢はうるい、オカヒジキ、貝柱のからし酢味噌.和え

亭主相伴
鉢などを引き、小吸い(姫皮と山椒の花)を

八寸はホタルイカとタラの芽

正客の「どうぞご納杯を」
「お湯おねがいいたします」
湯斗・香の物

膳を引く
菓子は「柳緑花紅金団」

「お菓子お召し上がりの上、席を改めとうございますので中立を」
「ご用意が整いましたら お鳴り物で」
「ことによりましては」と中立ち
軸を上げ、花入れを掛け、湯、炭を見て
花はかろうじて残っていた金漁葉椿と鶯神楽

茶入れを置いて銅鑼を「大 小 中中 大」
後席は続き薄茶で
ご飯が無事に炊けるかどうか心配しましたが
後入りに続く事ができ
お客様にはとっても喜んでいただけました
米を釜に入れる音から始まり
火吹き竹を手に自慢の肺活量を試し
ぐつぐつごはんが炊ける音、香り
おこげのできる音、香り
宗徳釜が、お鍋が揺れる風を感じ
目で見て、手に取り、音を聴いて、香りを嗅いて
ご飯一つで楽しめるのが最高!茶飯釜ならではです
又、来年もできたらいいですね