タイマーでシャッターが上ると寝室に朝日が射し込み、雨で
空気中のゴミが除かれたのか透明度の高い青空が見えました。
でもまた大陸から黄砂が襲来が・・・出かける時はマスクを。
暑くなりそうな一日がはじまりました。

 9時
9時
この季節の定番の自宅稽古での菓子は、在原業平が伊勢物語
九段で詠んだの歌から『唐衣』か『燕子花』になり、
5月13日まで公開されていた根津美術館所蔵の
国宝『燕子花図屏風』が有名、でも私は大和文華館所蔵の
『伊勢物語八橋図』岡田為恭を思い出します。
 伊勢物語八橋図
伊勢物語八橋図 
毎年のこと朝から稽古場の準備で忙しい中、紫芋を含む二種類
の練りきりに、黄身餡を足していたが、
この『燕子花』置き忘れ!そこまで手が回らなくなったのかな
でも一個一個心を込めましたよ。


漢字では「燕子花」と「杜若」と表され、
語源由来辞典によると
”カキツバタは、古くは「カキツハタ」と清音であった。
語源は、花汁を摺って衣に染めるための染料であったため
「カキツケハナ(搔付花)」「カキツケバタ(書付花)」の説
が通説、ただし音変化として考え難いため、語源は未詳。
漢字の「杜若」「燕子花」は漢名の借用だが、中国で「杜若」
はツユクサ科のヤブミョウガを指し「燕子花」はキンポウゲ科
ヒエンゾウ属の植物を指す。”と(一部改変)
皆様どちらの漢字を用いられますか、それともカタカナだけ。
空気中のゴミが除かれたのか透明度の高い青空が見えました。
でもまた大陸から黄砂が襲来が・・・出かける時はマスクを。
暑くなりそうな一日がはじまりました。

 9時
9時この季節の定番の自宅稽古での菓子は、在原業平が伊勢物語
九段で詠んだの歌から『唐衣』か『燕子花』になり、
5月13日まで公開されていた根津美術館所蔵の
国宝『燕子花図屏風』が有名、でも私は大和文華館所蔵の
『伊勢物語八橋図』岡田為恭を思い出します。
 伊勢物語八橋図
伊勢物語八橋図 
毎年のこと朝から稽古場の準備で忙しい中、紫芋を含む二種類
の練りきりに、黄身餡を足していたが、
この『燕子花』置き忘れ!そこまで手が回らなくなったのかな
でも一個一個心を込めましたよ。


漢字では「燕子花」と「杜若」と表され、
語源由来辞典によると
”カキツバタは、古くは「カキツハタ」と清音であった。
語源は、花汁を摺って衣に染めるための染料であったため
「カキツケハナ(搔付花)」「カキツケバタ(書付花)」の説
が通説、ただし音変化として考え難いため、語源は未詳。
漢字の「杜若」「燕子花」は漢名の借用だが、中国で「杜若」
はツユクサ科のヤブミョウガを指し「燕子花」はキンポウゲ科
ヒエンゾウ属の植物を指す。”と(一部改変)
皆様どちらの漢字を用いられますか、それともカタカナだけ。
























 になってほしいもの。
になってほしいもの。 



























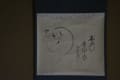






















 ”と記された義理チョコ、
”と記された義理チョコ、













