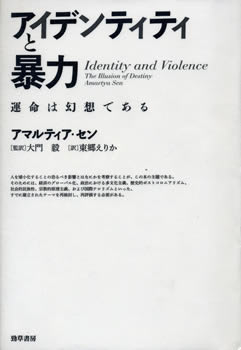
知識人という言葉はいまや使いにくい言葉の一つだが、この本は知識人の書と評するのが私にはいちばんしっくりする。もちろん哲学の書ではないし、思想の書とも呼びにくい。そして、読書後には、アマルティア・センは無色で透明な位置に立とうと志している、と思ったのである。
本書で語られていることは、きわめて明快だ。世界に蔓延する国家的、民族的、宗教的暴力を克服するためには、個人におけるアイデンティティ構成の多重性(複数性)を認め、その個人のアイデンティティ選択の自由を認めることが必要だ、という主張である。
同一性(アイデンティティ)の共有意識は、単に誇りや喜びの源となるだけでなく、力や自信の源にもなるアイデンティティという考えが、汝の隣人を愛せといったお決まりのうたい文句から社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)や共同体主義(コミュニタリアニズム)の自己認識の高尚な理論にいたるまで、幅広くもてはやされていることは驚くに値しない。
だが、アイデンティティは人を殺すこともできる。しかも、容易にである。一つの集団への強い――そして排他的な――帰属意識は往々にして、その他の集団は隔たりのある異なった存在だという感覚をともなう。仲間内の団結心は、集団相互の不和をあおりやすい。 (p. 17)
そして、単一のアイデンティティの共有がもたらす不幸な(不正義な,と言ってもいい)事例は後を絶たない。「住民が一致団結して……よく融和したコミュニティが、よそから移り住んできた移民の家の窓には嫌がらせのために煉瓦を投げ込むコミュニティ」 (p. 18) に容易に変容する。
多数の人びとを単一基準のアイデンティティ幻想に追い込むことによってさらにいっそう深刻な暴力、集団殺戮に至るような暴力に発展する事例がかつて数えきれないほどあり、現在も数えきれないほど起こり続けている。アーリア民族とユダヤ人、セルビア人とモスレム、フツ族とツチ族、シーア派とスンニ派、セルビア人とモスレム、イラク人(トルコ人)とクルド人、シンハラ人とタミル人、ミャンマーの仏教徒とモスレム、イラク・アブグレイブ刑務所におけるアメリカ兵・軍属とイラク人、などなど数え上げればキリがないほど暴力の根源としての単一基準アイデンティティの問題が挙げられる。
そのような現実を強く憂慮するアマルティア・センの思考は、自らの出自における強烈な経験と、アイデンティティに関する自己認識のありようという二重の始点から出発する。
私は一九四〇年代の分離政策と結びついたヒンドゥー・ムスリム間の暴動を経験した子供のころの記憶から、一月にはごく普通の人間だった人びとが、七月には情け容赦ないヒンドゥー教徒と好戦的なイスラム教徒に変貌していった変わり身の速さが忘れられない。殺戮を指揮する者たちに率いられた民衆の手で、何十万もの人びとが殺された。民衆は「わが同胞」のために、それ以外の人びとを殺したのだ。暴力は、テロの達人たちが掲げる好戦的な単一基準のアイデンティティを、だまされやすい人びとに押しつけることによって助長される。 (p. 17)
私はアジア人であるのと同時に、インド国民でもあり、バングラデシュの祖先をもつベンガル人でもあり、アメリカもしくはイギリスの居住者でもあり、経済学者でもあれば、哲学もかじっているし、物書きで、サンスクリット研究者で、世俗主義と民主主義の熱心な信奉者であり、男であり、フェミニストでもあり、異性愛者だが同性愛者の権利は擁護しており、非宗教的な生活を送っているがヒンドゥーの家系出身で、バラモンではなく、来世は信じていない(質問された場合に備えて言えば、「前世」も信じていない)。これは私が同時に属しているさまざまなカテゴリーのほんの一部にすぎず、状況しだいで私を動かし、引き込む帰属カテゴリーは、もちろんこれ以外にもたくさんある。 (p. 39)
やっかいなことは,野心や政治的意図によって単一基準アイデンティティに人びとを縛りつけてしまう考え方やその実践家ばかりではないことだ。多くの人びとは、なにか揺るぎない単一のアイデンティティを欲してしまう。「自分探し」などと言う言葉が流行るのもそのせいにちがいない。単一の,隣の人と同一のアイデンティティを確認することでなにがしかの安心があるのだろう。
私たちのアイデンティティが現実的に多様な側面から成り立っていること、私たちはある時には一つの側面を強調したアイデンティティを持つ者として振る舞い、別の時には異なった側面のアイデンティティを強調して生きていること、私と同じように他人もまたアイデンティティの多重性を生きていること、などを基本的な人間存在の事実として確認しておくことが、本書を読み進めるための最低の前提である。
本書では、そのかなりの部分を費やして、単一基準のアイデンティティで世界を理解しようとする考え方を批判している。その主要な批判的論述に入る前に、いわばウォーミングアップのような具合で、まったく反対の立場の考え方をしている「合理的な愚か者」を批判する。「合理的な愚か者」とはアイデンティティを軽視する人間、とくに経済人(経済学者やエコノミストと称する)を指す。
人はきわめて利己的であるという仮定は、現代の多くの経済学者にとって明らかに「自然の理」であるようだ。利己性こそ「理性」――こともあろうに――がつねに要求するものだというさらなる主張が、これまた頻繁になされることによって、そのような思い込みの奇妙さはいっそう際立つものになってきた。やたらによく耳にする――極めつけの議論と呼ばれる――主張もある。それは次のような問いかけをするものだ。「自分の利益にならないなら、なぜそもそもそれをやろうとしたのか?」このような、皮肉屋的な懐疑主義にかかれば、モハンダス・ガンディーやマーティン・ルーサー・キング・ジュニア、マザー・テレサ、ネルソン・マンデラのような偉人もたいそうな愚か者になり、その他大勢のわれわれのあいだにも、小粒の愚か者がいることになる。そういう主張は、社会のなかで多様な帰属関係と責務をもちながら生きている人間を動かすさまざまな動機をまったく無視している。一途で身勝手な人間は、行動に関する基礎を多数の経済理論に提供し、「経済人」とか「合理的エージェント」といった高尚な専門用語によって、やたらに美化されてきた。 (p. 42)
経済で世界を理解しようとする人びとが人間のアイデンティティを認めるとすれば、おそらくは、利潤を生み出しながら搾取される人間と、その利潤を集約する人間という二つのカテゴリーくらいではないのかと揶揄したくなるほど,彼らは単純明快に合理的であるらしい。著者が「合理的な愚か者」を相手するのはこの程度であって、著述の大部はもっぱら「高尚な理論による還元主義(リダクショニズム)〔過度の単純化〕」に充てられる。なぜなら、それは、「意図していなくても、低俗な政治による暴力を引き起こすうえで大きく寄与することがある」 (p. 8) からである。
「現代の社会や経済に関する考えに、こうした二種類の還元主義が蔓延している」 (p. 41) という。一つは、「社会関係資本」論や共同体主義(コミュニタリアニズム)である。
社会理論のいくつかの学派では、暗黙のうちにしろ、単一帰属を事実上決め込んでいるものが驚くほど多く見られる。そのような考え方は、共同体主義的な思想家のあいだでかなりよく受け入れられており、また世界の人びとを文明のカテゴリーに分けたがる政治文化学者にも好まれているようだ。人それぞれを、ただ一つの帰属関係にしっかりと組み込まれた存在と見なすことによって、複雑に入り組んだ複数の集団や多数の忠誠心などは消し去られ、人間らしい豊かな暮らしを送る贅沢さは、だれもがただ一つの生まれながらの枠内に「置かれて」いるのだとする型どおりの偏狭な主張にとって代わられている。 (p. 40-1)
もう一つの還元主義は、サミュエル・ハンチントンの『文明の衝突』に見るような文明という単一のカテゴリーで人間のアイデンティティを見る思想である。
想像から生まれた単一基準のアイデンティティが利用される顕著な例は、「文明の衝突」というよく議論されるテーマの知的背景となる基本的分類の概念に見られる。こうした考え方は、とくに近年、サミュエル・ハンチントンの『文明の衝突』が出版されて以降、提唱されるようになった。このアプローチの難点は、衝突が起きるのかどうかという問題をとりあげるはるか以前に、単一基準で分類されているところにある。実際、文明の衝突という命題は、いわゆる文明の境界線に沿った単一基準の分類法がもつ支配的な力に、概念的に依存している。それがたまたま宗教上の区分とほぼ一致しているため、そこにひたすら関心が集まっているのだ。ハンチントンは「西洋文明」を「イスラム文明」、「ヒンドウー文明」、「仏教文明」などと対比させている。宗教の違いによる対立だったはずのものが、一つの支配的で硬直した区分によって明確に色分けされた構想のなかに組み込まれているのだ。 (p. 27)
〈9・11〉をめぐって多くの思想家が真剣で深刻な反応を見せたが、ハンチントン流の文明の衝突として〈9・11〉があった、などとする言説はほとんどなかったと言っていい。〈9・11〉以前にハンチントンの「文明の衝突」論に対しては多くの批判が浴びせられ、否定されてもいた。
もともと、「キリスト教文明」ではなく「西洋文明」を「イスラム文明」、「ヒンドウー文明」、「仏教文明」と対比させるという前提自体で、概念規定の過ちがある主張だったのである。「ギリシャ・ローマ文明」の影響を受けた「キリスト教文明」であるに過ぎないのに、「西洋文明」は世界の基準となりうる普遍的な価値を持つもっとも先進的な文明であるというヨーロッパ中心主義的な奢りに基づいた過誤である。
しかし、テレビ・ジャーナリズムなどはいちおう「文明の衝突」論は否定してみせるものの、アメリカの新保守主義的世界戦略(経済侵略)という側面に触れることなく議論を進めるため、イスラム原理主義にその原因を見るという変形の「文明の衝突」論に陥っているのが普通だった。無知で思慮が足りないほど、人は過度の単純化をしてみせる還元主義(リダクショニズム)に取り込まれやすいのである。
著者は、この文明の衝突論を、論考として成立する以前の程度の悪い言説と見なす。
文明の衝突論の難点は、避けがたい衝突かどうかを論ずる以前の問題である。なにしろ、単一基準の分類法のみが妥当だという前提から始まるからだ。それどころか、「文明は衝突するのか?」という問いかけがもとにしている前提は、人間はなによりもまず異なった別々の文明に分類することができて、異なった人間相互の関係はなぜか、とくに理解をいちじるしく損ねることなく、異なった文明相互の関係という観点から判断できるというものなのだ。この命題の基本的な欠陥は、文明が衝突しなければならないのかを問うはるか以前にさかのぼるのである。
こうした還元主義(リダクショニズム)的な〔単純化した〕見解は、おおむね世界の歴史のあいまいな認識と結びついていると思われる。それは第一に、こうした文明のカテゴリー内部の多様性を見逃しているし、第二に、物流だけでなく知的な交流が、文明と呼ばれるものの地理的境界線を越えて及ぼす範囲と影響力を考慮していない……。 (p. 28-9)
このような文明の衝突論を支持するのは、西洋の排外主義者やイスラム原理主義者であるが、しかし、「それに反論しつつも衝突論者による枠組みの制約内で応じようとする人にまで」(p. 29) 影響が及んでいることは間違いがない。
著者は、文明の衝突論が成り立たないもっとも適切な例として,彼の生まれた国であるインドを挙げる
「文明の衝突」というハンチントンの解説では、インドを「ヒンドゥー文明」として紹介することは、インドには世界のどこにもまして多くのイスラム教徒がいて、例外はインドネシアと僅差のパキスタンのみ、という事実を軽視せざるを得ないということである。インドは恣意的に定義された「イスラム世界」には含まれないかもしれないが、それでもインドには(一億四五〇〇万人のイスラム教徒がいて、これはイギリスとフランスの全人口を合算したよりも多い)ハンチントンの定義による「イスラム世界」のほぼどの国よりも、はるかに多くのイスラム教徒がいることには変わりない。また、現代のインドの文明を、この国の歴史においてムスリムが果たした主要な役割を考慮せずに考えることもできない。 (p. 75-6)
偶然にも、二〇〇四年春にインドで行われた総選挙で、ヒンドゥー原理主義の党が率いる連立政権が大敗し、インドの国政が一変した。ムスリムの大統領が国家元首になったのみならず、非宗教的なインド共和国ではいまやシク教徒の首相と、キリスト教徒の与党党首が誕生したのだ(有権者の八〇パーセント以上がヒンドゥー教徒の世界最大の民主主義国としては、まんざらでもない結果である)。 (p. 77-8)
文明の衝突論は、現状認識においても歴史認識においても間違っている。とはいえ、「ヒンドゥトゥワ」〔ヒンドゥー原理主義〕の政治指導者による「極端に歪んだ歴史観と現実の情報操作に」ハンチントンはしばしば引用され、「偽りの信憑性」 (p. 77) を与えているという。だからこそハンチントン流の単純な還元主義は克服されねばならないのである。
もう一つの還元主義はマイケル・サンデルに代表される共同体主義(コミュニタリアニズム)である。著者は、少なくともコミュニタリアリズムの一部が「社会的文脈」のなかで評価しようとして、「人間をより「完全に」――そしてより「社会的に」――見ようとする実に称賛すべき理論上の試み」 (p. 245) をしたと評するもののその方法では限定的な理解にしか達しないと批判する。
彼らにとって、コミュニティのアイデンティティはあたかも生まれつき運命づけられたものであり、個人の意思決定など必要なく(彼らの表現で言えば、ただ「認識」するのみ)、比類ない至高のものなのだ。また、世界の人びとを文明ごとの狭い枠で分割する、揺るぎない文化論者もそのなかに含まれる。 (p. 20)
コミュニタリアンの思想家の多くは、コミュニティにもとづく支配的なアイデンティティは、選択するものではなく、単に自己認識の問題なのだとよく主張する。しかし、所属するいろいろな集団のうち、どれが相対的に重要であるかを決める選択権が当人には備わっておらず、あたかも純粋な自然現象であるかのごとく、(昼と夜を区別するように)そのアイデンティティをただ「発見」するしかないというのは信じがたい。 (p. 21)
政治哲学者のマイケル・サンデルは、この主張を(その他のコミュニタリアニズムの主張とともに)次のように明確に説いている。「コミュニティは、人びとがその一員としてなにをもっているかだけでなく、彼ら自身がなにであるかをも説明する。それは彼らが選んだ(自発的な付き合いのような)関係ではなく、彼らが発見する愛着であり、単なる属性を超えて、彼らのアイデンティティの構成要素となっている」。
しかし、実際には、人を豊かにするアイデンティティは、自分の居場所を発見することによってしか得られないとは限らない。それは取得し、獲得できるものでもある。 (p. 60-1)
さほどあからさまにではないが、強い影響力をもつ共同体主義(コミュニタリアニズム)の学派も、共同体への帰属にもとづいた、一人につき一つのアイデンティティのみを神聖視しており、人間を複雑で難解な社会的な生き物という本来のわれわれの姿につくりあげる、その他もろもろの共有意識を事実上ないがしろにしている。 (p. 245)
彼らは、人が「合理的」な行動基準を追求できるのは所属するコミュニティの価値観や規範に基づいてのみだと主張する。こうした考え方は異なったコミュニティとの円滑なコミュニケーションを阻害する。アメリカが中南米や中近東の人びとの価値観に無関心なのはそのせいなのかもしれないのだ。
極端な例で言えば,江戸時代に東北の貧しい農村に生まれた人びと(たぶん私の父祖はそうであった)は、飢えたままで短い一生をおくる水飲み百姓であるというアイデンティティに基づく以外に「合理的」な人生の判断を見いだすことができない、とコミュニタリアンは主張しているようだ。一揆を起こし、自ら死罪を得るような人間としてのアイデンティティは認められないのである。コミュニタリアンによればアイデンティティは運命のようなものである。本書の副題は「運命は幻想である」とされていて、そのような共同体主義の考えを明確に否定している。
今ここに、現前しているコミュニティの中にアイデンティティを見つけよ、という主張はさながら政治的支配者にとってもっとも望ましい言説のようだ。国営放送としてのNHKがサンデルの連続講義を放送するのにとてもふさわしかった理由である。
日本でのサンデルの講義の放送といい、かつての『文明の衝突』のもてはやされ方といい、還元主義の「過剰な単純さ」に人は惹きつけられやすい。これは、あたかも小泉純一郎の短い単純な政治的フレーズにほとんどの日本人が引っかけられたことと似たようなことだろう。
このように考えてくると、もっとも典型的な単一アイデンティティ主義者としての右翼ナショナリストの言説がきわめて簡明であることも頷ける。単一基準のアイデンティティは、思考の消費を極端に惜しむ人びとに受け入れられやすいのだ。
さらに私の興味を強く引いた本書の議論は、「多文化主義と文化的自由」と「グローバリゼーション」に関するものである。
「近年、多文化主義は重要なものとして,より正確に言えば力強いスローガンとして(その潜在的な価値はさほど明確でないため)多くの支持を得てきた」 (p. 160) としながらも、文化的自由を根拠とする多文化主義が、しばしばその文化的自由と矛盾することがある。つまり、文化的自由と文化的保護の共存が困難であることがしばしば生じるのだ。
多文化主義と対立する概念は「複数単一文化主義」と呼べるものだろう。そして、複数の文化スタイルが混じり合うことなく併存する場合には、多文化主義というよりは「複数単一文化主義」と見なす必要がある。「最近よく耳にする多文化主義を声高に擁護する声は、複数単一文化主義のための弁解にすぎないことが非常に多い」 (p. 218) のだ。
保守的な移民家庭の娘が、イギリスの青年とデートに出かけたくなったとすれば、それは明らかに多文化主義的な第一歩となるだろう。一方、彼女の保護者がこれを阻止しょうとすることは(たいていこのような事態になる)、文化を隔離して温存しょうとするので、とても多文化主義の行動とは言えない。ところが、複数単一文化主義を促進させるこうした親による禁止行為には、伝統文化は尊重すべきだという理由から、多文化主義者とされる多数の人びとから声高な賛同の意が寄せられる。まるで、若い女性の文化的自由にはなんの重要性もなく、それぞれの文化はなぜか枠内に押し込められて隔離されなければならないかのようである。 (p. 218)
宗教や民族性は人びとにとって重要なアイデンティティかもしれないが(継承し帰属する伝統を称えるか拒むか選択する自由がある場合はとくに)、それ以外にも人びとが尊重してしかるべき帰属先や関係があるというものだ。多文化主義は、ひどく奇妙に定義づけされない限りは、個人が市民社会に参加したり、国政に参加したり、社会的に非協調的な人生を送ったりする権利を踏みにじることはできない。そしてまた、多文化主義がどれほど重要であっても、伝統文化の命ずることが自動的にその他すべてに勝る優先順位を与えるものにはなりえない。 (p. 219)
多文化主義の尊重という名目によって,ある種の人びとをその固有の文化に閉じ込め、自由な選択としての「文化的自由」を阻害していることが多い。その一つの例として、著者は,イギリスにおける「ムスリム、ヒンドゥー、シクの子女向けの「宗教学校」を(従来のキリスト教学校に加えて)新たに創設することを積極的に推進する公共政策」を心配する。
これは、人のアイデンティティをその人の様々な帰属関係を捨象して、受け継がれてきた宗教や伝統を優先すべきだという狭量な多文化主義を根拠にしている。パキスタンのイスラム教の宗教学校に見られるように、「宗教優先の考えが世界で暴力を生む主要な要因になってきた」 (p. 222) のだ。
多文化主義は,異なった文化を尊重すると同時に,その文化が自らの意志で変化していく自由をも尊重しなければならない。文化的保護は、保護を自らのアイデンティティとして選択した場合になされるべきで、保護の名による文化の強制、文化の閉じ込めは許されないのである。
アマルティア・センは、世界の人びとは「国籍や文化、共同体、宗教の境界をはるかに越える」「幅広いアイデンティティ意識」を持っているし、持っていなければならないと考えている (p. 174) 。そのために、グローバリゼーションの持つ積極的な意義を評価する。
グローバリゼーションの積極的な意味は、皮肉なことに「反グローバル化」運動に象徴される。「抗議運動が表明する(ときとして、たしかにかなり乱暴な意見表明にもなるが)地球規模の不満の声は、グローバルなアイデンティティ意識が存在し、グローバルな倫理に対する関心もあることの証左と見なすことができる」 (p. 174) からである。
国境や宗教を越えたアイデンティティ意識を世界の人びとが獲得することが、単一アイデンティティ主義がもたらす現状の悲惨な暴力を克服する重要な道であることは否定できない。しかし、それはまた理念的すぎる印象を受ける。著者も指摘するように、現状のグローバリゼーションは「西洋帝国主義とつながる問題もある」 (p. 182) し、「グローバル資本主義が通常、民主主義の確立や、公教育の普及、あるいは社会の弱者のための社会的機会の向上などよりも、市場を優先していることは何度も立証されている」 (p. 193) のである。
著者は、「グローバル経済に依然として見られる不平等は、さまざまな制度上の失敗と深く関係しており、それらは克服しなければならない」とあっさり述べているが、イラクにおける悲惨と暴力が、アメリカ合州国が持ち込んだ「制度上の失敗」などとは考えられない。アメリカ合州国が存在するという世界の「制度」そのものが失敗というなら理解できるが、アメリカの明確な政治的意図を問題にしないで「制度上の失敗」に還元することはできないと考える。この点に関して言えば、私はナオミ・クライン [1] やノーム・チョムスキー [2] の分析を信じる。
アクチュアルな政治行動から距離を置いて語ろうとすることが、私が冒頭に記した「アマルティア・センは無色で透明な位置に立とうと志している」という印象に繋がったのだと思う。
[1] ナオミ・クライン(幾島幸子、村上裕見子訳)『ショック・ドクトリン ―惨事便乗型資本主義の正体を暴く』(岩波書店、2011年)。
[2] ノーム・チョムスキー(鈴木主税訳)『覇権か、生存か ―アメリカの世界戦略と人類の未来』(集英社新書、2004年)。










