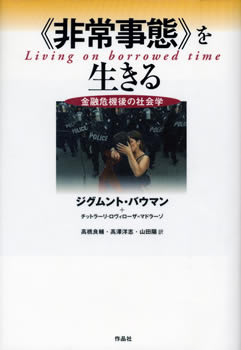2011年3月11日、講演のために来日していたアルンダティ・ロイは東北地方太平洋沖地震を東京で経験した。いくつかのインタビューをこなしながらも、彼女自身の講演は中止となり、インドに帰国した。そのいきさつを本書の「はじめに」に記して、その文を次のように結んでいる。
私がインドに帰ってから数日間、福島からの放射能が風に乗って東京に降り注いだ。放射能の広がりは六〇〇平方キロに及ぶ。それはチェルノブイリのそれに匹敵すると公表された。それでも原子力業界は結託して悪いニュースを知らせまいと、原子力エネルギーが人類にとって唯一の未来だと信じ込ませようとしている。
こうしてこの小さな島国は苦しみの円環を完成したのだ、戦争中も平和なときも、私たちの想像力が核によって摩滅してしまったために。人間の愚かさ、それが異なるデザインの海に囲まれた島で、ふたたび演じられている。 (p. viii)
世界で唯一、大量の市民殺傷を目的とした原発を広島と長崎という二つの都市で経験した日本は、66年後に「核の平和利用」の美名のもとに福島での原発溶融事故で美しい国土を失い、その地の人々を離散させた。「戦争」と「平和」という対極の名のもとで「苦しみの円環」を完成させてしまったのである。
その日本の「苦しみの円環」に想いを寄せるアルンダティ・ロイは、故国・インドにおける新自由主義、ヒンドゥー原理主義、イスラム原理主義、カースト制度からなる苦しみの多層構造との果敢な闘いに取り組んでいる。新自由主義の帝国、アメリカにおいても、ジュディス・バトラーが「(〈9・11〉後には)よりバランスのとれた国際紛争の報道の試みが放棄され、アメリカ合州国の軍事政策に対するアルンダティ・ロイやノーム・チョムスキーのような重要な批判が、アメリカの主要新聞から軒並み追放されてしまった」 [1] と述べているように、アメリカの外交・軍事行動への厳しい批判活動を行なってきた。東京にやってきた当時、その闘いの鋭さゆえに、「デリーの裁判所から煽動罪の嫌疑で召還されていた」というのである。
本書は、その東京で予定されていた講演「民主主義のあとに生き残るものは」の書き下ろしを中心に、新自由主義の本拠でありその象徴都市でもあるニューヨークからインドの森林地帯の開発現場、カシミールの民族(宗教)紛争までを広く視野においた論考で構成されている。
巻頭には、あたかも新自由主義への闘いの宣言であるかのように、ウォール街占拠運動支援演説「帝国の心臓に新しい想像力を」が配されている。ウォール街占拠運動とは、2011年9月19日にニューヨークで「ウォールストリートを占拠しろ(Occupy Wall Street)」という合い言葉のもとに起きた「オキュパイ運動」 [2] のことである。
新自由主義の経済思想のもとに世界経済を蹂躙してきた米国金融業界を吊し上げるべく1000人規模で始まったこのオキュパイ運動は、きわめて象徴的にウォール街から始まり、9月19日の最初のデモから一か月もしないうちに全米30都市に広がった。そこには資産を占有する1%のプルトノミーに対する99%のプレカリアートの抗議の意志の強さと広がりが示されていた。
著者は、オキュパイ運動を「九月一七日にアメリカで占拠運動が始まってから皆さんが獲得してきたのは、帝国の心臓に新しい想像力を喚起させ、新たな政治的言語を導き入れること」 (p. 3) と評価し、インドにおけるプルトノミー、プレカリアートに着いてこう述べる。
インド政府はアメリカ合州国の経済政策を崇めています。二〇年間にわたる自由市場経済のせいで、インドの上位一〇〇人の富豪がGNPの四分の一に当たる財産を所有する一方で、全人口の八割以上が一日五〇セント以下で暮らしています。死に至る悪循環に巻きこまれた二五万の農業生活者が自殺してしまいました。インド国民はこれを進歩と呼び、自国を超大国であるといまや考えているのです。あなたがたアメリカと同じく、インドにもその資格はあるだろう、核爆弾だって忌むべき不平等だってあるのだから、と。 (p. 4-5)
貧しい人々、政治的弾圧下にある人々の闘いは世界に何千とある。だが、「あなたたちアメリカ合州国の人びとが私たちの側について、帝国の真ん中でこんな運動を行ってくれることがあるなどと、私たちのほとんどは夢見たこともありませんでした」 (p. 5) と感動を込めて語るほど、オキュパイ運動には画期的な意味があった。金融資本を闘いの目標に据えるというのも新しかったし、1%-99%という語り口は世界中に一挙に拡散した。
著者は、オキュパイ運動の意味をふたたび評価しつつ、次のように支援演説を結ぶのである。
この闘いは、私たちの想像力をふたたび喚起してくれました。どこかでいつのまにか資本主義は、正義の概念をたんに「人権」を意味するものに矮小化してしまい、平等を夢見ることを罰当たりだと貶めてきました。私たちが闘っているのは、システムを改良しようとしていじくるためではない、このシステムそのものを置き換えるためなのです。
ひとりのふたする者(リッダイト)および覆いをかける者(キャピスト)として、私は皆さんの闘いに挨拶を送ります。サラーム、そしてジンダーバード。 (p. 6)
「民主主義のあとに生き残るものは」の章において、著者は、民主主義を「理想や希望としての民主主義ではなく、実際に機能するモデルとして、つまり現存する西欧型の自由民主主義、そしてその派生型」 (p. 9) と定義した上で、この問いの意味を次のように述べる。
しかし民主主義があらゆる「発展途上」の社会がめざしているユートピアであるべきかどうかはまったく別の間題である。(私自身はそうであるべきだと考えている。民主主義の初期、理想に燃えている段階では、それは大きな躍動をもたらすことができる。)「民主主義のあとに生き残るもの」という問いは、すでに民主主義のなかで暮らしている私たちのような人間か、あるいは民主主義のふりをしている国に住む人たちに向けられた問いだ。それは私たちが以前の、信用をすでに失った独裁や専制的な統治に帰ることを意味しているわけではない。この問いが示唆しているのは、いまの代議制民主主義が、あまりにも多くのことが代表されてしまうことで少ししか民主主義がない、それゆえ構造的な調整を必要としているということなのである。 (p. 9-10)
ドミニク・ブールとケリー・ホワイトサイドが、人間の資本主義的活動による地球生物圏の避けがたい危機について議論し、政治体制としての代表制民主主義は原理的にその危機を解決することが不可能なシステムであることを論じている [3] 。
アルンダティ・ロイが論じるのは、もちろん地球生物圏の危機ではなく、インドの最貧層の人々とインドの自然の危機である。しかし、どちらも現在の代表制(代議制)民主主義の不能性から派生する問題を扱い、あたかも民主主義は存在していながら存在していない、「機能するモデル」としての民主主義は危機に瀕しているという現状から、民主主義の〈後〉を問わざるを得ないという点においては共通している。
話題は、第2次世界大戦以後のつぎつぎと発生する各国の民主化の動きに対する反動としてのソ連やアメリカの行動への批判から始まる。東欧圏の国々に軍事介入したソ連は自ら崩壊したが、アメリカは中南米から中東へとその軍事的、経済的な干渉、侵略を続けている。つまり、「「民衆の力」が自ら未来のさまざまな「民主主義」を創りあげようとするのを、世界を支配する権力はよってたかって牽制しようとする、その有様を私たちはいま目撃している」 (p. 12) のだ。そうした事情については、ノーム・チョムスキー [4] やナオミ・クライン [5] の著作に詳述されている。
主題はもちろんインドにおける民主主義の様相についてであるが、植民地解放後の「民主主義」国家インドは次のように始まる。
一九四七年に民主主義国として主権を獲得したインドは、ほとんど即座に植民地を獲得する権力に姿を変えて領土を併合し戦争を仕かけた。政治問題を処理するためにインドが軍事介入を躊躇したことはない――カシミ—ルでも、ハイデラバードでも、ゴアでも、ナガランドでも、マニプールでも、テレンガナでも、アッサムでも、パンジャブでも、西ベンガルのナクサライト反乱〔農民による武装闘争〕でも、ビハールでも、アンドラ•プラデシュでも。何万という人びとが殺されたが、殺した側には何の咎めもなく、無数の人びとが拷問されてきた。……つまり他の国々におけると同様にインドでも、進歩と民主主義は血ぬられた基礎の上に成り立っているのである。 (p. 13-4)
ソ連が崩壊し、冷戦が終了すると、インドはアメリカ合州国の国際戦略(グローバリゼーションという名の経済的・軍事的侵略)とシンクロナイズして変化を始める。新自由主義的市場原理主義とヒンドゥー原理主義の導入による国家運営である。例えば、「係争中」のため閉鎖されていたモスクを開放することで宗教間の争い、カースト間の争いを煽り、そして、市場が突然国際金融と自由貿易に開放された。
暴力的なヒンドゥートヴァ運動の隆盛が、アメリカ合州国にとつて最大の敵が共産主義からイスラームへと代わったのと、時を同じくしているのは偶然ではない。ほとんど同時に、かつてはパレスチナ人の強固な友邦であったインド政府が、イスラエルの「本来の盟友」となった。いまやインドとイスラエルとアメリカ合州国は共同で軍事演習を行い、諜報を共有し、それぞれの占領地域をどのように管理するかの情報を交換しているのだ。(皮肉なことに、軍事支配されている世界のほとんどの地域――イラク、アフガニスタン、パレスチナ、カシミール、マニブール、ナガランド――は、自らを民主主義と称する国家によって支配されている。) (p. 16)
そうしてインドは経済成長を遂げるのだが、「社会や環境に巨大な負荷」を与えるという多大な犠牲のうえに成り立っている。ヒンドゥートヴァ運動はインド国内のイスラム教徒へのテロを誘発し、カシミールへの軍事行動を後押しする。
ヒンドゥー原理主義は市場原理主義と協同的にインド社会を席巻する。
二〇〇二年の二月、アヨーディヤから帰る巡礼者たちの乗った列車が焼き討ちされて五八人のヒンドゥー教徒が焼き殺されたとき、ダジャラート州の首相であったナレンドラ・モディに率いられたインド人民党は、その州のムスリムに対する虐殺をきわめて周到に計画し実行した。二〇〇一年九月一一日以降、世界中で蔓延していたイスラーム嫌悪がそれを後押しする。ダジャラート州の政権や警察は、二〇〇〇人以上の人びとが殺されるのを何もせず見ていた。女性たちは集団で強かんされたあと、生きながら焼き殺され、一五万人のムスリムが家を追われたのである。
インドの市場は開放され、大規模投資の目的地として賛美されていたので、この虐殺事件には幕が引かれてしまう。投資の矛先を鈍らせてはならない、というわけだ。 (p. 21)
新自由主義的な経済改革がもたらしたものは何だったのか。アルダティ・ロイは、それを次のように概括する。
改革が意味したものは、水資源、電気、電信、医療、住宅、教育、交通といった基本的なインフラの私有化だ。それは労働者の権利を守る法律の破棄でもある。IMF(国際通貨基金)、世界銀行、アジア開発銀行のような国際的な金融機関は、借款に合意する前に、そうした法律の破棄をはっきりと条件として要求する。それを示す言葉が「構造調整」である。巨大な私的資金が流入したため経済成長率が急激に上昇した。こうして作り出された膨大な中産階級が、突然の富とそれに伴う突然の尊敬に酔ったようになる一方で、それよりもずっと膨大で絶望的な貧困層が作り出された。何千万という人びとが、無差別な環境破壊や、ダム建設や鉱山開発、経済特区(SEZ)のような大規模な社会整備事業によって引き起こされた洪水や日照りや砂漠化によって、財産や土地を奪われた。すべては貧困救済のためと言いながら、実際には新たに作り出された特権階層の欲求を満たすために行われた開発である。経済成長率の急激な上昇にもかかわらず、国連開発計画の人間開発指数でインドは一三四位にすぎず、赤道ギニア、ウズベキスタン、キルギスよりも下位に位置する。栄養失調の子どもが世界でもっとも多いのもインドである。最近の数年間で、一八万人のインドの農民が自殺した、その多くは農薬を飲んで。国家の穀物庫には食糧がいっぱいで結局腐らせているが、サハラ以南のアフリカと同レベルの飢餓がこの国を襲っている。インド総人口の八パ—セントにあたる八三〇〇万人以上が、一日二〇ルピー(五〇セント)で暮らしているのである。 (p. 25-6)
当然のことながら、そうした国家政策に抵抗する人々、集団はたくさん生まれた。それには、鉱物資源の豊富な中央インドの「毛沢東主義派」の武装叛乱も含まれるが、インド政府は圧倒的な軍事力で彼らを攻撃している。
もちろん反乱を起こしているのは毛沢東主義者たちだけではない。上地や家を持たない人びと、ダリット、労働者、貧農、織工など、国じゅうでさまざまな階層の人たちによる闘争が展開されているのだ。彼らが闘っているのは、人びとの土地や資源を企業が奪うことを許す政策を含む、巨大な不正である。彼ら彼女らの抵抗戦略は、ダム建設反対運動のナルマダ救済運動(NBA)のようなデモ、座りこみ、ハンガーストライキといったガンディー的な戦術から、オリッサ州やジャールカンド州の鉱業に反対する運動のような武力に訴える、より過激なもの、西ベンガル州のナンディグラムやラールガル地域における人民蜂起、そして他のいくつかの州における経済特区に対する抗議まで多種多様だ。 (p. 27-8)
政府が「緑の捕獲」作戦と名付けて毛沢東主義派と資源開発に抵抗する村人の掃討を行なっている現場にアルンダティ・ロイは出かけ、そこで行なわれている「反民主主義的」政策を観察し、村人と話し合い、「外からは静かに見える森の中の生活では、軍事支配が徹底しているように見えた」 (p. 33) と語る。
アルンダティ・ロイが見るこのような「インドの民主主義」は、アマルティア・センがいくぶん誇らしげに書いた「インドの民主主義」とはかなり様相が異なる。
偶然にも、二〇〇四年春にインドで行われた総選挙で、ヒンドゥー原理主義の党が率いる連立政権が大敗し、インドの国政が一変した。ムスリムの大統領が国家元首になったのみならず、非宗教的なインド共和国ではいまやシク教徒の首相と、キリスト教徒の与党党首が誕生したのだ(有権者の八〇パーセント以上がヒンドゥー教徒の世界最大の民主主義国としては、まんざらでもない結果である)。 [6]
同じナショナリティであっても、どのような国家の位相に我が身を置こうと意志するのか、どのような眼差しを獲得しようとするのか、その違いによって母国がどのように見えるかはこれほど違うのである。
アルダティ・ロイは、インドにおける絶望的な民主主義の惨状を多くの事例を挙げて示し、この論考を次のように締めくくるのである。
資本主義がそのただなかに非資本主義社会を認めざるをえなくなる日、資本主義が自らの支配には限度があると認める日、資本主義が自分の原料の供給には限りがあると認識する日、その日こそ変化の起きる日だ。もし世界になんらかの希望があるとすれば、それは気候変動を議論する会議の部屋でも高層ビルの建ち並ぶ都会にもない。希望が息づいているのは、地表の近く、自分たちを守るのが森や山や川であることを知っているからこそ、その森や山や川を守るために日ごとに戦いに出かける人びとと連帯して組む腕のなかである。
ひどく間違った方向に進んでしまった世界を再想像するための最初の一歩は、異なる想像力をもつ人びとの絶滅を止めることだ。この想像力は資本主義のみならず、共産主義にとっても外部にある。それは何が幸福や達成を構成するかについて、まったく異なる理解を示す想像力である。このような哲学に場所を与えるためには、私たちの過去を保持しているように見えて、実は私たちの未来の導き人びとの絶滅を止めることだ。この想像力は資本主義のみならず、共産主義にとっても外部にある。それは何が幸福や達成を構成するかについて、まったく異なる理解を示す想像力である。このような哲学に場所を与えるためには、私たちの過去を保持しているように見えて、実は私たちの未来の導き手であるかもしれない人びとの生存のために物理的な空間を提供することが必要となる。そのために私たちは支配者たちにこう問わなくてはならない――水を川に留めておいてくれるか? 木々を森に留めておいてくれるか? ボーキサイトを山に留めておいてくれるか? と。それはできないと、もし彼らが答えるのであれば、彼らは自分が起こした戦争の犠牲者に説教をたれることを即刻やめるべきだ。 (p. 41-2)
「資本主義――ある幽霊の話」の章では、資本主義の繁栄がもたらしたインドの厳しい格差の状況、その格差が資本と国家権力(軍事的暴力)との協同的圧政によって生み出されていく様々な事実を述べ、そして資本が「財団」やその財団の資金援助を受けるNGOを通じて行なう「文化的活動」が事実を隠蔽しつつ文化や学術に関わる階層の取り込みを行なって叛乱の芽を摘もうとしている状況に批判を投げかけている。
まずは、インド資本主義の現状を見ておこう。
インドでは私たち三億人が、IMF「改革」以降の新興中産階級に属していることになっている。その別名は「市場」だが、それが闇世界の亡霊たち、死に絶えた川や渇いた井戸、禿山や裸にされた森林の騒がしい霊たちのかたわらで暮らしているのだ。そこには借金を背負って自殺した二五万人の農民たち、加えて私たちに道を譲るために財産を失って貧しくなった八億人の幽霊もいる。そして一日二〇ルピー以下で暮らす者たちも。 (p. 46)
インドでは、何百万という人びとの土地が「公共の利益」のために接収され、私企業の手に渡った――経済特区のため、インフラ計画のため、ダムや高速道路の建設、車両製造、化学プラント、F1カーレース、といったもののために。(私有財産の聖域が貧しい者の土地に適用されたためしはない。) いつものことだが、地域の人びとになされる約束として、たとえ彼ら彼女らが自分の土地から追われたり、あらゆる搾取を蒙ったとしても、それが現実には雇用を生み出しているのだ、と言われる。しかし今では、GNPの成長と雇用とがつながっているというのは神話にすぎないことを私たちは知っている。二〇年間にわたる「成長」を経て、インドの勤労人口の六割が自営であり、労働力の九割が未組織部門で働いているのだから。 (p. 48)
一方、チヤッティスガールでは、サルワ・ジュドウムによって何百という森のなかの村々が焼かれ、人びとが暴行を受けたり殺されたりして、六〇〇の村が破壊され、五万人の人びとが警察の収容所へと追い立てられ、三五万人が逃げ去った。州首相によれば、森のなかから出てこない者たちは「毛沢東主義派のテロリスト」と見なすという。このようにして今のインドには、畑を耕したり種を蒔いたりすることがテロ活動と定義されるようになってしまった地域があるのだ。結局のところサルワ•ジュドウムの暴虐によって、毛沢東主義派ゲリラの軍隊は数が増えて抵抗運動が強化されることになった。二〇〇九年に政府は「緑の捕獲」作戦を発表する。これによってチヤッティスガール、オリッサ、ジャールカンド、それに西ベンガル州で、二〇万のパラミリタリーが配備されたのである。 (p. 51)
そして、貧しい人々の土地を奪い取ることで成長した巨大複合企業は文化・芸術に手を出し始める。これらに企業があたかも表現の自由を後押しするかのように「映画、アート、文学フェスティヴァル」を支援するのだ。しかし、アルンダティ・ロイはその欺瞞性を見逃さない。
いったい表現の自由とはどこの話なのか? カリンガナガルについて誰が言及したか? インド政府が歓迎しない主題――スリランカにおける内戦でタミル人虐殺にインド政府がどう関与していたかとか、カシミールで最近になって発見された死体埋葬の形跡、といったこと――をあつかうジャーナリストや学者、映像作家たちにはヴィザが発給されず、空港からすぐに送還された事件を、誰も報道しなかったではないか。 (p. 59)
こうした文化活動を装って資本主義の反民主主義性を偽りつつ、思想を統制し、世論を誘導していく手段は、企業の慈善活動として20世紀初めのアメリカ合衆国で始まった。「カーネギー財団」、「ロックフェラー財団」、「フォード財団」が設立され、「経済的な富を政治的、社会的、文化的な資本に拡張し、お金を権力に変え……世界を支配する」 (p. 63) 手段としての慈善活動をつうじて「世界中の政府の教育や保健、農業政策を企画」 (p. 64) するのである。
これらの財団は世界戦力として外交問題評議会(CFR)を創り、そのメンバーを世界銀行の主要メンバー(総裁)に送り込む。世界銀行とIMFがアメリカの経済的世界戦略の先兵として中・後進国の経済制覇に果たした役割についてはナオミ・クライン [4] やアントニオ・ネグリとマイケル・ハート [7] も詳しく言及している。
たとえば、ノーベル賞受賞で話題となったバングラデシュのグラミン銀行のアイデアは、アメリカのクレジット・ユニオン運動に端を発しているという。それは「労働者に返済可能なクレジットを与えて消費物品を購入させて大衆消費社会をつくる」 (p. 67) という理想で始まったが、資本主義的変容を受けて「労働者に何千万ドルという「返済可能な」金を貸し出すことによって、アメリカ合州国の労働者階級を自分たちの生活様式に追いつくために走り続けなくてはならない借金漬けの人間に仕立てた」 (p. 68) のである。この経済政策は2008年9月の金融危機として資本主義を脅かすことになるが、南アジアにも深刻な影響を及ぼす。
それから何年もたってから、この考えはバンダラデシュの貧しい田舎へと流れつき、ムハマド・ユヌスとグラミン銀行が少額のクレジットを飢えた貧しい農民たちに与えることで壊滅的な結果をもたらす。インド亜大陸の貧しい人びとは、それまでも常に地元の村の高利貸バニヤの無慈悲な支配下で借金を負わされてきた。しかし少額貸付はそれさえも企業化してしまったのだ。インドにおける少額貸付会社は何百という自殺――アンドラ・ブラデシュ州では二〇一〇年だけで二〇〇人が自殺した――の原因となっている。近ごろ日刊全国紙に掲載された一八歳の女性の遺書には、自分の学費であった最後の一五〇ルピーを少額貸付会社の執拗な従業員に手渡すことを強要されたとある。そこにはこう書かれている、「一生懸命働いてお金を稼ぐこと。借金をしてはいけない」。
貧しさを使って儲けることもできれば、ノーベル賞をもらうこともできるのだ。 (p. 68)
もう一つの有名な例は、ロックフェラーの資金でアメリカのシカゴ大学に留学して新自由主義経済を学んだチリの学生たちは「シカゴ・ボーイズ」と呼ばれ、1973年のチリの軍事クーデターとその後の軍事政権を支え、「17年にわたる殺害と行方不明と暴力の支配」 (p. 69) に重要な役割を果たした。そして、ロックフェラー財団などの奨学金によってアメリカで学び、帰国して指導的な地位を占めた日本人が多数いることも忘れてはならない。経済学者やエコノミスト、政治評論家や政治家の言説に注目してみるとよい。彼らの言説の中に明瞭な「洗脳」の痕跡が見出されるかもしれない。
財団と良好な関係を保っている経済学や政治学の研究者には、奨学金や研究資金やさまざまな寄付金だけでなく、仕事のポストが報奨として与えられてきた。財団に批判的な意見を持つ研究者には資金も与えられず、周縁に追いやられて孤立させられ、その学科は閉鎖の危機にさらされる。単一で強大、きわめて単線的な経済思想の屋根の下、しだいに学問機関で支配的になってきたのは、ただひとつの想像力――寛容と多文化主義のもろくて表面的な装いである。(その実、それらは簡単に人種主義や排外的ナショナリズム、民族的自己中心主義、好戦的イスラーム嫌悪に転じる。) (p. 73)
このように資本主義の政治的・経済的・文化的支配は網の目のように世界中に張り巡らされている。状況は困難と言うしかないが、それでもアルンダティ・ロイは、資本主義の集約体としての金融資本にまっすぐに立ち向かったオキュパイ運動に希望を繋ぐ。
しかし今ようやく「ウォール街占拠運動」のおかげで、ほかの言語と思想がアメリカ合州国の街頭や大学キャンパスに出現しつつある。学生たちが「階級戦争」とか「あんたたちが金持ちなのはかまわないが、私たちの政府をその金で買うのは許せない」といったブラカードを掲げていること、それは新たな賭けであり、ほとんど革命そのものだ。 (p. 73-4)
「自由(アーザーディー)――カシミールの人びとが欲する唯一のもの」の章は、文字通りカシミール問題についての論考である。カシミールは第2次世界大戦後の1047年の植民地独立以来、第1次から第3次のインド・パキスタン戦争も含めてずっと紛争の地であった。それは国家間の領土をめぐる主権争いの形を取りながら、民族の争いであり、宗教の争いでもある。
アルンダティ・ロイがここで語ろうとしているのは、2008年に始まったカシミール渓谷の非暴力的な集団抗議についてである。その「闘争を養っているのは、長年にわたる抑圧に対する人びとの記憶」、つまり、インドの軍事占領下で「何千という人びとが「消され」、何十万人もの人びとが拷問され、傷つけられ、強かんされ、辱めを受けた」 (p. 93) 記憶である。
カシミールの人びとは、様々なスローガンを掲げて非暴力の抵抗を続ける。アルンダティ・ロイは、抵抗運動の現場で立ち、そのスローガンを聞く。
私をナイフで切り裂き、心に楔を打ちこんだのは、次のスローガンだ。「裸で飢えたインド、命そのものであるパキスタンとどちらが大事?」これを聞くことがどうしてそれほどつらく、痛みを伴うのか? そのことを考えてみて私は次の三つの理由に行き当たった。第一に、このスローガンの最初の部分が、興隆しつつある超大国インドに関する、露骨で飾らない真実を言い当てていること。第二に、裸でも飢えてもいないあらゆるインド人は、インド社会をこれほど残酷に、すさまじいまでに不平等なものとした文化的経済的システムに対する歴史的な責任を逃れることができないということ。そして第三に、自らこれほど苦しんできた人びとが、異なる仕方とはいえ、同様の抑圧のもとで同じくらいの苦しみをなめてきた人びとを揶揄する言葉を聞くことの痛みがある。このスロ—ガンに私は、犠牲者が簡単に加害者となることの種を見たのだった。 (p. 105)
アルンダティ・ロイはムスリムではない。しかし、透徹する眼差しは、被害と加害、ヒンドゥーとイスラムの輻輳する悲劇そのものを見るしかない。だから、カシミールの自由は、インドの自由と切り離せないのだと、次のような結語を述べるのである。
インドによるカシミールの軍事占領は、私たち皆を怪物にしているのだ。それによって、カシミールにおけるムスリムの解放闘争を口実にして、インド国内の排斥主義的なヒンドゥーたちが、ムスリムをつかまえて犠牲にすることが許されてしまう。それは私たちの血管のなかに、まるで静脈注射のように毒を注ぎこむのである。
こうしたことすべての中核には、倫理にかかわる問いがある。どんな政府が人びとの自由を軍事力によって取り去る権利があるのか、という。
カシミールがインドからの自由(アーザーディ)を必要としているのと同じくらい――それ以上とは言わないまでも――インドはカシミールからの自由(アーザーディ)を必要としているのである。 (p. 110-1)
最後の章は、2011年に来日して〈3・11〉の翌日、翻訳者の本橋哲也のインタビューに答えた「運動、世界、言語」の書き下ろしで、アルンダティ・ロイの作家活動や政治批評・運動について語っている。貧しい人びとの政治闘争はほとんど敗北に終らざるを得ないのだが、「道義的な論争では勝利を収めましたし、人びとが抵抗する権利を持っていることも示すことができた」 (p. 120) と評価しつつ、敗北の理由を次のように語ったのが印象的である。
多くの失敗のなかで、中産階級が運動の指導層だったこと、もっとはっきり言えば、一人のリーダーがメディアによって指導者に祭りあげられ、運動もそれを止めようとしなかったことがあげられると思います。
……一人の指導者に頼りすぎたことは運動をひ弱なものにしてしまったと私は思います。それは真の民主主義を運動のなかに作りだすことができませんでした。もし中産階級出身の人間が指導者だと、彼女たちは自動的に中産階級の武器に頼ろうとします、裁判所に訴え出ようとか……。ですから実際に武器を取って武装闘争を行うべきだと主張する人たちを抑圧するかたちで、裁判の書類手続きを書いたりすることに習熟した教育のある人たちが運動内で権力をにぎって、他の人びとは力を奪われてしまうことが生じる。
……ですからこれはたんに非暴力運動がなぜ機能しなかったのかという問題にとどまらず、非暴力抵抗運動といっても、どんな構造を持った非暴力運動なのか、非武装の戦闘性とは何なのかを問うことが大事なのです。この問題をめぐる論議はまだインドでは行われているとは言えません。これがひとつの大きな問題です。 (p. 120-1)
「この問題をめぐる論議」は、日本では行なわれているだろうか(いただろうか)。少なくても、かつて日本の抵抗運動の多くは高学歴(大学も指定できるが)の指導者(インテリゲンチャ)を擁する左翼に担われてきたことは確かであり、現在ではすでに左翼は見る影がないこともまた確かである。現在の日本でもっとも明確な大衆の抵抗は「脱原発運動」であるが、それは旧左翼・既成左翼を含んではいるものの、その指導とはまったく無縁である。そのような点では、希望があるのかもしれない。
[1] ジュディス・バトラー(本橋哲也訳)『生のあやうさ 哀悼と暴力の政治学』(以文社、2007年)p.22。
[2] ノーム・チョムスキー(松本剛史訳)『アメリカを占拠せよ!』(ちくま新書、2012年)。
[3] ドミニク・ブール、ケリー・ホワイトサイド(松尾日出子、中原毅志訳)『エコ・デモクラシー』(明石書店、2012年)。
[4] ナオミ・クライン(幾島幸子、村上裕見子訳)『ショック・ドクトリン』(岩波書店、2011年)。
[5] ノーム・チョムスキー(鈴木主税訳)『覇権か、生存か――アメリカの世界戦略と人類の未来』(集英社、2004年)。
[6] アマルティア・セン(大門毅、東郷えりか訳)『アイデンティティと暴力』(勁草書房、2011年)(p. 77-8)。
[7] アントニオ・ネグリ、マイケル・ハート(幾島幸子訳、水島一憲、市田良彦監修)『マルチチュード/〈帝国〉時代の戦争と民主主義(上、下)』(NHKブックス、2005年)。
 はたよしこ
はたよしこ 【上】ヴィレム・ファン・ヘンク(1927-2005)《マドリード》制作年不詳、絵の具、ハードボード、
【上】ヴィレム・ファン・ヘンク(1927-2005)《マドリード》制作年不詳、絵の具、ハードボード、

 【上】坂上チユキ(1882-1961)《さがしもの》1995-99年、ミクストメディア
【上】坂上チユキ(1882-1961)《さがしもの》1995-99年、ミクストメディア