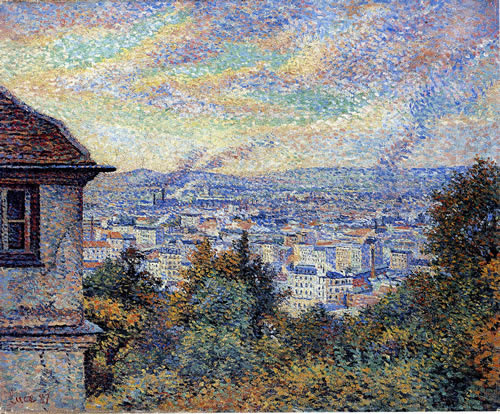【2015年1月30日】
1914年生れの小山田二郎の生誕100年の回顧展である。あまり見る機会の多くなかった小山田の絵を見に府中市まで出かけた。府中市は初めての街で、お決まりの街歩きを企てていたが、ホテルの窓から見る東京は朝から雪降りで、どうしたものか判断に迷った。
雪のため、いくぶん遅れが出ているJR山手線、京王線と乗り継いで府中に向かう。雪はベタ雪なのに、街は真っ白になっている。結局、地図まで調べて計画していた府中の街歩きを諦めて、府中市美術館に直行した。
小山田二郎は、シュールレアリズム系の画家だとばかり思っていたので、期待半分の美術展である。半分というのは、シュールレアリズムが描き出すイメージはしばしば私の感性というか想世界からまるっきり外れて、感覚的な手がかりがまったく見つからないことが時々あるためだ。
雪のせいか、観覧者も少なくて美術館はひっそりとしている。受付の女性に、「今日は小学校の美術教室がありますので、騒がしいかもしれません」という意味のことを伝えられた。会場の中で二度ほど40人ほどの小学生の集団とすれ違ったが、ほとんどの時間は会場を見渡す限り、2、3人の観覧者が見えるだけだった。
周りに誰もいない静寂な場所で、小山田二郎の絵を次々に見ていくのは、正直言って、とても疲れる行いだった。小山田二郎の絵が発散する情念のエネルギーが直接私だけに向かってくるようで、多くの観覧者のざわめきにまぎれるということがない。

【左】《顔》1940年代後期、キャンヴァス・油彩、53.1×45.3cm、府中市美術館 (図録、p. 12)。
【中】《娘》1940年代後期、キャンヴァス・油彩、90.1×72.4cm、府中市美術館 (図録、p. 14)。
【右】《顔》1950年、紙・水彩、41.5×29.0cm、府中市美術館 (図録、p. 18)。
最初期の具象的な人物画、シュールレアリズムやキュビズムに影響を受けたような《娘》や《顔》を見て、前日見たジュール・パスキンのように初期の人物の描き方から最盛期の人物像に至るような変遷を想像したりしたのだが、結果はまったく異なっていた。この3点の人物像からは想像できない展開が待っていたのだった。

《月と子供》19537年、キャンヴァス・油彩、145.5×97.0cm
(図録、p. 28)。
三角形や矩形で人体を構成するという作品はかなりの数があった。《月と子供》はそのような絵を代表する作品の一つだと思うが、私が気になったのは月の位置である。
子供の膝のあたりの高さに位置する月は、砂漠のような地平に立つ子供を見上げるように描けば、何の不思議もない。問題は、頭部の脇に空中に浮かぶように描かれている山岳である。
空間の多重構成はよくあることだが、異なった空間を示すのはその山だけだというのは不思議だ。子供が辿る時間を空間に託したのだろうかとも思ったが、よく分らない。

【上】《ピエタ》1955年、キャンヴァス・油彩、80.3×116.2cm、
個人蔵(府中市美術館寄託) (図録、p. 39)。
【下】《愛》1956年、キャンヴァス・油彩、130.3×193.9cm、
愛知県美術館 (図録、p. 41)。

《母》1956年、キャンヴァス・油彩、130.3×162.2cm (図録、p. 40)。
聖書に題材をとった幾つかの絵は会場の中でとくに(私の)目を惹いた。《ピエタ》は、新約聖書の中では最重要なシーンである。しかし、ここではキリストの死は崇高な死としては描かれていない。私にはそう思える。無惨な死を死ぬ我が子を抱きあげるマリアに見えるのは母という存在の悲惨である。
《愛》という作品は、さらに象徴的である。無数の人を包み込むであろうマリアの愛は、じっさいは無数の死者たちを包含することで成り立っている。マリアから母親へと一般化した《母》もまた、背後に多数の死者が配置されていて、経時的に死者たちを背負い込んでいることを示している。
小林真結は、図録 [1] に「キーワードから見る主要作品解説」という論考を寄せていて、小山田二郎の次のような言葉を引用して、《ピエタ》や《愛》は「戦時下の渾沌と恐怖をまざまざと表わし」、「戦時下の人間存在に加えられた迫害の記憶を描き出す、戦後リアリズムの一断面を示している」 (p. 179) と解説している。
『愛』とは、私の内部の覚書である。戦争の惨禍が暗き日の傷口を開いて、黒い太陽にさらしていた時、突如脳裏を掠める忌まわしきことども、恐怖、饑餓、受身に於けるささやかな祈の混淆した重圧。そして人間の条件が、1枚ずつはぎとられて行ったあの日の覚書である。 (小山田二郎「作品と作家の言葉」『美術手帖』101号、1956年7月、p. 70)

【上】《盲人達》1954年、キャンヴァス・油彩、51.7×64.0cm (図録、p. 52)。
【下】《亡者達》1956年、キャンヴァス・油彩、72.7×116.7cm (図録、p. 54)。
《盲人達》と《亡者達》は、同じ構図で、主題も同じと考えていいと思う。盲人を亡者と同一視するのは盲人を差別するかのようだが、悲しさや無惨さ、苦しみをおのれ自信の中に見る画家は、我が身の存在そのものを亡者や盲人に仮託しているのだと思う。盲人や亡者としての「存在」へのシンパシーが深いのだ。私はそう受け取った。
小山田の絵の中では《盲人達》と《亡者達》は、他者への視線を向けた比較的穏やかな(小山田の絵には似つかわしくない表現だが、あくまで「比較的に」である)絵だと思う。
しかし、図録の巻頭にねじめ正一が一文を寄せていて、父親が月賦で買った《盲人達》にまつわるエピソードを書いている。父親の亡くなった後、認知症の母が、母親には刺激が強いだろうと息子が片付けてしまった「小山田さんの絵」をとても見たがるのだという。「私は驚く。母のエネルギーに驚く。認知症になっても「盲人達」の絵を平気で見ることのできる母の命には驚かされる。母はまだ生きる。母はまだ生きる。………」 (p. 7) と詩人は綴っている。
小山田二郎の絵は、どんなに穏やかであっても、それを見るには多大なエネルギーが必要だということだ。

【上】《鳥女》1960年頃、キャンヴァス・油彩、161.0×130.0cm (図録、p. 61)。
【下】《いこひ》1968年、キャンヴァス・油彩、32.2×41.1cm (図録、p. 119)。
《鳥女》という作品はかなりの数が描かれている。一連の《鳥女》のシリーズを、「人間でありながら鳥でもあるこの生き物は、小山田が彼自身の内部から掬いとった悪魔のイメージでもあり、人間そのものに巣くう矛盾の表現」 (p. 180) だと小林真結は評している。
ほとんどの《鳥女》という作品は、私にとってはすんなりと受容できるような容易な絵ではない。画家の激しく厳しい自己認識は、否定的であれ何であれ自己受容(許容ではない)の形として絵画化されているはずだと思うのだが、どうにもそのプロセスがイメージできないのだ。
そのシリーズの中で、少しばかり近づけそうな気分がした作品が上の《鳥女》である。逞しい肉体と存在感のある両手が特徴だ。他の《鳥女》の手は、文字通り鳥の手のように細いのだが、この絵の《鳥女》の手は、はるかに人間の手に近い。そのせいか、この《鳥女》の実在感が私の受容範囲に引っかかったのかもしれない。
《鳥女》は、画家の自己イメージであり、さらには人間存在そのもののイメージを仮託したものだろう。だとすれば、自己嫌悪のように描くこともあれば、他者の存在のあり方として描くこともある。後の場合が、《いこひ》という作品であろう。
家族のような二人が腰掛けて休らう様子は、色調も鳥女の姿もいくぶん他者を慈しむ視線によって描かれているように感じられる。この絵によって、鳥女は自分自身でもあり、家族でもあり、そしておそらくは他者一般となって、人間そのものへと昇華したのではないかと想像する。

《夜の塔》1954年頃、紙・水彩、34.0×25.7cm (図録、p. 90)。
正直に言おう。小山田二郎のたくさんの展示作品の中で、どれか一品と問われれば、問題なく《夜の塔》である。理由は簡単である。家に飾ることが可能であれば、と考えたのである。ねじめ正一ではないが、他の作品では、その絵によって日々喚起されるエネルギーの消耗に私は耐えられないのではないかと思う。
《夜の塔》は、実在か心象風景は定かではないが、あきらかに小山田作品の中では例外的な風景画である。例外的な絵が一番のお気に入りというのは、なにか絵画受容としては問題があるように思うが、こればかりはどうにもならない。

《納骨堂略図》1964年、キャンヴァス・油彩、72.3×90.0cm、栃木県立美術館
(図録、p. 112)
《夜の塔》を一番のお気に入りだとしたのだが、もっとも足止めされて眺め入ったのは《納骨堂略図》である。黒い物全体が納骨堂なのか、その一部が納骨堂なのかはよくわからないが、全体を納骨堂と考えることにする。
真っ赤に燃え上がるような背景も異常だが、右下の地面近くで火が燃え上がっている。それはあたかも死者を焼く炎のように見える。左上の穴(窓)からは炎が吹き上がっている。あたかも納骨堂の内部は燃えさかっていて、炎が隙間から吹き出しているかのようだ。
納骨堂としてはありえない情景なのだ。骨になり、灰になった死者たちは、いったい何を燃やし続けているのか。考え込んで、考え込んで、結局分からない。怨念のようなものか、などとつまらないことしか思い浮かばない自分に嫌気がさして《納骨堂略図》を後にした。

《火のモニュメント》1976年、キャンヴァス・油彩、130.3×162.1cm (図録、p. 138)。
《火のモニュメント》の前では、少しばかり不謹慎なことを考えた。『BLEACH』という漫画がある。私はもっぱらアニメで見ているのだが、そこにメノスという霊体が登場するのだが、《火のモニュメント》の細身で長躯の人物像にそっくりなのである。
ジャコメッティの彫刻の人物像を思い出せば良さそうなものを、先に思い出したのは、堕ちてしまった人間の魂が救われないままに人間を襲う霊体となったメノスという怪物なのである。しかし、画家の主情は、ジャコメッティよりも、人間の悲惨も辛苦も体現しているようなメノスに近いのではないかと、これは決して負け惜しみではなく、そう思うのである。

《舞踏》1982年、キャンヴァス・油彩、130.0×162.0cm (図録、p. 142)。
最後に、《舞踏》をあげておく。舞踏も長い期間にわたって小山田の主題だったようだ。踊る人の下半身が大きく開いているというのが、初期の作品から後期のこの作品まで共通している特徴である。初期の作品の踊り手の足の開き具合には、どこか縄文時代の遮光土偶を思わせる作品もある。
この《舞踏》作品は、小山田作品の中では数少ない明るい色調である。踊り手は様式化されているように見え、小林真結によれば、「小山田にとって、《舞踏》は過去の記憶を呼び起こすためのテーマでもあり、色彩と形態の実験場でもあった」 (p. 179) という。小山田にとって《舞踏》を描く時間は、人間存在がかき立てるおどろおどろしい情念から離れて、造形と色彩へ思いを傾注した希有な時間だったことを意味しているのではないか。
小山田二郎の絵を眺め続けながら会場を行きつ戻りつしているとき、小学生の集団のざわめきで鑑賞が中断されたが、それは救いであった。小学生のざわめきが聞こえる間に十分に息継ぎをして、気を取り直して次の絵に進むことができた。小山田二郎の絵を見るのは、緊張を強いられ、エネルギーを消耗する感じが強かったのである。
[1] 『生誕100年 小山田二郎』図録(以下、『図録』)(府中市美術館、2014年)。