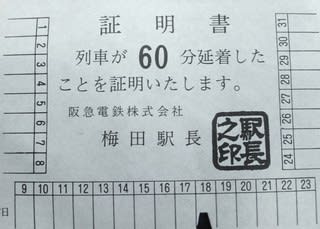労働者が、宿直勤務や早朝の勤務の対応など、その業務の関係で施設内で仮眠をする必要が有る場合、事業者は仮眠の施設を設置しなければならないことがある。
「で、仮眠の施設ってどんな風に設置しなくてはならないの?」と問われて、「そんなん労働安全衛生法に書いてあるやん」と答えたが・・・あれ?
労働安全衛生規則((昭和47年9月30日労働省令第32号)
(睡眠及び仮眠の設備)第616条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
あれ?あれ?漠然としている。
事務所衛生基準規則(昭和47年9月30日労働省令第43号)にも同じ内容が定められているだけで、「夜間作業で労働者に睡眠を与える必要のある場合」または「夜間作業で、労働者が就業の途中で仮眠しうる機会のある場合」とは、具体的にどんな場合を指すのかについての解釈例規はみつからない。
さらに、その「適当な睡眠又は仮眠の場所」については男と女を分けろということ以外、まったく具体的に書いてはいない。
で、もっといろいろ調べてみたら、ようやくこんな通達を見つけた。
【昭33・4・16基発237号】タクシー事業における運転手の睡眠施設の基準については次によられたい。
(1)仮眠室の床の高さは35センチメートル以上、天井の高さは2.12メートル以上とし、室の面積は同時仮眠者1人当たり2.5平方メートル以上とすること。
(2)寝具は、同時に仮眠する人数と同数以上を備え付け、毎月1回以上日光消毒その他の消毒を行うこと。
(3)各人専用のえり布、まくらカバー、敷布を備え、常時清潔に保つこと。
「タクシー事業においては、その事業における特殊性にかんがみて」ということでこのような運転手の睡眠施設の基準が当時示されたという。
「この通達って今でも生きているのですか?」と厚生労働省に問い合わせてみたら、少なくとも取り消されたり改正されたりはしていないとのこと。
しかしながら、この通達が出されたのは労働安全衛生法が施行された昭和47年6月8日よりも以前なので、その優先順位が微妙ではあるとのこと・・・(非公式な見解ですので、あくまでも)。
とりあえずこの通達を参考にするしかないようだ、あとはじゃあどうするのかってことは個別の労使関係で解決するしか無い。

バイクを購入。ヤマハアクシストリート、125ccです。 鎌倉から家まで、久々のバイクの運転は緊張した~。
「で、仮眠の施設ってどんな風に設置しなくてはならないの?」と問われて、「そんなん労働安全衛生法に書いてあるやん」と答えたが・・・あれ?
労働安全衛生規則((昭和47年9月30日労働省令第32号)
(睡眠及び仮眠の設備)第616条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
あれ?あれ?漠然としている。
事務所衛生基準規則(昭和47年9月30日労働省令第43号)にも同じ内容が定められているだけで、「夜間作業で労働者に睡眠を与える必要のある場合」または「夜間作業で、労働者が就業の途中で仮眠しうる機会のある場合」とは、具体的にどんな場合を指すのかについての解釈例規はみつからない。
さらに、その「適当な睡眠又は仮眠の場所」については男と女を分けろということ以外、まったく具体的に書いてはいない。
で、もっといろいろ調べてみたら、ようやくこんな通達を見つけた。
【昭33・4・16基発237号】タクシー事業における運転手の睡眠施設の基準については次によられたい。
(1)仮眠室の床の高さは35センチメートル以上、天井の高さは2.12メートル以上とし、室の面積は同時仮眠者1人当たり2.5平方メートル以上とすること。
(2)寝具は、同時に仮眠する人数と同数以上を備え付け、毎月1回以上日光消毒その他の消毒を行うこと。
(3)各人専用のえり布、まくらカバー、敷布を備え、常時清潔に保つこと。
「タクシー事業においては、その事業における特殊性にかんがみて」ということでこのような運転手の睡眠施設の基準が当時示されたという。
「この通達って今でも生きているのですか?」と厚生労働省に問い合わせてみたら、少なくとも取り消されたり改正されたりはしていないとのこと。
しかしながら、この通達が出されたのは労働安全衛生法が施行された昭和47年6月8日よりも以前なので、その優先順位が微妙ではあるとのこと・・・(非公式な見解ですので、あくまでも)。
とりあえずこの通達を参考にするしかないようだ、あとはじゃあどうするのかってことは個別の労使関係で解決するしか無い。

バイクを購入。ヤマハアクシストリート、125ccです。 鎌倉から家まで、久々のバイクの運転は緊張した~。











 既往歴及び業務歴の調査
既往歴及び業務歴の調査 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査
身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 胸部エックス線検査及び喀痰検査
胸部エックス線検査及び喀痰検査 血圧の測定
血圧の測定 血色素量及び赤血球数の検査(貧血検査)
血色素量及び赤血球数の検査(貧血検査) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(肝機能検査)
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(肝機能検査) 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査)
低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査) 血糖検査
血糖検査 心電図検査
心電図検査