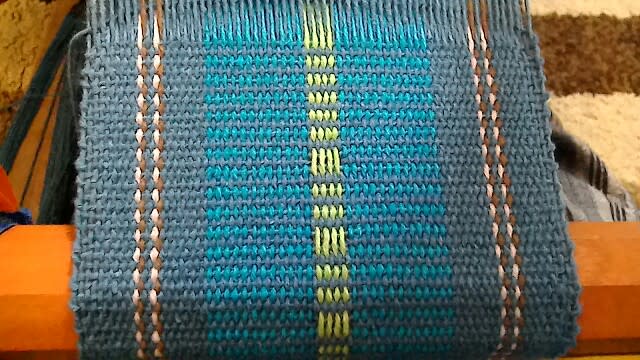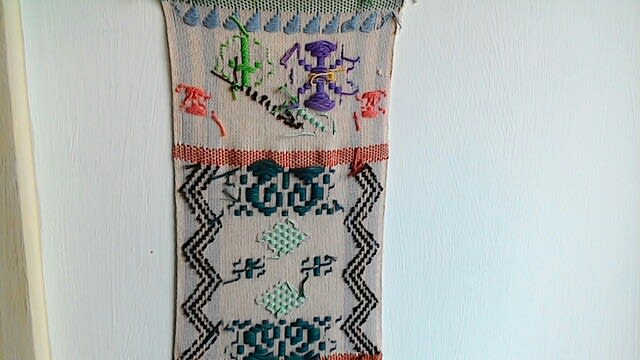腰機( 無機台腰機 / 輪状式原始機 )で6作目を織りました。
経浮織りの続きです。
参考にした色合い

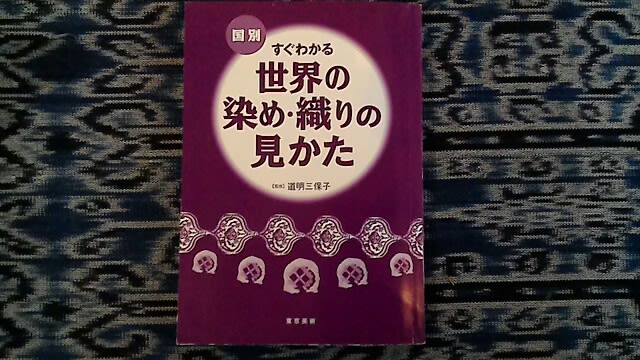
整経
156本 、半分の78周
輪の長さ 120cm
上糸 / 主に黒
下糸 / 茶と白
2目づつ動かすと、斜めの模様になるのを使いました。
下糸が上の状態から。

上糸(黒)が上。下糸ソウコウを中筒に添わせて開口を
作り、刀杼を手前に近づけて、強くはたきます。


浮かせる下糸(茶と白)を持ち上げます。

すくい棒を中筒に添わせ、浮かせた糸もいっしょに
刀杼を手前に動かす。

刀杼を立て、板杼を右側から入れます。

軽く、はたきます。

下糸ソウコウを持ち上げ、刀杼を入れます。
立てて、板杼を左側から入れます。



一往復が終わり、上糸が上になりました。
下糸ソウコウを中筒に添わせて開口を作り、
浮き糸を持ち上げます。2本ずらし、4本を持ち上げます。



上糸が上の開口に下糸の浮き糸が上の状態になります。


同じように続けます。



斜めに浮織りを入れていくだけですが上糸と下糸が
反転する色合いによって、複雑に見えます。
織り上がりました。
浮織りの工程が入るので時間がかかりました。
出来上がりの実寸
織り幅 14~15 cm
長さ 82 cm ( ふさ分4cm含む )

裏側も

経浮織りの続きです。
参考にした色合い

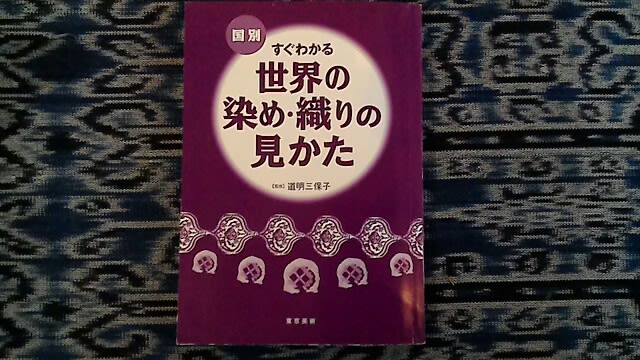
整経
156本 、半分の78周
輪の長さ 120cm
上糸 / 主に黒
下糸 / 茶と白
2目づつ動かすと、斜めの模様になるのを使いました。
下糸が上の状態から。

上糸(黒)が上。下糸ソウコウを中筒に添わせて開口を
作り、刀杼を手前に近づけて、強くはたきます。


浮かせる下糸(茶と白)を持ち上げます。

すくい棒を中筒に添わせ、浮かせた糸もいっしょに
刀杼を手前に動かす。

刀杼を立て、板杼を右側から入れます。

軽く、はたきます。

下糸ソウコウを持ち上げ、刀杼を入れます。
立てて、板杼を左側から入れます。



一往復が終わり、上糸が上になりました。
下糸ソウコウを中筒に添わせて開口を作り、
浮き糸を持ち上げます。2本ずらし、4本を持ち上げます。



上糸が上の開口に下糸の浮き糸が上の状態になります。


同じように続けます。



斜めに浮織りを入れていくだけですが上糸と下糸が
反転する色合いによって、複雑に見えます。
織り上がりました。
浮織りの工程が入るので時間がかかりました。
出来上がりの実寸
織り幅 14~15 cm
長さ 82 cm ( ふさ分4cm含む )

裏側も