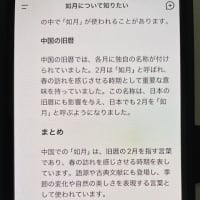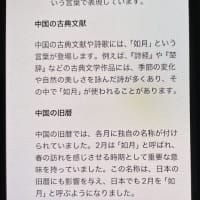日本哲学15
哲学探究の思いはすでに記すところで、生きる知恵、善なること、そして思想を知ることにあった。如何にしていくべきかを少年期に自覚したわたしには、その理想には真善美なる追求にあって、生き方を模索した。ここまでその変わらぬ思いには言と事である。こと、わざ、そこにある実である。真実、事実、忠実に現実がある。生い立ちになにやら変わった環境があったわけではない。敗戦に引き上げた家族に生を享け、歩き始めて間もなくのこと、故郷と呼ぶなら甲山に風景を描き、長じて職を得たのは国語国文学の教員、教官そして教職員である。哲学に縁あるはこの生き方にある。小我をもって大我に目覚めることが成長の沈潜の心にあった。絶対矛盾の自己同一を得るは絶対無を見ることになる、見えればのことであるが、有なるもので、個の存在を消し去ることになる。それはまた、ニーチェの哲学史が哲学研究の物語だと知る。神々は死んだという、その原意は、神なのか、神々なのか、もとはといえば拝火教の根源を諭したので、ニーチェの哲学でない、その人の思想にあると摂取した。ニーチェは神が死んでなお、神を認識しようとしたのか、それは権力にあらわされていたのであるから、極まりなく人間社会であった。かくして哲学の学習は日本語にロゴスありきを求めるようなことである。