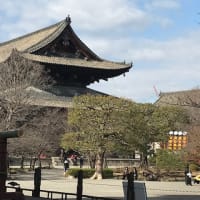素晴らしい花のサイト、季節の花300 http://www.hana300.com/index.html 10000枚の写真を楽しませてくれる。
このサイトにお正月用語を載せる。
さて、正月の松の内は松飾をするあいだのこと、松は神の憑代であるという。
新年にはその歳神様を迎える。
お正月にやってくるという「年神様」とは NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2135683685546616201
正月、松の内は松飾をするあいだのこと、松は神の憑代であるという。
その神は歳神であるが・・・、
正月|日本文化いろは事典
iroha-japan.net › 年中行事
>そもそも、私たちの祖先は"全てのモノには命がありなんらかの意味がある"という「アニミズム」を信仰しており、作物の生命〔いなだま〕と人間の生命〔たま〕は1つのものであると考えていました。そのため、人間が死ぬとその魂はこの世とは別の世界に行き、ある一定の期間が過ぎると個人の区別が無くなり「祖霊」という大きな集団、いわゆる「ご先祖様」になると信じられていました。この祖霊が春になると「田の神」に、秋が終わると山へ帰って「山の神」に、そして正月には「歳神」になって子孫の繁栄を見守ってくれているのだと言います。
門松は冥途の旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし
>『一休蜷川狂歌問答』に「門松はめいどのたびの一里づか馬かごもなくとまり屋もなし」という類似の歌がある。
世界大百科事典 第2版の解説
としがみ【年神(歳神)】
正月に家に迎えまつる神。トシトクサマ(年徳様),トシトコさん,正月さまなどとも呼ぶ。年棚を設けてまつる土地が多い。年神の神格については,正月の守り神,作神さま,社日さまと同じ神様であるとか,タガミ(田神)さまが年神さまになるなどと伝える地方があるように,作神としての性格が顕著である。年神の司祭者である年男は,家長とする地方が多いが,主婦の任務としている所もある。 年神のトシは米を意味しており,さらに年神を老人の姿とする所が多く,先祖の霊とも考えられている。
世界大百科事典 第2版の解説
まつのうち【松の内】
正月の松飾をしておく期間内のこと。門松や年棚の松は年神の依代(よりしろ)と考えられるから,松飾のある間は正月の年神祭が続いていると理解することができる。その期間は土地によって必ずしも一定せず,元旦から3日まで,あるいは7日,15日前後までとする所などがあるが,一般に松の内は短くなる傾向にある。しかし,4日朝の僧侶による寺年始までには門松をとってしまうべきだとする所でも,屋内の神棚の松飾や注連(しめ)飾をはずすのはそれより後だとする所が少なくないし,また3日など比較的早い時期に門松をとる所では,その穴の跡に門松の芯の小枝をとって少し挿しておく所が珍しくないことから,3日などではなく,7日もしくはそれよりも長い期間が本来の松の内ではなかったかと思われる。
世界大百科事典内の年神(歳神)の言及
【死】より
…
【生物における死】
死とは,生体系の秩序ある制御された形態と機能が崩壊することである。本来は生物個体が生命を失うことの概念であるが,種・個体群や器官,組織,細胞,原形質などの系についても考えられている。老衰による死,つまり寿命が尽きるまで生存する個体は自然ではまれで,多くの個体は捕食,病気,飢餓,気候,事故などの外的要因で死亡する。同じときに生まれた生物の集団の個体の死亡時の齢を記録して曲線を描くと,次の3種類の曲線が得られる。…
【正月】より
…暦の上での1年の切れめを祝う新年の行事。新年を迎えることを,年取り,年越しともいう。大晦日から元日にかけての行事に主体があるが,ほぼ1月いっぱい続く。行事の流れは,1日を中心にする大正月と,15日を中心にする小正月とに大別できるが,このほか7日の七日正月,20日の二十日正月を重視する場合もある。12月はすでに正月の始まりで,東北地方北部では,12月中に神仏の年取りがある。正月のしたくの開始は,一般には12月13日である。…
【年玉】より
…年玉は歳暮(せいぼ)とは逆に目上など上位の者から贈られるのが特徴で,語源を年の賜物とする説もある。ただ単なる下賜の品ではなく,年神からの賜物とする民俗学的解釈が有力である。正月鏡餅のほかに数多くの小餅をつくり家族の一人一人に配分したり,人数分の餅を神棚に上げておく風は各地にあり,鹿児島の甑(こしき)島では,〈トシドン(年殿)〉という年神に扮した村人が元朝各家を訪れ子どもらに配る丸餅を年玉と呼ぶ。…
【松の内】より
…正月の松飾をしておく期間内のこと。門松や年棚の松は年神の依代(よりしろ)と考えられるから,松飾のある間は正月の年神祭が続いていると理解することができる。その期間は土地によって必ずしも一定せず,元旦から3日まで,あるいは7日,15日前後までとする所などがあるが,一般に松の内は短くなる傾向にある。…
ウイキペディアより。
>神様が宿ると思われてきた常盤木の中でも、松は「祀る」につながる樹木であることや、古来の中国でも生命力、不老長寿、繁栄の象徴とされてきたことなどもあり、日本でも松をおめでたい樹として、正月の門松に飾る習慣となって根付いていった。能舞台には背景として必ず描かれており(松羽目・まつばめ)、日本の文化を象徴する樹木ともなっている。
>もと、平安の貴族達が好んだ小松引きと言う行事で持ち帰った「子の日の松」を長寿祈願のため愛好する習慣から変遷したもので、現在も関西の旧家などでは、「根引きの松」という玄関の両側に白い和紙で包み金赤の水引を掛けた根が付いたままの小松(松の折枝は略式)が飾られる。
デジタル大辞泉の解説
こまつ‐ひき 【小松引き】
平安時代、正月初めの子(ね)の日に、野に出て小松を引き抜いて遊んだ行事。子の日の遊び。
このサイトにお正月用語を載せる。
さて、正月の松の内は松飾をするあいだのこと、松は神の憑代であるという。
新年にはその歳神様を迎える。
お正月にやってくるという「年神様」とは NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2135683685546616201
正月、松の内は松飾をするあいだのこと、松は神の憑代であるという。
その神は歳神であるが・・・、
正月|日本文化いろは事典
iroha-japan.net › 年中行事
>そもそも、私たちの祖先は"全てのモノには命がありなんらかの意味がある"という「アニミズム」を信仰しており、作物の生命〔いなだま〕と人間の生命〔たま〕は1つのものであると考えていました。そのため、人間が死ぬとその魂はこの世とは別の世界に行き、ある一定の期間が過ぎると個人の区別が無くなり「祖霊」という大きな集団、いわゆる「ご先祖様」になると信じられていました。この祖霊が春になると「田の神」に、秋が終わると山へ帰って「山の神」に、そして正月には「歳神」になって子孫の繁栄を見守ってくれているのだと言います。
門松は冥途の旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし
>『一休蜷川狂歌問答』に「門松はめいどのたびの一里づか馬かごもなくとまり屋もなし」という類似の歌がある。
世界大百科事典 第2版の解説
としがみ【年神(歳神)】
正月に家に迎えまつる神。トシトクサマ(年徳様),トシトコさん,正月さまなどとも呼ぶ。年棚を設けてまつる土地が多い。年神の神格については,正月の守り神,作神さま,社日さまと同じ神様であるとか,タガミ(田神)さまが年神さまになるなどと伝える地方があるように,作神としての性格が顕著である。年神の司祭者である年男は,家長とする地方が多いが,主婦の任務としている所もある。 年神のトシは米を意味しており,さらに年神を老人の姿とする所が多く,先祖の霊とも考えられている。
世界大百科事典 第2版の解説
まつのうち【松の内】
正月の松飾をしておく期間内のこと。門松や年棚の松は年神の依代(よりしろ)と考えられるから,松飾のある間は正月の年神祭が続いていると理解することができる。その期間は土地によって必ずしも一定せず,元旦から3日まで,あるいは7日,15日前後までとする所などがあるが,一般に松の内は短くなる傾向にある。しかし,4日朝の僧侶による寺年始までには門松をとってしまうべきだとする所でも,屋内の神棚の松飾や注連(しめ)飾をはずすのはそれより後だとする所が少なくないし,また3日など比較的早い時期に門松をとる所では,その穴の跡に門松の芯の小枝をとって少し挿しておく所が珍しくないことから,3日などではなく,7日もしくはそれよりも長い期間が本来の松の内ではなかったかと思われる。
世界大百科事典内の年神(歳神)の言及
【死】より
…
【生物における死】
死とは,生体系の秩序ある制御された形態と機能が崩壊することである。本来は生物個体が生命を失うことの概念であるが,種・個体群や器官,組織,細胞,原形質などの系についても考えられている。老衰による死,つまり寿命が尽きるまで生存する個体は自然ではまれで,多くの個体は捕食,病気,飢餓,気候,事故などの外的要因で死亡する。同じときに生まれた生物の集団の個体の死亡時の齢を記録して曲線を描くと,次の3種類の曲線が得られる。…
【正月】より
…暦の上での1年の切れめを祝う新年の行事。新年を迎えることを,年取り,年越しともいう。大晦日から元日にかけての行事に主体があるが,ほぼ1月いっぱい続く。行事の流れは,1日を中心にする大正月と,15日を中心にする小正月とに大別できるが,このほか7日の七日正月,20日の二十日正月を重視する場合もある。12月はすでに正月の始まりで,東北地方北部では,12月中に神仏の年取りがある。正月のしたくの開始は,一般には12月13日である。…
【年玉】より
…年玉は歳暮(せいぼ)とは逆に目上など上位の者から贈られるのが特徴で,語源を年の賜物とする説もある。ただ単なる下賜の品ではなく,年神からの賜物とする民俗学的解釈が有力である。正月鏡餅のほかに数多くの小餅をつくり家族の一人一人に配分したり,人数分の餅を神棚に上げておく風は各地にあり,鹿児島の甑(こしき)島では,〈トシドン(年殿)〉という年神に扮した村人が元朝各家を訪れ子どもらに配る丸餅を年玉と呼ぶ。…
【松の内】より
…正月の松飾をしておく期間内のこと。門松や年棚の松は年神の依代(よりしろ)と考えられるから,松飾のある間は正月の年神祭が続いていると理解することができる。その期間は土地によって必ずしも一定せず,元旦から3日まで,あるいは7日,15日前後までとする所などがあるが,一般に松の内は短くなる傾向にある。…
ウイキペディアより。
>神様が宿ると思われてきた常盤木の中でも、松は「祀る」につながる樹木であることや、古来の中国でも生命力、不老長寿、繁栄の象徴とされてきたことなどもあり、日本でも松をおめでたい樹として、正月の門松に飾る習慣となって根付いていった。能舞台には背景として必ず描かれており(松羽目・まつばめ)、日本の文化を象徴する樹木ともなっている。
>もと、平安の貴族達が好んだ小松引きと言う行事で持ち帰った「子の日の松」を長寿祈願のため愛好する習慣から変遷したもので、現在も関西の旧家などでは、「根引きの松」という玄関の両側に白い和紙で包み金赤の水引を掛けた根が付いたままの小松(松の折枝は略式)が飾られる。
デジタル大辞泉の解説
こまつ‐ひき 【小松引き】
平安時代、正月初めの子(ね)の日に、野に出て小松を引き抜いて遊んだ行事。子の日の遊び。