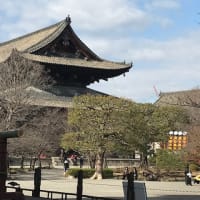日本語の文法について 20130414より再掲
~に~が 日本語の文法について その5
日本語文法の文は述語を捉えて分類する。述語にある品詞を見る。文に動詞がある。その動詞の第1は存在を表す。その存在にはわたしたちはそこにとどまることで意識している。すなわちじっとしているものか、動いているものか、動くものであっても、そこにとどまって動かないでいるものかどうか、そのいずれかを捉える。有るかないか、居るかどうか。
それがまずとらえられて文となるが、そのときに、日本語は空間のとらえ方を表現して、場所を示すことから文が始まっていると考える。文頭にそれを示している言い方である、~に という言い方である。このとらえ方が文の表現にまずあると説明できるが、これはいわば意識する最初の認識であるからふつうに表現されていてそれで文を言う。
この場所すなわち空間の認識があるかどうかは、~に という言い方はまた時間の認識でもあるので、空間と時間を位置としてまず認めているということである。場所として空間の位置を捉える言い方が目前のことを捉えるのにわかりやすいのでそれを示して、~に については動詞の第1と関係して結びつく。~にある また、~にいる となる。
古文の学習で経験することであるが、むかし、おとこありけり という表現で始まる物語があり、それを素朴なとらえ方の、昔、男があった、つまり、いたというふうに理解して時間を位置として捉えた。どこにいたのかとなるが、伊勢に男あり、とでもなるので、それを題名にして伊勢の物語とした。また、大和の地であろうか、類似の物語もあった。
第1の動詞とするのはこの文はものの存在を表すからである。古文の例は日本語としてはおよそ1000年をさかのぼるので、その時から長い使い方を経て当代のこととしてその分析をするが、いまはむかし、竹取の翁といふもの有りけり というように、ものの存在がまずあるという認識であって、これは言語の表現においてはもののとらえ方の基盤となる。
その存在についていまのわたしたちは、ある と、いる を使い分けている。そこに動かないものを、ある と言い、動いているものがそこにとどまるものを、いる と言う。漢字を書くと、有る居るとすることができる。この動詞の意味との結びつきでものには生き物の区別や動く物の区別をしていたことがあったのである。
~に~がある ~に~がいる この言い分けは動詞を捉えて表現する。あり、をり、はべり、いまそがり などを存在を表すとしたとらえ方は、現代語ではその語のそれぞれの消長で、現代語では、あります います となって、この文の表す意味内容から存在文また存現文と呼ぶ。その後の日本語の分析に位置のとらえ方を重視すべきである。
主語を示す 日本語の文法について その6
文法用語に主語を用い、加えて主題、主格という。文に主語があるという説明から文にある主格が主語であると言われ、主格はどうか、日本語ではわかりにくい。主格は語にあるとするのがよいが、日本語の膠着語の現象のため説明が行われなくなったようである。それに話題、題目と言った主題があるということになると、その主題はどうかとなってくる。
主語を文の要素とするとらえ方は語の自立を見る。語の構成とそれに格変化を含める自立性についてみると、日本語の主語の要素に語形変化がないとすることになる。国語の規定では、語形変化をしない、主語になることがある、これが品詞分類でとらえる名詞である。主格が語にあるかどうかは第1の格を名詞の語形変化に求めたとらえ方である。
主語を文に規定する、主格を語に規定する、主題は何に規定するか、それは文章にとなれば日本語文法は考えやすくなる。ただ文法は文の単位を規定するものとしての考え方が長く行われてきたので、文についての文法にさらに文章についての文法論議が必要である。とすると語についての文法があるかとなるとそれは語法というとらえ方もしてきた。
文法は語法であり句法であり文章法である。その違いは文を捉えての文法の考え方が出来る前には語法と句法がおこなわれ文章法もまたあったのであるが法則のとらえ方のそれぞれをあきらかにするためにも言語に統一した考え方を定義して文法としてきた経緯がある。
主語述語を捉えるのはその文法にあるのは当然で日本語にあてはまる。
国語では文の主語をはじめ述語修飾語独立語の4つを文の成分とした。修飾語は被修飾語を要するのでそれを加えることもできる。文の成分というとらえ方は要素と同じようなとらえ方だと考えてよいが要素成分だとすると述語は述語動詞また動詞だけでよい。すると国語の修飾語を名詞にみて文の要素として目的語としたり補語としたりすることがある。
主格については国語の膠着語としての現象を見るので格助詞が分出してその分析を受けてが格といったりする。これは日本語学習者に語形を明示して ~が の付くものを動詞との対応で説明する。その名詞が文の主語となるときである。~に~が存在文となって表わされるときが主語の要素としてわかりよい。
文の要素 - Mt. English Project mep.papiko.com/index.php? 文の要素
主部の中の主語(S)/述部の中の動詞(V)/目的語(O)/補語(C)を、文を構成する主な要素として文の要素(Elements of a Sentence)と呼ぶ。 どの語句がどの文の要素になるかは、その語句が果たす品詞的役割によって決定する。
必須要素の主語 日本語の文法について その7
日本語文法の考え方には日本語にある現象に即してさまざまとらえられて説明が行われてきている。日本語の主語は文にとらえられた。その主語は文の要素であり、主語は述語動詞に対応するので、述語または動詞とする考え方である。主語と動詞の関係で見るのがよい。すると主語は文頭に置かれて動詞との関係または場合を見ることで、格を持つ。
いわば主語主格と動詞の関係で文における主語ということが規定されているのである。動詞が主語にあたる名詞と関係するのはこの名詞が主格で述語にある動詞とのあいだで、主語主格名詞プラス述語動詞の順序で成立する考え方である。主語がなければ動詞が述語として成り立たない考え方であるから、主語を説明する場合に必須のものと考える。
主格は述語動詞と関係してその第1にあたる格を示しているととらえるとその格を示す形があると考える。名詞が語形変化をすることによってその形また形式を表す。それは名詞が変化形を持つ場合にほかの変化の形また形式と異なる。日本語は名詞がそれ自身で変化形を作らないので、~が という形をくっつけて、わたしが というのを主格とみる。
主語主格は、わたし について、わたしが となる。つくえ について、つくえが となる。わたしが います つくえが あります という文を作るが、述語動詞の いる ある に関係して、います あります と言う丁寧な表現となる。日本語はこの表現を述語動詞との関係でまず、これを存在文としてきたが、~に~が動詞構文として分析する。
しかし存在文は語の順序、構成する要素をとらえて、例文 机の上に本があります とみると、場所を示す名詞のあとに主語主格を表す名詞がくる順序としてとらえ、文のはじまりは存在を示す場所があり、主語に対する動詞は ある で示される。存在文というのはこの例文の形式であり、この文にはことばの現象を日本語文法としてとらえることになる。
英語でとらえるTHERE構文との対象で考えると日本語の存在の表し方はまず主語となるものが表わされていることになるので特徴的である。ものの存在をまず認めるなり名称として名付けを行うなりその存在を言い出すなりしてとらえる日本語ではものの名が既に与えられていた。必須要素がない英語の文の場合に語とものの認識に順序があったのである。
存在文に必須要素である主語があるかないかについての議論は存現文として中国語にその現象がありそれは英語と同様に動詞のあとに主語に相当する語が表現される。存在文には、在 を用いて、有 を用いる存現文とはさらに現象を捉える考え方が文の表現に表れている。中国語の影響は文の構造によるよりも熟語の取り入れ方の場合に日本語に見られる。
存在文 日本語の文法について その8
日本語の存在文は場所を示す名詞を に とともに文頭に置き、動詞 ある を文末において結んでいる。場所は空間の位置を捉える一方で時間の位置を捉えて同じように時間を示すこともできる。そして主語主格の名詞として が とともに用いると、~に~が動詞ある 文になる。これは現代中国語の存現文の用法にみる語順と主語の位置が異なる。
~に~が動詞の文について、名詞が を、名詞は にすると、文頭に位置して、~は~にある とすることができて、この 名詞は に主語を捉えることになる。語順を変えた文と、語順を変えない文では、それぞれ情報が同じでもその意味内容が異なる。すなわち ~に~が動詞 ~は~に動詞 において文情報の意味のちがいが生まれるのである。
この 名詞は の出現を、名詞が の出現する関係とで見ると次のようである。~は~にある ~には~がある となり、このそれぞれは文情報が異なるとわたしたちはとらえている。つまり、 ~に~がある ⇔ (その)~は~にある となる。教室に机がある ⇒ (その)机は教室にある となる。
表現すると、机はどこにある と言い出すと、机は教室にある となることが多いので、主語としても捉えることができて、これを主語主格と比べると主語主題とみることができる。本来的には、まず机があり、机が教室にある となるのであるが、この存在を表す文は主語主格が文頭に立つ前に場所の名詞が捉えられる。空間認識、ものへの順である。
日本語の表現に、~がある ~はある という二つの言い方があり、語の順序としてみると、~に~がある と言い、また、~は~にある と言えるのは、~には~がある と言うこと、~には~はある と言うことがでて、*~がは *~はが と言うことはできないからである。~は の表現内容に、~が の働きをふくみもつとみる。
存在文の文頭に、名詞が を置いて語順を変えて言うことは日本語では可能である。それはおそらく、この言い方には、有り なに 人 、それで、人 あり どこに 伊勢の国 伊勢に 人 あり というふうに捉えていたから、それをまた、 人 伊勢にあり というふうに言うこともできたからである。人 を取りたてて、人は伊勢にあり。
日本語は中国語の漢字を取り入れて言葉にした。語順については熟語のままに受け入れている。日本語の漢字による熟語を作り出すこともあった。主語をあとに置く語には、日常の漢字熟語の中に、 開花 降雨 積雪 出火 出血 停電 発芽 満潮 有人 立春 少量 多数 难题 無害 いずれも存現文の語順としてみることのできる熟語である。
日本語の文 日本語文法について その9
主語述語を文とするのは動詞を述語に置く場合の構文である。そのときに主格が現れる。それを第1の動詞としてみると存在を表す動詞がある。~に~が構文とし存在文とみる。
述語に動詞があるので文構造に動詞を核にもつと捉える。いわば動詞述語であるので、文につき、動詞を述語に持つことから動詞文と呼ぶ。すると日本語の文はどうであるか。
日本語の文をみて述語に基本構造をおくと動詞のほかに形容詞名詞がありこの3つの核がある。動詞と同じように主語述語を文とすると、形容詞述語名詞述語を動詞述語と同様に捉えることになるが、それぞれ形容詞であり名詞であるので主語と述語の関係に動詞としての構造があるかどうか、検討がいる。それは主格と動詞述語の関係に準ずるか。
形容詞述語をみると名詞に が のついた、が格 が形容詞と結びつく。沈む太陽があかい、水のある地球があおい、かがやく星がしろい、これは夜の闇がくらいので黄色に見えるが、この文が成立するなら、それぞれ形容詞が動詞述語の位置にあって形容詞述語となり、日本語ではこの表現も文である。太陽が赤い、地球が青い、星が白い、となる。
この述語は対象としてみる太陽、地球、星のそれぞれが、あかい太陽、あおい地球、しろい星と見えるので、地球が青いと言えるようになったのはつい最近であるが、このことを太陽が赤いこと、地球が青いこと、星が白いこと、というふうに表現した。したがって対象に見える現象を文にしている。が格 の表す意味は述語の対象である。
この表現をまた、対象とその現象の存在を捉えて、太陽が赤いコト 地球が青いコト 星が白いコト ⇒太陽が赤いのよ 地球が青いのよ 星が白いのよ ⇔太陽が赤いのである 地球が青いのである 星が白いのである とみれば、それぞれに存在を示す動詞がある。現代語でとらえる以前は、あかくあり、あおくあり、しろくあり。
名詞述語の文は主語の位置に名詞そして述語に名詞があり結びつく。名詞は 名詞 となるが、名詞述語に、名詞に断定をあらわす だ がつくと、この断定また指定ともとらえ判断を示し、名詞 は 名詞だ となる。名詞に丁寧 です がつくと、話し言葉に使う発話文としてあらわれる。断定存在を加えると、議論をする である という調子である。
名詞述語の文については名詞と名詞を結び付ける は をみると、主語主格の、が格を示さないとする。しかし文表現で、名詞が 名詞です という言い方ができるので、この場合の が格をとらえると、名詞が 名詞である とすると断定存在を示し形容詞述語の文と同じ述語の構造を持つ。日本語文の基本構造に述語の言い方、動詞の要素を分析する。
主語と文の基本構造 日本語の文法について その10
日本語教育用文法で日本語文の基本文型に3文型プラスアルファがあるととらえる。いわく、動詞文、形容詞文、名詞文にプラスして、…wa…ga構文とする。ここに第1の動詞である存在を表す文型を加えて5つにすることがある。これは動詞文である。先のプラスアルファも文末に述語を置くのでその品詞によって3文型のいずれかに入る。
基本文は述語を分類にしている。それは述語動詞に準ずるものとしている。動詞文に形容詞文と名詞文が準ずるとはどういうことか。その分類は説明されることがないが、形容詞がそれだけで言い切りになって述語になることは注意できるのでその言い方があれば、動詞述語でないものがあるということで、文法構造は動詞文でないものがある説明になる。
述語動詞は格に応じて主格、目的格などを名詞の格とする。その基本構造は動詞の種類によって日本語の文にも分析できる。さきの…wa…ga構文は格を含みもつ文型となり、述語に動詞述語だけではない形容詞述語、名詞述語もあるので格の対応が異なり、形式の命名をした文型である。国語では述語に格を見て述格と言ったりする文法学説もある。
日本語教育の導入文型を、N名詞、V動詞、Aj形容詞であらわして、その順序は名詞文から始まる。次いで形容詞用法、形容詞文、存在文、動詞文となる。1 N1wa N2desu。2 Aj N→Nwa/ga Aj desu。3 Pni Nga arimasu/imasu。4 Nga Vmasu。5 …wa…ga 初級の段階で3文型から基本事項をすすめる。Pは場所を示す名詞である。
中級になると表現の文型が導入される。このそれぞれは会話文として、名詞文の文末には ~です 、形容詞文も ~です を用いている。丁寧な言い方から学習をするので動詞文にも ~ます がつく。ここで学習段階における導入の工夫があって丁寧形の動詞と、名詞に ~です を用いることが、存在を表す動詞の文型に準じていることになる。
形容詞文の ~です も同様となるが、この文型には日本語として使われるようになった経緯があって議論があるところである。~です には存在の動詞にあたるとするのは構文に述語動詞の文を置いて考え方を捉えようとするものであるので、必ずしも ~でありますに相当すると分析をしなくてもよい。名詞述語、形容詞述語を現代語文法にすえる。
その場合に形容詞文の主語とするものは、~が格 になるか、名詞文の主語とするものは、~が格 ではなくて、~は とまず置くことから異なる捉え方があることになり、それぞれに日本語文の主語を新たに考えなければならない。名詞文、~は には主題主語、形容詞文、~が主語には対象格主語を捉えるとよいだろう。
主題の議論 日本語の文法について その11
主題を持つ文は、主語主題の文章である。主格で示す文は主語主格の文である。したがって主語は文章にあり文にある。象は耳が大きい という文は、象、耳、大きいよ 象は耳が大きいことだ 象は耳がおおきいです という情報を持つ文章をあらわし、それを端的に感覚として表現したのである。文の構文は、 ~が形容詞述語 と、~は名詞述語 。
これに対して、「『象は鼻が長い』、のように、『主語‐述語』の代わりに『題目‐述部』と捉えるべき文が非常に多いことを考えると、日本語の文にはそもそも主語は必須でないという見方も成り立つ」フリー百科事典ウイキペディアより。とする説明があって、以下、その記述を批判する。この説明の骨子は主語が必要でない見方があるということである。
これについて三上章学説は主語廃止論で主語という文法用語をやめる提案を唱えたと言うが、これは必須要素としてのとらえ方あるいは第1格ではないということの三上学説の主張のようであるので注意がいる。次のような例文を図解している。甲ガ乙ニ丙ヲ紹介シタ という文において重要なのがそれらをまとめる述語の部分であるとするようである。
~ガ ~ニ ~ヲ はすべて述語の補語となる、と言うので、まず補語の概念が広げられてしまっているのはいかがか。英語などの文で主語は述語と人称などの点で呼応し特別の存在であるというのはよいとして、補語がなんであるかを取り違えているように思える。次いで、この考え方に従えば、と、英語式の観点で次の主語の省略という文の説明がある。
ハマチの成長したものをブリという ここでニュースをお伝えします 日一日と暖かくなってきました などは、いわゆる主語のない文である、とする。これを、日本語の文では述語に中心があり、補語を必要に応じて付け足すと考えれば、上記のいずれも、省略のない完全な文と見なして差し支えない、という説明をしているのだが、違うのである。
だれが なにが を読むと次のようになる。ひとびとはハマチが成長したものをぶりだという ここでアナウンサーがニュースをお伝えします 日一日と気候が暖かくなってきました という文情報になる。そう理解していくと、省略した主語を推測して読み込むことができる。例に上がった文は誰が何について述べる情報かを不足に思うだろう。
いま読み込んだ文の情報は、だれがなにをについて、漁師、わたし、気温とすることもできるので、これはやはり必要な情報を読み取ることができない可能性を持つので完全な文ではない。この例文としたものは句のレベルにあると言ってよいだろう。文章があり文がありして、さらに句を考え次に語を捉えることになる、その文法レベルには文節がある。
主題は文章にある 日本語の文法について その12
象は鼻が長い という文は文章の構造を持つ文である。文章の謂いは文が複数あるということ、文を超える日本語の文法単位である。象は~ことです 鼻が長い この二つが組み合わさったととらえるのがよい。*象が鼻が長い となれば二つの主格があって形容詞述語一つに関係するので文としては認められない。象が長い とは言わないだろう。
文章の主題は文章がそれについて述べようとするものである。いくつかの文が連なっているとその文の意味内容はいくつかの文のまとまりとなって文章となり、その文章の内容を脈絡として作り出す。文章から文を切り取ることによってそれを単位として文を見ることになるが、主題主語の表れる文はいわば重文また複文の構造を示すことが多い。
こんにちは と言う挨拶は、いいお天気ですね と続けるなら、気候の話題である。お元気ですか と続けるなら、相手へのご機嫌伺いである。どちらへお出かけですか と続けるなら、具体的に聞こうとしているわけだが、挨拶であるから、ちょっとそこまで 、と応じて言葉のやり取りでおしまいである。今日 と漢字に書かれた けふ の意味がある。
こんにちわ とすれば挨拶語になるようだが、もともと文章の主題主語であるので、今日は と書き出せばそこには主語に応じた述語が表現されるだろう。挨拶であるからその場に応じて、この頃気候の変化が激しいですね と言うように会話があれば文章が成立する。文、文章を文字記録の言語資料とするなら、一方で発話、談話としての分析を会話に行う。
わたしは と名乗りをする場合にも主題主語を持ち出した表現法で、~は の用法に人、ものについて語ることがあるので、主語を意識する。これを、 わたしが と名乗ってもそれは主格主語として現れて、わたしは と表現法が対比される。~がの本来的な用法に、名詞が名詞 と捉えることができるので、おまえが~ を思い合せることになる。
主題主語の文と主格主語の文はそれぞれ文章の単位と文の単位とをその分析に用いることになるので文の意味解釈には異なった内容を見ることができる。形容詞述語にして対象格主語を用いると、あなたは わるい あなたが わるい この二つに表れた意味内容は異なる。主題主語と主格主語となるが、~が~ の結びつきが強くなるだろう。
日本語の文法に文の単位の文法分析と文章の単位の文法があると捉えるのであるが、それは言語としての単位をどう見るかによって連続しあうものであるから、一つ文法でよいだろう。文法単位体の句の構造、語の構造となると文法の分析が語の単位に置かれることになる。その単位は、文章と文、句と語、詞と辞、形態とおよぶ文法となる。
文、文章の構成 日本語の文法について その13
文の基本構造には主語と述語がある。主語には主語として文頭に立って文を統括する働きがある。その主語には、文を分類して述語におく動詞には主格主語、形容詞には対象格主語、名詞には主題主語と捉える。述語は存在を表す第1の動詞があって、その述語動詞が核となっている。動詞は文の要素に応じて文法変容があり、動詞述語を形成する。
文の成分は主語、述語、修飾語、被修飾語、独立語があった。必須なのは述語であるが、そのほかに成分として、独立、接続、並列および補助を考え、いずれも文に応じて分析される。修飾を連体、連用また状況と捉えるものがある。文の要素には主語、述語動詞、目的語、補語などがあげられ、付加語、修飾語、独立語を加える。
文章の成分は文の成分をもとにして複数の文の構造を分析する。文章には文章の構造があるので文法分析における語を持ち、句を持ち、語句に文をふくみ持つ。また文章の中に文章を構造として持つ。文章を単位体として文法に据える場合には文が持つ情報による表現分析に及ぶことがある。語の単位に形態があるように文章を超える単位は資料体である。
文の構成には語の単位を用いる。文を分節すると文節になる。機能言語学による二重分節の考え方を日本語に当てはめると偶然に同じ発音で分節が文節であると気づく。文節は橋本進吉学説で、文をゆっくり読んで切れるときに単位を求め、自立語または自立語に付属するものがくっついたものである。二重分節にまず求められる文節は意味の単位である。
第1次分節は記号素また単語、第2次分節は音素また単音と、その分節は極めて分かりよい。それを日本語に当てはめて分節をつくると、語と音のひとつの単位にそれぞれさらに分けて自立部分と音節が分析できる。表記を入れたとらえ方で二重の分節にさらに分肢を見ることになる。いわば漢字、語、ひらがな、ローマ字による表記によるレベルである。
文の要素を捉えるのは語の単位である。日本語はこれについて、学校文法では文節の考え方をすすめてきた。そのままに語を捉えて主語とし述語としてきたが、自立語と付属のものという語の分析に文節を捉えて、文の部分とした。つまり文における第1次分節は文節であるから、文節がそのままに語となる。語に付属するものは接辞としてとらえるとよい。
主語述語に語の単位を見ると、それは主語または述語の語構成を自立形態とあるいは自立のものと付属するものとしてみることができる。文節はその結合形態であったので、それをそのままに語と考えてよい。文また文章を構成するのは語である。文の構成を成分また要素に分析してみると文のなかで働く役割が語の単位としてとらえられる。
品詞、文節、形態 日本語の文法について その14
文法は言語現象を切り取る。そこに法則を見出す。分析と総合のあいだをいわばいきつもどりつして観察が行われる。文法単位体は文法分析に視点を与える。文法論はそのスタートにどの単位体を視点にするかでその分析の立場が決まってくる。日本語は文法のいくつかを文法論として作り上げてきた。古典語で古漢語、現代語で近英語を学んできた。
橋本進吉学説は音声を観察し、国語音韻による文法論を視点に詞辞の大別を立場に作り上げた。学校文法の品詞は橋本文法論の考え方を多く取り入れ文節を国語の単位に与えた。その品詞は一方で話部であったのだが、それを分節としてみたときに、文節の単位で見て取れる国語に適した分析であった。品詞は文節相当に捉えるとよいとしたのである。
いま品詞は自立語と付属語に同じ詞の名称を持つ。国語の助詞、助動詞という名前が学校教育で普及している。自立語の名詞と付属語の助詞を同じ品詞レベルでとらえるのは考え方の基本を取り違えると、が、を、に といった文法的に機能する付属語を単語として扱って、自立語と付属語の語としての混同が起こって考え方の説明ができなくなる。
自立語と言い、付属語と言う、わかりやすい分類はそれはそれで新たに説明のための言葉であったのであるが、詞と辞としての分類をほどこすところを考え方から変えてしまうのである。自立詞とか、付属辞とか名前を付けていれば詞辞の2大別を学んできた伝統を継承したであろう。品詞分類における考え方を名称によってしわけるのがよい。
品詞は話を音声でとらえて息継ぎ、休止、強弱などで切ったときの話の部分である。つまり日本語でいえば、自立詞と付属辞が分析されてそれを品詞にするかどうかはそれぞれの意味情報や文法機能によって厳密を期せばその文また文章における構成要素としては同一視すべきではなかったのである。テニヲハとした分類はそれなりに継承すべきであった。
それを文節として文を構成する最小単位としたのは炯眼である。つまり品詞と言うのは文節である。なかなか分かりにくいが、わたしが わたしに わたしの と言うのは、わたし と言う名詞であると抽象しているのであるから、この文節の単位のままに、わたしガ わたしニ わたしヲ と名詞 わたし における変容を見るとわかりよかったのである。
このとらえ方は文法を形態論の視点で進めると、自立形式と付属形式の結合態による形態の分析で説明できることになる。国語文法の文節が言語研究の品詞で日本語教育用の文法で形態の分析となる。それぞれの立場を混同してはならないが、漢語文法を取り入れ漢文訓読として日本語をとらえてきたその背景には脈々と詞と辞としての見方がある。
文章にあるもの 日本語の文法について その15
文章に主題主語があり、文に主格主語がある。さらに句にも主語があるという句構成をみると、文章にはいくつもの主語に相当するものがあり、文に複数の主語を持つとするのは、文章が文の組み合わさったものあり、文がほかの文と関係してその文を作り出しているからである。文が複数から成り立てばいくつも含まれる主語が文の数に応じて認められる。
言語の現象は複雑であり、語句、文、文章と抽出する。それは文の単位に論理性が捉えられて主語と述語動詞を主要な構成要素とする。それはまた述語動詞に従う目的語、補語のほかに語と語との関係で句あるいは節ができるとする捉え方である。文の主語を必須とすれば文の単位を基本構造として文法の構成を分析することが可能である。
文に必須である主語をその文にもたない、ほかの文との関係で主語を示す文があり、それが文章に示される構造と捉えられるのが日本語の言語表現である。文に主語が必須であるという規定は文の成立を主語の有無に置く基本構造がある。文の成立をその基本である主語に置くことは言語現象の帰納によるからであるから、その言語の特徴である。
主語は文の必須要素でない、文は主語を持たずに成立する場合があると規定をすればその主語がないままに文情報を読み取るかと言えば必ずしもそうではなくて、その表現に主語の相当のものを解釈することになるが、それはほかの文との関係でいくつかの文のうちに主語をもとめる。主語を求めその主語はそれは複数の文を連ねた文章のうちにある。
文章に主語を求め、文に主語を認め、語句にその主語を特定することができる。いいかえれば文を単位にして言語の表現理解において主語があるということである。この日本語の構造は語と語とを連ねて句とし、その語には言語主体による表出があったのであるが、それに加えて句が文を構成する考え方のもとに文に主語を規定するようになったのである。
日本語の現象には言語主体とする言語の表出者と言語の文における主語とが重なり合って表現に対比されることがないことがある。言語を思想や意志、意見の表出とその機能を捉えるうえで、一方で日本語は感情を表現とするという考え方が行われてきている。どの言語も感情を表現できるがそれを感情表出としての手段に心情の吐露としてみる。
嘆きを嘆きのままに言語表現とするというのは伝統の日本文学の表現にある歌の技巧である。これを文学作用の分野に分析をして言語をそこから抽象しようとしてきた経緯があるので、このとらえ方は表現の用法において文を分析する際にも行われてきている。すなわち主格主語が捉えられ分析される前の文法現象である主題主語の句と文章に象徴される。
語にあるもの 日本語の文法について その16
文法のレベルを捉える。宮地裕学説による文法単位体の視点から文章、文、節、句、語、モーフを設定する。そのうちモーフであるmorphは形態分析になる。日本語教育用文法の立場にモーフの分析は有効である。すなわち音素レベルのとらえ方である。すると語は
音節レベルのとらえ方であることがわかる。語は言語記号であり、意味の単位である。
日本語文法は単位語に品詞を分析してきた。国語教育用文法の立場では品詞論と構文論のとらえ方で整理してきた考え方に自立語、付属語の二大別があり、品詞として付属する語を助詞、助動詞といている。この分類と名称は語をわけてそれぞれを語とし詞としたものであるが、それまでの詞と辞の二大別を継承する考え方で、いわば自立詞、付属辞である。
語は単位に抽出されると種類に分けられる。品詞分類である。品詞というのは翻訳語として成立している。parts of speechは話部であった。それはまた文を切ったときに分けるわけ方でいえば橋本学説の文節である。語は品詞としてみれば文節が相当する。文節の自立して意味をあらわす部分を取れば、付属する部分と分けられる。それは語の構成である。
文法上の職能に単語の区分けをして品詞に分類して説明する。国語教育では名詞、代名詞、動詞、形容詞、形容動詞、連体詞、副詞、接続詞、感動詞、助動詞、助詞、11品詞にしている。品詞論は日本語の品詞に形容動詞をどう見るか、数詞があるか、それはまた形容詞であるか、助数をつけて名詞であるか、助詞助動詞の文法機能についてなどの議論である。
文法は文に分析される機能を捉える、すなわち職能を見ることになるので、付属辞は自立詞と共に働く文節に捉えられたように、品詞に文法職能を付与するものである。語にある自立しない部分としては品詞にならないのが付属辞である。形態分析をすれば自立形式に対する結合形式である。日本語の文法でこの付属辞は文だけでなく文章にも機能している。
品詞は職能を見ると主語と述語をまず捉えることになる。その主語また述語に修飾語を分析し連体と連用の修飾関係を考えるか、述語動詞との関係で主格の語を分析し目的の語を捉えて文の中で語の支配による文型を考えるか、さらには主題の語を捉えて述語を詳しく表現する状況の語をとらえるかなどを、文情報の意味を担う語の単位体に見ることになる。
品詞の名称は翻訳された語でとらえると助動詞の分類としてのものと翻訳できないテニヲハのとらえ方で議論を残してきたのである。語構成要素に見る語の論を語と語との関係で見る語句の論を必要とする。それは句の論をみて伝統的な日本語のとらえ方にあったのであるが、詞と辞の考え方のまま、漢語文法にのみとどめられた訓読語法に押しやられた。
文典、文法書 日本語の文法について その17
詞と辞は漢文訓読の語法の影響を受けている。単語と品詞は近代英語の翻訳によって捉えられた。文と文節は日本語の言葉にふさわしく分析された。言語の現象のままにさまざまに視点を持ち漢語を取り入れ英語を学び続けている日本語文法である。形態論は統語論とともに文法として日本語学習の立場を見せた。漢語、英語、国語そして日本語学である。
伝統文法は国語分析に品詞分類をすすめて規範とした。文典と呼ばれた文法書は文法分析に軌跡を持つ。広日本文典、広日本文典別記はその後の口語法とその別記とあわせて日本語文法の考え方を近代において作り上げている。それ以前、さかのぼって17世紀初めにはロドリゲスの日本文典が書かれ、その日本大文典はポルトガル語による記述である。
文典に文法があると説明をするときそれは文法を記述する書であって厳密な文法学説の理論書との違いがあるが、文典の価値は規範に与えた考え方において重要なものである。文典にはさらに新文典および新文典別記が著わされ、その一方で日本新文典のように形容動詞を分類するものがあった。1921年至文堂刊、藤村作, 島津久基の名前が並ぶ。
文典を検索すると日本俗語文典がある。中国留学生教育に寄与し国語学国文学研究の足跡を残した松下大三郎の著述だ。日本俗語文典、1901年は初めて体系的に口語文法を説いたとされる。ほかに標準日本文法、標準日本口語法、標準漢文法などの著作にみるべきものが多い。断句、詞、原辞の捉え方は詞辞の視点にあり、形態文法の先駆けを内容とする。
このようにみて文典には文法記述があってそれぞれに特徴がある。21世紀初頭の動きとして1902年、明治35年に国語に関する調査、国語調査委員会が文部大臣の直属機関として活動した。成果を上げ、送仮名法、口語法、疑問仮名遣などを編纂したが、それはⅠ913年、大正2年に廃止となる。国語国字問題解決の目的を持っていたとされる。
国語の音韻、方言、国語史調査を行い国語学の基礎ともなっている。このころから国語文法に記述説明書が作られてそれまでの翻訳による文法から独自性を持った日本語文法のいわば整理期に入るとみられる。自立語付属語と言われる分類に当初は自立ではなくて独立語という名称がありそれを踏まえた独立詞付属辞という分類もなされていたのである。
文法の視点と立場はその拠って来る理論志向に正しくみれば専門の術語としての使用混同は避けられなければならない。それぞれの規定を受けて言語現象をその用語で解釈するので融通されるものではないが、日本語文法はその多くを取り入れ学びながら、その理論的な構築を果たした。現代日本語文典の必要とされるところ、しばらく彼我を述べてみたい。
体用 日本文語の文法について その18
文典は文法の体系を解説する。その記述は品詞論のレベルで構文論には及ぶことが少ない。構文の原理が文にありその単位文の終止は外形的に決められた。すなわち述語に置かれる品詞の終止形によって帰納された。文とは何かと言えば日本語は文末終止また終わる詞の機能を抽出して規定されている。いわば主語と述語が文として働くための句点で終わる。
実は日本語にある文としての単位は句によってあらわされる。その句構造は文構造に包含されるものである。さきに文が終わるための句点を機能としてとらえたのであるが、それが文の終止であるなら、句読点は句としての休止終止でもあった。単位文に主語述語を規定すると一文の終わりはその単位の終わりに句を持ち、それで句点と言うことになる。
文法は語法であり句法でもある。文法の文について分析をすると句が析出する。その句にあったのは体と用のことである。体言用言として語句の分類に用いられてさらに品詞類を分けるようになった。そもそもは句構造を示す原理であった。ただその論理が言語の現象と所作の解明にあって文法の抽象を得ることがなかったので名称が文法では引き継がれた。
体用は、たいよう、たいゆう、である。その説明を見ると、デジタル大辞泉の解説では、
たい‐ゆう 【体▽用】1 本体とその作用。たいよう、2 連歌・俳諧で、山・水辺・居所に関する語を分類して、その本体となる「峰」「海」などを体、その作用・属性を表す「滝」「浪」などを用としたこと、3 能楽で、基本的な芸と、そこから生じる風趣、と解説する。
たい‐よう【体用】1 文法で、体言と用言。2 ⇒たいゆう(体用)、と見える。また、詳しくする世界大百科事典 第2版の解説【体用 tǐ yòng】では、中国の哲学・思想・レトリック運用のための概念範疇と見えて、少し明らかにされるところ、それを論理と理解することが少ないのは、わたしたちにとっての言語がそのままに当てはめられるからであろう。
解説は、その基本形式は〈甲は丙の体,乙は丙の用〉または〈甲は乙の体,乙は甲の用〉つまり〈甲は体なり、乙は用なり〉という風に体用が対挙されることである、因果概念がたとえば風と波の関係をいうのに対して、体用は水と波の関係を示す。しばしば実体とその作用(または現象)と解される、として、やはりわかりにくい体用の説明である。
この解説がどこまでのものかが疑問であるのは、次のように結ぶからである。いわく、もっとゆるやかに〈体とは根本的なもの、第一次的なもの、用とは従属的なもの、二次的なもの〉としておく方がよい、というわけで、日本語文法に取り入れたこの概念はさかのぼれば古代インドの哲学にも及びそうである。向後の究明さるべき課題、体用のことである。
語句 日本文語の文法について その19
語句の構造は日本語文法のポイントである。語の構造は語構成にある。句の構成は句法にあった。が、そのそれぞれが関係しあうことはなかった。句法は文法にひとしくさらに分析が必要とする。いまだ日本語は句の構造が捉えられない。その構造には、語、句、文と共有する文法に統一した原理がなければならないのであるが、語と文では異なるのである。
理由は語の構成にある。日本語は古代漢語を取り入れ熟語とした。その後は漢字語として漢語のままに単語としてきた。その語には熟合した文字の組み合わせがあり熟語が文法の構造を持っているので、漢字語彙として日本語と異なる構成を見ることになる。熟語は名詞として扱われその意味を用いてきた。熟語が熟語であるのは漢語文法があるからである。
文字としての言葉、漢字を入れて漢語とした。その漢語はもともと日本語の語順にない構造を持っている。漢字を読むときに日本語音として漢字語彙にする。その漢語は古代の漢文法を持つ。そのために漢字を日本語読みにして、つまり訓読みをして言葉として理解している。危険は危なくて険しい、投球は球を投げる、あるいは、なげる、たま、となる。
その語の構造のままに文に働くのは名詞としての機能であるので、日本語文は漢語構成に日本語構造を持つという二重になっている。その漢字語と漢字語が日本語文法の関係構成で結びついている。交流文化は交流する文化と読みながら、その一方で、文化を交流するととらえている。文化交流は文化が交流するとなるのであるが、文化の交流とするだろう。
だから、交流文化を進めようと言うばあいと、文化交流を進めようと言のとでは、その句の構造がそれぞれに文法構造を持つ。意味内容の異なりを感じることもあるだろう。文化を交流することと、文化の交流すなわち文化が交流することとはその表現の主語と主体にかかわることとしてそれぞれが理解されることになるから、それを聞きわけることがある。
この句の構造に語の構成をみるか、文の構造を見るかということで、日本語の言い方が文法的に理解される。そこには文を成立させる要素がかかわることになる。語句の構造には文となるべき言い方が解釈されるから、句が関係しあって構成する語句は複雑に絡み合うことになる。そのままに漢字語を使っている日本語として理解するのである。
日本語は漢字熟語に漢語の文法を持っているので、それを捉えて、それに加えて、現代文の構造に英語の文法を解析しようとしてきた経緯がある。語句の構造に漢語と日本語をとりあわせた関係構成を見て取るので、句の構造を解明することによって語の構成と文の構造とを見ることになり、語句、慣用句、従属句のなんであるかを分析する必要がある。
~に~が 日本語の文法について その5
日本語文法の文は述語を捉えて分類する。述語にある品詞を見る。文に動詞がある。その動詞の第1は存在を表す。その存在にはわたしたちはそこにとどまることで意識している。すなわちじっとしているものか、動いているものか、動くものであっても、そこにとどまって動かないでいるものかどうか、そのいずれかを捉える。有るかないか、居るかどうか。
それがまずとらえられて文となるが、そのときに、日本語は空間のとらえ方を表現して、場所を示すことから文が始まっていると考える。文頭にそれを示している言い方である、~に という言い方である。このとらえ方が文の表現にまずあると説明できるが、これはいわば意識する最初の認識であるからふつうに表現されていてそれで文を言う。
この場所すなわち空間の認識があるかどうかは、~に という言い方はまた時間の認識でもあるので、空間と時間を位置としてまず認めているということである。場所として空間の位置を捉える言い方が目前のことを捉えるのにわかりやすいのでそれを示して、~に については動詞の第1と関係して結びつく。~にある また、~にいる となる。
古文の学習で経験することであるが、むかし、おとこありけり という表現で始まる物語があり、それを素朴なとらえ方の、昔、男があった、つまり、いたというふうに理解して時間を位置として捉えた。どこにいたのかとなるが、伊勢に男あり、とでもなるので、それを題名にして伊勢の物語とした。また、大和の地であろうか、類似の物語もあった。
第1の動詞とするのはこの文はものの存在を表すからである。古文の例は日本語としてはおよそ1000年をさかのぼるので、その時から長い使い方を経て当代のこととしてその分析をするが、いまはむかし、竹取の翁といふもの有りけり というように、ものの存在がまずあるという認識であって、これは言語の表現においてはもののとらえ方の基盤となる。
その存在についていまのわたしたちは、ある と、いる を使い分けている。そこに動かないものを、ある と言い、動いているものがそこにとどまるものを、いる と言う。漢字を書くと、有る居るとすることができる。この動詞の意味との結びつきでものには生き物の区別や動く物の区別をしていたことがあったのである。
~に~がある ~に~がいる この言い分けは動詞を捉えて表現する。あり、をり、はべり、いまそがり などを存在を表すとしたとらえ方は、現代語ではその語のそれぞれの消長で、現代語では、あります います となって、この文の表す意味内容から存在文また存現文と呼ぶ。その後の日本語の分析に位置のとらえ方を重視すべきである。
主語を示す 日本語の文法について その6
文法用語に主語を用い、加えて主題、主格という。文に主語があるという説明から文にある主格が主語であると言われ、主格はどうか、日本語ではわかりにくい。主格は語にあるとするのがよいが、日本語の膠着語の現象のため説明が行われなくなったようである。それに話題、題目と言った主題があるということになると、その主題はどうかとなってくる。
主語を文の要素とするとらえ方は語の自立を見る。語の構成とそれに格変化を含める自立性についてみると、日本語の主語の要素に語形変化がないとすることになる。国語の規定では、語形変化をしない、主語になることがある、これが品詞分類でとらえる名詞である。主格が語にあるかどうかは第1の格を名詞の語形変化に求めたとらえ方である。
主語を文に規定する、主格を語に規定する、主題は何に規定するか、それは文章にとなれば日本語文法は考えやすくなる。ただ文法は文の単位を規定するものとしての考え方が長く行われてきたので、文についての文法にさらに文章についての文法論議が必要である。とすると語についての文法があるかとなるとそれは語法というとらえ方もしてきた。
文法は語法であり句法であり文章法である。その違いは文を捉えての文法の考え方が出来る前には語法と句法がおこなわれ文章法もまたあったのであるが法則のとらえ方のそれぞれをあきらかにするためにも言語に統一した考え方を定義して文法としてきた経緯がある。
主語述語を捉えるのはその文法にあるのは当然で日本語にあてはまる。
国語では文の主語をはじめ述語修飾語独立語の4つを文の成分とした。修飾語は被修飾語を要するのでそれを加えることもできる。文の成分というとらえ方は要素と同じようなとらえ方だと考えてよいが要素成分だとすると述語は述語動詞また動詞だけでよい。すると国語の修飾語を名詞にみて文の要素として目的語としたり補語としたりすることがある。
主格については国語の膠着語としての現象を見るので格助詞が分出してその分析を受けてが格といったりする。これは日本語学習者に語形を明示して ~が の付くものを動詞との対応で説明する。その名詞が文の主語となるときである。~に~が存在文となって表わされるときが主語の要素としてわかりよい。
文の要素 - Mt. English Project mep.papiko.com/index.php? 文の要素
主部の中の主語(S)/述部の中の動詞(V)/目的語(O)/補語(C)を、文を構成する主な要素として文の要素(Elements of a Sentence)と呼ぶ。 どの語句がどの文の要素になるかは、その語句が果たす品詞的役割によって決定する。
必須要素の主語 日本語の文法について その7
日本語文法の考え方には日本語にある現象に即してさまざまとらえられて説明が行われてきている。日本語の主語は文にとらえられた。その主語は文の要素であり、主語は述語動詞に対応するので、述語または動詞とする考え方である。主語と動詞の関係で見るのがよい。すると主語は文頭に置かれて動詞との関係または場合を見ることで、格を持つ。
いわば主語主格と動詞の関係で文における主語ということが規定されているのである。動詞が主語にあたる名詞と関係するのはこの名詞が主格で述語にある動詞とのあいだで、主語主格名詞プラス述語動詞の順序で成立する考え方である。主語がなければ動詞が述語として成り立たない考え方であるから、主語を説明する場合に必須のものと考える。
主格は述語動詞と関係してその第1にあたる格を示しているととらえるとその格を示す形があると考える。名詞が語形変化をすることによってその形また形式を表す。それは名詞が変化形を持つ場合にほかの変化の形また形式と異なる。日本語は名詞がそれ自身で変化形を作らないので、~が という形をくっつけて、わたしが というのを主格とみる。
主語主格は、わたし について、わたしが となる。つくえ について、つくえが となる。わたしが います つくえが あります という文を作るが、述語動詞の いる ある に関係して、います あります と言う丁寧な表現となる。日本語はこの表現を述語動詞との関係でまず、これを存在文としてきたが、~に~が動詞構文として分析する。
しかし存在文は語の順序、構成する要素をとらえて、例文 机の上に本があります とみると、場所を示す名詞のあとに主語主格を表す名詞がくる順序としてとらえ、文のはじまりは存在を示す場所があり、主語に対する動詞は ある で示される。存在文というのはこの例文の形式であり、この文にはことばの現象を日本語文法としてとらえることになる。
英語でとらえるTHERE構文との対象で考えると日本語の存在の表し方はまず主語となるものが表わされていることになるので特徴的である。ものの存在をまず認めるなり名称として名付けを行うなりその存在を言い出すなりしてとらえる日本語ではものの名が既に与えられていた。必須要素がない英語の文の場合に語とものの認識に順序があったのである。
存在文に必須要素である主語があるかないかについての議論は存現文として中国語にその現象がありそれは英語と同様に動詞のあとに主語に相当する語が表現される。存在文には、在 を用いて、有 を用いる存現文とはさらに現象を捉える考え方が文の表現に表れている。中国語の影響は文の構造によるよりも熟語の取り入れ方の場合に日本語に見られる。
存在文 日本語の文法について その8
日本語の存在文は場所を示す名詞を に とともに文頭に置き、動詞 ある を文末において結んでいる。場所は空間の位置を捉える一方で時間の位置を捉えて同じように時間を示すこともできる。そして主語主格の名詞として が とともに用いると、~に~が動詞ある 文になる。これは現代中国語の存現文の用法にみる語順と主語の位置が異なる。
~に~が動詞の文について、名詞が を、名詞は にすると、文頭に位置して、~は~にある とすることができて、この 名詞は に主語を捉えることになる。語順を変えた文と、語順を変えない文では、それぞれ情報が同じでもその意味内容が異なる。すなわち ~に~が動詞 ~は~に動詞 において文情報の意味のちがいが生まれるのである。
この 名詞は の出現を、名詞が の出現する関係とで見ると次のようである。~は~にある ~には~がある となり、このそれぞれは文情報が異なるとわたしたちはとらえている。つまり、 ~に~がある ⇔ (その)~は~にある となる。教室に机がある ⇒ (その)机は教室にある となる。
表現すると、机はどこにある と言い出すと、机は教室にある となることが多いので、主語としても捉えることができて、これを主語主格と比べると主語主題とみることができる。本来的には、まず机があり、机が教室にある となるのであるが、この存在を表す文は主語主格が文頭に立つ前に場所の名詞が捉えられる。空間認識、ものへの順である。
日本語の表現に、~がある ~はある という二つの言い方があり、語の順序としてみると、~に~がある と言い、また、~は~にある と言えるのは、~には~がある と言うこと、~には~はある と言うことがでて、*~がは *~はが と言うことはできないからである。~は の表現内容に、~が の働きをふくみもつとみる。
存在文の文頭に、名詞が を置いて語順を変えて言うことは日本語では可能である。それはおそらく、この言い方には、有り なに 人 、それで、人 あり どこに 伊勢の国 伊勢に 人 あり というふうに捉えていたから、それをまた、 人 伊勢にあり というふうに言うこともできたからである。人 を取りたてて、人は伊勢にあり。
日本語は中国語の漢字を取り入れて言葉にした。語順については熟語のままに受け入れている。日本語の漢字による熟語を作り出すこともあった。主語をあとに置く語には、日常の漢字熟語の中に、 開花 降雨 積雪 出火 出血 停電 発芽 満潮 有人 立春 少量 多数 难题 無害 いずれも存現文の語順としてみることのできる熟語である。
日本語の文 日本語文法について その9
主語述語を文とするのは動詞を述語に置く場合の構文である。そのときに主格が現れる。それを第1の動詞としてみると存在を表す動詞がある。~に~が構文とし存在文とみる。
述語に動詞があるので文構造に動詞を核にもつと捉える。いわば動詞述語であるので、文につき、動詞を述語に持つことから動詞文と呼ぶ。すると日本語の文はどうであるか。
日本語の文をみて述語に基本構造をおくと動詞のほかに形容詞名詞がありこの3つの核がある。動詞と同じように主語述語を文とすると、形容詞述語名詞述語を動詞述語と同様に捉えることになるが、それぞれ形容詞であり名詞であるので主語と述語の関係に動詞としての構造があるかどうか、検討がいる。それは主格と動詞述語の関係に準ずるか。
形容詞述語をみると名詞に が のついた、が格 が形容詞と結びつく。沈む太陽があかい、水のある地球があおい、かがやく星がしろい、これは夜の闇がくらいので黄色に見えるが、この文が成立するなら、それぞれ形容詞が動詞述語の位置にあって形容詞述語となり、日本語ではこの表現も文である。太陽が赤い、地球が青い、星が白い、となる。
この述語は対象としてみる太陽、地球、星のそれぞれが、あかい太陽、あおい地球、しろい星と見えるので、地球が青いと言えるようになったのはつい最近であるが、このことを太陽が赤いこと、地球が青いこと、星が白いこと、というふうに表現した。したがって対象に見える現象を文にしている。が格 の表す意味は述語の対象である。
この表現をまた、対象とその現象の存在を捉えて、太陽が赤いコト 地球が青いコト 星が白いコト ⇒太陽が赤いのよ 地球が青いのよ 星が白いのよ ⇔太陽が赤いのである 地球が青いのである 星が白いのである とみれば、それぞれに存在を示す動詞がある。現代語でとらえる以前は、あかくあり、あおくあり、しろくあり。
名詞述語の文は主語の位置に名詞そして述語に名詞があり結びつく。名詞は 名詞 となるが、名詞述語に、名詞に断定をあらわす だ がつくと、この断定また指定ともとらえ判断を示し、名詞 は 名詞だ となる。名詞に丁寧 です がつくと、話し言葉に使う発話文としてあらわれる。断定存在を加えると、議論をする である という調子である。
名詞述語の文については名詞と名詞を結び付ける は をみると、主語主格の、が格を示さないとする。しかし文表現で、名詞が 名詞です という言い方ができるので、この場合の が格をとらえると、名詞が 名詞である とすると断定存在を示し形容詞述語の文と同じ述語の構造を持つ。日本語文の基本構造に述語の言い方、動詞の要素を分析する。
主語と文の基本構造 日本語の文法について その10
日本語教育用文法で日本語文の基本文型に3文型プラスアルファがあるととらえる。いわく、動詞文、形容詞文、名詞文にプラスして、…wa…ga構文とする。ここに第1の動詞である存在を表す文型を加えて5つにすることがある。これは動詞文である。先のプラスアルファも文末に述語を置くのでその品詞によって3文型のいずれかに入る。
基本文は述語を分類にしている。それは述語動詞に準ずるものとしている。動詞文に形容詞文と名詞文が準ずるとはどういうことか。その分類は説明されることがないが、形容詞がそれだけで言い切りになって述語になることは注意できるのでその言い方があれば、動詞述語でないものがあるということで、文法構造は動詞文でないものがある説明になる。
述語動詞は格に応じて主格、目的格などを名詞の格とする。その基本構造は動詞の種類によって日本語の文にも分析できる。さきの…wa…ga構文は格を含みもつ文型となり、述語に動詞述語だけではない形容詞述語、名詞述語もあるので格の対応が異なり、形式の命名をした文型である。国語では述語に格を見て述格と言ったりする文法学説もある。
日本語教育の導入文型を、N名詞、V動詞、Aj形容詞であらわして、その順序は名詞文から始まる。次いで形容詞用法、形容詞文、存在文、動詞文となる。1 N1wa N2desu。2 Aj N→Nwa/ga Aj desu。3 Pni Nga arimasu/imasu。4 Nga Vmasu。5 …wa…ga 初級の段階で3文型から基本事項をすすめる。Pは場所を示す名詞である。
中級になると表現の文型が導入される。このそれぞれは会話文として、名詞文の文末には ~です 、形容詞文も ~です を用いている。丁寧な言い方から学習をするので動詞文にも ~ます がつく。ここで学習段階における導入の工夫があって丁寧形の動詞と、名詞に ~です を用いることが、存在を表す動詞の文型に準じていることになる。
形容詞文の ~です も同様となるが、この文型には日本語として使われるようになった経緯があって議論があるところである。~です には存在の動詞にあたるとするのは構文に述語動詞の文を置いて考え方を捉えようとするものであるので、必ずしも ~でありますに相当すると分析をしなくてもよい。名詞述語、形容詞述語を現代語文法にすえる。
その場合に形容詞文の主語とするものは、~が格 になるか、名詞文の主語とするものは、~が格 ではなくて、~は とまず置くことから異なる捉え方があることになり、それぞれに日本語文の主語を新たに考えなければならない。名詞文、~は には主題主語、形容詞文、~が主語には対象格主語を捉えるとよいだろう。
主題の議論 日本語の文法について その11
主題を持つ文は、主語主題の文章である。主格で示す文は主語主格の文である。したがって主語は文章にあり文にある。象は耳が大きい という文は、象、耳、大きいよ 象は耳が大きいことだ 象は耳がおおきいです という情報を持つ文章をあらわし、それを端的に感覚として表現したのである。文の構文は、 ~が形容詞述語 と、~は名詞述語 。
これに対して、「『象は鼻が長い』、のように、『主語‐述語』の代わりに『題目‐述部』と捉えるべき文が非常に多いことを考えると、日本語の文にはそもそも主語は必須でないという見方も成り立つ」フリー百科事典ウイキペディアより。とする説明があって、以下、その記述を批判する。この説明の骨子は主語が必要でない見方があるということである。
これについて三上章学説は主語廃止論で主語という文法用語をやめる提案を唱えたと言うが、これは必須要素としてのとらえ方あるいは第1格ではないということの三上学説の主張のようであるので注意がいる。次のような例文を図解している。甲ガ乙ニ丙ヲ紹介シタ という文において重要なのがそれらをまとめる述語の部分であるとするようである。
~ガ ~ニ ~ヲ はすべて述語の補語となる、と言うので、まず補語の概念が広げられてしまっているのはいかがか。英語などの文で主語は述語と人称などの点で呼応し特別の存在であるというのはよいとして、補語がなんであるかを取り違えているように思える。次いで、この考え方に従えば、と、英語式の観点で次の主語の省略という文の説明がある。
ハマチの成長したものをブリという ここでニュースをお伝えします 日一日と暖かくなってきました などは、いわゆる主語のない文である、とする。これを、日本語の文では述語に中心があり、補語を必要に応じて付け足すと考えれば、上記のいずれも、省略のない完全な文と見なして差し支えない、という説明をしているのだが、違うのである。
だれが なにが を読むと次のようになる。ひとびとはハマチが成長したものをぶりだという ここでアナウンサーがニュースをお伝えします 日一日と気候が暖かくなってきました という文情報になる。そう理解していくと、省略した主語を推測して読み込むことができる。例に上がった文は誰が何について述べる情報かを不足に思うだろう。
いま読み込んだ文の情報は、だれがなにをについて、漁師、わたし、気温とすることもできるので、これはやはり必要な情報を読み取ることができない可能性を持つので完全な文ではない。この例文としたものは句のレベルにあると言ってよいだろう。文章があり文がありして、さらに句を考え次に語を捉えることになる、その文法レベルには文節がある。
主題は文章にある 日本語の文法について その12
象は鼻が長い という文は文章の構造を持つ文である。文章の謂いは文が複数あるということ、文を超える日本語の文法単位である。象は~ことです 鼻が長い この二つが組み合わさったととらえるのがよい。*象が鼻が長い となれば二つの主格があって形容詞述語一つに関係するので文としては認められない。象が長い とは言わないだろう。
文章の主題は文章がそれについて述べようとするものである。いくつかの文が連なっているとその文の意味内容はいくつかの文のまとまりとなって文章となり、その文章の内容を脈絡として作り出す。文章から文を切り取ることによってそれを単位として文を見ることになるが、主題主語の表れる文はいわば重文また複文の構造を示すことが多い。
こんにちは と言う挨拶は、いいお天気ですね と続けるなら、気候の話題である。お元気ですか と続けるなら、相手へのご機嫌伺いである。どちらへお出かけですか と続けるなら、具体的に聞こうとしているわけだが、挨拶であるから、ちょっとそこまで 、と応じて言葉のやり取りでおしまいである。今日 と漢字に書かれた けふ の意味がある。
こんにちわ とすれば挨拶語になるようだが、もともと文章の主題主語であるので、今日は と書き出せばそこには主語に応じた述語が表現されるだろう。挨拶であるからその場に応じて、この頃気候の変化が激しいですね と言うように会話があれば文章が成立する。文、文章を文字記録の言語資料とするなら、一方で発話、談話としての分析を会話に行う。
わたしは と名乗りをする場合にも主題主語を持ち出した表現法で、~は の用法に人、ものについて語ることがあるので、主語を意識する。これを、 わたしが と名乗ってもそれは主格主語として現れて、わたしは と表現法が対比される。~がの本来的な用法に、名詞が名詞 と捉えることができるので、おまえが~ を思い合せることになる。
主題主語の文と主格主語の文はそれぞれ文章の単位と文の単位とをその分析に用いることになるので文の意味解釈には異なった内容を見ることができる。形容詞述語にして対象格主語を用いると、あなたは わるい あなたが わるい この二つに表れた意味内容は異なる。主題主語と主格主語となるが、~が~ の結びつきが強くなるだろう。
日本語の文法に文の単位の文法分析と文章の単位の文法があると捉えるのであるが、それは言語としての単位をどう見るかによって連続しあうものであるから、一つ文法でよいだろう。文法単位体の句の構造、語の構造となると文法の分析が語の単位に置かれることになる。その単位は、文章と文、句と語、詞と辞、形態とおよぶ文法となる。
文、文章の構成 日本語の文法について その13
文の基本構造には主語と述語がある。主語には主語として文頭に立って文を統括する働きがある。その主語には、文を分類して述語におく動詞には主格主語、形容詞には対象格主語、名詞には主題主語と捉える。述語は存在を表す第1の動詞があって、その述語動詞が核となっている。動詞は文の要素に応じて文法変容があり、動詞述語を形成する。
文の成分は主語、述語、修飾語、被修飾語、独立語があった。必須なのは述語であるが、そのほかに成分として、独立、接続、並列および補助を考え、いずれも文に応じて分析される。修飾を連体、連用また状況と捉えるものがある。文の要素には主語、述語動詞、目的語、補語などがあげられ、付加語、修飾語、独立語を加える。
文章の成分は文の成分をもとにして複数の文の構造を分析する。文章には文章の構造があるので文法分析における語を持ち、句を持ち、語句に文をふくみ持つ。また文章の中に文章を構造として持つ。文章を単位体として文法に据える場合には文が持つ情報による表現分析に及ぶことがある。語の単位に形態があるように文章を超える単位は資料体である。
文の構成には語の単位を用いる。文を分節すると文節になる。機能言語学による二重分節の考え方を日本語に当てはめると偶然に同じ発音で分節が文節であると気づく。文節は橋本進吉学説で、文をゆっくり読んで切れるときに単位を求め、自立語または自立語に付属するものがくっついたものである。二重分節にまず求められる文節は意味の単位である。
第1次分節は記号素また単語、第2次分節は音素また単音と、その分節は極めて分かりよい。それを日本語に当てはめて分節をつくると、語と音のひとつの単位にそれぞれさらに分けて自立部分と音節が分析できる。表記を入れたとらえ方で二重の分節にさらに分肢を見ることになる。いわば漢字、語、ひらがな、ローマ字による表記によるレベルである。
文の要素を捉えるのは語の単位である。日本語はこれについて、学校文法では文節の考え方をすすめてきた。そのままに語を捉えて主語とし述語としてきたが、自立語と付属のものという語の分析に文節を捉えて、文の部分とした。つまり文における第1次分節は文節であるから、文節がそのままに語となる。語に付属するものは接辞としてとらえるとよい。
主語述語に語の単位を見ると、それは主語または述語の語構成を自立形態とあるいは自立のものと付属するものとしてみることができる。文節はその結合形態であったので、それをそのままに語と考えてよい。文また文章を構成するのは語である。文の構成を成分また要素に分析してみると文のなかで働く役割が語の単位としてとらえられる。
品詞、文節、形態 日本語の文法について その14
文法は言語現象を切り取る。そこに法則を見出す。分析と総合のあいだをいわばいきつもどりつして観察が行われる。文法単位体は文法分析に視点を与える。文法論はそのスタートにどの単位体を視点にするかでその分析の立場が決まってくる。日本語は文法のいくつかを文法論として作り上げてきた。古典語で古漢語、現代語で近英語を学んできた。
橋本進吉学説は音声を観察し、国語音韻による文法論を視点に詞辞の大別を立場に作り上げた。学校文法の品詞は橋本文法論の考え方を多く取り入れ文節を国語の単位に与えた。その品詞は一方で話部であったのだが、それを分節としてみたときに、文節の単位で見て取れる国語に適した分析であった。品詞は文節相当に捉えるとよいとしたのである。
いま品詞は自立語と付属語に同じ詞の名称を持つ。国語の助詞、助動詞という名前が学校教育で普及している。自立語の名詞と付属語の助詞を同じ品詞レベルでとらえるのは考え方の基本を取り違えると、が、を、に といった文法的に機能する付属語を単語として扱って、自立語と付属語の語としての混同が起こって考え方の説明ができなくなる。
自立語と言い、付属語と言う、わかりやすい分類はそれはそれで新たに説明のための言葉であったのであるが、詞と辞としての分類をほどこすところを考え方から変えてしまうのである。自立詞とか、付属辞とか名前を付けていれば詞辞の2大別を学んできた伝統を継承したであろう。品詞分類における考え方を名称によってしわけるのがよい。
品詞は話を音声でとらえて息継ぎ、休止、強弱などで切ったときの話の部分である。つまり日本語でいえば、自立詞と付属辞が分析されてそれを品詞にするかどうかはそれぞれの意味情報や文法機能によって厳密を期せばその文また文章における構成要素としては同一視すべきではなかったのである。テニヲハとした分類はそれなりに継承すべきであった。
それを文節として文を構成する最小単位としたのは炯眼である。つまり品詞と言うのは文節である。なかなか分かりにくいが、わたしが わたしに わたしの と言うのは、わたし と言う名詞であると抽象しているのであるから、この文節の単位のままに、わたしガ わたしニ わたしヲ と名詞 わたし における変容を見るとわかりよかったのである。
このとらえ方は文法を形態論の視点で進めると、自立形式と付属形式の結合態による形態の分析で説明できることになる。国語文法の文節が言語研究の品詞で日本語教育用の文法で形態の分析となる。それぞれの立場を混同してはならないが、漢語文法を取り入れ漢文訓読として日本語をとらえてきたその背景には脈々と詞と辞としての見方がある。
文章にあるもの 日本語の文法について その15
文章に主題主語があり、文に主格主語がある。さらに句にも主語があるという句構成をみると、文章にはいくつもの主語に相当するものがあり、文に複数の主語を持つとするのは、文章が文の組み合わさったものあり、文がほかの文と関係してその文を作り出しているからである。文が複数から成り立てばいくつも含まれる主語が文の数に応じて認められる。
言語の現象は複雑であり、語句、文、文章と抽出する。それは文の単位に論理性が捉えられて主語と述語動詞を主要な構成要素とする。それはまた述語動詞に従う目的語、補語のほかに語と語との関係で句あるいは節ができるとする捉え方である。文の主語を必須とすれば文の単位を基本構造として文法の構成を分析することが可能である。
文に必須である主語をその文にもたない、ほかの文との関係で主語を示す文があり、それが文章に示される構造と捉えられるのが日本語の言語表現である。文に主語が必須であるという規定は文の成立を主語の有無に置く基本構造がある。文の成立をその基本である主語に置くことは言語現象の帰納によるからであるから、その言語の特徴である。
主語は文の必須要素でない、文は主語を持たずに成立する場合があると規定をすればその主語がないままに文情報を読み取るかと言えば必ずしもそうではなくて、その表現に主語の相当のものを解釈することになるが、それはほかの文との関係でいくつかの文のうちに主語をもとめる。主語を求めその主語はそれは複数の文を連ねた文章のうちにある。
文章に主語を求め、文に主語を認め、語句にその主語を特定することができる。いいかえれば文を単位にして言語の表現理解において主語があるということである。この日本語の構造は語と語とを連ねて句とし、その語には言語主体による表出があったのであるが、それに加えて句が文を構成する考え方のもとに文に主語を規定するようになったのである。
日本語の現象には言語主体とする言語の表出者と言語の文における主語とが重なり合って表現に対比されることがないことがある。言語を思想や意志、意見の表出とその機能を捉えるうえで、一方で日本語は感情を表現とするという考え方が行われてきている。どの言語も感情を表現できるがそれを感情表出としての手段に心情の吐露としてみる。
嘆きを嘆きのままに言語表現とするというのは伝統の日本文学の表現にある歌の技巧である。これを文学作用の分野に分析をして言語をそこから抽象しようとしてきた経緯があるので、このとらえ方は表現の用法において文を分析する際にも行われてきている。すなわち主格主語が捉えられ分析される前の文法現象である主題主語の句と文章に象徴される。
語にあるもの 日本語の文法について その16
文法のレベルを捉える。宮地裕学説による文法単位体の視点から文章、文、節、句、語、モーフを設定する。そのうちモーフであるmorphは形態分析になる。日本語教育用文法の立場にモーフの分析は有効である。すなわち音素レベルのとらえ方である。すると語は
音節レベルのとらえ方であることがわかる。語は言語記号であり、意味の単位である。
日本語文法は単位語に品詞を分析してきた。国語教育用文法の立場では品詞論と構文論のとらえ方で整理してきた考え方に自立語、付属語の二大別があり、品詞として付属する語を助詞、助動詞といている。この分類と名称は語をわけてそれぞれを語とし詞としたものであるが、それまでの詞と辞の二大別を継承する考え方で、いわば自立詞、付属辞である。
語は単位に抽出されると種類に分けられる。品詞分類である。品詞というのは翻訳語として成立している。parts of speechは話部であった。それはまた文を切ったときに分けるわけ方でいえば橋本学説の文節である。語は品詞としてみれば文節が相当する。文節の自立して意味をあらわす部分を取れば、付属する部分と分けられる。それは語の構成である。
文法上の職能に単語の区分けをして品詞に分類して説明する。国語教育では名詞、代名詞、動詞、形容詞、形容動詞、連体詞、副詞、接続詞、感動詞、助動詞、助詞、11品詞にしている。品詞論は日本語の品詞に形容動詞をどう見るか、数詞があるか、それはまた形容詞であるか、助数をつけて名詞であるか、助詞助動詞の文法機能についてなどの議論である。
文法は文に分析される機能を捉える、すなわち職能を見ることになるので、付属辞は自立詞と共に働く文節に捉えられたように、品詞に文法職能を付与するものである。語にある自立しない部分としては品詞にならないのが付属辞である。形態分析をすれば自立形式に対する結合形式である。日本語の文法でこの付属辞は文だけでなく文章にも機能している。
品詞は職能を見ると主語と述語をまず捉えることになる。その主語また述語に修飾語を分析し連体と連用の修飾関係を考えるか、述語動詞との関係で主格の語を分析し目的の語を捉えて文の中で語の支配による文型を考えるか、さらには主題の語を捉えて述語を詳しく表現する状況の語をとらえるかなどを、文情報の意味を担う語の単位体に見ることになる。
品詞の名称は翻訳された語でとらえると助動詞の分類としてのものと翻訳できないテニヲハのとらえ方で議論を残してきたのである。語構成要素に見る語の論を語と語との関係で見る語句の論を必要とする。それは句の論をみて伝統的な日本語のとらえ方にあったのであるが、詞と辞の考え方のまま、漢語文法にのみとどめられた訓読語法に押しやられた。
文典、文法書 日本語の文法について その17
詞と辞は漢文訓読の語法の影響を受けている。単語と品詞は近代英語の翻訳によって捉えられた。文と文節は日本語の言葉にふさわしく分析された。言語の現象のままにさまざまに視点を持ち漢語を取り入れ英語を学び続けている日本語文法である。形態論は統語論とともに文法として日本語学習の立場を見せた。漢語、英語、国語そして日本語学である。
伝統文法は国語分析に品詞分類をすすめて規範とした。文典と呼ばれた文法書は文法分析に軌跡を持つ。広日本文典、広日本文典別記はその後の口語法とその別記とあわせて日本語文法の考え方を近代において作り上げている。それ以前、さかのぼって17世紀初めにはロドリゲスの日本文典が書かれ、その日本大文典はポルトガル語による記述である。
文典に文法があると説明をするときそれは文法を記述する書であって厳密な文法学説の理論書との違いがあるが、文典の価値は規範に与えた考え方において重要なものである。文典にはさらに新文典および新文典別記が著わされ、その一方で日本新文典のように形容動詞を分類するものがあった。1921年至文堂刊、藤村作, 島津久基の名前が並ぶ。
文典を検索すると日本俗語文典がある。中国留学生教育に寄与し国語学国文学研究の足跡を残した松下大三郎の著述だ。日本俗語文典、1901年は初めて体系的に口語文法を説いたとされる。ほかに標準日本文法、標準日本口語法、標準漢文法などの著作にみるべきものが多い。断句、詞、原辞の捉え方は詞辞の視点にあり、形態文法の先駆けを内容とする。
このようにみて文典には文法記述があってそれぞれに特徴がある。21世紀初頭の動きとして1902年、明治35年に国語に関する調査、国語調査委員会が文部大臣の直属機関として活動した。成果を上げ、送仮名法、口語法、疑問仮名遣などを編纂したが、それはⅠ913年、大正2年に廃止となる。国語国字問題解決の目的を持っていたとされる。
国語の音韻、方言、国語史調査を行い国語学の基礎ともなっている。このころから国語文法に記述説明書が作られてそれまでの翻訳による文法から独自性を持った日本語文法のいわば整理期に入るとみられる。自立語付属語と言われる分類に当初は自立ではなくて独立語という名称がありそれを踏まえた独立詞付属辞という分類もなされていたのである。
文法の視点と立場はその拠って来る理論志向に正しくみれば専門の術語としての使用混同は避けられなければならない。それぞれの規定を受けて言語現象をその用語で解釈するので融通されるものではないが、日本語文法はその多くを取り入れ学びながら、その理論的な構築を果たした。現代日本語文典の必要とされるところ、しばらく彼我を述べてみたい。
体用 日本文語の文法について その18
文典は文法の体系を解説する。その記述は品詞論のレベルで構文論には及ぶことが少ない。構文の原理が文にありその単位文の終止は外形的に決められた。すなわち述語に置かれる品詞の終止形によって帰納された。文とは何かと言えば日本語は文末終止また終わる詞の機能を抽出して規定されている。いわば主語と述語が文として働くための句点で終わる。
実は日本語にある文としての単位は句によってあらわされる。その句構造は文構造に包含されるものである。さきに文が終わるための句点を機能としてとらえたのであるが、それが文の終止であるなら、句読点は句としての休止終止でもあった。単位文に主語述語を規定すると一文の終わりはその単位の終わりに句を持ち、それで句点と言うことになる。
文法は語法であり句法でもある。文法の文について分析をすると句が析出する。その句にあったのは体と用のことである。体言用言として語句の分類に用いられてさらに品詞類を分けるようになった。そもそもは句構造を示す原理であった。ただその論理が言語の現象と所作の解明にあって文法の抽象を得ることがなかったので名称が文法では引き継がれた。
体用は、たいよう、たいゆう、である。その説明を見ると、デジタル大辞泉の解説では、
たい‐ゆう 【体▽用】1 本体とその作用。たいよう、2 連歌・俳諧で、山・水辺・居所に関する語を分類して、その本体となる「峰」「海」などを体、その作用・属性を表す「滝」「浪」などを用としたこと、3 能楽で、基本的な芸と、そこから生じる風趣、と解説する。
たい‐よう【体用】1 文法で、体言と用言。2 ⇒たいゆう(体用)、と見える。また、詳しくする世界大百科事典 第2版の解説【体用 tǐ yòng】では、中国の哲学・思想・レトリック運用のための概念範疇と見えて、少し明らかにされるところ、それを論理と理解することが少ないのは、わたしたちにとっての言語がそのままに当てはめられるからであろう。
解説は、その基本形式は〈甲は丙の体,乙は丙の用〉または〈甲は乙の体,乙は甲の用〉つまり〈甲は体なり、乙は用なり〉という風に体用が対挙されることである、因果概念がたとえば風と波の関係をいうのに対して、体用は水と波の関係を示す。しばしば実体とその作用(または現象)と解される、として、やはりわかりにくい体用の説明である。
この解説がどこまでのものかが疑問であるのは、次のように結ぶからである。いわく、もっとゆるやかに〈体とは根本的なもの、第一次的なもの、用とは従属的なもの、二次的なもの〉としておく方がよい、というわけで、日本語文法に取り入れたこの概念はさかのぼれば古代インドの哲学にも及びそうである。向後の究明さるべき課題、体用のことである。
語句 日本文語の文法について その19
語句の構造は日本語文法のポイントである。語の構造は語構成にある。句の構成は句法にあった。が、そのそれぞれが関係しあうことはなかった。句法は文法にひとしくさらに分析が必要とする。いまだ日本語は句の構造が捉えられない。その構造には、語、句、文と共有する文法に統一した原理がなければならないのであるが、語と文では異なるのである。
理由は語の構成にある。日本語は古代漢語を取り入れ熟語とした。その後は漢字語として漢語のままに単語としてきた。その語には熟合した文字の組み合わせがあり熟語が文法の構造を持っているので、漢字語彙として日本語と異なる構成を見ることになる。熟語は名詞として扱われその意味を用いてきた。熟語が熟語であるのは漢語文法があるからである。
文字としての言葉、漢字を入れて漢語とした。その漢語はもともと日本語の語順にない構造を持っている。漢字を読むときに日本語音として漢字語彙にする。その漢語は古代の漢文法を持つ。そのために漢字を日本語読みにして、つまり訓読みをして言葉として理解している。危険は危なくて険しい、投球は球を投げる、あるいは、なげる、たま、となる。
その語の構造のままに文に働くのは名詞としての機能であるので、日本語文は漢語構成に日本語構造を持つという二重になっている。その漢字語と漢字語が日本語文法の関係構成で結びついている。交流文化は交流する文化と読みながら、その一方で、文化を交流するととらえている。文化交流は文化が交流するとなるのであるが、文化の交流とするだろう。
だから、交流文化を進めようと言うばあいと、文化交流を進めようと言のとでは、その句の構造がそれぞれに文法構造を持つ。意味内容の異なりを感じることもあるだろう。文化を交流することと、文化の交流すなわち文化が交流することとはその表現の主語と主体にかかわることとしてそれぞれが理解されることになるから、それを聞きわけることがある。
この句の構造に語の構成をみるか、文の構造を見るかということで、日本語の言い方が文法的に理解される。そこには文を成立させる要素がかかわることになる。語句の構造には文となるべき言い方が解釈されるから、句が関係しあって構成する語句は複雑に絡み合うことになる。そのままに漢字語を使っている日本語として理解するのである。
日本語は漢字熟語に漢語の文法を持っているので、それを捉えて、それに加えて、現代文の構造に英語の文法を解析しようとしてきた経緯がある。語句の構造に漢語と日本語をとりあわせた関係構成を見て取るので、句の構造を解明することによって語の構成と文の構造とを見ることになり、語句、慣用句、従属句のなんであるかを分析する必要がある。