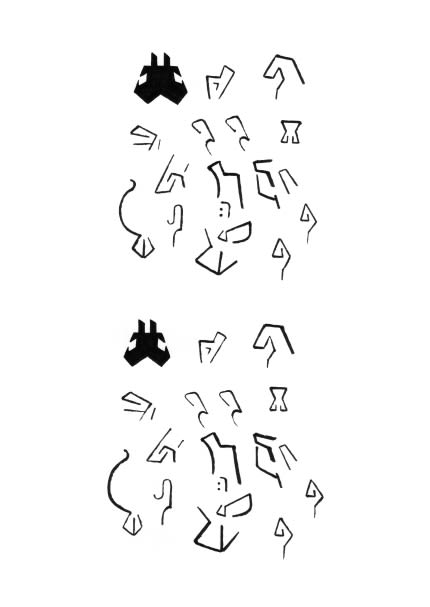三浦佑之の『浦島太郎の文学史――恋愛小説の発生』(五柳書院)を読んでの気付き。
これは、日本文学者で共立女子短期大学助教授(執筆時)の三浦(小説家の三浦しをんの父でもある)が、浦島太郎に関する様々な文献を狩猟し、浦島の物語は時代ごとにどのように語られてきたか、どのようなバリエーションがあるのか、他の神話や昔話との共通点・相違点は何かなど、昔話『浦島太郎』の歴史を深く掘り下げた一冊である。
三浦はこの中の第二章二節「丹後国風土記の浦島子」で、浦島太郎以外の異境を訪問する神話や説話では、異境(仙境)と地上(人間界)の時間の流れが異なっているのは珍しく、竜宮城の3年が地上の300年に当たるような〈超時間〉が描かれるのは例外的であると指摘したうえで、次のように述べている。
浦島子物語の「玉匣」は、こうした仙境と地上との時間差を埋めるための品物として準備されているのである。地上の移ろう時間による風化から人間の肉体を守るための呪宝だったとみればよい。
(中略)
この「玉匣」の「匣」とは箱の意であり、玉匣とは立派な箱という意味に解すればよい。最後に付された歌に音仮名で「たまくしげ」と表記されているし、『万葉集』には「たまくしげ」という枕詞が存するから、この「玉匣」もタマクシゲと訓んでよい。そして、クシゲとは「櫛・笥」の意であり、櫛を入れておく箱のことである。また、「玉」は石玉のタマであり、讃め言葉として接頭語のかたちで付けられる「玉」であるが、タマ(玉)は、古代においては、タマ(魂)とほとんど重なる言葉でもある。そして、櫛という品物が魂を籠もらせる呪的な品物であるということは、『古事記』のヤマトタケル説話において海の神の生贄となって入水したオトタチバナヒメの櫛が浜辺に流れ着いたという伝承に端的に示されてもいる。つまり、古代の人たちにとっては、「玉匣」という言葉は、〈魂の籠められた箱〉という認識を容易に導くものだったはずである。そして、浦島子物語における時間認識を重ねて考えれば、「玉匣」の中には、地上の時間の経過から島子を守るために、島子の魂が封じ籠められていたのだと読むことができるのである。そのおかげで、島子は地上に戻ることができたし、何の変化も被らずに十日余りを過ごせたのである。
いやー、なるほどなるほど。子供の頃、浦島太郎の物語を聞いて、理不尽に思っていた。乙姫様は、なぜあんな物騒な物を持たせたのかと。
「玉手箱の中から煙が出てきて、太郎はたちまち白髪のおじいさんになってしまいました」という箇所を読んで、玉手箱の煙には、人を老化させる作用があると解釈したからだ。浦島がかわいそうじゃないかと。
しかし、そうではなかった。玉手箱の中には、人間(浦島)の若さを維持するための呪術、もしくはエネルギーのようなものが籠められていたのだ。
浦島が白髪のおじいさんになったのは、煙の老化作用の影響によるものではなく、箱を開封したことで呪力、もしくはエネルギーが四散し、若さを保てなくなって老化したのだ。
そのように考えれば、乙姫が玉手箱を持たせたのも、持たせたうえで「絶対に開けてはいけません」と注意したのも合点がいく。すべては浦島のためだったのだ。仮に浦島が玉手箱を持たずに帰郷していたら、陸に上がった瞬間に300年という時間の風雪に晒されて白髪のおじいさんになっていたわけだ。
でも、それならそうと言ってくれればいいのにな、とも思うけど。
それと、もし玉手箱の中身が呪術やエネルギーではなく、浦島の魂そのものだったとすれば、『魔法少女まどか☆マギカ』のソウルジェムみたいなものだということになる。『まどマギ』の元ネタは浦島太郎にあった。
三浦は上の引用文のあとで、浦島が300年も歳を取ったにもかかわらず、老人になっただけで死去しないという不自然さを指摘。浦島が仙人になった可能性があると示唆している。
玉手箱の開封によって仙人に転じた浦島太郎と、ソウルジェムの消尽によって魔女に転じる魔法少女。この変化の点でも共通しているように見えるが、どうだろう。
・この手の話がお好きな方は、「桃太郎はなぜ桃から生まれたのか」(2019・2・28)も併せてお読みください。
https://blog.goo.ne.jp/gokudo0339/e/7964c0f1054f8295ac626723f1e9974a
これは、日本文学者で共立女子短期大学助教授(執筆時)の三浦(小説家の三浦しをんの父でもある)が、浦島太郎に関する様々な文献を狩猟し、浦島の物語は時代ごとにどのように語られてきたか、どのようなバリエーションがあるのか、他の神話や昔話との共通点・相違点は何かなど、昔話『浦島太郎』の歴史を深く掘り下げた一冊である。
三浦はこの中の第二章二節「丹後国風土記の浦島子」で、浦島太郎以外の異境を訪問する神話や説話では、異境(仙境)と地上(人間界)の時間の流れが異なっているのは珍しく、竜宮城の3年が地上の300年に当たるような〈超時間〉が描かれるのは例外的であると指摘したうえで、次のように述べている。
浦島子物語の「玉匣」は、こうした仙境と地上との時間差を埋めるための品物として準備されているのである。地上の移ろう時間による風化から人間の肉体を守るための呪宝だったとみればよい。
(中略)
この「玉匣」の「匣」とは箱の意であり、玉匣とは立派な箱という意味に解すればよい。最後に付された歌に音仮名で「たまくしげ」と表記されているし、『万葉集』には「たまくしげ」という枕詞が存するから、この「玉匣」もタマクシゲと訓んでよい。そして、クシゲとは「櫛・笥」の意であり、櫛を入れておく箱のことである。また、「玉」は石玉のタマであり、讃め言葉として接頭語のかたちで付けられる「玉」であるが、タマ(玉)は、古代においては、タマ(魂)とほとんど重なる言葉でもある。そして、櫛という品物が魂を籠もらせる呪的な品物であるということは、『古事記』のヤマトタケル説話において海の神の生贄となって入水したオトタチバナヒメの櫛が浜辺に流れ着いたという伝承に端的に示されてもいる。つまり、古代の人たちにとっては、「玉匣」という言葉は、〈魂の籠められた箱〉という認識を容易に導くものだったはずである。そして、浦島子物語における時間認識を重ねて考えれば、「玉匣」の中には、地上の時間の経過から島子を守るために、島子の魂が封じ籠められていたのだと読むことができるのである。そのおかげで、島子は地上に戻ることができたし、何の変化も被らずに十日余りを過ごせたのである。
いやー、なるほどなるほど。子供の頃、浦島太郎の物語を聞いて、理不尽に思っていた。乙姫様は、なぜあんな物騒な物を持たせたのかと。
「玉手箱の中から煙が出てきて、太郎はたちまち白髪のおじいさんになってしまいました」という箇所を読んで、玉手箱の煙には、人を老化させる作用があると解釈したからだ。浦島がかわいそうじゃないかと。
しかし、そうではなかった。玉手箱の中には、人間(浦島)の若さを維持するための呪術、もしくはエネルギーのようなものが籠められていたのだ。
浦島が白髪のおじいさんになったのは、煙の老化作用の影響によるものではなく、箱を開封したことで呪力、もしくはエネルギーが四散し、若さを保てなくなって老化したのだ。
そのように考えれば、乙姫が玉手箱を持たせたのも、持たせたうえで「絶対に開けてはいけません」と注意したのも合点がいく。すべては浦島のためだったのだ。仮に浦島が玉手箱を持たずに帰郷していたら、陸に上がった瞬間に300年という時間の風雪に晒されて白髪のおじいさんになっていたわけだ。
でも、それならそうと言ってくれればいいのにな、とも思うけど。
それと、もし玉手箱の中身が呪術やエネルギーではなく、浦島の魂そのものだったとすれば、『魔法少女まどか☆マギカ』のソウルジェムみたいなものだということになる。『まどマギ』の元ネタは浦島太郎にあった。
三浦は上の引用文のあとで、浦島が300年も歳を取ったにもかかわらず、老人になっただけで死去しないという不自然さを指摘。浦島が仙人になった可能性があると示唆している。
玉手箱の開封によって仙人に転じた浦島太郎と、ソウルジェムの消尽によって魔女に転じる魔法少女。この変化の点でも共通しているように見えるが、どうだろう。
・この手の話がお好きな方は、「桃太郎はなぜ桃から生まれたのか」(2019・2・28)も併せてお読みください。
https://blog.goo.ne.jp/gokudo0339/e/7964c0f1054f8295ac626723f1e9974a
今日は棒状の芋です。

アメリカ産のお菓子。アメリカと言えばポテトですよね。小さいフライドポテトみたいな形で、シンプルな塩味がひたすら美味しいです。輸入菓子あつかってるお店で探してください。アメリカンカウチポテトになってむさぼり食いましょう。
そう、時代はSDGs・・・。SDGsについて話しましょうか。
かつて、「美しき青木・ド・ナウ」という、青木さやかの冠番組がありました。2006年10月から、約3年間放送されていた番組です。
今の若い人はわかんないでしょうけど、当時青木さやかの人気はすさまじかったんですね。そんな青木さやかイケイケ時代の番組でした。
んで、その番組内に「御冠」(おかんむり)というコーナーがあったんです。青木とゲストが、日頃不満に感じていること、腹を立てていることをぶちまける、というコーナーです。
ある回に、バナナマンの日村勇紀さんがゲスト出演したことがありました。日村さんは、「夜中にコンビニ行くと、弁当がひとつも置いてないことあるけど、あれなんなの?」とおっしゃいました。24時間営業のコンビニなら、24時間いつでも弁当買えるようにしとけ、という不満です。
それを聞いた僕は、「弁当がなかったとしても、カップ麺やら冷凍食品やらいろいろ置いてあるんだから、あるものなんでもありがたく食べればいいんじゃないの?」と思ったんですけど、日村さんはそう考えてはいなかったようです。
ご存じの通り、日本は食料の廃棄量がとても多い国です。食料自給率が低いので、大量に輸入しているのですが、にもかかわらず廃棄が多い。これはひとえに、食料供給のありかたに問題があるということです。
コンビニやスーパーで販売される弁当やパンなんかが典型ですね。お客さんが買い物に訪れて、もしほしいものがないと、「ねえのかよ」ってガッカリしてしまう。それは店のイメージダウンにつながってしまう。だからそうならないように、多少の廃棄が出ることを覚悟して多めに商品を用意するのです。
廃棄を出すことによる損失よりも、イメージダウンによる客離れのほうを優先的に防ごうとしているのですね。だから、けっこうな量の廃棄が出てしまう。
その点、日村さんが訪れた「夜中に弁当置いてないコンビニ」は、供給より需要がやや上回っていて、弁当の廃棄を出さないことに成功している店舗と言えるでしょう。
では仮に、そのコンビニが日村さんの求めに応じて仕入れを増やし、夜中でもつねに弁当を買える店になったらどうでしょうか。「真夜中に店頭に並ぶ弁当」は、確実に売り切れるわけではありません。日村さんみたいな人が毎晩訪れて、必ず弁当を買っていってくれるとは限らない。つまり、少なからず廃棄になってしまうわけです。
日村さんの、「コンビニだったら真夜中でも弁当買えるようにしとけよ」という要求は、「食料廃棄をさらに増やせ」と言っているのと同じことなのです。
そんな日村さん擁するバナナマンは、2021年、TBS系で開催されたSDGsプロジェクト「地球を笑顔にするweek」のキャンペーン大使に就任しました。まあようするに、こういう「顔」というのは、日頃からSDGsをどれだけ意識しているかとか、SDGsに沿った生活を送っているかどうかとは無関係に、単純に知名度で決まってくる、ということなんでしょうね。
ただ、念のため公正を期して言わせてもらいますと、当時の日村さんは、「夜中でも弁当置いとけ」という主張が、食料廃棄の増加を促しかねないものだということに気づいていなかった、という可能性もあります。無自覚な悪だった、ということですね。また、当時は食料廃棄にかんする意識が低かったけど、今は過去を反省して積極的にSDGsに取り組んでいる、ということなのかもしれません。あくまで可能性の話ですけどね。
なんでもケンドーコバヤシの証言によると、日村さんはフードファイターはだしの大食らいだそうでして、食べ物のこととなると理性を失いがちなのかもしれません。ダイエット中も「設楽に隠れてちょっと食べ」だったらしいですからね。
ビクトリー!!

アメリカ産のお菓子。アメリカと言えばポテトですよね。小さいフライドポテトみたいな形で、シンプルな塩味がひたすら美味しいです。輸入菓子あつかってるお店で探してください。アメリカンカウチポテトになってむさぼり食いましょう。
そう、時代はSDGs・・・。SDGsについて話しましょうか。
かつて、「美しき青木・ド・ナウ」という、青木さやかの冠番組がありました。2006年10月から、約3年間放送されていた番組です。
今の若い人はわかんないでしょうけど、当時青木さやかの人気はすさまじかったんですね。そんな青木さやかイケイケ時代の番組でした。
んで、その番組内に「御冠」(おかんむり)というコーナーがあったんです。青木とゲストが、日頃不満に感じていること、腹を立てていることをぶちまける、というコーナーです。
ある回に、バナナマンの日村勇紀さんがゲスト出演したことがありました。日村さんは、「夜中にコンビニ行くと、弁当がひとつも置いてないことあるけど、あれなんなの?」とおっしゃいました。24時間営業のコンビニなら、24時間いつでも弁当買えるようにしとけ、という不満です。
それを聞いた僕は、「弁当がなかったとしても、カップ麺やら冷凍食品やらいろいろ置いてあるんだから、あるものなんでもありがたく食べればいいんじゃないの?」と思ったんですけど、日村さんはそう考えてはいなかったようです。
ご存じの通り、日本は食料の廃棄量がとても多い国です。食料自給率が低いので、大量に輸入しているのですが、にもかかわらず廃棄が多い。これはひとえに、食料供給のありかたに問題があるということです。
コンビニやスーパーで販売される弁当やパンなんかが典型ですね。お客さんが買い物に訪れて、もしほしいものがないと、「ねえのかよ」ってガッカリしてしまう。それは店のイメージダウンにつながってしまう。だからそうならないように、多少の廃棄が出ることを覚悟して多めに商品を用意するのです。
廃棄を出すことによる損失よりも、イメージダウンによる客離れのほうを優先的に防ごうとしているのですね。だから、けっこうな量の廃棄が出てしまう。
その点、日村さんが訪れた「夜中に弁当置いてないコンビニ」は、供給より需要がやや上回っていて、弁当の廃棄を出さないことに成功している店舗と言えるでしょう。
では仮に、そのコンビニが日村さんの求めに応じて仕入れを増やし、夜中でもつねに弁当を買える店になったらどうでしょうか。「真夜中に店頭に並ぶ弁当」は、確実に売り切れるわけではありません。日村さんみたいな人が毎晩訪れて、必ず弁当を買っていってくれるとは限らない。つまり、少なからず廃棄になってしまうわけです。
日村さんの、「コンビニだったら真夜中でも弁当買えるようにしとけよ」という要求は、「食料廃棄をさらに増やせ」と言っているのと同じことなのです。
そんな日村さん擁するバナナマンは、2021年、TBS系で開催されたSDGsプロジェクト「地球を笑顔にするweek」のキャンペーン大使に就任しました。まあようするに、こういう「顔」というのは、日頃からSDGsをどれだけ意識しているかとか、SDGsに沿った生活を送っているかどうかとは無関係に、単純に知名度で決まってくる、ということなんでしょうね。
ただ、念のため公正を期して言わせてもらいますと、当時の日村さんは、「夜中でも弁当置いとけ」という主張が、食料廃棄の増加を促しかねないものだということに気づいていなかった、という可能性もあります。無自覚な悪だった、ということですね。また、当時は食料廃棄にかんする意識が低かったけど、今は過去を反省して積極的にSDGsに取り組んでいる、ということなのかもしれません。あくまで可能性の話ですけどね。
なんでもケンドーコバヤシの証言によると、日村さんはフードファイターはだしの大食らいだそうでして、食べ物のこととなると理性を失いがちなのかもしれません。ダイエット中も「設楽に隠れてちょっと食べ」だったらしいですからね。
ビクトリー!!