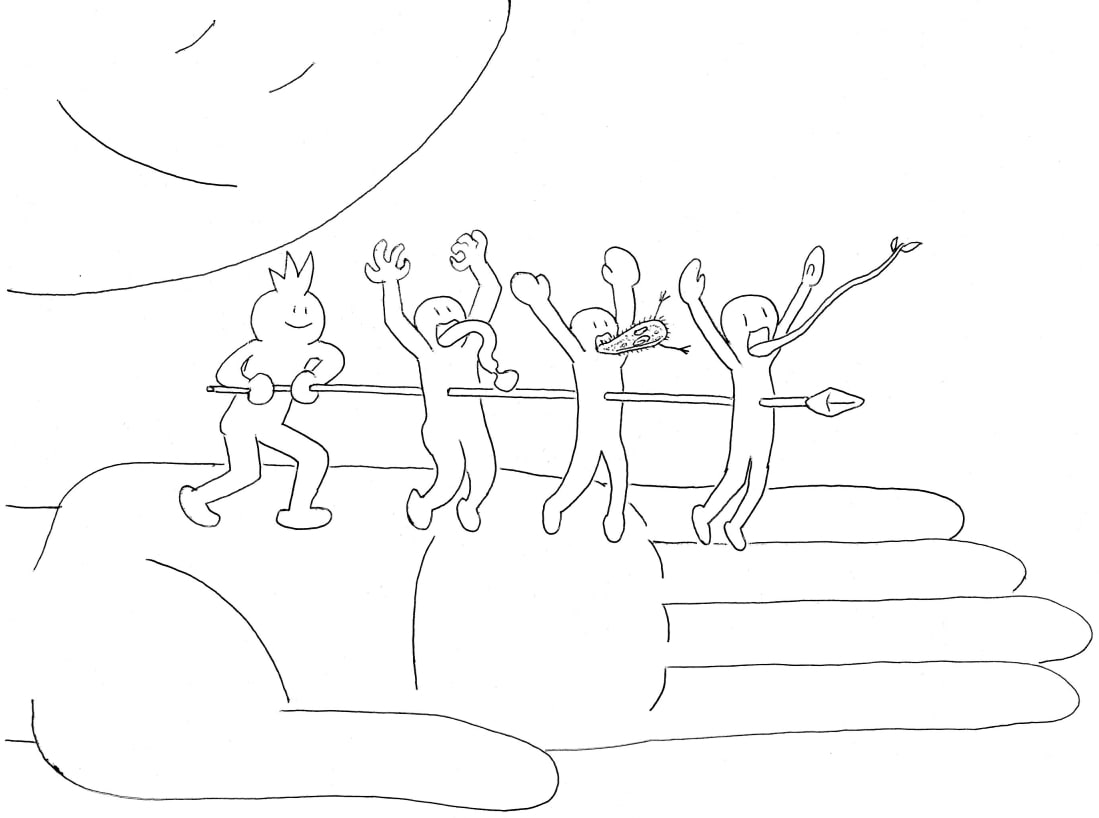
(②からの続き)
「叩かなければわからない子供もいる」とか「(学校現場などで、他の子供のことを考えて)やむを得ず叩かなければならない場合もある」などの意見もある。だが、本当にそうだろうか。
大人と子供には、それでなくても大きな力の差(ここで言う力とは、腕力のことだけではない。衣食住を構成する力――つまり経済力――や、社会的権力も含まれる)がある。本当に体罰しか手段がないのだろうか。
ここで先程の「口で言って聞かせることもできるのに、叩いたほうが手っ取り早いから叩いた体罰」を見てみたい。
小生が子供の頃、公教育の現場ではまだ体罰がまかり通っていた。自分自身殴られたこともあるし、他の生徒が殴られているのも何度となく目撃している。その経験から言うと、ほとんどの教師は、まず言葉による説得を行い、それが聞き入れられなかった場合に初めて殴る、というプロセスを経ることなく、最初からいきなり殴っていた。
大人になった今振り返ってみて、体罰以外の手段を模索しようとしなかった彼等は、やはり無能であったと思う。無能という言葉が強すぎると言うなら、「安易」や「怠惰」に言い換えてもいい。いずれにせよ、尊敬に値しない点において変わりはない。
敬意も信頼も生み出さず、逆に軽蔑や恨みをもたらす体罰とは、一体何なのか。体罰を肯定する者は、「子供に言うことをきかせる」という、その場限りでの効用のみ考えているようだが、その後の子供との信頼関係に与える影響だってあるし、むしろ諸々の影響を総合すると、体罰はマイナス面のほうが大きいかもしれないのだ。
もちろんこれは個人的体験に基づいた個人的意見でしかない。ただ、体罰を許容していると、このような考えを抱く人間を生み出してしまうわけで、小生は、決して自身が少数派ではないと信じている。
体罰が禁止されているのをいいことに、生徒が教師に暴力を振るう、という事例があり、それを根拠に体罰の復活を訴える人もいる。
ならば、正当防衛のための体罰ならギリギリ認めてもいいと思う。実際に手を出さなくても、「これ以上言うことを聞かないなら殴るぞ。その気になれば手を出せるんだぞ」と脅しをかければ、それだけで統御することができるからだ。つまり、「体罰そのもの」ではなく「体罰というカード」を利用する、ということだ。
だが、そんな繊細な使い方ができる人がいるだろうか。体罰について突き詰めて考えられていない状態で解禁してしまえば、不必要な体罰を横行させてしまうのではないだろうか。
「叩かなければわからない子供もいる」というのも、確かに(部分的に)事実ではある。小生の同級生の中にも何人か、いわゆる「ワル」がいた。彼らは、実際よく大人に殴られていた。そして、ずーっとワルだった。
ならば、彼らはいつ、どのようにして更生したのか。
それは、就職の時だ。「もういいかげんバカやってられない。社会人にならなくちゃいけない」
彼らは、体罰によってではなく、必要に迫られて更生したのだ。
体罰は、その場限りの反省、もしくは反省したフリを引き出すことはできる。だが、その場限りのものでしかないのなら、使わないほうがいいのではないだろうか。
そもそも、いついかなる場面でも、子供は大人に従わねばならないのだろうか。「言うことを聞かないなら、放っておく」という選択肢があってもいいのではないだろうか。日本の公教育の管理体制の過剰さは、よく指摘されている。外国からは、日本の学校は、軍隊や監獄、あるいは奴隷制に見えるらしい。外からは異常にしか見えない体制を懸命に維持しようと努め、そのためには体罰すらためらうべきではないとするならば、それは有害なものを有害な行為で塗り固めていることにならないだろうか。
さて、以上の議論をよく読んで頂ければ、小生が「体罰を振るうことによる問題」に対してはきちんと反証を加えているものの、「体罰を禁じることによる問題」は完全には解決できていないことがおわかり頂けると思う。
体罰肯定論者が、体罰を復活させる根拠としている点に対して、小生は、具体的な解決策を部分的にしか提示しきれていない。だが、開き直りではないが、小生はそれで構わないと思っている。
体罰を解放するにせよ、禁じるにせよ、問題が付きまとうことに変わりはない。しかし、問題を抱える主体は違ってくる。
体罰を解放すると、子供の側が問題を負わねばならず、その逆だと大人の側が負わねばならない。
負担は、大人が負うべきだと思う。そもそも、「解決できない問題を抱えつつも、なんとかそれと折り合いをつけていく者」のことを大人と呼ぶのである。
「体罰を容認しろ」という訴えは、小生には「ラクをさせろ」と聞こえる。子供に負担を押し付けて、自分達はラクをしたい、と主張している様に聞こえる。
大人は、ラクをしてはならない。
体罰に依らずに教育を施すこと。子供のことも、それ以外のことも、思い通りにならない面を受け入れること。いじめや虐待をなくすために、ます自分が暴力の種を蒔かないこと。
それらの困難を抱えてこそ、大人は大人として成熟するのではないだろうか。
大人自身が成熟しようとしていないのに、今の子供を「幼稚だ」と揶揄することはできない。
オススメ関連本・大澤真幸『社会は絶えず夢を見ている』朝日出版社
「叩かなければわからない子供もいる」とか「(学校現場などで、他の子供のことを考えて)やむを得ず叩かなければならない場合もある」などの意見もある。だが、本当にそうだろうか。
大人と子供には、それでなくても大きな力の差(ここで言う力とは、腕力のことだけではない。衣食住を構成する力――つまり経済力――や、社会的権力も含まれる)がある。本当に体罰しか手段がないのだろうか。
ここで先程の「口で言って聞かせることもできるのに、叩いたほうが手っ取り早いから叩いた体罰」を見てみたい。
小生が子供の頃、公教育の現場ではまだ体罰がまかり通っていた。自分自身殴られたこともあるし、他の生徒が殴られているのも何度となく目撃している。その経験から言うと、ほとんどの教師は、まず言葉による説得を行い、それが聞き入れられなかった場合に初めて殴る、というプロセスを経ることなく、最初からいきなり殴っていた。
大人になった今振り返ってみて、体罰以外の手段を模索しようとしなかった彼等は、やはり無能であったと思う。無能という言葉が強すぎると言うなら、「安易」や「怠惰」に言い換えてもいい。いずれにせよ、尊敬に値しない点において変わりはない。
敬意も信頼も生み出さず、逆に軽蔑や恨みをもたらす体罰とは、一体何なのか。体罰を肯定する者は、「子供に言うことをきかせる」という、その場限りでの効用のみ考えているようだが、その後の子供との信頼関係に与える影響だってあるし、むしろ諸々の影響を総合すると、体罰はマイナス面のほうが大きいかもしれないのだ。
もちろんこれは個人的体験に基づいた個人的意見でしかない。ただ、体罰を許容していると、このような考えを抱く人間を生み出してしまうわけで、小生は、決して自身が少数派ではないと信じている。
体罰が禁止されているのをいいことに、生徒が教師に暴力を振るう、という事例があり、それを根拠に体罰の復活を訴える人もいる。
ならば、正当防衛のための体罰ならギリギリ認めてもいいと思う。実際に手を出さなくても、「これ以上言うことを聞かないなら殴るぞ。その気になれば手を出せるんだぞ」と脅しをかければ、それだけで統御することができるからだ。つまり、「体罰そのもの」ではなく「体罰というカード」を利用する、ということだ。
だが、そんな繊細な使い方ができる人がいるだろうか。体罰について突き詰めて考えられていない状態で解禁してしまえば、不必要な体罰を横行させてしまうのではないだろうか。
「叩かなければわからない子供もいる」というのも、確かに(部分的に)事実ではある。小生の同級生の中にも何人か、いわゆる「ワル」がいた。彼らは、実際よく大人に殴られていた。そして、ずーっとワルだった。
ならば、彼らはいつ、どのようにして更生したのか。
それは、就職の時だ。「もういいかげんバカやってられない。社会人にならなくちゃいけない」
彼らは、体罰によってではなく、必要に迫られて更生したのだ。
体罰は、その場限りの反省、もしくは反省したフリを引き出すことはできる。だが、その場限りのものでしかないのなら、使わないほうがいいのではないだろうか。
そもそも、いついかなる場面でも、子供は大人に従わねばならないのだろうか。「言うことを聞かないなら、放っておく」という選択肢があってもいいのではないだろうか。日本の公教育の管理体制の過剰さは、よく指摘されている。外国からは、日本の学校は、軍隊や監獄、あるいは奴隷制に見えるらしい。外からは異常にしか見えない体制を懸命に維持しようと努め、そのためには体罰すらためらうべきではないとするならば、それは有害なものを有害な行為で塗り固めていることにならないだろうか。
さて、以上の議論をよく読んで頂ければ、小生が「体罰を振るうことによる問題」に対してはきちんと反証を加えているものの、「体罰を禁じることによる問題」は完全には解決できていないことがおわかり頂けると思う。
体罰肯定論者が、体罰を復活させる根拠としている点に対して、小生は、具体的な解決策を部分的にしか提示しきれていない。だが、開き直りではないが、小生はそれで構わないと思っている。
体罰を解放するにせよ、禁じるにせよ、問題が付きまとうことに変わりはない。しかし、問題を抱える主体は違ってくる。
体罰を解放すると、子供の側が問題を負わねばならず、その逆だと大人の側が負わねばならない。
負担は、大人が負うべきだと思う。そもそも、「解決できない問題を抱えつつも、なんとかそれと折り合いをつけていく者」のことを大人と呼ぶのである。
「体罰を容認しろ」という訴えは、小生には「ラクをさせろ」と聞こえる。子供に負担を押し付けて、自分達はラクをしたい、と主張している様に聞こえる。
大人は、ラクをしてはならない。
体罰に依らずに教育を施すこと。子供のことも、それ以外のことも、思い通りにならない面を受け入れること。いじめや虐待をなくすために、ます自分が暴力の種を蒔かないこと。
それらの困難を抱えてこそ、大人は大人として成熟するのではないだろうか。
大人自身が成熟しようとしていないのに、今の子供を「幼稚だ」と揶揄することはできない。
オススメ関連本・大澤真幸『社会は絶えず夢を見ている』朝日出版社
(①からの続き)
そもそも、体罰は純粋に躾のためだけに行われている、と断言できるだろうか。
小生の考えでは、体罰は次の3つに分類できる。
〈A〉子供のためにやむを得ず行われた体罰
〈B〉口で言って聞かせることもできるのに、叩いたほうが手っ取り早いから叩いた体罰
〈C〉ただ単に、怒りをぶつけただけの体罰
この分類は、あくまで便宜的なものである。実際に行われる体罰は、これら3種の混合体として現れるだろう。体罰を振るう親(大人)は、少なからずイライラしているはずなので、〈A〉にも〈B〉にも、いくらか〈C〉の要素が混じってくるはずだ。
さて、この3分類の中で問題視すべきは、〈B〉と〈C〉に思えるだろう。
〈C〉に検討を加えてみたい。「イライラをぶつけただけ」の体罰は、客観的には有害な暴力である。積極的な教育効果をもたらさず、親(大人)との間の人間関係に亀裂を生じさせ、先に述べた暴力の有効性を教えてしまう。
このように解説すると、体罰肯定論者は、「だから〈A〉と〈C〉(及び〈B〉)を峻別し、〈C〉(及び〈B〉)の体罰を行う親(大人)を教え諭せば、体罰の問題は解決されるではないか」と考えるかもしれないが、ことはそう簡単にはいかない。
〈C〉の体罰を〈A〉と〈B〉から区別するには、どうすればいいだろうか。「イライラ」というのは、本人の中にのみ存在する感情である。傍からは怒っているように見えても、実際は平静だったり、あるいはその逆であったりすることはザラにある。感情は、本人にしかわからない。もっと言えば、人間に無意識の領域がある以上、本人であっても100%把握できるわけではない。
つまり、〈C〉の体罰を〈A〉と〈B〉から厳密に区別することは不可能なのである。第三者の目には、どう見ても〈C〉にしか思えない体罰であっても、本人が「これはやむを得ず躾としてやっているんです(この体罰は〈A〉です)」と強弁すれば、それを反証するのは難しい。出来ることといったら、明らかに行き過ぎた体罰が行われていた場合に、それを虐待として通報することぐらいだろう。(虐待には性的虐待と心理的虐待とネグレクトもあるが、ここでは身体的虐待のみに話を絞る)
もし、親(大人)が自省的な人間で、〈C〉の体罰を行使した後に、「ああ、私はイライラをぶつけてしまった。子供に申し訳ない」と冷静に自己分析できるのであれば、さほど問題はない。だが、「〈C〉なのに〈A〉だと思い込んでいる場合」、そして「〈C〉である自覚がありながら、保身のために〈A〉だと言い張る場合」はどうだろう。いずれにせよ、イライラが内面の現象でしかない以上、これらを区別することは第三者には(そして、おそらく本人にも)できない。
つまり、体罰を容認するのは、イライラをぶつけただけの行為を許容することに繋がり、それは究極的には虐待へと結びついてしまうのである。
虐待を働いた親が逮捕される事件が、よく報道されている。逮捕された親は、必ずと言っていいほど「躾のためにやった」と証言する。罪の軽減を狙って発言している者もいるだろう。だがおそらく、多くの場合、本人は本気でそう思い込んでいるのである。純粋に子供のためを思って、善意で苛烈な体罰を振るっていたのだ。
周囲からは良い父(母)親だと評価され、子供とも良好な関係を築いている親の体罰と、虐待で逮捕されるに至る親の体罰は、その意味で、実質的な違いはない。
体罰を開放すると、イライラをぶつけただけの行為を野放しにしてしまう。
ここまでに述べた理由から、小生は、体罰を肯定する者に、いじめや虐待を非難する資格はないと思っている。
小生はあらかじめ「体罰」と「暴力」の二語を定義しておいた。しかし、これまでの議論を踏まえると、この弁別自体が極めて曖昧なものであったことがおわかりいただけるだろう。この定義は、主観に基づく分類でしかないのだ。主観が恣意的に働くものである以上、「体罰」か、ただの「虐待」かの解釈は、それを行使する本人によってしか規定し得ない。
(③に続く)
オススメ関連本・内田樹『武道的思考』筑摩選書
そもそも、体罰は純粋に躾のためだけに行われている、と断言できるだろうか。
小生の考えでは、体罰は次の3つに分類できる。
〈A〉子供のためにやむを得ず行われた体罰
〈B〉口で言って聞かせることもできるのに、叩いたほうが手っ取り早いから叩いた体罰
〈C〉ただ単に、怒りをぶつけただけの体罰
この分類は、あくまで便宜的なものである。実際に行われる体罰は、これら3種の混合体として現れるだろう。体罰を振るう親(大人)は、少なからずイライラしているはずなので、〈A〉にも〈B〉にも、いくらか〈C〉の要素が混じってくるはずだ。
さて、この3分類の中で問題視すべきは、〈B〉と〈C〉に思えるだろう。
〈C〉に検討を加えてみたい。「イライラをぶつけただけ」の体罰は、客観的には有害な暴力である。積極的な教育効果をもたらさず、親(大人)との間の人間関係に亀裂を生じさせ、先に述べた暴力の有効性を教えてしまう。
このように解説すると、体罰肯定論者は、「だから〈A〉と〈C〉(及び〈B〉)を峻別し、〈C〉(及び〈B〉)の体罰を行う親(大人)を教え諭せば、体罰の問題は解決されるではないか」と考えるかもしれないが、ことはそう簡単にはいかない。
〈C〉の体罰を〈A〉と〈B〉から区別するには、どうすればいいだろうか。「イライラ」というのは、本人の中にのみ存在する感情である。傍からは怒っているように見えても、実際は平静だったり、あるいはその逆であったりすることはザラにある。感情は、本人にしかわからない。もっと言えば、人間に無意識の領域がある以上、本人であっても100%把握できるわけではない。
つまり、〈C〉の体罰を〈A〉と〈B〉から厳密に区別することは不可能なのである。第三者の目には、どう見ても〈C〉にしか思えない体罰であっても、本人が「これはやむを得ず躾としてやっているんです(この体罰は〈A〉です)」と強弁すれば、それを反証するのは難しい。出来ることといったら、明らかに行き過ぎた体罰が行われていた場合に、それを虐待として通報することぐらいだろう。(虐待には性的虐待と心理的虐待とネグレクトもあるが、ここでは身体的虐待のみに話を絞る)
もし、親(大人)が自省的な人間で、〈C〉の体罰を行使した後に、「ああ、私はイライラをぶつけてしまった。子供に申し訳ない」と冷静に自己分析できるのであれば、さほど問題はない。だが、「〈C〉なのに〈A〉だと思い込んでいる場合」、そして「〈C〉である自覚がありながら、保身のために〈A〉だと言い張る場合」はどうだろう。いずれにせよ、イライラが内面の現象でしかない以上、これらを区別することは第三者には(そして、おそらく本人にも)できない。
つまり、体罰を容認するのは、イライラをぶつけただけの行為を許容することに繋がり、それは究極的には虐待へと結びついてしまうのである。
虐待を働いた親が逮捕される事件が、よく報道されている。逮捕された親は、必ずと言っていいほど「躾のためにやった」と証言する。罪の軽減を狙って発言している者もいるだろう。だがおそらく、多くの場合、本人は本気でそう思い込んでいるのである。純粋に子供のためを思って、善意で苛烈な体罰を振るっていたのだ。
周囲からは良い父(母)親だと評価され、子供とも良好な関係を築いている親の体罰と、虐待で逮捕されるに至る親の体罰は、その意味で、実質的な違いはない。
体罰を開放すると、イライラをぶつけただけの行為を野放しにしてしまう。
ここまでに述べた理由から、小生は、体罰を肯定する者に、いじめや虐待を非難する資格はないと思っている。
小生はあらかじめ「体罰」と「暴力」の二語を定義しておいた。しかし、これまでの議論を踏まえると、この弁別自体が極めて曖昧なものであったことがおわかりいただけるだろう。この定義は、主観に基づく分類でしかないのだ。主観が恣意的に働くものである以上、「体罰」か、ただの「虐待」かの解釈は、それを行使する本人によってしか規定し得ない。
(③に続く)
オススメ関連本・内田樹『武道的思考』筑摩選書
今更ながら、体罰について論じてみたい。
公教育の現場では、体罰が禁止されて久しい。家庭においても、体罰を振るう親の総数、及び振るわれる体罰の度合いは、一貫して減少傾向にあると思われる。
その流れの中にあって、たまに体罰必要論が唱えられる。曰く「叩かなければわからない子供もいる」「痛みを感じるのもひとつの教育効果だ」等。これらの言説は少数派に属するので、大きな潮流を生み出す程の力はない。
だが、僅かにせよ必要論を信奉する人々がいるという点、また、組織によっては、暗黙の了解として体罰が公然とまかり通っている点などを概観すると、日本社会は、「体罰は悪である」との共通認識を持つまでには至っていないようだ。
小生は、原則として体罰に反対である。
その理路を述べる前に、まず言葉の定義をしておく。
本論では「体罰」と「暴力」の二つの言葉を使う。普段、二つの言葉を混同して使っている人もいるだろうし、「体罰は暴力ではない」と主張している人もいるが、ここでは体罰を「行使する側が、必要に迫られてやむを得ず、もしくは何らかの教育的効果を求めて執行する肉体的加害行為」、暴力を「体罰も含む加害行為全般」の意味で使用する。
まず、親が体罰を振るう時、子供の側に何が起きているか、を見てみたい。
子供が親から体罰を受ける。すると子供は、「親(大人)の言うことを聞かないと痛い目に遭う」ことを学ぶ。そこまでは誰にでもわかることだが、ほとんどの人は、子供が学んでいるのはそれだけだと思い込んでいるのではないだろうか。だが、それだけではない。同時に子供は、「他者を従わせるのに、暴力行為は極めて有効だ」という真理をも学んでいるのである。
この学習に基づき、子供がどのような行動を取るかは、想像に難くない。子供は、自分よりも弱い者に狙いを定め、暴力によるコントロールを計るだろう。
一口に子供の暴力と言っても、同い年同士、対等な力関係にある者同士の殴り合い、つまり一般的なケンカもあるが、それはここでは問題としない。該当するのは「年上から年下への暴力」「男から女への暴力」「気の強い者から気の弱い者への暴力」である。この構造が固定化・持続化したのが、いわゆる「いじめ」である。
つまり、親(大人)は体罰を振るうことで、いじめのやり方を子供に教えてもいるのである。
もちろん、体罰を受けた子供の全員が全員、このような行動に走るわけではない。だが、一部の子供がそうなるだけで、充分大きな影響があるのである。
「年上から暴力を振るわれた年下」は、何を思うだろうか。やはり彼も、「他者を従わせる暴力の有効性」を学ぶだろう。そして、その学びを自分よりさらに年下の者に適用するだろう。かくして、暴力は連鎖する。
ここでは肉体的暴力に限って話を進めているが、勘のいい子供ならやり方を応用し、精神的な手段でも他人を支配しようとするはずだ。
いじめも、社会問題として長年議論され、様々な対策が講じられているが、あまり大きな成果は上がっていない。その原因の一つには、親(大人)の子供への体罰があると思う。子供の暴力の連鎖の源は、親(大人)の体罰である。親(大人)がいじめを肯定する行為を行っておきながら、「いじめをやめろ」と言っているのだ。欺瞞を孕んだ者の言説は、説得力を持ち得ない。(先に述べたように、いじめは必ずしも物理的暴力を伴うものではないが、何らかの力による脅迫で抵抗させなくする、という点で、暴力行為と同根である)
これに対しては、「体罰は躾のために許される行為であって、弱い相手に、私的な願望を強いるために行われるそれとは違う」という点を、体罰と同時に子供に言い含めればいいのではないか、という反論が予想される。
しかし、言って聞かせたとして、子供はそれに納得するだろうか。もとより、親(大人)の振る舞いに、いじめを肯定しつつ否定するという矛盾が含まれているのだ。
(②に続く)
オススメ関連本・諏訪哲二『オレ様化する子どもたち』中公新書ラクレ
公教育の現場では、体罰が禁止されて久しい。家庭においても、体罰を振るう親の総数、及び振るわれる体罰の度合いは、一貫して減少傾向にあると思われる。
その流れの中にあって、たまに体罰必要論が唱えられる。曰く「叩かなければわからない子供もいる」「痛みを感じるのもひとつの教育効果だ」等。これらの言説は少数派に属するので、大きな潮流を生み出す程の力はない。
だが、僅かにせよ必要論を信奉する人々がいるという点、また、組織によっては、暗黙の了解として体罰が公然とまかり通っている点などを概観すると、日本社会は、「体罰は悪である」との共通認識を持つまでには至っていないようだ。
小生は、原則として体罰に反対である。
その理路を述べる前に、まず言葉の定義をしておく。
本論では「体罰」と「暴力」の二つの言葉を使う。普段、二つの言葉を混同して使っている人もいるだろうし、「体罰は暴力ではない」と主張している人もいるが、ここでは体罰を「行使する側が、必要に迫られてやむを得ず、もしくは何らかの教育的効果を求めて執行する肉体的加害行為」、暴力を「体罰も含む加害行為全般」の意味で使用する。
まず、親が体罰を振るう時、子供の側に何が起きているか、を見てみたい。
子供が親から体罰を受ける。すると子供は、「親(大人)の言うことを聞かないと痛い目に遭う」ことを学ぶ。そこまでは誰にでもわかることだが、ほとんどの人は、子供が学んでいるのはそれだけだと思い込んでいるのではないだろうか。だが、それだけではない。同時に子供は、「他者を従わせるのに、暴力行為は極めて有効だ」という真理をも学んでいるのである。
この学習に基づき、子供がどのような行動を取るかは、想像に難くない。子供は、自分よりも弱い者に狙いを定め、暴力によるコントロールを計るだろう。
一口に子供の暴力と言っても、同い年同士、対等な力関係にある者同士の殴り合い、つまり一般的なケンカもあるが、それはここでは問題としない。該当するのは「年上から年下への暴力」「男から女への暴力」「気の強い者から気の弱い者への暴力」である。この構造が固定化・持続化したのが、いわゆる「いじめ」である。
つまり、親(大人)は体罰を振るうことで、いじめのやり方を子供に教えてもいるのである。
もちろん、体罰を受けた子供の全員が全員、このような行動に走るわけではない。だが、一部の子供がそうなるだけで、充分大きな影響があるのである。
「年上から暴力を振るわれた年下」は、何を思うだろうか。やはり彼も、「他者を従わせる暴力の有効性」を学ぶだろう。そして、その学びを自分よりさらに年下の者に適用するだろう。かくして、暴力は連鎖する。
ここでは肉体的暴力に限って話を進めているが、勘のいい子供ならやり方を応用し、精神的な手段でも他人を支配しようとするはずだ。
いじめも、社会問題として長年議論され、様々な対策が講じられているが、あまり大きな成果は上がっていない。その原因の一つには、親(大人)の子供への体罰があると思う。子供の暴力の連鎖の源は、親(大人)の体罰である。親(大人)がいじめを肯定する行為を行っておきながら、「いじめをやめろ」と言っているのだ。欺瞞を孕んだ者の言説は、説得力を持ち得ない。(先に述べたように、いじめは必ずしも物理的暴力を伴うものではないが、何らかの力による脅迫で抵抗させなくする、という点で、暴力行為と同根である)
これに対しては、「体罰は躾のために許される行為であって、弱い相手に、私的な願望を強いるために行われるそれとは違う」という点を、体罰と同時に子供に言い含めればいいのではないか、という反論が予想される。
しかし、言って聞かせたとして、子供はそれに納得するだろうか。もとより、親(大人)の振る舞いに、いじめを肯定しつつ否定するという矛盾が含まれているのだ。
(②に続く)
オススメ関連本・諏訪哲二『オレ様化する子どもたち』中公新書ラクレ










