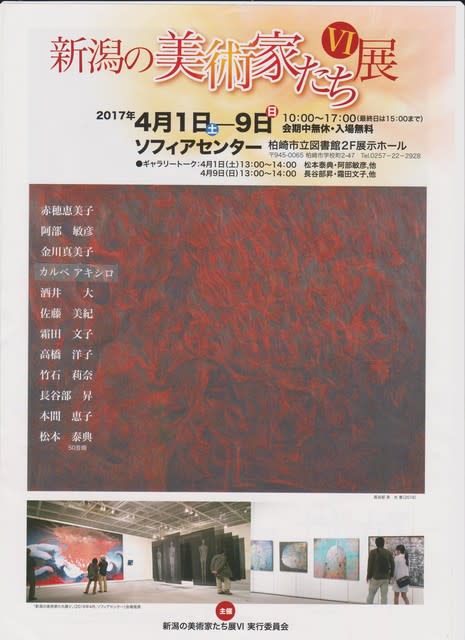写真は備前焼の人間国宝、伊勢崎淳氏の傘寿を記念した作品集である。この豪華本の著者は巌谷國士氏。昨秋、游文舎宛てに寄贈を受けた。巌谷氏と伝統的な陶芸というとちょっと意外な気がする。実際多くの人の反応もそうだったらしい。しかしページを繰るとその謎は一気に氷解する。
そこには、花器や皿といった、用途を持った作品ばかりでなく、太古の地層からむくむくと生まれ出て、蠢き出している、そんな生命感あふれるオブジェが、ごろごろしているのだった。
「物質」「生命」「風土」「有為自然」と章立てされた解説もまた、一般的な陶芸の本とは一線を画すが、何よりもこの本の特異さは年譜にある。ほとんど評伝に近い詳細な年譜は、伊勢崎氏の関心や嗜好が呼び寄せるかのように、次々と人のつながりができ、創作源となってきたことを明かしていく。若いときから少し年長で同郷のオブジェ作家・岡崎和郎と交友があったことは大きい。しかしそれも伊勢崎氏の資質がもたらしたともいえよう。そして瀧口修造や河原温、池田満寿夫、イサム・ノグチ等と親交を結び、さらに瀧口の紹介でミロの工房も訪れたという。また2015年には岡崎和郎、中西夏之との三人展を行っている。
さて、5月13日から伊勢崎氏の作品展が開催され、オープニングには巌谷氏の講演もあるという。会場は京都のギャルリー宮脇。アール・ブリュットはじめいつも意欲的な企画をしていて、游文舎でも「フランソワ・ビュルラン」展では企画協力をしていただいている。この組み合わせを見逃すわけにはいかない。
会場には割れ目や穿孔が効果的な「クレイ・ボール」や、精霊が深呼吸しているような「魑魅魍魎」「幻想植物」等が並ぶ。そして2014年に制作された「倒木再生」という、根とも幹ともつかない陶片のインスタレーション。いずれも重量感がありながら伸びやかで、陶土自体が流動し変成したかのようで、作為を感じさせない。その上で大地に根ざしていることを忘れさせない圧倒的な存在感、物質感を放っている。土と火と水が織りなす最もシンプルにして力強い、まさに「物自体」―オブジェなのだ。
巌谷氏は講演の中で、伊勢崎氏の言う「伝統とは革新の連鎖である」について、室町以前の穴窯を復活させたことが大きいとし、穴窯という古来の手法が、不安定故の偶然性も含めて、その物質性を最大限に引き出しているのだという。伝統の復活とは創造行為に他ならないのだ。そして、そこで作られた作品は、人間の営みとしての陶芸を思い起こさせ、風土、土地の記憶と結びつき、アニミズムをも感じさせ、国家の枠を超えた普遍性を持つのだと語った。
現代アートに接近するほどに、伊勢崎氏の作品は土や大地を意識させるものになっている。そして太古から生き続け、現代アートが滅んだ後も生き延びるであろう生命を想像させるのである。(霜田文子)



















 酒井大はプロ写真家として魚沼の自然や人を感性豊かに撮り続けている。雪の中の木々を縦構図に切り取った写真に暖かさと厳しさを見た。展示方法にも注目したい。
酒井大はプロ写真家として魚沼の自然や人を感性豊かに撮り続けている。雪の中の木々を縦構図に切り取った写真に暖かさと厳しさを見た。展示方法にも注目したい。