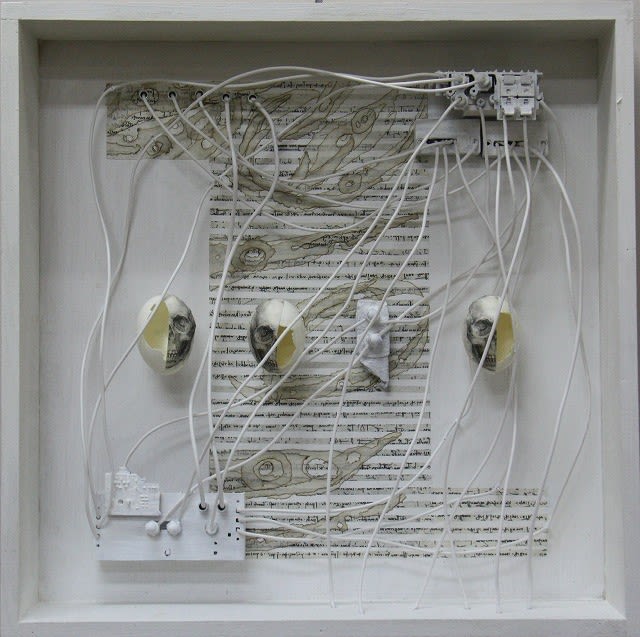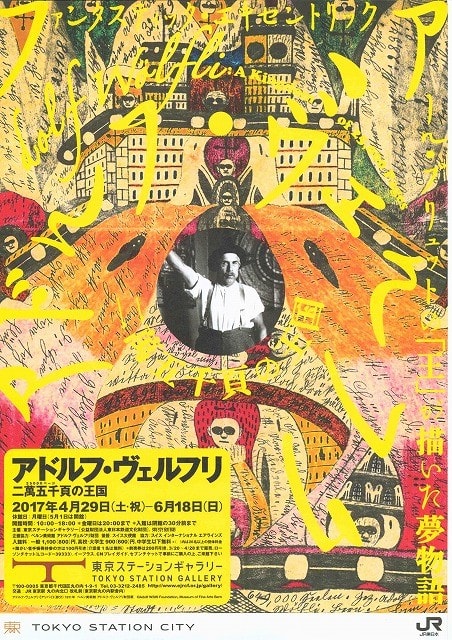ジャコメッティの彫刻作品についてまず思いをめぐらせてみる。それが誰にとっても「見える通りに」作られていないことは一目瞭然であり、ならば「見える通りに」を「私に見える通りに」と言い換える必要があるだろう。
ジャコメッティのものの見方が一般とは違うのではないか。つまりは対象に対して何を見ようとするかという、基本的なところが違っているのだとしか考えられない。
たとえば、ジャコメッティが対象となる人物の中に、その〝本質〟を見ようとしたのだと考えることもできる。しかし、本質とは何か? 本質とは言語によって分節化された事物や事象を規定する普遍的な概念であって、高度に抽象的なものである。
ジャコメッティの細長い人物像は、ほとんど表情というものをもっていないし、肉体の固有性も、人物としての固有性すら失われている。だからそれを抽象的な作品と呼ぶこともできるのだが、ではなぜジャコメッティはモデルに拘ったのだろう。
モデルを長時間坐らせ続け、少しでも動けばすべてが台無しになったとでも言うように、悲嘆の声を上げたのはなぜだったのだろう。それはモデルに対して人間としての普遍性を求めてなどおらず、そのモデルの固有性を追究するためだったとしか思えない。
そのことは《モデルを前にした制作》のセクションに展示された、弟ディエゴの胸像を見ていると理解されることである。それらの作品は明らかに、夕暮れ時の影のように引き伸ばされた人間の像とは違っている。ディエゴの像はジャコメッティが創造した規範に従いつつも、対象の個性というものを写し取っているではないか。
ではジャコメッティは抽象的な本質と、個別の本質という二重の規範を打ち立てたのだろうか? そしてジャン=ポール・サルトルが「ジャコメッティは実存を描いた」と言うときの実存とは、どちらのケースに当て嵌まるのだろうか。そもそも個別の本質などというものが存在するのだろうか。
サルトルは「実存主義はヒューマニズムである」で、「実存は本質に先立つ」という有名なテーゼを残しているが、ジャコメッティは本質をではなく本質に先立つ実存を形象化したのだろうか。
サルトルの思想が破綻して以降、今日では〝実存〟という言葉はほとんど使われなくなったが、サルトルが言っていることの意味は分かる。本質とは言語の文節機能が生み出す規範(モデル? 典型?)としての概念であり、それはいわば〝制度〟の中に置かれる。それに対して実存は、なにものでもないものとしての存在を意味し、一回きりの固有の存在を意味している(サルトルは神が創り出した規範としての本質と、無神論的な実存とを対比させているが、私は神を持ち出さずに言っている)。
そこにサルトルのいう実存主義の要諦はあったし、サルトルはジャコメッティの作品の中に自分の思想を裏付ける証拠を見ようとしたのだと言うことができる。
本当にでは、ジャコメッティはサルトルの言う実存を指向していたのだろうか。確かに〈犬〉という、人物像ばかり作っていたジャコメッティにとっては例外的な作品を見ていると、そこには作者によって感情移入された老残の犬がいて、ジャコメッティはその犬の固有の存在を追究しているのに違いないと思わせる。
まさに実存的な犬、あるいは存在論的に創造された犬とでも呼ぶしかないそれは、怖ろしい作品ではあるが、ジャコメッティにとってはあくまで例外的な作品なのだ。人物がそのような相貌のもとに形象化されたことはない。
ところで私は、まだ彫刻以外の作品について触れていない。私が見たかったのはジャコメッティの油彩作品だったので、今回それが二点しか展示されていないことに失望を覚えた。
でも〈マルグリット・マーグの肖像〉と一点の風景画に、ジャコメッティの彫刻とは別の〝規範〟を見る思いがした。マルグリットは正面を向き、手を組んで座っている。こんな変哲もないポーズの肖像画をジャコメッティはなぜ描いたのか。
「見える通りに」描くために、モデルが長時間一定のポーズをとり続けるとしたら、このポーズ以外他にあり得ない。しかし、こんなポーズではその人間の個性や実存など描きようがないではないか。
そしていつものように、顔はいくつもの黒い線でつぶされていて、まるで黒人の肖像画のようだ。あるいは〝亡霊のような〟と言ってもよい。背景はグレーの絵の具でぞんざいに描かれているから、ジャコメッティの彫刻家としての視点はよく理解できる。背景はほとんど意味をなしていない。
ところがこのグレーを基調としたいい加減な背景が、亡霊を出現させるための舞台装置となる。顔を黒くつぶされたマルグリットはそこに亡霊のように座っている。リアリティを欠落させた背景の方が、亡霊の舞台として相応しいのである。
顔が無数の線で描かれると言うよりは、破壊されていくさまを我々は矢内原伊作の肖像デッサンに見ることができる。この線はいったい何なのだろう?
真実を確定させるために引かれる無数の線の試行錯誤の軌跡とでも言えばいいのだろうか。とにかくジャコメッティという人は作品の完成を目指そうとしない。それは多分、自分の行為が不可能に向かっての無益なそれであることを自覚していたからなのであろう。
「見える通りに彫刻し、描き、あるいはデッサンすることが、私には到底不可能だということを知っています」という言葉はそのように理解されなければならない。
(この項おわり)