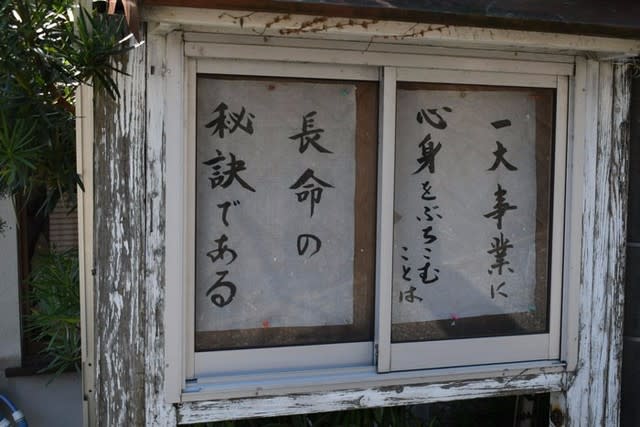3月11日(日)、霧島市隼人町の鹿児島神宮で初午祭が開催されました。
例年通り9時半から15分置きに22団体が出場。鈴掛馬を先頭に鉦と三味線に合わせた賑やかな踊りが披露・奉納されました。
木田の御神馬を参道広場で待つ

これまでは踊りの列に同行して撮影していましたが、今年は参道広場に一行が到着するのを9時半頃からずっと待ちました。9時半に出発した一行が広場に到着したのは10時20分頃でした。
撮影には待つことも必要ですが40分も待つのは久しぶりでした。桜島の夜間爆発撮影では一晩中寝ずに待ちますので、それに比べれば大したことではありません。広場の柵にもたれ一脚を調整。お隣さんと世間話を交わし期待感を高めながら待ちました。
踊りの様子 神宮社殿は森の上

神宮側から撮影

鈴掛馬を先頭に踊り広場に入場し時計回りで2周踊ります。そのあと馬は休憩し随行の踊り手が一曲踊り、鈴掛馬が再び先頭に立ち広場を回って神宮境内へ上がっていきます。
一脚が活躍し安定した動画撮影もできました。望遠レンズ使用時も高さを調整しながら撮影に集中できました。歩き回るときに左手で持ちまわるのは荷物でしたが、人込みの中では三脚よりはるかに威力を発揮しました。
鹿児島神宮参道階段からの撮影

同じく踊り広場に接近

参道には踊り連と観覧客の人波がずっと続いています。鈴掛馬に随行して撮影する人も多いですが参道両側に出店が並び人波もあって、スナップ程度にしか撮影できません。快晴のため光が強烈でコントラストが強すぎて撮影しにくい状態でした。
木田の御神馬

ポニーの鈴掛馬

色とりどりに美しい椿 岩根絞

祭りの名物 ポンパチ

人を集める射的

水分とアルコール分を補給

13時を回ると次第に人波も引き始めたので参道を下り東方向に向かいました。殆ど隙間なく出店が並び、氷菓を手にする子供たちもいました。振る舞い酒も見かけましたが車運転の人が多かったようで、もらう人は少ないようでした。
出店を見ると幼い頃が思い出されますが、とにかく人が多くて感慨にふける間もなく数か所をスナップした程度でした。
新燃岳からの降灰なし
3月1日から噴火している霧島連山新燃岳では火口からあふれた溶岩がわずかに斜面に出ています。参道入口からも新燃岳からのわずかな白煙が見えました。警戒範囲は新燃岳から4km以内に拡大されていますが、初午祭には全く影響がなくて幸いなことでした。
例年通り9時半から15分置きに22団体が出場。鈴掛馬を先頭に鉦と三味線に合わせた賑やかな踊りが披露・奉納されました。
木田の御神馬を参道広場で待つ

これまでは踊りの列に同行して撮影していましたが、今年は参道広場に一行が到着するのを9時半頃からずっと待ちました。9時半に出発した一行が広場に到着したのは10時20分頃でした。
撮影には待つことも必要ですが40分も待つのは久しぶりでした。桜島の夜間爆発撮影では一晩中寝ずに待ちますので、それに比べれば大したことではありません。広場の柵にもたれ一脚を調整。お隣さんと世間話を交わし期待感を高めながら待ちました。
踊りの様子 神宮社殿は森の上

神宮側から撮影

鈴掛馬を先頭に踊り広場に入場し時計回りで2周踊ります。そのあと馬は休憩し随行の踊り手が一曲踊り、鈴掛馬が再び先頭に立ち広場を回って神宮境内へ上がっていきます。
一脚が活躍し安定した動画撮影もできました。望遠レンズ使用時も高さを調整しながら撮影に集中できました。歩き回るときに左手で持ちまわるのは荷物でしたが、人込みの中では三脚よりはるかに威力を発揮しました。
鹿児島神宮参道階段からの撮影

同じく踊り広場に接近

参道には踊り連と観覧客の人波がずっと続いています。鈴掛馬に随行して撮影する人も多いですが参道両側に出店が並び人波もあって、スナップ程度にしか撮影できません。快晴のため光が強烈でコントラストが強すぎて撮影しにくい状態でした。
木田の御神馬

ポニーの鈴掛馬

色とりどりに美しい椿 岩根絞

祭りの名物 ポンパチ

人を集める射的

水分とアルコール分を補給

13時を回ると次第に人波も引き始めたので参道を下り東方向に向かいました。殆ど隙間なく出店が並び、氷菓を手にする子供たちもいました。振る舞い酒も見かけましたが車運転の人が多かったようで、もらう人は少ないようでした。
出店を見ると幼い頃が思い出されますが、とにかく人が多くて感慨にふける間もなく数か所をスナップした程度でした。
新燃岳からの降灰なし
3月1日から噴火している霧島連山新燃岳では火口からあふれた溶岩がわずかに斜面に出ています。参道入口からも新燃岳からのわずかな白煙が見えました。警戒範囲は新燃岳から4km以内に拡大されていますが、初午祭には全く影響がなくて幸いなことでした。