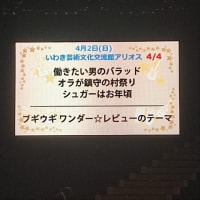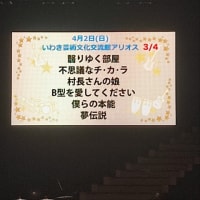D・ヘンリッヒ『神の存在論的証明』(叢書・ウニベルシタス)
この本は、
デカルト→スピノザ→ライプニッツ→ヒューム→カント
という大まかな近世哲学の流れの中で、改めて「課題」として取り上げられ続けていく「神の存在証明」の歴史を見ていく本である。
まあ実際には
デカルト→マールブランシェ→スピノザ→モアとカドワース→ライプニッツ→ヴォルフ→バウムガルデン→メンデルスゾーン→ガッサンディ→ユエ、エルミニエ、パーカー→ウェーレンフェルス→ジャクロとクルージウス→モスハイム→リュディガーとクルージウス→ベーリング→ヒューム→カント
(あー長っ!)
という順番でそれぞれの「神の存在論的証明」とそれに対する反駁が挙げられていきますが。
それぞれの思想家の「哲学」の核をきちんと拾っていく本ではない。
ただひたすら「神様の存在」の証明に関して追跡していくものだ。
だが、これがすこぶる面白い。
こういう本の常として、文字を追っていくだけでは全体の意図と配置が見えにくい
。だから、一度読んだだけでは何のことやら、というのが実情だ。
購入したのは震災前だったはず。
何度か読んでは巻を置き、しばらくしてまた手に取るという状態が続いていた。
だが、震災以後、そして自分の中でのスピノザブレイク以後、次第にこの「神」の存在を証明しようとする近世哲学者の営為が、ただの「面白い行為」ではなく、身近に切実なものとして感じられるようになってきつつある。
そんな中で読み直し始めたら、これがなんと「読める」ようになっていた。
自分の中で「神」に向き合うスタンスがいつのまにか醸成されてきていた、ということなのだろう。
ま、もちろん「読める」っていうのは一つの「偏見」から別の「偏見」にジャンプすることにすぎない(目から鱗が落ちるのか、目が鱗で塞がるのか区別できない)という見方もありえる。
だが、そのみかけの「相対主義」めいた「懐疑」の向こう側というか、その懐疑によっては「解決」しない「問い」の存在が、ようやく私にも見えてきた、ということのようだ。
やっぱり年、かな?
ともあれ、これからスピノザ入門講座もいよいよ『エチカ』に入っていく。
しかし、『エチカ』冒頭に置いてある神の存在証明の「読めなさ」たるや、かなりのものだ。
ようやくそのテキストの麓に立とうとしている、ということかもしれない。
内容理解についてはまだおぼつかないのだが、このヘンリッヒによれば、
近世における(デカルト以後の)神の存在証明には二つのポイントがあって、
第一の存在論的証明→「完全な存在者」にこだわる考え方。
第二の存在論的証明→「必然的存在者」に関わる考え方。
どちらかといえば、個人的には第2番目の、「必然的存在者」という考え方の方が腑に落ちる。
ちなみにスピノザもこちらに分類されています。
いわゆる「神は<自己原因>である」っていう考えですね。
何かが存在するためには、その原因が考えられなければならない。
何かに因って生じている存在は、その他者たる原因に依存している。
だが、このリミットを考えれば、第一の根本原因に遡らねばならない。
もし、自己を原因とする「第一動者?」的なものが必然的に存在する、と考えなければ、もしそういう「神」的なものがないというリミットを取れば、結局全ての形而上的認識が成立しなくなっちゃう……
(この「必然的存在者」の証明の方向の延長線上に、ヒューム的経験論を踏まえたカントの形而上学批判があるって話なんですが、まだそこまでは理解してません)。
ま、とりあえずそんな方向だと読み始めています。
この二番目の「必然」っていう感じはよく分かる。っていうかフィットする。
でも、前者の「完全な存在者」が存在するっていう、中世神学からの連続性を感じさせる一番目の「神の存在証明」は、正直、できの悪い冗談みたいにしか感じられません。
でも、「アンセルムス以来の」とか書かれているので、これから中世神学の参考書をひっくり返してもう少し考えてみます。
神は、それ以上に大きなものを決して考えることができないような存在者として思惟される。
神の本質のうちでは、現実性や可能的なもののすべての積極的規定が合一されている。神は賢明で、力能があり、善なるものであり、しかも比類無くそうである。それゆえ、神は最も完全な存在者である……
分からない(笑)。
でも、今個々に「ある」っていうことにおける存在と認識とを、徹底的に考えていくっていうことをしようとしているんだろうな、ってことは分かる。
「神」は当時の議論における超越性(1なるものへと収斂する議論)を論じる上の必須アイテムだったのだろうから。
でも、当時といっても近世は、中世とはやっぱり違う。
その議論の基盤の変化、みたいなこともいずれは少しずつ学んでいかねばならないのだろうし、そのためには中世神学論争みたいなところもさらっとは見ておかないといけないんでしょうねえ。
いくら時間があっても足りないですが、面白いっちゃ面白い。
ただのいわゆる哲学史を無味乾燥になぞっていくよりは、「神の存在証明」っていう「問題設定」を巡ってさまざまな哲学者がどんな風に腕を振るったのか,意味不明ながら少しずつ理解していければかなり楽しいんじゃないかな、と。
本当は早くカントのところにたどり着いて、一度大まかに理解してから17世紀にまた戻っていきたいのだけれど、とりあえずはアンセルムスを調べてきます。ふいぃー。
でもこういうの、いいですね。
だんだん学者さんの論文というか本を読んでるだけじゃあつまらなくなってくるんですよねえ。
それぞれの哲学者のテキストそれ自体を読みたくなる。
ほんと、老後の時間がどれだけあっても足りません。
引退準備にしては、風呂敷が広がりすぎそうです。
この本は、
デカルト→スピノザ→ライプニッツ→ヒューム→カント
という大まかな近世哲学の流れの中で、改めて「課題」として取り上げられ続けていく「神の存在証明」の歴史を見ていく本である。
まあ実際には
デカルト→マールブランシェ→スピノザ→モアとカドワース→ライプニッツ→ヴォルフ→バウムガルデン→メンデルスゾーン→ガッサンディ→ユエ、エルミニエ、パーカー→ウェーレンフェルス→ジャクロとクルージウス→モスハイム→リュディガーとクルージウス→ベーリング→ヒューム→カント
(あー長っ!)
という順番でそれぞれの「神の存在論的証明」とそれに対する反駁が挙げられていきますが。
それぞれの思想家の「哲学」の核をきちんと拾っていく本ではない。
ただひたすら「神様の存在」の証明に関して追跡していくものだ。
だが、これがすこぶる面白い。
こういう本の常として、文字を追っていくだけでは全体の意図と配置が見えにくい
。だから、一度読んだだけでは何のことやら、というのが実情だ。
購入したのは震災前だったはず。
何度か読んでは巻を置き、しばらくしてまた手に取るという状態が続いていた。
だが、震災以後、そして自分の中でのスピノザブレイク以後、次第にこの「神」の存在を証明しようとする近世哲学者の営為が、ただの「面白い行為」ではなく、身近に切実なものとして感じられるようになってきつつある。
そんな中で読み直し始めたら、これがなんと「読める」ようになっていた。
自分の中で「神」に向き合うスタンスがいつのまにか醸成されてきていた、ということなのだろう。
ま、もちろん「読める」っていうのは一つの「偏見」から別の「偏見」にジャンプすることにすぎない(目から鱗が落ちるのか、目が鱗で塞がるのか区別できない)という見方もありえる。
だが、そのみかけの「相対主義」めいた「懐疑」の向こう側というか、その懐疑によっては「解決」しない「問い」の存在が、ようやく私にも見えてきた、ということのようだ。
やっぱり年、かな?
ともあれ、これからスピノザ入門講座もいよいよ『エチカ』に入っていく。
しかし、『エチカ』冒頭に置いてある神の存在証明の「読めなさ」たるや、かなりのものだ。
ようやくそのテキストの麓に立とうとしている、ということかもしれない。
内容理解についてはまだおぼつかないのだが、このヘンリッヒによれば、
近世における(デカルト以後の)神の存在証明には二つのポイントがあって、
第一の存在論的証明→「完全な存在者」にこだわる考え方。
第二の存在論的証明→「必然的存在者」に関わる考え方。
どちらかといえば、個人的には第2番目の、「必然的存在者」という考え方の方が腑に落ちる。
ちなみにスピノザもこちらに分類されています。
いわゆる「神は<自己原因>である」っていう考えですね。
何かが存在するためには、その原因が考えられなければならない。
何かに因って生じている存在は、その他者たる原因に依存している。
だが、このリミットを考えれば、第一の根本原因に遡らねばならない。
もし、自己を原因とする「第一動者?」的なものが必然的に存在する、と考えなければ、もしそういう「神」的なものがないというリミットを取れば、結局全ての形而上的認識が成立しなくなっちゃう……
(この「必然的存在者」の証明の方向の延長線上に、ヒューム的経験論を踏まえたカントの形而上学批判があるって話なんですが、まだそこまでは理解してません)。
ま、とりあえずそんな方向だと読み始めています。
この二番目の「必然」っていう感じはよく分かる。っていうかフィットする。
でも、前者の「完全な存在者」が存在するっていう、中世神学からの連続性を感じさせる一番目の「神の存在証明」は、正直、できの悪い冗談みたいにしか感じられません。
でも、「アンセルムス以来の」とか書かれているので、これから中世神学の参考書をひっくり返してもう少し考えてみます。
神は、それ以上に大きなものを決して考えることができないような存在者として思惟される。
神の本質のうちでは、現実性や可能的なもののすべての積極的規定が合一されている。神は賢明で、力能があり、善なるものであり、しかも比類無くそうである。それゆえ、神は最も完全な存在者である……
分からない(笑)。
でも、今個々に「ある」っていうことにおける存在と認識とを、徹底的に考えていくっていうことをしようとしているんだろうな、ってことは分かる。
「神」は当時の議論における超越性(1なるものへと収斂する議論)を論じる上の必須アイテムだったのだろうから。
でも、当時といっても近世は、中世とはやっぱり違う。
その議論の基盤の変化、みたいなこともいずれは少しずつ学んでいかねばならないのだろうし、そのためには中世神学論争みたいなところもさらっとは見ておかないといけないんでしょうねえ。
いくら時間があっても足りないですが、面白いっちゃ面白い。
ただのいわゆる哲学史を無味乾燥になぞっていくよりは、「神の存在証明」っていう「問題設定」を巡ってさまざまな哲学者がどんな風に腕を振るったのか,意味不明ながら少しずつ理解していければかなり楽しいんじゃないかな、と。
本当は早くカントのところにたどり着いて、一度大まかに理解してから17世紀にまた戻っていきたいのだけれど、とりあえずはアンセルムスを調べてきます。ふいぃー。
でもこういうの、いいですね。
だんだん学者さんの論文というか本を読んでるだけじゃあつまらなくなってくるんですよねえ。
それぞれの哲学者のテキストそれ自体を読みたくなる。
ほんと、老後の時間がどれだけあっても足りません。
引退準備にしては、風呂敷が広がりすぎそうです。