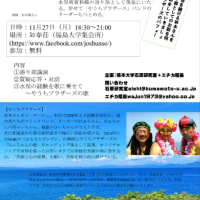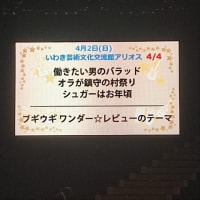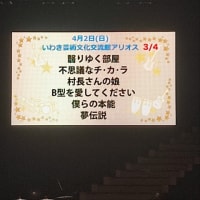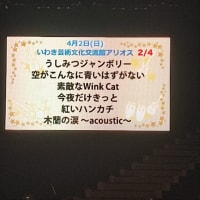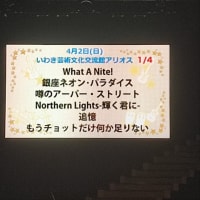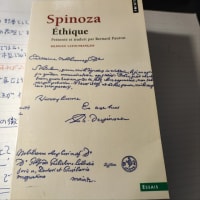ちょっとだけメモ代わりに。
ハイデッガーは、技術が自然の中に隠されたものを見えるようにさせる力があり、人間はその技術的な振る舞いにむしろ「徴発」されて、その仕組みの前に立たされ坊主のように向き合わされ、場合によっては隷属状態になっちゃう、と言う。
で、だから「省察」が必要で、その技術の中に生きる(Yes)と同時にそれにこだわらない(No)を言わなくちゃならなくて、それが「放下」ってことで、と話が展開してく。
でも、ちょっと待ってほしい。
そこで「土着」って出てくるのはなんだかへんだ。
技術の圧倒的な「攻撃」で、土着からは離陸したっていっておいて、その技術は人間の営為とは別立てだっていっておいて、その上で人間の「省察」だけを別途「徴発」しているハイデッガーの手続きは、ちょっと手品っぽくはないか?
丁寧に切り分けながら問題を深めていくステップは凄いと思う。
もしかすると、途中でついていけなくなってるから私が逆ギレしてるだけなのかな、とも思わないでもない。
でも、人間の無力を前提として、なおも人間の「省察」による「土着」に対する思惟の称揚っていうのは、よく考え抜かれた、というよりは、ハイデッガーのやってみたい手品の種、に近いという印象を、今の私はどうしても感じてしまうのだ。
技術の圧倒的な「攻撃」の前で、また、腹蔵された自然のエネルギーを開示する技術によって、むしろ徴兵されるかのように「徴発」され、圧倒的なエネルギーを解放するために奉仕作業をさせられる人間、という分析は間違いなく鋭いと思う。
私の、私たちの実感と結びつく。
そして、遠い所に答えを見いだすのではなく、見つめるべきは自らの傍らにある、というハイデッガーの指摘も納得だ。
だが「土着」ってどうなんだろう。
その後の「放下」はどうなんだろう。
スピノザより「神秘的」な感じがしちゃうのは私だけだろうか。
二重の往復運動を、異質なものの上に交差しながら重ねていくような手捌きを、意味が分からないまま傍観しているしかない、みたいな感触が今の状態だ。
でも、ここをもう少し読み抜きたい。
どの道から谷を降りていくのかの違い、ということなのかもしれないが。
ハイデッガーは、技術が自然の中に隠されたものを見えるようにさせる力があり、人間はその技術的な振る舞いにむしろ「徴発」されて、その仕組みの前に立たされ坊主のように向き合わされ、場合によっては隷属状態になっちゃう、と言う。
で、だから「省察」が必要で、その技術の中に生きる(Yes)と同時にそれにこだわらない(No)を言わなくちゃならなくて、それが「放下」ってことで、と話が展開してく。
でも、ちょっと待ってほしい。
そこで「土着」って出てくるのはなんだかへんだ。
技術の圧倒的な「攻撃」で、土着からは離陸したっていっておいて、その技術は人間の営為とは別立てだっていっておいて、その上で人間の「省察」だけを別途「徴発」しているハイデッガーの手続きは、ちょっと手品っぽくはないか?
丁寧に切り分けながら問題を深めていくステップは凄いと思う。
もしかすると、途中でついていけなくなってるから私が逆ギレしてるだけなのかな、とも思わないでもない。
でも、人間の無力を前提として、なおも人間の「省察」による「土着」に対する思惟の称揚っていうのは、よく考え抜かれた、というよりは、ハイデッガーのやってみたい手品の種、に近いという印象を、今の私はどうしても感じてしまうのだ。
技術の圧倒的な「攻撃」の前で、また、腹蔵された自然のエネルギーを開示する技術によって、むしろ徴兵されるかのように「徴発」され、圧倒的なエネルギーを解放するために奉仕作業をさせられる人間、という分析は間違いなく鋭いと思う。
私の、私たちの実感と結びつく。
そして、遠い所に答えを見いだすのではなく、見つめるべきは自らの傍らにある、というハイデッガーの指摘も納得だ。
だが「土着」ってどうなんだろう。
その後の「放下」はどうなんだろう。
スピノザより「神秘的」な感じがしちゃうのは私だけだろうか。
二重の往復運動を、異質なものの上に交差しながら重ねていくような手捌きを、意味が分からないまま傍観しているしかない、みたいな感触が今の状態だ。
でも、ここをもう少し読み抜きたい。
どの道から谷を降りていくのかの違い、ということなのかもしれないが。