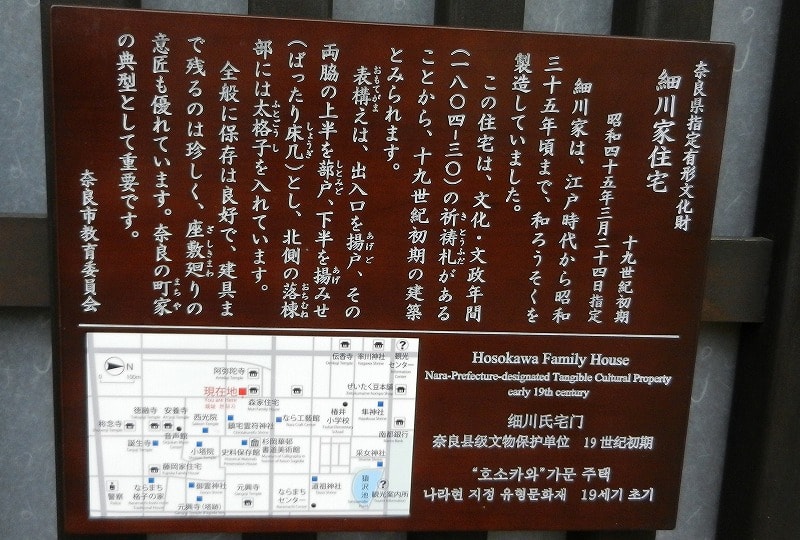県南部の現存する最古の鉄筋コンクリート造の1つです 撮影日;2012.04.08
平成18年度に登録;旧六十八銀行八木支店(旧和歌山銀行橿原支店)
現在はウエディングレストランとして活用されています「La BANK」
近代建築の優美さと重厚なたたずまいで、道行く人々の目を止めます
昭和3年竣工、設計は元奈良県技師・舟橋俊一氏です
国道165号線沿いに建っています
両翼を薄く張り出したルネッサンス風の形態で、中央部の玄関とその上部の半円形窓の左右にイオニア式の円柱を配しています
幾何学的な細部や玄関廻りタイルの芋目地貼等に新味が認められます
六十八銀行は旧郡山藩主柳沢保申が明治12年(1879)に提唱した国立銀行です
その後、昭和9年(1934)に吉野銀行・八木銀行・御所銀行と六十八銀行は合併し、現在の南都銀行となりました
昭和38年からは和歌山相互銀行橿原支店(後に改組により、和歌山銀行橿原支店)として使用されていましたが、支店統合で橿原支店消滅となりました
一時は、映画館としても使われたそうです
★所在地;橿原市八木町1-501-2
★交通;近鉄
 八木西口駅下車 徒歩3分
八木西口駅下車 徒歩3分★駐車場;なし
★問合せ;0744-29-5902(橿原市文化財局文化財課)