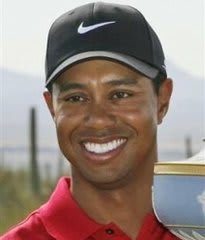毎年恒例の「初市」(※注)に際して自転車レーンと自動車道を立体的に区画する縁石とポラードが取り外され、積雪期の真っ只中であるだけに除雪車の円滑な稼動のためにこれらの立体的区画物は春までに取り外されたままになるのかとも心配していたが、この初市が終了後は上の写真の通りポラード(棒杭)だけは再び取り付けられた。
※注:前回の記事か姉妹ブログ「山形の過去、現在、未来」の1月10日付けの記事を参照
だが、自転車愛好者には喜ばれる自転車専用レーンではあるが、やはり冬季には難点があり、行政にも頭が痛い問題であることは確かである。
それは当然、積雪や凍結の場合の問題である。
除雪車は自動車道路では幅員が広いために稼動しやすいし、ここの歩道は中心商店街の沿道であるために地下水循環による融雪設備が張り巡らされているため、かなりの歩道上の積雪もすぐ融解するので歩行者は転倒の心配もなく歩くことができる。
これに対して自転車レーンでの除雪はこの狭い幅員を稼動できる除雪車(または除雪機)の数が限られていることもあり、この写真でわかるように後回しされがちのようである。
自動車、歩行者、自転車の3者の中で最も雪道や凍結道路が苦手なのが自転車である。
クルマは減速さえすればわずかなスリップはあっても横転まですることは少ないし、歩行者も用心して歩けば転倒することはやはり少ない。
しかし、雪道や凍結道路での自転車ほど転倒の危険性が高いものはない。
だから、冬季はよほどこまめな除雪がなされないと、多くの自転車族は自転車レーンでの走行を避けがちで、融雪される歩道を走行し、歩行者を危険にさらすようになる。
むろん、自転車専用レーンがある区間だけを除雪しても他の専用レーンのない地域を走る自転車は冬季は極少になるから、自転車専用レーンがある区間を走る自転車もかなり少なくなるであろう。
それでも、行政が環境に優しい乗り物として積極的に市民に対し自転車利用を推奨するなら、やはり積雪がある場合は真っ先に自転車レーンから除雪を始めるべきであろう。
併せて、自転車レーン設置の地域の急速な拡大策を図るべきであろう。
中心商店街の周辺で新たに拡幅または新設された道路ではかなりゆったりした幅員の融雪歩道も敷設されている場合が多いので、その一部を自転車レーンに変更したとしても、そのために自動車の部分が削減されることもないのでクルマ利用者からの苦情もほとんど考えられない。
※注:前回の記事か姉妹ブログ「山形の過去、現在、未来」の1月10日付けの記事を参照
だが、自転車愛好者には喜ばれる自転車専用レーンではあるが、やはり冬季には難点があり、行政にも頭が痛い問題であることは確かである。
それは当然、積雪や凍結の場合の問題である。
除雪車は自動車道路では幅員が広いために稼動しやすいし、ここの歩道は中心商店街の沿道であるために地下水循環による融雪設備が張り巡らされているため、かなりの歩道上の積雪もすぐ融解するので歩行者は転倒の心配もなく歩くことができる。
これに対して自転車レーンでの除雪はこの狭い幅員を稼動できる除雪車(または除雪機)の数が限られていることもあり、この写真でわかるように後回しされがちのようである。
自動車、歩行者、自転車の3者の中で最も雪道や凍結道路が苦手なのが自転車である。
クルマは減速さえすればわずかなスリップはあっても横転まですることは少ないし、歩行者も用心して歩けば転倒することはやはり少ない。
しかし、雪道や凍結道路での自転車ほど転倒の危険性が高いものはない。
だから、冬季はよほどこまめな除雪がなされないと、多くの自転車族は自転車レーンでの走行を避けがちで、融雪される歩道を走行し、歩行者を危険にさらすようになる。
むろん、自転車専用レーンがある区間だけを除雪しても他の専用レーンのない地域を走る自転車は冬季は極少になるから、自転車専用レーンがある区間を走る自転車もかなり少なくなるであろう。
それでも、行政が環境に優しい乗り物として積極的に市民に対し自転車利用を推奨するなら、やはり積雪がある場合は真っ先に自転車レーンから除雪を始めるべきであろう。
併せて、自転車レーン設置の地域の急速な拡大策を図るべきであろう。
中心商店街の周辺で新たに拡幅または新設された道路ではかなりゆったりした幅員の融雪歩道も敷設されている場合が多いので、その一部を自転車レーンに変更したとしても、そのために自動車の部分が削減されることもないのでクルマ利用者からの苦情もほとんど考えられない。