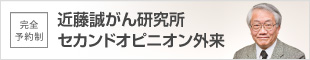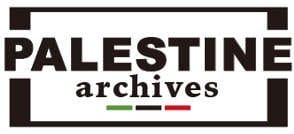総タイトル:【日本人のルーツを取り戻す(4)・・・元々は多民族国家であった日本の中の一部に、アブラハム―イサク―ヤコブの血統のユダヤ人の子孫が・・・「日本人のルーツはユダヤ人だ―古代日本建国の真相」を読んで】
「日本人のルーツはユダヤ人だ―古代日本建国の真相」(著者:小谷部全一郎氏、出版社:たま出版、出版日:1991/11/20) (※1929年(昭和4年)出版で現在絶版の同氏著「日本及日本国民の起源」上・下巻を編集したもの。)
神学者・牧師・教師・哲学博士・アイヌ研究家の著者の原書が出版されたのは今から84年前になります。過去に購入して読んだ本書を再読しました。元々は多民族国家であった日本の中の一部に、アブラハム-イサク-ヤコブの血統のユダヤ人の子孫が含まれている事を伺う事が出来ます。全ての日本人がユダヤ人の子孫である訳ではありません。
本書の中からの極一部の概要を以下に記します。
・七草粥、門松、・・・「過越しの祭り」、七日間、無醗酵のパン(餅)、苦菜、常磐木の枝、旧約聖書・出エジプト記12章。
・鳥居・・・鴨居と左右の柱に羊の血。旧約聖書・出エジプト記12章。
・禊・・・洗礼。潔斎(モノイミ)。神殿前の手洗盤。履物を脱いで(足を洗って)家に上がる風習。 潔癖症。
・おみくじ・・・くじによる取決め。イスラエル十二部族のカナン相続地割当(旧約聖書・ヨシュア記14章2節)等。
・養蚕・・・桑、絹、機織り。
・捺印。文章右書出し(~戦前)。
・一日と十五日の休日(~江戸時代)・・・旧約聖書・エステル記からのプリム祭(14・15日)。
・相撲・・・旧約聖書・創世記32章24~30節。
・神宮の構造・・・神殿の構造。拝殿と奥殿、聖所と至聖所。
・獅子・獅子舞・・・神社、神殿。
・榊・・・ヒソプ。清めの式、玉串の神前への供え。
・注連縄(しめなわ)・・・神殿の柱、神器、手洗盤等。
・神社の神の数詞「柱」・・・唯一の創造主である神の表示。創世記31章等。
・純白の尊重・・・白亜麻布の祭服・エポデ。純白の斎服、白馬、白猪、白鶴、白雉……。
・清めの塩・・・旧約聖書・士師記9章45節等。保存食の腐敗予防。調味、調和。死海。
・触穢(しょくわい)の禁忌・・・旧約聖書・民数記6章6節等。神職、祭司。
・お守り札・・・住居の入口、木製小箱。
・鳩・・・旧約聖書・レビ記12章6・8節。罪の為のいけにえ。
・賽銭箱・・・旧約聖書・列王記 第二12章7~16節、新約聖書・マルコの福音書12章41~44節等。献金箱。
・神酒・・・旧約聖書・出エジプト記29章40節等。注ぎの奉げ物のぶどう酒。
・新嘗祭・・・ 旧約聖書・出エジプト記23章19節等。初穂、初なり、初子、初物の奉げ物。
・拍手とお辞儀。
・神輿・・・契約の箱。
・神楽舞・・・旧約聖書・サムエル記 第二6章5節等。琴、瑟(しつ)、鼓、鈴、鐃鈸(にょうはち、シンバル)、立琴(竪琴、ハープ)、カスタネット。
・祇園祭・・・旧約聖書・創世記8章4節、7月17日「ノアの箱舟」のアララト山漂着。シオン(Zion)→ギオン。
・室(ムロ)・・・旧約聖書・サムエル記 第二5章9節「ミロ」。ダビデの城塞。
・スサノオノミコトはスサ(ペルシャ)の王・・・天孫族。 エソ人はスサノオノミコトを首長として先住民クシ人と協力。
・土着民で出雲の「エビス人(クシ、土蜘蛛)」・・・故郷カナン(現パレスチナ、エルサレム付近)。エブス人→ エビス人。
・出雲民族「エソ人」・・・故郷カナン(現パレスチナ)。アブラハムと正妻サラとの子イサクとその妻リベカの子エサウ→エドム人→エソ人(蝦夷、イズモ人、アイヌ人)。エサウの双子の弟ヤコブ(イスラエル)→へブル人→ユダヤ人。
・武蔵一宮氷川神社・・・イズモ人の東遷。エドム→江戸。
・高天原・・・アルメニア・タガーマ州ハラン→アメ(天)のタカマガハラ(高天原)。
・御船代・・・伊勢神宮。三種の神器。諏訪神社「御船祭」。Ark(契約の箱、ノアの方舟)。神輿水中渡御。 旧約聖書・出エジプト記14章15~31節。
・日本・・・アブラハムの子イサクの子ヤコブの子ガドの子「ツェフォン(Zephon、ゼポン、ツィフヨン)」→「ニッポン」。旧約聖書・創世記46章16節、同・民数記26章15節。
・帝(御門、ミカド)・・・「御」+「ガド」→「ミカド」。
・十二社神社・・・十二社(じゅうにそう、十二祖)。熊野三山(熊野大社)。八咫烏。ヤコブ(イスラエル)の十二子息(十二部族)。十二弁菊花紋。
・日本の地名は殆どアイヌ語・・・島根(サパネ、君臨統治の所(首都))、鎌倉(カマカラ、機織る所)等。
・世界を動かすユダヤ人。
・ダン族の建てた英国。
私のブログの、過去の関連ウェブページが次に在ります。↓↓
「日本の正月に存在する古代ユダヤの風習」
「多民族国家の日本に古代ユダヤ人」
以下に、関連動画を添付します。↓↓
尚、次の動画は、1/5~5/5の5分割となっています。↓↓
尚、次の動画は、第1回~第7回の計7回分が有ります。↓↓


「日本人のルーツはユダヤ人だ―古代日本建国の真相」(著者:小谷部全一郎氏、出版社:たま出版、出版日:1991/11/20) (※1929年(昭和4年)出版で現在絶版の同氏著「日本及日本国民の起源」上・下巻を編集したもの。)
神学者・牧師・教師・哲学博士・アイヌ研究家の著者の原書が出版されたのは今から84年前になります。過去に購入して読んだ本書を再読しました。元々は多民族国家であった日本の中の一部に、アブラハム-イサク-ヤコブの血統のユダヤ人の子孫が含まれている事を伺う事が出来ます。全ての日本人がユダヤ人の子孫である訳ではありません。
本書の中からの極一部の概要を以下に記します。
・七草粥、門松、・・・「過越しの祭り」、七日間、無醗酵のパン(餅)、苦菜、常磐木の枝、旧約聖書・出エジプト記12章。
・鳥居・・・鴨居と左右の柱に羊の血。旧約聖書・出エジプト記12章。
・禊・・・洗礼。潔斎(モノイミ)。神殿前の手洗盤。履物を脱いで(足を洗って)家に上がる風習。 潔癖症。
・おみくじ・・・くじによる取決め。イスラエル十二部族のカナン相続地割当(旧約聖書・ヨシュア記14章2節)等。
・養蚕・・・桑、絹、機織り。
・捺印。文章右書出し(~戦前)。
・一日と十五日の休日(~江戸時代)・・・旧約聖書・エステル記からのプリム祭(14・15日)。
・相撲・・・旧約聖書・創世記32章24~30節。
・神宮の構造・・・神殿の構造。拝殿と奥殿、聖所と至聖所。
・獅子・獅子舞・・・神社、神殿。
・榊・・・ヒソプ。清めの式、玉串の神前への供え。
・注連縄(しめなわ)・・・神殿の柱、神器、手洗盤等。
・神社の神の数詞「柱」・・・唯一の創造主である神の表示。創世記31章等。
・純白の尊重・・・白亜麻布の祭服・エポデ。純白の斎服、白馬、白猪、白鶴、白雉……。
・清めの塩・・・旧約聖書・士師記9章45節等。保存食の腐敗予防。調味、調和。死海。
・触穢(しょくわい)の禁忌・・・旧約聖書・民数記6章6節等。神職、祭司。
・お守り札・・・住居の入口、木製小箱。
・鳩・・・旧約聖書・レビ記12章6・8節。罪の為のいけにえ。
・賽銭箱・・・旧約聖書・列王記 第二12章7~16節、新約聖書・マルコの福音書12章41~44節等。献金箱。
・神酒・・・旧約聖書・出エジプト記29章40節等。注ぎの奉げ物のぶどう酒。
・新嘗祭・・・ 旧約聖書・出エジプト記23章19節等。初穂、初なり、初子、初物の奉げ物。
・拍手とお辞儀。
・神輿・・・契約の箱。
・神楽舞・・・旧約聖書・サムエル記 第二6章5節等。琴、瑟(しつ)、鼓、鈴、鐃鈸(にょうはち、シンバル)、立琴(竪琴、ハープ)、カスタネット。
・祇園祭・・・旧約聖書・創世記8章4節、7月17日「ノアの箱舟」のアララト山漂着。シオン(Zion)→ギオン。
・室(ムロ)・・・旧約聖書・サムエル記 第二5章9節「ミロ」。ダビデの城塞。
・スサノオノミコトはスサ(ペルシャ)の王・・・天孫族。 エソ人はスサノオノミコトを首長として先住民クシ人と協力。
・土着民で出雲の「エビス人(クシ、土蜘蛛)」・・・故郷カナン(現パレスチナ、エルサレム付近)。エブス人→ エビス人。
・出雲民族「エソ人」・・・故郷カナン(現パレスチナ)。アブラハムと正妻サラとの子イサクとその妻リベカの子エサウ→エドム人→エソ人(蝦夷、イズモ人、アイヌ人)。エサウの双子の弟ヤコブ(イスラエル)→へブル人→ユダヤ人。
・武蔵一宮氷川神社・・・イズモ人の東遷。エドム→江戸。
・高天原・・・アルメニア・タガーマ州ハラン→アメ(天)のタカマガハラ(高天原)。
・御船代・・・伊勢神宮。三種の神器。諏訪神社「御船祭」。Ark(契約の箱、ノアの方舟)。神輿水中渡御。 旧約聖書・出エジプト記14章15~31節。
・日本・・・アブラハムの子イサクの子ヤコブの子ガドの子「ツェフォン(Zephon、ゼポン、ツィフヨン)」→「ニッポン」。旧約聖書・創世記46章16節、同・民数記26章15節。
・帝(御門、ミカド)・・・「御」+「ガド」→「ミカド」。
・十二社神社・・・十二社(じゅうにそう、十二祖)。熊野三山(熊野大社)。八咫烏。ヤコブ(イスラエル)の十二子息(十二部族)。十二弁菊花紋。
・日本の地名は殆どアイヌ語・・・島根(サパネ、君臨統治の所(首都))、鎌倉(カマカラ、機織る所)等。
・世界を動かすユダヤ人。
・ダン族の建てた英国。
私のブログの、過去の関連ウェブページが次に在ります。↓↓
「日本の正月に存在する古代ユダヤの風習」
「多民族国家の日本に古代ユダヤ人」
以下に、関連動画を添付します。↓↓
尚、次の動画は、1/5~5/5の5分割となっています。↓↓
</object>
YouTube: 漢字に隠された聖書の物語(1/5)
尚、次の動画は、第1回~第7回の計7回分が有ります。↓↓
</object>
YouTube: 日本人のルーツ研究セミナー 第1回
</object>
YouTube: 祇園祭り・剣山の謎
</object>
YouTube: ヤタの鏡と日本(古代ユダヤとの関係)
</object>
YouTube: 相撲は古代イスラエルの神事だった
</object>
YouTube: 諏訪大社のイサクの祭り
</object>
YouTube: 武蔵一宮氷川神社
</object>
YouTube: 剣山本宮例大祭 御神輿 平成23年7月17日

| 日本人のルーツはユダヤ人だ―古代日本建国の真相価格:¥ 1,223(税込)発売日:1991-11 |

| 日本縦断アイヌ語地名散歩価格:¥ 2,310(税込)発売日:1995-07 |