
天岩屋戸(あまのいわやど)は、誰でも知っていると思っていたのですが、
高2の娘の言うことには、歴史の授業で天岩戸を知っているかという先生の質問に、知っていると答えられたのはごく少数だったとか。
あら、そうなの。
古事記を通して読んだなかで、私の想像力というか妄想力がフル回転したのは天岩屋戸で、
天照大御神が閉じこもり、高天原も葦原中つ国も暗闇に包まれ、禍に満ちるという深刻な場面なのに、何故か笑えました。
なんせ、カフカ「変身」で笑いを抑えられなかった私ですから、
多分、天岩戸をコメディーっぽく感じたのは私だけでしょう。
八百万の神が天の安河に勢ぞろいして「どうする?どうするよ?」と頭を寄せあって
相談しているところや、あれを作れ、これを持ってこい、鹿の骨を焼け~、などと大慌てな様子を想像してみてください。
ちょっといじけモードに入っている天照大御神が、鏡に見入ってそろそろと岩戸から出てくるのをドキドキしながら見守る八百万の神たち。
出てきたところを「今だ!」とばかりに注連縄で天岩屋に戻れなくしちゃう。
ちょっとしたコントですね。
本文から察するに天照大御神は、初めて鏡で自分を見たのですね。
これで思い出すのが落語の松山鏡で、もしかしたら原型は古事記にあるのかもしれません。
天照大御神が岩屋の戸を閉めてしまうことで禍に満ちるというところで、似ているなと思ったのはギリシア神話のパンドラの箱。
箱を開けることで禍を世に広めてしまい、慌てて閉めたときに残ったのは
希望だったというあの話。
小学生の頃だったと思います。
初めてパンドラの話を知ったとき、何で希望が残っているんだろうと不思議に思ったんです。
それじゃあ、世の中に希望がないじゃないかと。
この考え方は、天岩戸を先に知っていたからなのだと思います。
今なら希望が残っているという言葉どおりの意味なんだとわかるんですが。
最後に布刀玉命(フトダマノミコト)が渡す注連縄ですが、
これは立ち入り禁止という意味で使われているんですね。
天照大御神でさえ注連縄の効力があるというのも、古事記の神様らしさを感じるところですが、この注連縄の使い方におやっと思ってしまいました。
注連縄があるのは神社や神棚とか、そういう神聖な場所のイメージだったので、
天照大御神という偉大な神様が立ち入り禁止だなんてちょっと意外ですが、立ち入り禁止を示すことから発展して、不浄と清浄を分ける役割や、悪気が入らないようにする役割を持つようになったのかもしれませんね。
天岩屋戸の騒動で、八百万の神様達から高天原を追放されてしまったスサンヲは、出雲に降り立ち、八俣のおろちを退治して、その尾から草なぎの太刀を得、櫛名田比売(クシナダヒメ)を娶り、新居の宮を造る土地を探し、「私はここに来て、気分がすがすがしい」と言った須賀の地に新居の宮を構えます。
スサノヲの2代あとの子孫であるのが大国主神。
この後は、大国主神が中心となって語られ、スサノヲは根の堅洲国に行くようです。
大国主神には多くの兄弟神がいて、各々稲の八上比売(ヤガミヒメ)を娶ろうと
妻問いに出かけます。
後に大国主神となる大穴牟遅神(オホナムヂノカミ)は袋を持たされて、
従者として最後尾を歩いていきます。
そこで、かわいそうな因幡の白兎に会う。
その白兎を癒し、兎はあなたがヤガミヒメを娶るでしょうと告げます。
そのとおりになるのですが、面白くないのは兄弟神たちで、彼らはオホナムヂノカミを亡き者にしようと仕掛け、2度ほど死にますが、2度とも母の手で蘇らされます。
そして、母の勧めでスサノヲのいる根の堅洲国に出かけます。
根の堅洲国というのは、常世の国と同じように彼方にあると考えられた異郷で、黄泉ひら坂(よもつひらさか)が境界であるとされているので、黄泉の国と同一と考えられるようにもみえますが、違う世界と考えるのが妥当だろうと思います。
古事記では、天つ神の高天原、国つ神の葦原中つ国、死者の国黄泉の国、常世の国、根の堅洲国という5つの国がありますが、高天原が天にあること、葦原中つ国が地上であること以外は、その場所がどこにあるのかはっきりと示されているわけではありません。
黄泉の国や、根の堅洲国は、イメージから地下にあるように考えられますが、黄泉の国から逃げ帰るイザナキは黄泉ひら坂を下りてくるようです。
黄泉ひら坂という切りたった崖のような坂を隔てて、
そこにあって無いような異世界と勝手に想像しています。
考えてみれば、高天原というのも漠然と天上にあるとされているだけですから、
想像力によって然るべしなんでしょうけど。

高2の娘の言うことには、歴史の授業で天岩戸を知っているかという先生の質問に、知っていると答えられたのはごく少数だったとか。
あら、そうなの。
古事記を通して読んだなかで、私の想像力というか妄想力がフル回転したのは天岩屋戸で、
天照大御神が閉じこもり、高天原も葦原中つ国も暗闇に包まれ、禍に満ちるという深刻な場面なのに、何故か笑えました。
なんせ、カフカ「変身」で笑いを抑えられなかった私ですから、
多分、天岩戸をコメディーっぽく感じたのは私だけでしょう。
八百万の神が天の安河に勢ぞろいして「どうする?どうするよ?」と頭を寄せあって
相談しているところや、あれを作れ、これを持ってこい、鹿の骨を焼け~、などと大慌てな様子を想像してみてください。
ちょっといじけモードに入っている天照大御神が、鏡に見入ってそろそろと岩戸から出てくるのをドキドキしながら見守る八百万の神たち。
出てきたところを「今だ!」とばかりに注連縄で天岩屋に戻れなくしちゃう。
ちょっとしたコントですね。
本文から察するに天照大御神は、初めて鏡で自分を見たのですね。
これで思い出すのが落語の松山鏡で、もしかしたら原型は古事記にあるのかもしれません。
天照大御神が岩屋の戸を閉めてしまうことで禍に満ちるというところで、似ているなと思ったのはギリシア神話のパンドラの箱。
箱を開けることで禍を世に広めてしまい、慌てて閉めたときに残ったのは
希望だったというあの話。
小学生の頃だったと思います。
初めてパンドラの話を知ったとき、何で希望が残っているんだろうと不思議に思ったんです。
それじゃあ、世の中に希望がないじゃないかと。
この考え方は、天岩戸を先に知っていたからなのだと思います。
今なら希望が残っているという言葉どおりの意味なんだとわかるんですが。
最後に布刀玉命(フトダマノミコト)が渡す注連縄ですが、
これは立ち入り禁止という意味で使われているんですね。
天照大御神でさえ注連縄の効力があるというのも、古事記の神様らしさを感じるところですが、この注連縄の使い方におやっと思ってしまいました。
注連縄があるのは神社や神棚とか、そういう神聖な場所のイメージだったので、
天照大御神という偉大な神様が立ち入り禁止だなんてちょっと意外ですが、立ち入り禁止を示すことから発展して、不浄と清浄を分ける役割や、悪気が入らないようにする役割を持つようになったのかもしれませんね。
天岩屋戸の騒動で、八百万の神様達から高天原を追放されてしまったスサンヲは、出雲に降り立ち、八俣のおろちを退治して、その尾から草なぎの太刀を得、櫛名田比売(クシナダヒメ)を娶り、新居の宮を造る土地を探し、「私はここに来て、気分がすがすがしい」と言った須賀の地に新居の宮を構えます。
スサノヲの2代あとの子孫であるのが大国主神。
この後は、大国主神が中心となって語られ、スサノヲは根の堅洲国に行くようです。
大国主神には多くの兄弟神がいて、各々稲の八上比売(ヤガミヒメ)を娶ろうと
妻問いに出かけます。
後に大国主神となる大穴牟遅神(オホナムヂノカミ)は袋を持たされて、
従者として最後尾を歩いていきます。
そこで、かわいそうな因幡の白兎に会う。
その白兎を癒し、兎はあなたがヤガミヒメを娶るでしょうと告げます。
そのとおりになるのですが、面白くないのは兄弟神たちで、彼らはオホナムヂノカミを亡き者にしようと仕掛け、2度ほど死にますが、2度とも母の手で蘇らされます。
そして、母の勧めでスサノヲのいる根の堅洲国に出かけます。
根の堅洲国というのは、常世の国と同じように彼方にあると考えられた異郷で、黄泉ひら坂(よもつひらさか)が境界であるとされているので、黄泉の国と同一と考えられるようにもみえますが、違う世界と考えるのが妥当だろうと思います。
古事記では、天つ神の高天原、国つ神の葦原中つ国、死者の国黄泉の国、常世の国、根の堅洲国という5つの国がありますが、高天原が天にあること、葦原中つ国が地上であること以外は、その場所がどこにあるのかはっきりと示されているわけではありません。
黄泉の国や、根の堅洲国は、イメージから地下にあるように考えられますが、黄泉の国から逃げ帰るイザナキは黄泉ひら坂を下りてくるようです。
黄泉ひら坂という切りたった崖のような坂を隔てて、
そこにあって無いような異世界と勝手に想像しています。
考えてみれば、高天原というのも漠然と天上にあるとされているだけですから、
想像力によって然るべしなんでしょうけど。










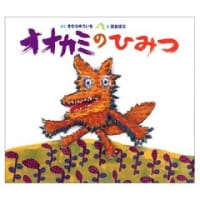
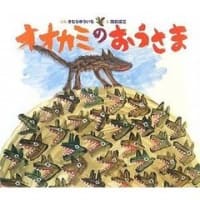
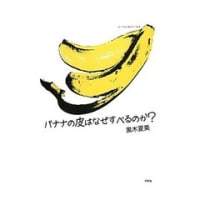
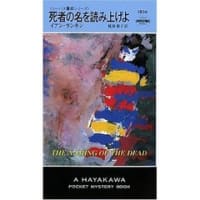
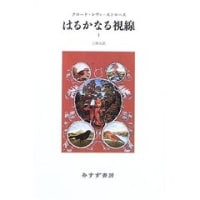
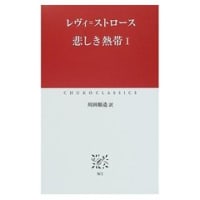
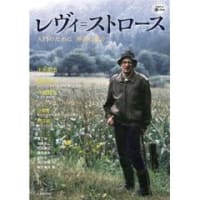
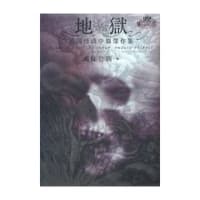
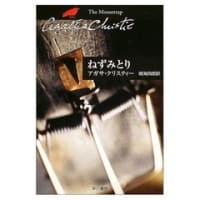
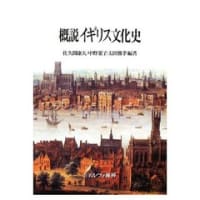
現代のタジカロウは重機のようです。
高千穂には浅見光彦シリーズでしか行ったことがありません。天岩戸温泉とかもあるようです。宮崎がかつては新婚旅行のメッカだったなんて信じられませんね。
根の国はうちの近所でして「黄泉のひらふの坂」あります。
出雲大社・・・正月しか入れないところでも正面から大国主さんは拝めず、なぜか大国主の前にいる天照系の神様を拝む事になります。
で・・・裏に小さなほこらがあってそこに須佐神なぞいらっしゃいます。
大国主の産地なので・・・お土産に隣町では「いなばのしろうさぎ」まんじゅうなぞあります。これはバルタン星人みたいでキュートです
スサノヲは暴風雨神でもあるらしいですから、このところの大雨はスサノヲが引き起こしているのかもしれませんね。
静岡にはこのニュースが伝わっていないというところに地方色を感じます。
静岡県民をはじめ、関東以東の人間は、神話にあまりゆかりがないので、このニュースが流れたとしてもピンとはこないでしょう。
面白いニュースを教えていただいてありがとうございます。
むぎこさまのご近所から、根の国へ行けるのですね!
天岩戸とされているところは、全国で幾つかあるらしいです。
とはいえほとんど関西以西ですが。
なんせ、神様から関東以東はほとんど無視されてますから(笑)
むぎこさまのコメントから、出雲など神話にゆかりの土地は、今でも神話と近しい間柄であるのがわかります。
しろうさぎまんじゅう、、、食べてみたいな。
頭には虱のかわりにムカデがいますし、、、キモっ。
私にとって一番馴染みがある神話とは何かと考えてみました。
私が生まれ育った伊豆河津町には、鳥精進酒精進と言って、12月17日からの一週間、鶏肉、卵を食べない、酒を飲まないという習慣があります。
杉桙別命(スギホコワケノミコト)という神様がお酒を飲んで野原で気持ちよく眠っている間に、燃え盛る野火に囲まれてしまいます。
そのとき、空が暗くなり水の粒が落ちてきました。
よく見ると、それは数多くの鳥達で、近くの河津川で羽を濡らし、その水で火を防いでくれたのです。
という言い伝えがあります。
その習慣は、今でも続けられています。
さすがに河津に住んでいない今では、守っていませんが、実家に住んでいた頃は当たり前のこととして過ごしてきました。
守らないと家が火事になると本気で信じてましたし(笑)
神様の名前までは、さすがに覚えていなくて、今調べてみたんですが、スギという樹の名前が用いられていることを考えてみると、天城山付近は、古代、良い木を多く産出していたと講談社学術文庫の古事記の解説にはあったので、関連性もあるのかなと思います。
あら、以外に関係があったわ(笑)