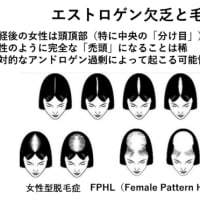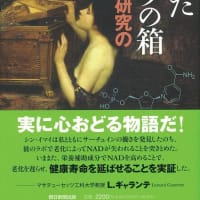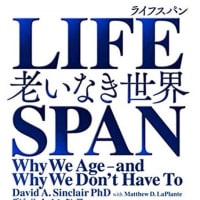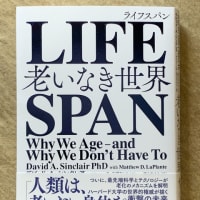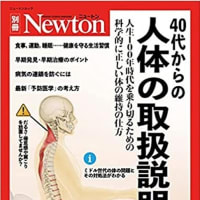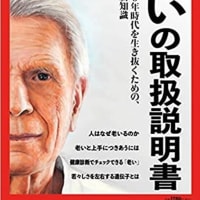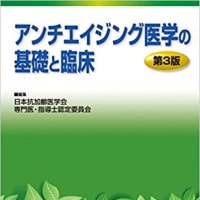Chronic abruption-oligohydramnios sequence (CAOS) was defined by the following criteria: (1) clinically significant vaginal bleeding in the absence of placenta previa or other identifiable source of bleeding, (2) amniotic fluid volume initially documented as normal, and (3) oligohydramnios (amniotic fluid index ?5) eventually developing without concurrent evidence of ruptured membranes.
CAOSの診断基準 (1998年、Elliotらにより提唱された)
①前置胎盤などの明らかな出血源なく性器出血が持続し、
②発症の当初は羊水量が正常で、
③明らかな破水の証拠がないにも関わらず、最終的には羊水過少(AFI≦5)となる。
常位胎盤早期剥離はらせん動脈の破綻により生じ、急速に経過すると考えられている。そのため、母児共に重篤となり、絨毛膜板にヘモジデリンが沈着する前に分娩となる。一方、CAOS は胎盤外壁につながる静脈叢の破綻が原因で慢性早剥となると考えられている。静脈性早剥は通常、母子のバイタルに変化がこないので、出血した血液の退縮時に血漿成分が腟内に漏れ出て、pH 試験陽性より破水と誤診されることがある。広範囲の絨毛膜下血腫が胎盤機能不全と胎児の腎還流障害を起こし、羊水過少の原因となっていると考えられる。また、血性羊水の吸引が繰り返され、遊離鉄による肺障害をもたらすと考えられている。
絨毛膜下血腫は日常的に遭遇する疾患だが、その予後に関しては一定の見解が得られていない。絨毛膜下血腫が長期化し、血腫が増大して慢性早剥となる症例が存在する。CAOS を提唱したElliot らの臨床統計によると、26,440 分娩中40 例(0.15%)に慢性早剥を認め、慢性早剥40 例中24 例(60%)にCAOS を認めたと述べている。すべての絨毛膜下血腫がCAOS へ移行するわけではなく、そのリスク因子も不明である。
CAOS の症例では、平均在胎期間は妊娠27~28 週と言われ、生後に慢性肺疾患、壊死性腸炎、頭蓋内出血などに至る症例が多い。
Elliot らは、CAOS を出血開始時期で2 群に分け、慢性早剥をコントロールとしてその予後を比較検討している。出血が20 週以前のCAOS 症例の初回出血の平均週数は15.2 ± 2.0 週に対し、コントロール群(慢性早剥群)では16.1 ± 1.7 週と有意差を認めなかったが、分娩週数はCAOS 症例が26.1 ± 3.9 週に対し、コントロール群(慢性早剥群)では33.0 ± 5.3 週と、CAOS 症例は有意に分娩週数が早かった。20 週以降に発生したCAOS 症例はコントロール群(慢性早剥群)に比較して初回出血の平均週数や分娩週数等に有意差は認めなかった。
CAOS の原因が不明である以上、治療法として特別なものはなく、一般的な切迫流産・早産治療に準ずる。
****** 文献
Elliot JP, Gilpin B, Strong TH Jr, et al. Chronic Abruption-Oligohydramnios Sequence. J Reprod Med 1998; 43: 418-422
中山摂子、安達知子、中林正雄: Chronic abruption-oligohydramnios sequence(CAOS)、 産婦人科の実際 2008; 57: 1933-1937
湯澤映、三浦理絵、熊坂諒大ら:慢性早剥羊水過少症候群(CAOS)の3 症例、青森臨産婦誌 2009;24:67-75