現在は少ない産科医の奪い合いの状況にあり、各自治体であの手この手の対策を講じても、産科医を新たに確保するのは本当に至難の業です。
いくら働く意欲があっても、職場の勤務環境があまりに過酷な状況のまま放置されたら、誰だってその職場での勤務を続けることはできなくなってしまいます。
体力・気力とも充実している働き盛りの中堅産科医達を使い捨てにしているようでは、この国の産科崩壊の問題は永久に解決しないと思います。
****** 毎日新聞、2007年12月25日
医師確保、悩む自治体 類似策で奪い合い
国の08年度予算案でも重点項目の一つとなった医師不足対策。毎日新聞が先月実施した都道府県調査からは、自治体も医師確保対策に力を入れている現状が浮かぶ。日本における医師の絶対数不足は深刻だ。ドクターバンク、給与優遇、再就業支援……。あの手この手の対策で医師不足は解消できるのか。問題解決のための抜本策はあるのか。現状と課題を追った。【河内敏康、五味香織、鯨岡秀紀】
好条件に“応募ゼロ”も--研究費100万円補助、月給20万円上乗せ…
「研究費助成!」「国内外での研修が可能!」。医師向け新聞のホームページに掲載された岩手県の「ドクターバンク」の求人広告には、こんな勧誘文句が並んでいる。
岩手県のドクターバンク事業は、06年12月にスタートした。医師不足に悩む県内の病院や診療所に勤務できる医師を登録する。任期は3年で、うち1年間は有給のまま国内外の大学などで研修できる。3年間で最大100万円の研究費も補助し、かなりの好条件だ。
さらに県内の医師にダイレクトメールも送ったが、この1年間、応募実績はゼロ。
県医師確保対策室は「利用しやすいよう制度の見直しを検討中だが、医師の絶対数が少なすぎる」と頭を抱える。
山梨県も同様の制度を実施しているが、採用はいまだない。昨年9月にドクターバンクを始めた愛知県では、今年10月までに13人を医療機関に紹介したが、医師不足の解消には程遠いのが実情だ。
埼玉県は、医師確保のため給与面で優遇する策をとる。臨床研修病院が、産婦人科と小児科の後期研修医を医師不足地域に派遣する場合、医師1人当たり月に最大で20万円を給与に上乗せできる支援制度を実施。2病院で6人の産科医を確保することに成功した。
埼玉県医療整備課は「産科や小児科の勤務医が少ない中、後期研修医は即戦力になる。しかし、各都道府県が同じような医師確保策を実施しているため、限られたパイの奪い合いをしているような状況だ」と嘆く。
少な過ぎる絶対数--各国平均に「14万人不足」
毎日新聞の調査では、各自治体の医師確保対策予算は急増している。回答のあった46都道府県の合計額は、03年の約22億4000万円と比べ、07年は3倍以上の約74億6000万円になった。各都道府県はこのほか、地方で勤務する医師を養成する自治医大の負担金を年に1億2700万円ずつ支出している。
だが、医師不足解消の見通しは立っていない。島根県は「専任スタッフ7人で取り組み、02年度以降で29人の医師を招いたが、地方の取り組みには限界がある」と回答した。
背景には、日本の医師数の少なさがある。経済協力開発機構(OECD)によると、日本の医師数は04年、人口1000人当たり2・0人。加盟30カ国でワースト4だ。各国平均の3・0人に追いつくには約14万人も足りないとの試算もある。国は「地域や診療科によって医師数に偏りがあるのが医師不足の原因」との姿勢だが、医師の絶対数そのものが少ないのが実情だ。
医療法の医師配置基準は、一般病院では入院患者16人に1人以上、外来患者40人に1人以上。厚生労働省によると、常勤医だけでこの基準を満たす病院は04年度でわずか35・5%。最も医師数が多い東京都でも45・8%にとどまる。非常勤医を含めると83・5%の病院が基準を満たすが、フルタイムで働くわけではない医師もカウントした上での数字だ。しかも、この基準は1948年に定められたものだ。
(以下略)
(毎日新聞、2007年12月25日)










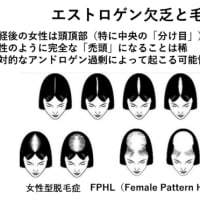


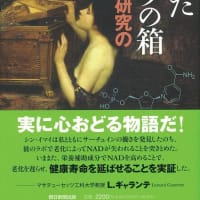
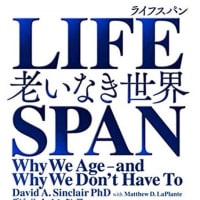
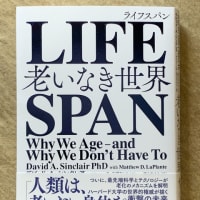
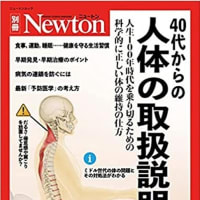
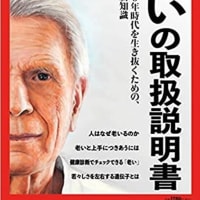
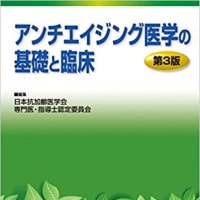

開業医は元勤務医でしたので、勤務医の苦労は承知してます。しかし、勤務医時代は開業後の苦労は知りませんでした。
比べるとは少なくとも両方やって初めて言えることではないでしょうか?
お気持ちは分かりますが、あまりに公平さを欠く意見です。
>比べるとは少なくとも両方やって初めて言えることではないでしょうか?
>お気持ちは分かりますが、あまりに公平さを欠く意見です。
この記事を書いた新聞記者に対して抱いた感情かと思いましたが、「締められている」「お気持ちは分かりますが」というところをみると、ブログ主の先生相手のようですね。もっと言うなら、これは三重県の勤務医達の意見ですよね。
だとするとブログ主に言っても仕方ないと思いますよ。たとえ、ブログ主が内心では同じ意見だったとしても。
まあ、長野県は開業しても広告さえ自由に出せなかったり、エコーも満足に出来ない爺さん達が地元医師会や産婦人科医会で幅を利かせたりで、開業も楽じゃないみたいですけどね。
>だとするとブログ主に言っても仕方ないと思いま>すよ。たとえ、ブログ主が内心では同じ意見だっ>たとしても。
特定の「誰に対して」とかそんな恐れ多いです。そのような趣旨で言ったのではありません。開業してまだ数年の「駆け出し」の状態ですので、むしろ今まで長かった勤務医の心情は理解できるつもりで言ったのみです。相手は、しいて言うならマスコミと国に対してです。
この記事のみではないですが、分娩に関しても開業医を意図的に無視している記事を多く見られます。 「病院と助産所」とか
でも現実は診療所は全分娩数の半数に近いですので、分娩の問題を語る場合は無視できない存在です。
勤務医の状況を改善するのは当然の事です。産科に限ったことではないですが、医師の総数が絶対的に少ない事(いまだに国は認めていない!)が最大の要因ですので、長期間にわたる政策の失敗です。それを隠すため勤務医を離れた事をすべて「悪」のようにとらえ、「偏在」などと詭弁を使っている事を修正し改善しない限り、管理人様のおっしゃる通り、お金と人の「奪い合い」のみに終始するでしょう。
しょうもない愚痴でした。長々と失礼しました。
医師が絶対的に足りないというのは真実ですが国の財政がこのような状況では医療費を大幅に上げることは不可能で、医師を1・5倍にすれば医師一人当たりの収入は良く見積もっても2~3割減る事になると思います。
産科医療の現場では悲観論ばかりが先行していますが、発想を転換すれば、今こそ産科勤務医が必要十分な待遇を得るチャンスだと思うのですが。
http://obgy.typepad.jp/blog/2007/10/post_4683.html
日産婦誌でちょうどご意見募集中です。
p1866に産科ガイドラインへのご意見募集Faxが載っています。
ところで、12月号にのった産科ガイドラインは以下の点などが目に付きます。
・「作成委員の8割以上の賛成を得て決定された推奨レベル」で
「必ずしもエビデンスレベルとは一致していない」わりに、
A/B/Cとランク付けをすることに関しての是非。
・他のガイドラインでは治療法とABCのエビデンスレベルは相関している。
産科ガイドラインは読むものに著しい誤解を与える。
・80%以上の地域で実施可能とされた検査法・治療法に含まれる検査方法(推奨)について、無理な検査法が含まれている。どこの地域でもやれるものであると考えているのか?裁判にこれが利用されるのか?
(CQ24 TTTSに対するレーザー凝固術
CQ29 羊水中または臍帯血中の風疹ウィルスの検出
CQ31 羊水中のCMVのウィルスの検出)
・研究レベルと考えられる記載がそこここに見受けられる。
(CQ24 TTTSのStage分類 CQ24 TTTSのレーザー凝固術
CQ25 胎児貧血評価に関するMCA最大血流速の計測(再現性なし)
CQ31 CMVのウィルス量検出 同、胎内治療
CQ49 羊水過多症に関するインドメタシン療法
CQ50 羊水過少に人工羊水注入など)
・倫理上の問題がある検査法が記載されている
(CQ19 NT検査は、倫理上に問題があるのに標準診断とすべきか?)
・他にもエビデンスのない診断法が多数存在するのでは?
産科ガイドライン、ちょっぴり現場(病院においても)でもちょっとそぐわないと思うのですけれど、開業医さんにとっては、もっと(?)というガイドラインのように思えるのです。そのうえ、まとまっていませんよね?
実際問題、サイトメガロウィルスがそれほど重要な妊婦感染症で頻度が高いとは思えませんし、なんだか時々とんでもなくマニアックです。これが裁判に使われるの?と思うと、このままでは全然ダメなんじゃないかと思います。
どう思われますか?