地域の産婦人科医不足の問題に対して各病院や自治体ごとに個別で対応しているようでは、所属する産婦人科医のうちの誰か一人でも個人の都合で辞職したり妊娠したりする度に、上を下への大騒ぎとなってしまい、どの病院も数カ月先の診療体制の維持さえ予測不能で、全く先が読めない不安定な状況が永遠に続くことになります。
やはり、県全体で一体となって産婦人科医療を維持していく体制を構築する必要があるのではないかと思います。たとえ、基幹病院の産婦人科部長が突然の病気で倒れたとしても、地域で必要とされる産婦人科医療の提供は翌日からも滞りなく維持されるような仕組みになってないことには、おちおち病気もできません。
当科でも数年前、中堅~若手の産婦人科医3人が同時に個人都合(開業、転科など)により辞職を表明し、ある日突然、科存亡の危機に陥った苦しい時期がありました。その時は、(里帰り分娩受け入れ中止などの)診療規模の大幅縮小も一時期本気で検討しましたが、大学の医局人事で救済して頂いて、診療規模を大幅に拡大しながら科存亡の危機的状況からも素早く脱することができました。
新人産婦人科医の勧誘・受け入れ、若手医師の教育・育成、地域の産婦人科医療提供体制の維持などを、各病院の個別の努力だけで何とかしようとしても大きな限界があります。大学病院が中心となり、県全体で一体となり一致協力して、若手産婦人科医を育成し、地域の産婦人科医療提供体制を維持していくことが重要だと思います。
そろそろ転勤のシーズンで、当科でも3月31日付けでベテラン医師が一人退職し、そのかわりに4月1日付けで大学から若手医師(後期研修医)を迎えることになりました。私も自分の後任者を迎えるまでもうしばらくここで頑張る必要があります。突然病気で倒れたりしないように健康維持には十分注意しながら、若い医師達と一緒にもうしばらく頑張ってみたいと思います。










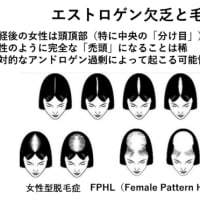


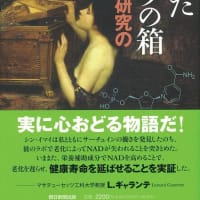
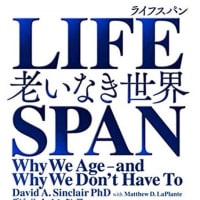
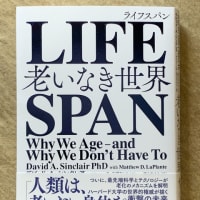
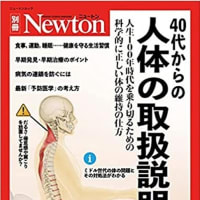
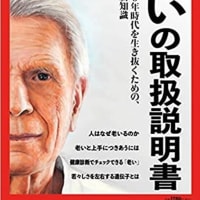
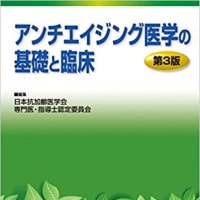

はじめまして、医療+医薬品の業界まとめニュースを運営しています。
このたび突然ご連絡をさせていただいたのは
当サイトと相互リンク、相互RSSの登録をして頂きたくご連絡をさせていただました。
ご迷惑でしたらこの文章は削除して頂いて結構です。申し訳ありませんでした。
まだまだ未熟ブログではありますが、ぜひ宜しくお願いいたします。
こちらでは貴サイトのリンクは登録済みです。
今後ともよろしくお願いいたします。
医療+医薬品の業界まとめニュース
ブログ:http://mednews.blog.fc2.com/
RSS:http://mednews.blog.fc2.com/?xml
・ 無心体双胎は、無心体児が健常児から供給される血流で生存するため、健常児に心負荷がかかり、羊水過多、胎児水腫をきたす予後不良な疾患である。
・ 妊娠初期に1絨毛膜双胎の一児死亡と診断されていた児に発育が認められるときは、無心体双胎を疑い精査することが大切である。
・ 血流ドプラ検査にて無心胎児の臍帯動脈血流が通常とは逆行性に(胎盤から無心体への拍動する血流)存在することが確認されると診断できる。
・ 治療法としては、無心体児の臍帯血流遮断術が行なわれる。侵襲度の低い方法として超音波ガイド下ラジオ波凝固術がある。(実施施設:国立成育医療研究センター周産期診療部など)