コメント(私見):
OECD(経済協力開発機構)がまとめた加盟国の人口10万人当たりの医師数のデータを見ると、全体平均は290名ですが日本は200名で、日本の医師数は加盟国の中では最低クラスです。従って、長期的な医師不足対策としては、医師数そのものを増やす(医師養成数を増やす)必要があると思われます。
しかし、今、医学部の入学定員を増やしたとしても、実際にその効果が現れるまでには最低でも10年はかかりますから、現実に目の前で進行している医療崩壊現象に対する即効薬にはなり得ません。
当面の短期的対策としては、現状の少ない医師を何とかうまくやりくりし、地域医療を維持していくようにいろいろ工夫していく必要があります。例えば、医師の拠点病院への集約化、病診連携システムの構築など、さまざまな対策を推進していく必要があります。
個々の病院の対策としては、なるべく多くの後期研修医に来てもらえるように、研修態勢を整備し、新人の勧誘に力を入れていく必要があります。
ただ、この後期研修医獲得競争では、自分の部署だけが独り勝ちすればいいというものではなく、各部署にバランスよく新人が参入してくれないと困ります。例えば、ある病院の産婦人科医が倍増したとしも、その病院の小児科、麻酔科が医師不足で消滅してしまえば、周産期医療を維持することはできません。
****** 中國新聞、2007年5月21日
http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh200705210084.html
医師不足 制度再構築は国の責任
深刻な医師不足にどう対処するのか。先週末に開かれた政府、与党の「医師確保対策に関する協議会」で、総合対策を六月上旬までにまとめ、政府の骨太の方針に盛り込むことになった。
(1)国公立大学の医学部定員に、へき地勤務を条件に入学を認める「地域枠」を新設する(2)国立病院など中核的な拠点病院から、不足地域の病院、診療所へ医師を一年程度の期限付きで派遣する―などが対策の柱。地域枠は四十七都道府県にほぼ五人ずつ、全国で二百五十人程度定員を増やす。
これまで厚生労働省は「医師の総数は足りており、将来は過剰になる」としてきただけに、定員増を認める方向は一歩前進だが、それにしても遅すぎる。地域で診療できる医師を養成するには、最低でも十年以上はかかるからだ。
一方で、日本病院会の調査では、宿直をしている全国の病院勤務医のうち、約九割が翌日も通常に仕事をせざるを得ない状況がある。長時間の過酷な労働実態を放置したままでは、不足地域への医師派遣もそう簡単とは思えない。
そこで、開業医を幅広い疾患に対応できる「総合医」として養成し、救急や往診などもこなしてもらい、病院勤務医の負担を軽減するプランも浮上している。だが、日本医師会は「医師不足は国の責任」と反発しており、難航しそうだ。二〇〇四年からの国の研修制度改革で都市部に若手医師が集中し、過疎地などの不足を招いた背景があるからである。
リスクが大きいため敬遠され、病院の診療科閉鎖などが起きている小児科や産科には、特に「即効薬」が必要だ。出産・育児などでいったん退いた女性医師の復職を促進する対策や、診療報酬の加算などが検討されている。
問題は、誰が責任を持って制度の再構築を進めていくかである。診療報酬の見直しや療養病床の削減など、国は自らの医療費負担の削減ばかりに目を向けてきた。これまでの手法を改めるのでなければ説得力に乏しい。思い切って国費を投入し、企業にも負担を求める覚悟がなければ、抜本的な仕組みの実現は難しいだろう。
医師確保のための法案を、参院選後の臨時国会に提出することも考えられている。国の責任の取り方によっては、地方自治体の財政を一層圧迫することにもなりかねない。本当に実効性のある対策にするには、医療現場や患者らの声も聞き、論議を深めるべきだ。
(中國新聞、2007年5月21日)










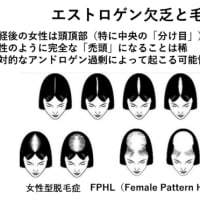


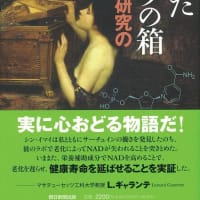
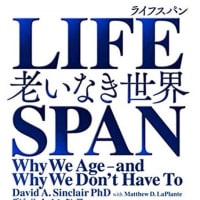
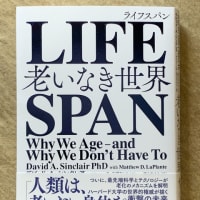
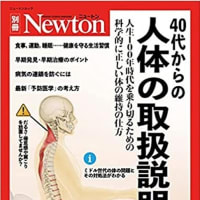
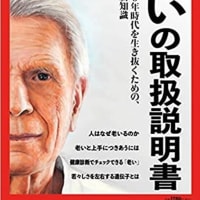
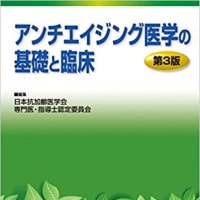

今、在籍している産科医たちが、みんな心の底から楽しく気持ちよく働いていて、誰も辞めたいとは思わないような職場環境・待遇を実現すれば、研修医たちもそれを実感してくれる筈で、勧誘も非常にやりやすくなります。
逆に、今、在籍している産科医たちにとって毎日の勤務が辛くて辛くて、離職者が続出しているような職場だとしたら、そんな職場は研修医からも敬遠されるのは当然のことで、いくら熱心に勧誘しても、誰も入って来る筈ないと思います。
> 産科医に新規になる医師を増やす対策と産科業務から去ろうとする医師を引き止めることとどちらが優先されると思いますか。どちらも大切だとは思いますが、私は、後者の方がはるかに大切で即効性があると思います。
自分も全く同じく思います。
ただ、新規に入ってくる若い人を犠牲にすることのないよう、特段のご配慮を賜れば幸いと思います。
5月号に医療崩壊についての特集記事があって、(かなり落ち着いていて好感のもてる感じなのですが)止血が大事、と書いてあり、その通りだなあとしみじみ。
腸管出血にしろ、産後の出血にしろ、もちろん輸血も必要ですが、「出血点を止める」は基本です。今の医師不足論議にはこの「止血」の視点がまったく空白地帯というか、放置されているというか。
こういった態度がますます出血(中堅医師の離職)に拍車をかけているような気がします。
また、「女性医師を大事にしよう」とみなさんおっしゃいますが、所詮口だけです。と、子持ちの女性医師は思います。
仕事を普通に(といってもその裏には水面下のたゆみない努力があり、もちろんそれは男性医師であろうが、独身医師であろうが一緒だろうとは思うのですが)やっていますと、「普通」に「やれる」と思われ放置されます。
もちろん今の職場では上司に深い理解があり、普段から朝疲れきっていても「朝、頑張って子供送り出してきてるから仕方ないな~」とか甘やかしてもらっていますが(具体的な何かではなく、態度として大目に見てくれることが一番楽です。かわりに○○やっといたよ、とか。ちょっと手が回らなかったからできてないけど、こうだったよ、とか。)、「できる」と信頼されすぎないように気をつけないと、もうそこからの世界は折れるまで放置一辺倒になってしまうんです。(前回の職場ではこの点、頑張りすぎて大失敗だったと思っています。既婚男性医師より働いてしまいましたし。)
今は、自分だけに仕事が偏りすぎないようにブロックすることも、自分自身が長く働き、みんなにとってもいいことだ、と思っています。
やりたくってもセーブ、言いたくなくてもこまめに文句です。みんながそうすべきです。(言いたくないけど、こまめに言っていかないと、相手もどこがどうなのか、考慮してくれることさえできません)それでも時々テンパりますが。そして月に一度くらいの波で「辞めてやる~っ!!!」と叫んでいますけれど。
だんだん意味がわからなくなってきましたが、「あの人は大丈夫」な人など世の中に誰もいないということ、限界になる前にこまめに文句・愚痴の言える、お互いに適度に甘やかし(考慮とも言います)ができる関係、限界になる前に「もうダメだもん!」とひっくり返そうね、と約束しておくような関係で仕事ができるといいなと思っています。
人間短距離走では、長距離を走れません。
前回の国勢調査の時に、この一週間の労働時間という項目があり、自分がその週103時間だったのに、夫が45時間しか働いていなかったのが印象的でした。
やっぱりマイナー科だったかな、と思いました。
(私が今更、そう思っても仕方のないことですが、若い子達がそう思うのは無理ありません)
ただでさえ人手少ない現場で、誰かが力つきて辞めることは、総崩れにつながります(実際そうなっている病院が沢山ありますよね)。
短期的には人は増えないのですから、まずは、即効性のある経済的なincentiveが絶対必要だと思います(それでもいつまで続くか、という声も聞こえそうですが、言い訳をしながらなにもしなければ、確実に崩壊します。今、何かを、できることをしなければならないのです)。分娩手当や救急手当をつけることを国策として宣言し、各医療機関にそうやって医師確保をやらないと、次の医療機能評価は通りませんよ、と言えば、各病院は、どんどんやるでしょう。まず産科問題を片づけて、次は外科問題にとりくまないと、本当に取り返しがつかないことになります。周産期死亡率があがるどころか、Appeでopeができなくて人が死ぬことになります。