昨日、日本婦人科腫瘍学会学術講演会に出席するために、佐賀市まで行ってきました。学会会場(佐賀市民会館)の書籍販売で、「卵巣がん治療ガイドライン 2010年版」(2010年11月25日発行、162ページ、定価:本体2600円+税)をみつけてさっそく購入しました。2007年版(95ページ)と比べてページ数がかなり増えました。
******
卵巣には、表層上皮、性索間質(顆粒膜細胞、莢膜細胞)、胚細胞などがあり、これらの組織から多種多様な腫瘍が発生する。卵巣癌の組織型は多様であり、その発生も単一の機序では説明できず、卵巣癌の発生には複数の要因が関与していると考えられる。
大部分は散発性であるが、乳癌と同じくBRCA1、BRCA2遺伝子変異が知られている(母親や姉妹が卵巣癌である場合は卵巣癌のリスクが約3倍になる)。他のリスク要因として不妊、出産歴がないこと、子宮内膜症、肥満、食事、排卵誘発剤の使用、ホルモン補充療法、動物性脂肪の多量の摂取や喫煙などが挙げられる。一方、経口避妊薬の使用や授乳(1回の妊娠で授乳期間も含めると卵巣は2年半休める)は卵巣癌のリスクを低下させる。
日本人の卵巣癌のリスクは欧米人(動物性脂肪を多くとる)に比べると半分以下とされているが、最近この差は縮まっている(生活が欧米化、晩婚化や出産回数の減少といった女性のライフスタイルの変化も関係)。
卵巣癌は癌が蔓延してから初めて自覚的な症状がでるため、早期診断しにくい癌である。半数以上が進行癌で診断される。また卵巣癌と良性卵巣腫瘍との鑑別は難しく、手術で摘出し検査して初めて癌と診断される場合も多い。
経腟超音波、CT、MRI、PET-CTなどの画像診断で、腫瘍の大きさや内容の性状、腹水・胸水の有無、転移病巣の有無など癌の進行の程度を調べる。
CA125、CA19-9などが主な卵巣癌の腫瘍マーカーで、これらが異常高値を示す場合には悪性の可能性が高い。治療前に高値を示した腫瘍マーカーは治療中・治療後に繰り返し検査して、治療効果の判定や経過観察に利用する。
腹水や胸水が貯留する場合には、これらを一部採取して悪性細胞の有無を調べる。また膣内、腹部、鼠径部など採取しやすい場所に転移病巣がみられる場合にはこれを一部生検し病理組織検査を実施する場合もある。
術前に卵巣癌の診断を確定することは困難で、開腹手術で摘出した卵巣腫瘍の組織診断が最終診断となる。
卵巣癌の治療は手術療法と化学療法が密接に連動する複合療法として行われる。
初回治療は手術療法であり、基本術式として両側付属器摘出術、子宮全摘術、大網切除術が含まれ、staging laparotomyとして腹腔細胞診、生検、後腹膜リンパ節(骨盤・傍大動脈節)郭清術ないし生検が必要となる。さらに進行癌では初回腫瘍減量術(primary debulking surgery)が必要である。
卵巣癌では術後の残存腫瘍が予後と相関することから、手術は完全切除を目指した最大限の腫瘍減量術(maximum debulking surgery)を行うべきである。しかし、進行例では腫瘍の可及的摘出に終る場合もあるため、腹腔内腫瘍の状態および全身状態を確認したうえで、腫瘍減量術の程度を考慮する。
進行癌では初回術後残存腫瘍径が化学療法効果を予言する。しかしながら、卵巣癌は進行癌が60%を占め、初回腫瘍減量術でoptimal disease(1cm未満の残存腫瘍)にできる確率が50~60%にとどまることより、interval debulking surgery (IDS)が導入されている。
術後low-risk群(Ⅰa/Ⅰb期、高分化癌、非明細胞腺癌)では手術のみで約95%の5年生存が期待できる。術後の化学療法は省略され、厳重な経過観察を行う。一方、highrisk群(Ⅰc期以上、低分化癌、すべての明細胞腺癌)では術後に化学療法が実施される。
初回化学療法(first-line chemotherapy)は、TC療法(パクリタキセル175~180mg/m2+カルボプラチンAUC 5~6)が標準的治療として広く世界中で推奨されている。カルボプラチンの投与量はmg/m2ではなくAUCを用いて算出され、Calvert計算式〔目標AUC×(GFR+25)〕が用いられる。
初回手術が、1cm未満の残存腫瘍(optimal disease)の場合と、1cm以上の残存腫瘍(suboptimal disease)で予後は異なる。optimal diseaseの場合は術後化学療法(TC療法)を6コース行う。suboptimal diseaseに対してもTC療法6コースが予定治療となる。しかし、試験開腹例や大きな残存腫瘍(測定可能病変)を有する症例では化学療法を3(2~5)コース行い、増悪例を除いた症例に対してIDSを行い、さらに術後化学療法を3コース程度継続することが臨床上推奨される。初回化学療法に非奏効例は初回薬剤と交差耐性を有さない薬剤を用いた二次化学療法(second-line chemotherapy)を行うが、奏効が得られない場合は緩和医療へ移行する。
IDSを前提とした術前化学療法の臨床試験が進んでいる。また、抗癌剤感受性に乏しい明細胞・粘液性腺癌に対しては術後化学療法として標準的なレジメンは科学的に確立されていない。
若年者に好発する胚細胞性悪性腫瘍は抗癌剤に高い感受性を有することより、患側付属器の摘出にとどめ(妊孕性温存手術)、術後はブレオマイシン、エトポシドとシスプラチンの併用療法(BEP療法)が標準的である。術後の残存腫瘍径が予後と相関するというコンセンサスは得られていない。
















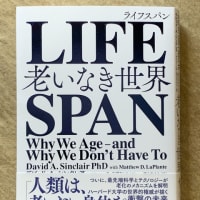




卵巣がんで長期治療中の患者です
おうかがいしたいのですが
調べていたのは、
わたしは、粘液性腺癌 だと言われましたが・・
10年近く、ほぼ半年ごとのTC療法が効いていてましたが、最近DCにチェンジしました
ふと目にした記事で、「粘液性」自分がなぜ抗がん剤がよく効くのが不思議で・・
また
粘液性が、抗がん剤が効かないとされるのに
代表的な組織内で、生存期間が長い、生存率が高いのはなぜなのでしょうか?
いずれも抗がん剤治療をした上ですね
相反しているのが不思議に思えて・・
教えていただけるとうれしく存じます
どうぞよろしくお願いします
当科の産婦人科常勤医師数が増えてきて、最近の症例は新進気鋭の先生方が主に担当しているので、私の担当する婦人科外来に通ってみえる方々の集団は、かなり以前に治療した昔馴染みの患者さんたちの比率が高くなっていて、結果的に再発後に長期間生存してらっしゃる患者さんも少なくないです。経過は人それぞれなので再発後の生存期間の予測は非常に難しいと思います。
個人差で、一概に言えないですね・・
治療ができるということは幸せなことだと思っています。