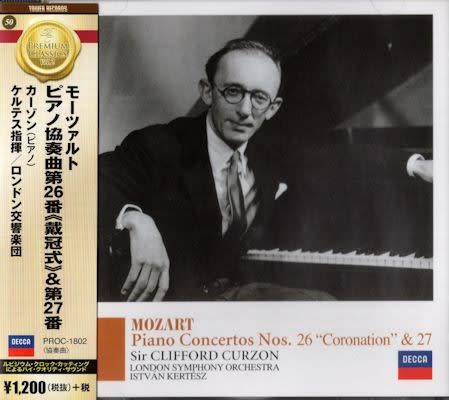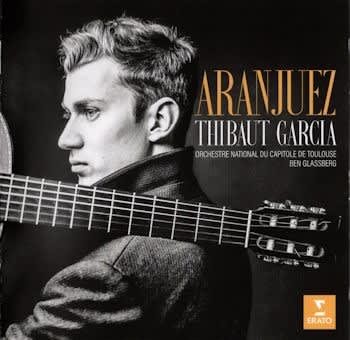岡田暁生さんと片山杜秀さんの対談形式で著された「ごまかさないクラシック音楽」(新潮社)という本が、書店で目に留まったので、購入して読んでみました。

(本書の紹介)
バッハ以前はなぜ「クラシック」ではないのか? ハイドンが学んだ「イギリス趣味」とは何か? モーツァルトが20世紀を先取りできた理由とは? ベートーヴェンは「株式会社の創業社長」? ショパンの「3分間」もワーグナーの「3時間」も根は同じ? 古楽から現代音楽まで、「名曲の魔力」を学び直せる最強の入門書。
(大まかな目次)
序章 バッハ以前の一千年はどこに行ったのか
第1章 バッハは「音楽の父か」
第2章 ウィーン古典派と音楽の近代
1. ハイドン
2. モーツァルト
3. ベートーヴェン 年末に〈第九〉の代わりに何を聴くか
第3章 ロマン派というブラックホール
1. ロマン派とは何か
2. ロマン派と「近代」 「人間は三分間しか音楽を聴けない」
3. ワーグナーのどこがすごいの
第4章 クラシック音楽の終焉?
1. 第二次世界大戦までのクラシック音楽
2. 第二次世界大戦後のクラシック音楽
ストリーミング配信で変わったこと これからのクラシック音楽をどう聴くか
(感想など)
時代順に、作曲家個人や作曲家の作品を、その時代の政治体制や社会経済状況に照らして、対談形式で論じている内容です。入門書ではありませんが、クラシック音楽の代表的な作曲家や有名曲が登場するので、興味深く読めました。
最も面白かったのは、第4章の「第二次世界大戦後のクラシック音楽」で、この時代の作曲家や作品が縦横に語られています。ストリーミング配信で、音楽の聴き方が変わったことや、これからのクラシック音楽の聴き方も願望を込めて片山さんが述べています。
片山さんのインタビュー時に、ルチアーノ・ベリオ(伊の現代作曲家)が『人間なんてものはね、音楽を聴けるのは三分間が限度なんだ』という発言をしていて(本書187p)、記憶に残りました。3分の例として片山さんはショパンの音楽を上げています。僕も連続して音楽を聴くのは、30分位がよいので、共感しました。
(著者略歴)
岡田暁生

1960年、京都市生まれ。音楽学者。大阪大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。京都大学人文科学研究所教授。『オペラの運命』でサントリー学芸賞、『ピアニストになりたい!』で芸術選奨文部科学大臣新人賞、『音楽の聴き方』で吉田秀和賞、『音楽の危機』で小林秀雄賞受賞。著書に『オペラの終焉』、『西洋音楽史』、『モーツァルトのオペラ 「愛」の発見』など多数
片山杜秀

1963年宮城県仙台市生まれ。政治思想史研究者、音楽評論家。慶應義塾大学法学部教授。慶應義塾大学法学部政治学科卒業、同大大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学。大学院時代からライター生活に入り、『週刊SPA!』で1994年から2003年まで続いたコラム「ヤブを睨む」は『ゴジラと日の丸――片山杜秀の「ヤブを睨む」コラム大全』(文藝春秋)として単行本化。主な著書に『音盤考現学』『音盤博物誌』(アルテスパブリッシング 吉田秀和賞・サントリー学芸賞)、『未完のファシズム――「持たざる国」日本の運命』(新潮社 司馬遼太郎賞)、『近代日本の右翼思想』(講談社選書メチエ)、『見果てぬ日本――司馬遼太郎・小津安二郎・小松左京の挑戦』(新潮社)、『鬼子の歌――偏愛音楽的日本近現代史』(講談社)、『尊皇攘夷――水戸学の四百年』(新潮選書)など。
【年末に聴きたい音楽】
本書の中で、『もう右肩上がりの時代じゃないんだから、(ベートヴェンの第九)とは別の方向(曲)を』年末に聴いたらどうかと岡田さんが発言し、片山さんも加わり、バッハ「フーガの技法」や、〈きよしこの夜〉などの教会音楽、モーツァルトのレクイエムなどが挙げられていました。
そこで、azuminoもこの時期に聴きたい音楽(CD)を挙げてみました。

「きよしこの夜」や「もろびと声上げ」などクリスマスキャロルが収録されているCDです。鈴木雅明指揮バッハ・コレギウム・ジャパンの演奏。編曲とオルガンは鈴木優人。(BISレーベル。2018年神戸松陰女子学院チャペルで収録)。クリスマスシーズンにぴったりのCD(SACD)です。

モーツァルト:レクイエム。鈴木雅明指揮バッハ・コレギウム・ジャパン(2013年録音)。このCDを、ジャズ喫茶「アンの家」でかけてもらったら、クラシックファンの方が、これは買わなくちゃと言って、お店を出てきました。

ビル・エヴァンス「Trio 64」。ジャズからは、ビル・エヴァンスのピアノで、「Santa Claus Is Coming to Town」(サンタが街にやってくる)が収録されている「Trio 64」を。明るめの演奏で、大好きなアルバムです。