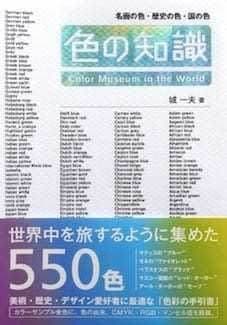本を読んだ。
本屋大賞(2005)だったり、映画化されたり(2006)と話題作でした。
フィクションかなと思ってたら、いえいえ、恩田さん母校、水戸第一高校では、《歩行祭》といって実際にやってるというから、びっくりである。高校のHPを覗くと、写真掲載で紹介されている。
とんでもない行事だなぁと思いつつも、なんとロマンチックな行事ではないかと右往左往。
好きな人はこれに青春を賭けるだろうし、嫌な人は頭が痛いだろうな腹が痛いだろうなと同情気分。生徒はもちろん、職員も保護者も地域の人たちもこれは大変だ。
みんなで、歩く。たったそれだけのことなのにね。
どうして、それだけのことが、こんなにも特別なんだろうね。(文中より)
わかるなこの感覚。特別なことを記憶したいという青春の感傷ではある。水戸の熱き想い(幕末の水戸藩のこと)は現代に引き継がれているのかと思った。
小説の感想も一応一言。
読んで面白かったよ。予定調和的ではあるが、
最後まで興味を持たせてくれた。
高校時代の物語はどうしても切なくなる。