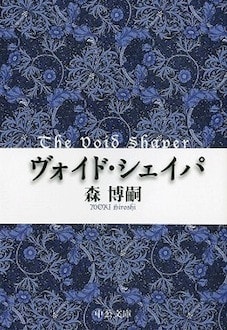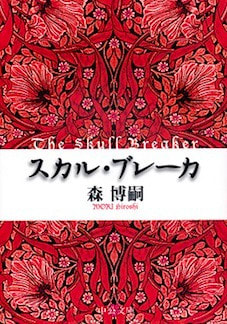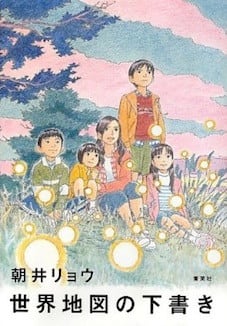本を読んだ。
★殿様の通信簿
著者:磯田道史
出版社:朝日新聞社
最近、よくお顔をテレビで拝見いたします。
人気なんですね。
本の帯には「平成の司馬遼太郎」の呼び声も高いと書いてあり
、司馬ファンとしては、これは一度読むより手はないでしょうと買ってしまった。
読んでみると、なるほど歯切れの良い文章リズムで、爽やかです。
司馬さんの書く物の中に、
「・・について書く」とか
「話がかわるが・・」
とかいった単刀直入の書き出しがよくあり、
ぐっと引きつけられるのですが、
磯田さんの文章にもそのような要素があります。
作家の磯田さんは年齢もまだお若いので、
今後どのような世界観を表現されるのか注目していきたいです。
最近、よくお顔をテレビで拝見いたします。
人気なんですね。
私には、「江戸時代、加賀100万石という大国が何故にたたきこわされずに残ったのか」という日本史上の疑問がずっとありました。この本には、さもその時代を見てきたように解説されています。お見事です。「武士の家計簿」も読んでみることにしました。