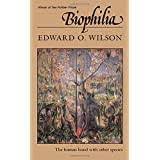
ヒトの脳は人類史においてホモ・ハビリスの時代から石器時代後期のホモ・サピエンスに至る約200万年の間に現在の形と機能に進化してきた。人々は狩猟採集民として群れを作り、自然環境に適応してくらして来た。自然の全てのシグナルは意味を持っており、生死を分ける重要な情報であった。それを感知できるかどうかは人類集団の繁栄か消滅に直結していた。今でも野生動物は、遺伝的に組み込まれたこの感受性をフルに発揮して生活している。一方、ヒトは言語によって学習した内容を子孫に伝承する能力を獲得した。言語による伝承という文化(学校)を発明した集団だけが困難な時代(氷河期)を乗り越えることができたとも言える。
自然のシグナルの中で生存に通ずるものは心地よいものとして、ヒトの脳の中に保存されている。すなわち、これがバイオフィリア(例えば花やミツバチ)である。一方、死滅につながる物の残存シグナルはバイオフォビア(例えばヘビや毒蜘蛛)である。高度な都市化した生活を営む人類は、文化におけるメタファーを通じて原始時代の感性を呼びおこしているのである。バイオフィリアとバイオフォビアの葛藤が現代社会における精神疾患の原因の根源かもしれない。バイオフィリアの起源は生存のための環境適応といえるが、もう一つは共生である。人は周囲に花壇を作り美しい花卉を育て、イヌを飼って心を交流させる。ウィルソンは現代人の家の庭は西洋庭園であれ日本庭園であれ原型は、人類が発祥したサバンナだという。文化の中にもレリック(遺存形質)が反映されているというのだ。
しかし同じ花を見ても感動する人としない人がいる。バイオフィリアも個人的な特性がある。一方、ウィルソンの子供時代のように毒蛇を手づかみできる人もおれば、小ヘビを見ただけで金縛りになる人もいる。バイオフォビアの程度も人によって違う。
ウィルソンはここでも生物多様性の重要性を強調している。これもバイオフィリアとバイオフォビアの二つのモーションで見なければならないことになる。一つはよく言われるバイオフィリア的な有益性であり、別の面はそれが持つ潜在的なリスクである。例えば熱帯の生物多様性は、デング熱、マラリア、トリパノゾーム、フィラリア、黄熱病、アメーバー赤痢、エボラ等多様な生き物が媒介する感染症を誘発する。バイオフォビアは生物多様性を不潔=病気と見なすのである。
参考書は人間の自然に対するメンタルな特性についての哲学書であるが、生物学の書でもある。特に社会性昆虫であるアリの行動生態については興味深く叙述されている。とりわけハキリアリ(Atta cephlalotes)の紹介はさすがにウィルソンの専門だけあって圧巻である。英語の原書は極めて読みにくいが、訳書は狩野により分かりやすく翻訳されている。
参考図書
エドワード・ウィルソン 『バイオフィリア』(狩野秀之訳)平凡社 1994
SR・ケラート、EO・ウィルソン編 『バイオフィリアをめぐって』 (荒木正純ら訳) 法政大学出版会
2009。
追記1)2021/05/24
クモ恐怖症候群 (アラクノフォビア)についてはP.ヒルヤード著『クモ・ウオッチング』(新海栄一ら訳 平凡社 1995)で詳しく解説されている。これを治療するにはクモにとことん馴れさせるために、患者にしこたまクモの標本を見せるらしい。コウモリ恐怖症候群 (バツドフォビア)については『バイオフィリアをめぐって』でエリザベス・アトウッド・ローレンスが詳しく述べている。感染症のキャリアーとしての忌避ではなく、その特異な形態や生態に由来するとしている。
追記2)2021/06/14
ユダヤーキリスト教は本質的にバイオフォビアの思想である。それは旧約聖書の冒頭アダムとイブをそそのかすヘビに象徴されている。













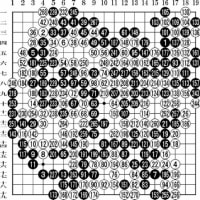












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます