昨夜、一冊の本を読み終えました。
貫井徳郎『慟哭』(創元推理文庫、2008年5月、46版)
小説は、連続幼女誘拐事件に遭遇した捜査一係長(佐伯)と、心の中に埋めがたい闇を持つ人物(彼)と二元的に進みます。全部で69に区分された物語は、奇数が「彼」の物語、偶数が佐伯の物語です。
遅々として解決に向かわない連続幼女誘拐事件の指揮を執る佐伯の苦悩、そして、心の闇を取り払いたいと思う「彼」の宗教への思い入れ。そして佐伯の家族関係やスキャンダル、「彼」がのめり込む新興宗教。あまりに人間的な苦悩と、あまりに猟奇的な宗教儀式、この二つが交互に描かれます。
そして何より、最後の大どんでん返し。この小説は、大団円で解決したように描かれますが、実は解決していない事件が最後の3行で示されます。
まさに慟哭。
今日、おおよそ20年前に発生した東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人が死刑を執行されたというニュースが配信されました。
「彼」の現在の年齢を見て、『もうそんなになるのか』と、あの当時報道された写真の顔つきを思い出していました。
『慟哭』は、文庫本の初版が1999年、単行本は1993年に発行されています。東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件が1988年~89年の事件でした。この小説はあの事件の猟奇さに着想を求めたのではないかと思ってしまいます。
とはいえ、シチュエーションはまったく異なりますし、小説と事実は、何の因果関係もありません。
被害者、そして遺族の立場に立てば死刑はやむなしという意見もあるでしょう。一方で死刑制度が世界的に廃止の流れにある中で、「先進国」である日本で死刑制度を持つなどとんでもないという意見もあるでしょう。
しかしそんなことは関係ありません。
事実は、自分の愛する子どもが殺害され、そして子どもを危めた人物を許せないという親の気持ち。
その気持ちは、制度としての死刑などとは無関係な、人として当然の感情だと思います。
昨夜読み終えた小説と、実際に20年前に発生した事件の当事者の死刑執行。
あまりにかけ離れた関係ながら、どうしても結びつけて考えてしまう感情を、子を持つ親として、抑えることができません。
そして強く思います、やっぱり許せないと。
貫井徳郎『慟哭』(創元推理文庫、2008年5月、46版)
小説は、連続幼女誘拐事件に遭遇した捜査一係長(佐伯)と、心の中に埋めがたい闇を持つ人物(彼)と二元的に進みます。全部で69に区分された物語は、奇数が「彼」の物語、偶数が佐伯の物語です。
遅々として解決に向かわない連続幼女誘拐事件の指揮を執る佐伯の苦悩、そして、心の闇を取り払いたいと思う「彼」の宗教への思い入れ。そして佐伯の家族関係やスキャンダル、「彼」がのめり込む新興宗教。あまりに人間的な苦悩と、あまりに猟奇的な宗教儀式、この二つが交互に描かれます。
そして何より、最後の大どんでん返し。この小説は、大団円で解決したように描かれますが、実は解決していない事件が最後の3行で示されます。
まさに慟哭。
今日、おおよそ20年前に発生した東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人が死刑を執行されたというニュースが配信されました。
「彼」の現在の年齢を見て、『もうそんなになるのか』と、あの当時報道された写真の顔つきを思い出していました。
『慟哭』は、文庫本の初版が1999年、単行本は1993年に発行されています。東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件が1988年~89年の事件でした。この小説はあの事件の猟奇さに着想を求めたのではないかと思ってしまいます。
とはいえ、シチュエーションはまったく異なりますし、小説と事実は、何の因果関係もありません。
被害者、そして遺族の立場に立てば死刑はやむなしという意見もあるでしょう。一方で死刑制度が世界的に廃止の流れにある中で、「先進国」である日本で死刑制度を持つなどとんでもないという意見もあるでしょう。
しかしそんなことは関係ありません。
事実は、自分の愛する子どもが殺害され、そして子どもを危めた人物を許せないという親の気持ち。
その気持ちは、制度としての死刑などとは無関係な、人として当然の感情だと思います。
昨夜読み終えた小説と、実際に20年前に発生した事件の当事者の死刑執行。
あまりにかけ離れた関係ながら、どうしても結びつけて考えてしまう感情を、子を持つ親として、抑えることができません。
そして強く思います、やっぱり許せないと。










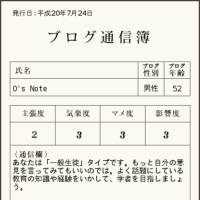









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます