
2月はじめから3月半ばまで、6回にわたりNHKで放映された土曜ドラマ『ハゲタカ』。ご覧になった方もたくさんいると思います。
この放映と合わせて書店に並んだ原作。真山仁著『ハゲタカ(上)・(下)』(講談社文庫、2006年3月)。そして最初は『バイアウト』というタイトルで出版された『ハゲタカⅡ(上)・(下)』(講談社文庫、2007年3月)。
結論からいえば、ドラマと原作では、まったく内容が違っているという印象です。これはドラマが良くないというわけではなく、ドラマはドラマとして、原作は原作として楽しめるという意味です。もっとも、原作を読んでいるとドラマで主役たちを演じた役者さんの顔が浮かんできて、とくに『ハゲタカⅡ』の方では、チト、イメージが違ってきたかなと思いましたが。
『ハゲタカ』では1989年12月から2004年3月まで、『ハゲタカⅡ』では2004年12月から2006年12月までが対象になっています。いうまでもなく前者は、いわゆる失われた10年を含んでいますし、後者は、粉飾決算に揺れる老舗企業の「倒産」が日本を驚かせた時代です。
この小説では、外資ファンドの日本法人代表として鷲津政彦(ゴールデンイーグルと異名を取る。ドラマでは大森南朋-おおもり・なお-が演じています)、名門銀行を辞め、のちに再建が必要な企業のCRO(Chief Restructuring Officer:最高事業再構築責任者)として活躍する柴野建夫(ドラマでは柴田恭兵が演じてます)、そして柴野が辞めた銀行の頭取にまでなり、やがては政府の企業再生機構の総裁になる飯島亮介(中尾彬が演じてます)という、3人を中心にして、複数の企業事案が同時進行的に取り扱われています。
鷲津は、当初、外資ファンドを利用して「日本をバイアウトする」と、非常な行動で企業を買いまくります。しかしその本意は、日本を破壊することではなく、日本の文化や伝統をあっさりと捨て去る日本人の意識を変えようというところにありました。
「悪いか? 金には色も国も、そして民族もない、ただの金だ。それをどう使うかは、使う人間が決める。持っている人間は、期待した利回りがあれば何の文句も言わないだろ。世界中の金を使って、この愚かな国に思い知らせてやるのさ。本当の再生とは何かをな。」(『ハゲタカ(下)』p.317)
金には色がない、というフレーズは、かつて紹介したマネー・ロンダリングの本の中でも使われていました。それはさておき、「本当の再生とは何か」という問いかけは、本書を通じて考えさせられるテーマです。ハゲタカは悪(ワル)といいながら、最終的には保身のために改革も再生もできない経営者たち。それを知りつつ利益を確保しようとする銀行(銀行自体の保身は、ドラマでもバルクセールの場面で描かれています)。こういった組織とそこに所属する人間の行動がわかりやすく描かれています。
さて、『ハゲタカⅡ』では、2件の大型企業買収が扱われます。一つは鈴紡(カネボウかな、やっぱり)と月華(花王かしらん)との買収劇、曙電機(日立とNECの合作?)とシャイン(キャノン?)の買収劇です。
ここでは、ドラマとは違って、日米両政府を巻き込んでダイナミックな展開で物語が進みます。
物語の最後に、著者は柴野に次のように述懐させます。
「二十一世紀という激動の時代に突入し、伝統も名門というブランドも何の役にも立たないことを証明する皮肉な役回りを、両社(鈴紡と曙電機-引用者注)は担ってしまう。彼らの成功モデルだった多角化は否定され、運命共同体の名の下で構築された組織は馴れ合いと官僚的な事なかれ主義を生み、やがて責任の所在が不明確な無責任体質への腐敗していった。」(『ハゲタカⅡ(下)』p.426)
口では改革を叫んでいても、最終的には伝統と名門ということが改革の芽を摘んでしまい、自らではどうしようもないカオスの中に入り込んでしまう。その結果としての無責任な意思決定と行動。そして保身。そこに隙が生まれ、外部からの買収の標的になってしまいます。
『ハゲタカ』では悪(ワル)に徹していたかのような鷲津は、『ハゲタカⅡ』では柴野と協力して別の外資ファンドによる曙電機の買収を阻止しようとします(ドラマでも急転直下協力する関係になって終わりました)。結構、ハードボイルド的です。
『ハゲタカⅡ』を読みながら、『まだ解決されていない問題があるよなぁ』と思っていましたら、一番最後に「...to be continued」。物語はまだ続くようです。
先にも触れましたが、読みながらドラマの役者さんの顔が浮かんで、中でも一方の悪(ワル)として描かれた飯島をドラマで演じた中尾彬は、飯島そのものでした。(苦笑)
この本は、ぜひ学生さんたちやバブルを経験していない若い人たちに読んで欲しいなと思いました。
さて、この物語では、買収にからむたくさんの用語が出てきます。先に書いたバルクセール、バイアウトを始め、MBO、LBO、TOB、ゴールデン・パラシュート、ホワイト・ナイトなどなど。MBOやTOBは最近の新聞でよくお目にかかりますし、ホワイト・ナイトは、フジテレビとライブドアの一件でSBIがフジのホワイト・ナイトとして登場していましたのでご記憶の方もいるでしょう。
突然、こういった用語が一般にも使われ出しましたが、思い起こせば、今を去ること20年前、『ウォール街』という小説が出版され(映画にもなりました)、米国企業同士の合併が描かれておりました。その中で上記の買収がらみの用語が使われておりましたので、20年の時を経て、その行為を含めて日本に定着したといえるのかもしれません。
この放映と合わせて書店に並んだ原作。真山仁著『ハゲタカ(上)・(下)』(講談社文庫、2006年3月)。そして最初は『バイアウト』というタイトルで出版された『ハゲタカⅡ(上)・(下)』(講談社文庫、2007年3月)。
結論からいえば、ドラマと原作では、まったく内容が違っているという印象です。これはドラマが良くないというわけではなく、ドラマはドラマとして、原作は原作として楽しめるという意味です。もっとも、原作を読んでいるとドラマで主役たちを演じた役者さんの顔が浮かんできて、とくに『ハゲタカⅡ』の方では、チト、イメージが違ってきたかなと思いましたが。
『ハゲタカ』では1989年12月から2004年3月まで、『ハゲタカⅡ』では2004年12月から2006年12月までが対象になっています。いうまでもなく前者は、いわゆる失われた10年を含んでいますし、後者は、粉飾決算に揺れる老舗企業の「倒産」が日本を驚かせた時代です。
この小説では、外資ファンドの日本法人代表として鷲津政彦(ゴールデンイーグルと異名を取る。ドラマでは大森南朋-おおもり・なお-が演じています)、名門銀行を辞め、のちに再建が必要な企業のCRO(Chief Restructuring Officer:最高事業再構築責任者)として活躍する柴野建夫(ドラマでは柴田恭兵が演じてます)、そして柴野が辞めた銀行の頭取にまでなり、やがては政府の企業再生機構の総裁になる飯島亮介(中尾彬が演じてます)という、3人を中心にして、複数の企業事案が同時進行的に取り扱われています。
鷲津は、当初、外資ファンドを利用して「日本をバイアウトする」と、非常な行動で企業を買いまくります。しかしその本意は、日本を破壊することではなく、日本の文化や伝統をあっさりと捨て去る日本人の意識を変えようというところにありました。
「悪いか? 金には色も国も、そして民族もない、ただの金だ。それをどう使うかは、使う人間が決める。持っている人間は、期待した利回りがあれば何の文句も言わないだろ。世界中の金を使って、この愚かな国に思い知らせてやるのさ。本当の再生とは何かをな。」(『ハゲタカ(下)』p.317)
金には色がない、というフレーズは、かつて紹介したマネー・ロンダリングの本の中でも使われていました。それはさておき、「本当の再生とは何か」という問いかけは、本書を通じて考えさせられるテーマです。ハゲタカは悪(ワル)といいながら、最終的には保身のために改革も再生もできない経営者たち。それを知りつつ利益を確保しようとする銀行(銀行自体の保身は、ドラマでもバルクセールの場面で描かれています)。こういった組織とそこに所属する人間の行動がわかりやすく描かれています。
さて、『ハゲタカⅡ』では、2件の大型企業買収が扱われます。一つは鈴紡(カネボウかな、やっぱり)と月華(花王かしらん)との買収劇、曙電機(日立とNECの合作?)とシャイン(キャノン?)の買収劇です。
ここでは、ドラマとは違って、日米両政府を巻き込んでダイナミックな展開で物語が進みます。
物語の最後に、著者は柴野に次のように述懐させます。
「二十一世紀という激動の時代に突入し、伝統も名門というブランドも何の役にも立たないことを証明する皮肉な役回りを、両社(鈴紡と曙電機-引用者注)は担ってしまう。彼らの成功モデルだった多角化は否定され、運命共同体の名の下で構築された組織は馴れ合いと官僚的な事なかれ主義を生み、やがて責任の所在が不明確な無責任体質への腐敗していった。」(『ハゲタカⅡ(下)』p.426)
口では改革を叫んでいても、最終的には伝統と名門ということが改革の芽を摘んでしまい、自らではどうしようもないカオスの中に入り込んでしまう。その結果としての無責任な意思決定と行動。そして保身。そこに隙が生まれ、外部からの買収の標的になってしまいます。
『ハゲタカ』では悪(ワル)に徹していたかのような鷲津は、『ハゲタカⅡ』では柴野と協力して別の外資ファンドによる曙電機の買収を阻止しようとします(ドラマでも急転直下協力する関係になって終わりました)。結構、ハードボイルド的です。
『ハゲタカⅡ』を読みながら、『まだ解決されていない問題があるよなぁ』と思っていましたら、一番最後に「...to be continued」。物語はまだ続くようです。
先にも触れましたが、読みながらドラマの役者さんの顔が浮かんで、中でも一方の悪(ワル)として描かれた飯島をドラマで演じた中尾彬は、飯島そのものでした。(苦笑)
この本は、ぜひ学生さんたちやバブルを経験していない若い人たちに読んで欲しいなと思いました。
さて、この物語では、買収にからむたくさんの用語が出てきます。先に書いたバルクセール、バイアウトを始め、MBO、LBO、TOB、ゴールデン・パラシュート、ホワイト・ナイトなどなど。MBOやTOBは最近の新聞でよくお目にかかりますし、ホワイト・ナイトは、フジテレビとライブドアの一件でSBIがフジのホワイト・ナイトとして登場していましたのでご記憶の方もいるでしょう。
突然、こういった用語が一般にも使われ出しましたが、思い起こせば、今を去ること20年前、『ウォール街』という小説が出版され(映画にもなりました)、米国企業同士の合併が描かれておりました。その中で上記の買収がらみの用語が使われておりましたので、20年の時を経て、その行為を含めて日本に定着したといえるのかもしれません。










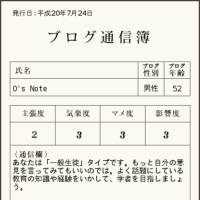









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます