前回は、教養は修養にあらず、と主張した。それは修養を目的として教養を積むいうことを非難したのであって、教養を積んでいくことが品性の向上に寄与することもあることを否定はしていない。
その理由を説明しよう。
私は以前から漢文を読むべし、と勧めているが
『漢文の中の文章には、人としての生き方を教えてくれる貴重なものが多い』
というのがその理由の一つであることは縷々述べたところである。生き方を教えてくれる漢文の文章は、特に史記を始めとした史書に多い。(現在連載している『資治通鑑に学ぶリーダーシップ』はその一例)史書では、事件にかかわる人達の説明があり、事件の背景が記述される。そして最後にその人達がどうなったかが記述されている。結末はハッピーエンドのこともあれば、理不尽で悲惨な運命で命を落とすこともある。いずれの場合も歴史の一事象としてそのまま受け入れるしかないが、論理的には別の結末も当然考えられる。悲惨な結末の場合、何故そういうふうになったのか、というより、何故その結末を回避できなかったのか、と考えさせられる。歴史は "Why" のみならず、"Why Not" を説明してはくれない。ギリシャ悲劇の貫通するテーマは『人間の傲慢』(hubris)と言われるが、歴史上の事件を考えることで、『人間の傲慢』がどういう結末をもたらすかが納得できるようになる。
一方では、歴史上の人物の生きざまに共感を覚えることがある。彼らの生きざまを知ることで、無意識のうちに持っていた、自分の理想とする生き方が固まってくるのを感じることができる。この意味で私は、特定の哲学や宗教の教義から自分の生き方を決めるやり方には賛同しない。教義が先にあるのではいけないのだ。そうではなく、過去の幾多の人々の言行の中から自分のロールモデルとなるべき人を見つけ、そこから自分の哲学や宗教観を作り上げていくべきだと私は考える。つまり、数学の公式を丸暗記することが必ずしも数学の本質を理解できないように、宗教の教義に形だけ沿った生き方では必ずしも自分の内に確固たる宗教観・人生観は確立できないのだ。
結局、歴史というのは政治体制の変遷を知るためではなく、生き方のケーススタディを学ぶためのものであると私は考える。この意味では、中国の史書だけでなく西洋の歴史書にも学ぶ所は多い。私が読んで自分の人生を考える指針となった本として、ヘロドトス、プルターク、リヴィウス、スウェトニウスなどを挙げておきたい。
【参照ブログ】
【座右之銘・45】『謂學不暇者、雖暇亦不能學矣』
【2011年度・英語授業】『日本の情報文化と社会(8)』
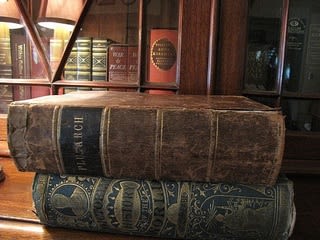
私が言いたいのは、『教養』を自分のものにしようとした場合、意味不明な『学術・芸術による品性の向上』や『修養』という題目振り回されず、最終到着点である
『多様な分野の横断的な理解を通して、世界の各文化の核(コア)となる概念をしっかりと把握すること』
を目指すべきだ、と言うことである。
ところで、漢文のような古典と言われている本を読むときの心がけについて一言述べておきたい。
古典というのは、幾世紀にもわたって読み継がれている本をさすが、世の中には古典というとあたかも神聖にして犯さざるべからずの本であるかのように錯覚している人が往々にしている。例えば、キリスト教の聖書やコーランはいうまでもなく、論語、古事記などにおいても読み方や語句の解釈は古来からのものを厳密に守らなければいけないように考えている。さらには、それを書いた人たちも、現代人よりはるかに優れている人たち(つまり聖人)であるかのように思い込んでいる。
私は、古典をこのように神聖視することは間違っていると考えている。
聖人と言われている人たちにも人間的欠陥があって、時と場合によっては、心にもないことや、わざと反発した意見を吐いたはずだと思っている。例えば、孔子は中国においてはこの2000年間、ずっと聖人として崇められてきた。彼の言ったこと、行ったことはあたかも全て合理的であり、正当であったかのごとく思われている。しかし、冷静になって論語を読むと、孔子もまた普通の感情をもった人間であることがわかる。普通人が犯すような間違いもする人たちが書いた本であるから、当然の事ながら正しくない文も交じっていて当然である。古典を神聖視し、批判的態度を自ら否定するのは、自由人たるべき人が目指すリベラルアーツではない。孟子の言う『盡信書、則不如無書』(尽く書を信ずれば則ち書なきに如かず)の趣旨だ。
【参照ブログ】
想溢筆翔:(第43回目)『40年前のあの時に戻れたら...』
【座右之銘・20】『盡信書、則不如無書』
更にいえば、古典だけでなく、過去の人物をその実態以上に評価することに対しても私は釘をさしておきたい。
例えば、幕末の志士の一人、吉田松陰に対する評価は依然として高いが、徳富蘇峰が言うように吉田松陰は『真誠の人』としては優れてはいるとは思うものの、その識見においては見るべきものは少ない。例えば彼の著書の一つに、『講孟箚記』(別名:講孟余話)という本があるが、別段、目を見張るような彼独自の解釈がなされている訳でもなければ、深い人生観が展開されている訳でもない。いくら早熟とはいえ、彼は当時、まだ30歳前の社会経験が未熟な若者であったから、それは当然とも言える。松陰の弟子たちが明治維新において大きな活躍をしたことと、我々が松陰の残した書きものから得るべきことをきっちりと区別すべきだと私は考える。
意外に思われるかもしれないが、尚古主義を標榜する儒教においてすら、過去の人物の過大評価について戒める考えがあった。孔子は民間の伝承をベースにして架空の人物、尭舜を聖人と崇めその時代を理想郷とする幻想を積極的に広めた。しかし、孔子の一番弟子の顏淵はそうした孔子の態度にたいして内心反発を感じていたようだ。孟子の『滕文公章句・上』には顏淵の『舜何人也?予何人也?有爲者亦若是。』(舜、何にびとそや?予(われ)何にびとぞや?為すある者はまたかくの如し。)という言葉が引用されている。つまり顏淵は、聖人といえども、理想化する必要はない、自分だって努力すれば舜のようになれる、と主張したのだ。
歴史を振り返ればわかるように、宗教にまつわる戦争や紛争は大抵の場合、自派の創立者や教義を絶対視するところに起因する。自分たちは正しい指導者に従い、正しい教義に則っているが、他派はそうではない。そういった邪道の人間は生きる価値がない、よって、そのような人間を殺すことは正しい行為なのだという理屈となる。客観的立場から、それぞれの宗派の創立者の言動を分析すれば、必ずしもいつも正しいとは言えないことが分かるはずだが、いったん教団に加入すると理性的な判断は禁じられ、強制的に思考停止状態にさせられる。オーム事件を持ち出すまでもなく、過去だけでなく現在においてもこのような状態の人たちがいかに多くの悲劇を引き起こしてきたか、枚挙に暇ない。
結局、過去の人を絶対視しない、この姿勢を持つべきだと私は考える。
【参照ブログ】
百論簇出:(第43回目)『陽明学を実践する前にすべきこと』
(続く。。。)
その理由を説明しよう。
私は以前から漢文を読むべし、と勧めているが
『漢文の中の文章には、人としての生き方を教えてくれる貴重なものが多い』
というのがその理由の一つであることは縷々述べたところである。生き方を教えてくれる漢文の文章は、特に史記を始めとした史書に多い。(現在連載している『資治通鑑に学ぶリーダーシップ』はその一例)史書では、事件にかかわる人達の説明があり、事件の背景が記述される。そして最後にその人達がどうなったかが記述されている。結末はハッピーエンドのこともあれば、理不尽で悲惨な運命で命を落とすこともある。いずれの場合も歴史の一事象としてそのまま受け入れるしかないが、論理的には別の結末も当然考えられる。悲惨な結末の場合、何故そういうふうになったのか、というより、何故その結末を回避できなかったのか、と考えさせられる。歴史は "Why" のみならず、"Why Not" を説明してはくれない。ギリシャ悲劇の貫通するテーマは『人間の傲慢』(hubris)と言われるが、歴史上の事件を考えることで、『人間の傲慢』がどういう結末をもたらすかが納得できるようになる。
一方では、歴史上の人物の生きざまに共感を覚えることがある。彼らの生きざまを知ることで、無意識のうちに持っていた、自分の理想とする生き方が固まってくるのを感じることができる。この意味で私は、特定の哲学や宗教の教義から自分の生き方を決めるやり方には賛同しない。教義が先にあるのではいけないのだ。そうではなく、過去の幾多の人々の言行の中から自分のロールモデルとなるべき人を見つけ、そこから自分の哲学や宗教観を作り上げていくべきだと私は考える。つまり、数学の公式を丸暗記することが必ずしも数学の本質を理解できないように、宗教の教義に形だけ沿った生き方では必ずしも自分の内に確固たる宗教観・人生観は確立できないのだ。
結局、歴史というのは政治体制の変遷を知るためではなく、生き方のケーススタディを学ぶためのものであると私は考える。この意味では、中国の史書だけでなく西洋の歴史書にも学ぶ所は多い。私が読んで自分の人生を考える指針となった本として、ヘロドトス、プルターク、リヴィウス、スウェトニウスなどを挙げておきたい。
【参照ブログ】
【座右之銘・45】『謂學不暇者、雖暇亦不能學矣』
【2011年度・英語授業】『日本の情報文化と社会(8)』
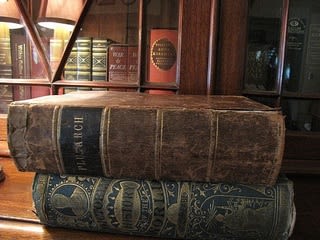
私が言いたいのは、『教養』を自分のものにしようとした場合、意味不明な『学術・芸術による品性の向上』や『修養』という題目振り回されず、最終到着点である
『多様な分野の横断的な理解を通して、世界の各文化の核(コア)となる概念をしっかりと把握すること』
を目指すべきだ、と言うことである。
ところで、漢文のような古典と言われている本を読むときの心がけについて一言述べておきたい。
古典というのは、幾世紀にもわたって読み継がれている本をさすが、世の中には古典というとあたかも神聖にして犯さざるべからずの本であるかのように錯覚している人が往々にしている。例えば、キリスト教の聖書やコーランはいうまでもなく、論語、古事記などにおいても読み方や語句の解釈は古来からのものを厳密に守らなければいけないように考えている。さらには、それを書いた人たちも、現代人よりはるかに優れている人たち(つまり聖人)であるかのように思い込んでいる。
私は、古典をこのように神聖視することは間違っていると考えている。
聖人と言われている人たちにも人間的欠陥があって、時と場合によっては、心にもないことや、わざと反発した意見を吐いたはずだと思っている。例えば、孔子は中国においてはこの2000年間、ずっと聖人として崇められてきた。彼の言ったこと、行ったことはあたかも全て合理的であり、正当であったかのごとく思われている。しかし、冷静になって論語を読むと、孔子もまた普通の感情をもった人間であることがわかる。普通人が犯すような間違いもする人たちが書いた本であるから、当然の事ながら正しくない文も交じっていて当然である。古典を神聖視し、批判的態度を自ら否定するのは、自由人たるべき人が目指すリベラルアーツではない。孟子の言う『盡信書、則不如無書』(尽く書を信ずれば則ち書なきに如かず)の趣旨だ。
【参照ブログ】
想溢筆翔:(第43回目)『40年前のあの時に戻れたら...』
【座右之銘・20】『盡信書、則不如無書』
更にいえば、古典だけでなく、過去の人物をその実態以上に評価することに対しても私は釘をさしておきたい。
例えば、幕末の志士の一人、吉田松陰に対する評価は依然として高いが、徳富蘇峰が言うように吉田松陰は『真誠の人』としては優れてはいるとは思うものの、その識見においては見るべきものは少ない。例えば彼の著書の一つに、『講孟箚記』(別名:講孟余話)という本があるが、別段、目を見張るような彼独自の解釈がなされている訳でもなければ、深い人生観が展開されている訳でもない。いくら早熟とはいえ、彼は当時、まだ30歳前の社会経験が未熟な若者であったから、それは当然とも言える。松陰の弟子たちが明治維新において大きな活躍をしたことと、我々が松陰の残した書きものから得るべきことをきっちりと区別すべきだと私は考える。
意外に思われるかもしれないが、尚古主義を標榜する儒教においてすら、過去の人物の過大評価について戒める考えがあった。孔子は民間の伝承をベースにして架空の人物、尭舜を聖人と崇めその時代を理想郷とする幻想を積極的に広めた。しかし、孔子の一番弟子の顏淵はそうした孔子の態度にたいして内心反発を感じていたようだ。孟子の『滕文公章句・上』には顏淵の『舜何人也?予何人也?有爲者亦若是。』(舜、何にびとそや?予(われ)何にびとぞや?為すある者はまたかくの如し。)という言葉が引用されている。つまり顏淵は、聖人といえども、理想化する必要はない、自分だって努力すれば舜のようになれる、と主張したのだ。
歴史を振り返ればわかるように、宗教にまつわる戦争や紛争は大抵の場合、自派の創立者や教義を絶対視するところに起因する。自分たちは正しい指導者に従い、正しい教義に則っているが、他派はそうではない。そういった邪道の人間は生きる価値がない、よって、そのような人間を殺すことは正しい行為なのだという理屈となる。客観的立場から、それぞれの宗派の創立者の言動を分析すれば、必ずしもいつも正しいとは言えないことが分かるはずだが、いったん教団に加入すると理性的な判断は禁じられ、強制的に思考停止状態にさせられる。オーム事件を持ち出すまでもなく、過去だけでなく現在においてもこのような状態の人たちがいかに多くの悲劇を引き起こしてきたか、枚挙に暇ない。
結局、過去の人を絶対視しない、この姿勢を持つべきだと私は考える。
【参照ブログ】
百論簇出:(第43回目)『陽明学を実践する前にすべきこと』
(続く。。。)
















