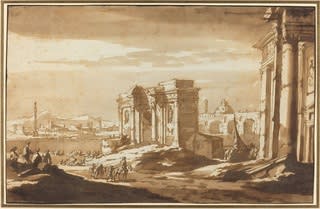(前回)
『TOEIC英語ではなく、多言語の語学を(19)』
【2.古典ギリシャ語・ラテン語の語彙と文体(その9)】
以前のブログでは、ラテン語が日本語と似ていると言ったが、当然のことながら、似ていない点も多くある。その内の一つのラテン語では(形容詞+名詞)の組み合わせが生き別れになることがよくある。(理論的には、ギリシャ語にもあるはずだが。。。)
とりわけ、韻律の制約がある詩には多く現われる(そうだ。)これも格変化が明確なおかげで、形容詞と名詞が離ればなれになっていても同じ格であることが分かるので連結しているということがすぐに分かる。一例を挙げると:
【ラテン語原文】 nullus agenti dies lungus est.
【英訳】 To one who is active, no day is long.
【英語直訳】 no to-active-person the-day long is.
英語的に考えると nullus は agenti とワンセットになりそうだが、nullus は主格であり、 agenti は3格(与格)であるので、一致しなのでペアになれない。しかし dies (day) は主格なので、nullus とペアになる。つまり、英語的に並びかえると
【英語的順序】 agenti nullus dies lungus est.
となる。この例では分離しているといっても、1ワード分だけだが、場合によっては数ワード離れていることもある。それでもラテン語の文章としては意味が通じる。もっとも、私の読んだ限りではこういった文章は詩ではかなり使われてはいるが、普通の文章ではあまり見かけない。漢文でも詩では破格の句も多いのと同様だ。
ところで、日本語では、句点の位置で意味が変わる文がある。
ここではきものをぬぐべからず。
【解釈1】 ここでは、きものを、ぬぐべからず。
【解釈2】 ここで、はきものを、ぬぐべからず。
これと同様のものがラテン語にもある。
Ibis redibis non morieri in bello.
は次の2通りに解釈できる。
【解釈1】Ibis, redibis, non morieri in bello. (行くべし、戻るべし、戦にて死ぬな。)
【解釈2】Ibis, redibis non, morieri in bello. (行くべし、戻るべからず、戦死せよ。)
日本語の回文では間違って理解しても命までとられないが、ラテン語では命が懸っている。しかし、中世になるまで、ラテン語(に限らず、ギリシャ語も)には句読点がなかったのだから、この文を読み間違えて命を落とした人もいたに違いない。
さて、日本語には上から読んでも同じ意味になる回文という文章がある。(例:竹藪焼けた [たけやぶやけた])

これと同様、ギリシャ語にも古来有名な回文がある。
ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ.
nipson anomemata me monan opsin.
(和訳:顔と一緒に罪も洗うべし)
閑話休題
これまで、ギリシャ語とラテン語の文体について述べたが、ヨーロッパではこれらの古典語は現在、どのように評価されているのかについて私の個人的な経験の範囲で知り得た情報と感想を述べてみたい。
アメリカ人は外国語に対して全般的に興味が低いので、古典語などにはほとんど関心がない。ヨーロッパ人に聞くと、流石にまだラテン語は高校あたりで数年間学ぶ人がいたが、たいていの場合、日本人の漢文同様、『やらされ感』が強く、興味が持てなかったという人が大半であった。
ギリシャ語はラテン語に比べると、かなり敷居が高いようである。それは、現地の大きな書店に入って辞書のコーナーをチェックしてみると一目瞭然である。一度、ドイツのケルンとフランクフルトの両都市で、日本でいうとジュンク堂や八重洲ブックセンターのような大型書店に入った。古典語のコーナーを見ると、ラテン語の辞書は曲がりなりにも何冊かまともな部類が置いてあったが、ギリシャ語の辞書はポケット辞書の類が何冊か申し訳程度に置いてあった。
私がもっているギリシャ語の中では中級レベルの辞書(具体的にはBenselerのGriechisch-deutsches Schulwörterbuch)すらなかったので、誰かの言いぐさではないが『ダメだこりゃ』と思わず溜息をついてしまった。それに引き換え、聖書(Bibel)はどこの書店でも一つの棚どころか棚二つ分一杯にあった。
また、西洋のいろいろな本に載せられている単語や文献の名前を見ていると、ざっくり言って、1960年代まではギリシャ語の単語や文献はギリシャ文字で書かれている
たとえば、科学史に関する金字塔的存在の René Tatonの本、"L'histoire générale des sciences”(全4冊)は1950年、1960年に書かれたが、ギリシャ語の単語はほとんどの場合ギリシャ文字で書かれている。辞書も同様だ。しかるに、 1977年発行のフランス語の辞書、Petit Robert はギリシャ語がローマ字で書かれている。その原因は、1960年以降ギリシャ語が高校(lycee)で選択になったので、ギリシャ文字が読めないフランス知識人が増えてきたためだと思われる。
ついでにラテン語について言うと:
私がヨーロッパ旅行中の経験したことだが、教会の中に入ると、石造の墓が置いてあったり、床にレリーフの墓が彫られていることがある。それらに書かれている文字を見ると、イギリスでは1600年以前はだいたいラテン語で書かれているが、それ以降は英語で書かれている。ところが、イタリアは 1900年まではラテン語で書かれている。これを見て、イタリア人とイギリス人のラテン語に対する愛着の歴然たる差を感じた。
ヨーロッパ人にとってラテン語がギリシャ語より遥かに親しみがある理由としては、一つにはラテン語がキリスト教会の公用語ということが挙げられるが、もう一つは、ラテン語が19世紀までヨーロッパ各国の博士論文の言語であったことが関係している。(【出典】ジャクリーヌ・ダンジェル、『ラテン語の歴史』(P.66)白水社・クセジュ文庫、遠山一郎訳)
これは、ちょうど中国、朝鮮(李朝、大韓帝国)および日本における漢文の役割に相当する。その意味で、ラテン語の習得を止めるということは日本で言うと漢文教育の廃止と同じ位のネガティブなインパクトをもっていると私には思える。
(続く。。。)
『TOEIC英語ではなく、多言語の語学を(19)』
【2.古典ギリシャ語・ラテン語の語彙と文体(その9)】
以前のブログでは、ラテン語が日本語と似ていると言ったが、当然のことながら、似ていない点も多くある。その内の一つのラテン語では(形容詞+名詞)の組み合わせが生き別れになることがよくある。(理論的には、ギリシャ語にもあるはずだが。。。)
とりわけ、韻律の制約がある詩には多く現われる(そうだ。)これも格変化が明確なおかげで、形容詞と名詞が離ればなれになっていても同じ格であることが分かるので連結しているということがすぐに分かる。一例を挙げると:
【ラテン語原文】 nullus agenti dies lungus est.
【英訳】 To one who is active, no day is long.
【英語直訳】 no to-active-person the-day long is.
英語的に考えると nullus は agenti とワンセットになりそうだが、nullus は主格であり、 agenti は3格(与格)であるので、一致しなのでペアになれない。しかし dies (day) は主格なので、nullus とペアになる。つまり、英語的に並びかえると
【英語的順序】 agenti nullus dies lungus est.
となる。この例では分離しているといっても、1ワード分だけだが、場合によっては数ワード離れていることもある。それでもラテン語の文章としては意味が通じる。もっとも、私の読んだ限りではこういった文章は詩ではかなり使われてはいるが、普通の文章ではあまり見かけない。漢文でも詩では破格の句も多いのと同様だ。
ところで、日本語では、句点の位置で意味が変わる文がある。
ここではきものをぬぐべからず。
【解釈1】 ここでは、きものを、ぬぐべからず。
【解釈2】 ここで、はきものを、ぬぐべからず。
これと同様のものがラテン語にもある。
Ibis redibis non morieri in bello.
は次の2通りに解釈できる。
【解釈1】Ibis, redibis, non morieri in bello. (行くべし、戻るべし、戦にて死ぬな。)
【解釈2】Ibis, redibis non, morieri in bello. (行くべし、戻るべからず、戦死せよ。)
日本語の回文では間違って理解しても命までとられないが、ラテン語では命が懸っている。しかし、中世になるまで、ラテン語(に限らず、ギリシャ語も)には句読点がなかったのだから、この文を読み間違えて命を落とした人もいたに違いない。
さて、日本語には上から読んでも同じ意味になる回文という文章がある。(例:竹藪焼けた [たけやぶやけた])

これと同様、ギリシャ語にも古来有名な回文がある。
ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ.
nipson anomemata me monan opsin.
(和訳:顔と一緒に罪も洗うべし)
閑話休題
これまで、ギリシャ語とラテン語の文体について述べたが、ヨーロッパではこれらの古典語は現在、どのように評価されているのかについて私の個人的な経験の範囲で知り得た情報と感想を述べてみたい。
アメリカ人は外国語に対して全般的に興味が低いので、古典語などにはほとんど関心がない。ヨーロッパ人に聞くと、流石にまだラテン語は高校あたりで数年間学ぶ人がいたが、たいていの場合、日本人の漢文同様、『やらされ感』が強く、興味が持てなかったという人が大半であった。
ギリシャ語はラテン語に比べると、かなり敷居が高いようである。それは、現地の大きな書店に入って辞書のコーナーをチェックしてみると一目瞭然である。一度、ドイツのケルンとフランクフルトの両都市で、日本でいうとジュンク堂や八重洲ブックセンターのような大型書店に入った。古典語のコーナーを見ると、ラテン語の辞書は曲がりなりにも何冊かまともな部類が置いてあったが、ギリシャ語の辞書はポケット辞書の類が何冊か申し訳程度に置いてあった。
私がもっているギリシャ語の中では中級レベルの辞書(具体的にはBenselerのGriechisch-deutsches Schulwörterbuch)すらなかったので、誰かの言いぐさではないが『ダメだこりゃ』と思わず溜息をついてしまった。それに引き換え、聖書(Bibel)はどこの書店でも一つの棚どころか棚二つ分一杯にあった。
また、西洋のいろいろな本に載せられている単語や文献の名前を見ていると、ざっくり言って、1960年代まではギリシャ語の単語や文献はギリシャ文字で書かれている
たとえば、科学史に関する金字塔的存在の René Tatonの本、"L'histoire générale des sciences”(全4冊)は1950年、1960年に書かれたが、ギリシャ語の単語はほとんどの場合ギリシャ文字で書かれている。辞書も同様だ。しかるに、 1977年発行のフランス語の辞書、Petit Robert はギリシャ語がローマ字で書かれている。その原因は、1960年以降ギリシャ語が高校(lycee)で選択になったので、ギリシャ文字が読めないフランス知識人が増えてきたためだと思われる。
ついでにラテン語について言うと:
私がヨーロッパ旅行中の経験したことだが、教会の中に入ると、石造の墓が置いてあったり、床にレリーフの墓が彫られていることがある。それらに書かれている文字を見ると、イギリスでは1600年以前はだいたいラテン語で書かれているが、それ以降は英語で書かれている。ところが、イタリアは 1900年まではラテン語で書かれている。これを見て、イタリア人とイギリス人のラテン語に対する愛着の歴然たる差を感じた。
ヨーロッパ人にとってラテン語がギリシャ語より遥かに親しみがある理由としては、一つにはラテン語がキリスト教会の公用語ということが挙げられるが、もう一つは、ラテン語が19世紀までヨーロッパ各国の博士論文の言語であったことが関係している。(【出典】ジャクリーヌ・ダンジェル、『ラテン語の歴史』(P.66)白水社・クセジュ文庫、遠山一郎訳)
これは、ちょうど中国、朝鮮(李朝、大韓帝国)および日本における漢文の役割に相当する。その意味で、ラテン語の習得を止めるということは日本で言うと漢文教育の廃止と同じ位のネガティブなインパクトをもっていると私には思える。
(続く。。。)