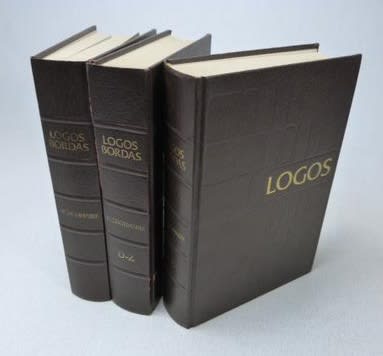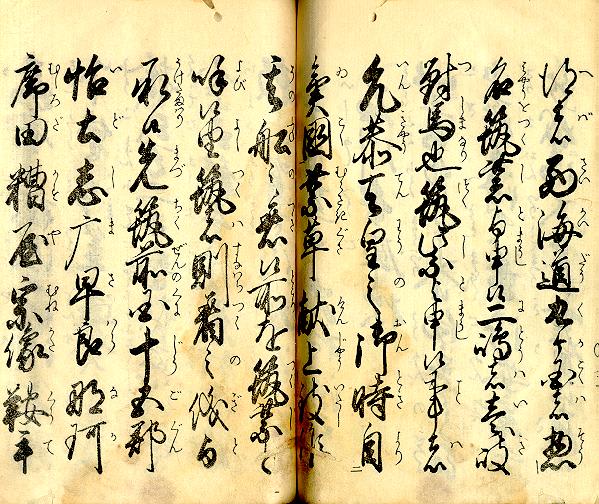(前回)
〇「プラトンとセネカに魅了される」(『教養を極める読書術』 P.22)
プラトンの対話篇を読むことの重要性については前回のブログだけでなくすでに何度も取り上げているが、再度(懲りもせず)なぜそれほどまでプラトンに魅了されたかについて述べよう。
よく「学生時代によむ100冊」「古典的名著」など、名著を紹介した特集でプラトンが言及されるときは、決まって『ソクラテスの弁明』『パイドン』『饗宴』『国家』が挙がる。確かに最初の2作、『ソクラテスの弁明』『パイドン』にはソクラテスの高い倫理観が凝縮されているのでヨーロッパの徳の理想を知るには最適の書といえよう。次に『饗宴』はシェークスピアの喜劇『十二夜』『お気に召すまま』のようなエンターテイメント・ドラマとして楽しめる傑作であるといえる。最後の『国家』はギリシャの教育や行政のあり方(現実と理想)がよくわかる、充実した内容だ。

しかし、私がプラトンに魅了されたのは別の観点だ。
プラトンから大いなる刺激を受けたのは話し方、学術的にいうと、レトリックである。レトリックはたいていは修辞学と訳されるが、ここでは「弁論術・雄弁術」という意味だ。人は訓練を受けなくともしゃべることはできるが、それは単なる「だべり」に過ぎない。あるいは、歩くことは誰でもできるが、競歩のように「速く、長く」歩けるには訓練が必要だ。それと同じく「だべり」ではなく、「聞かせる話し方」ができるようになるには訓練が必要だ。話し方の訓練といえば、アナウンサーや落語家のような特殊な職業に就く人だけに必要だと考えるかもしれないが、一般の社会人・ビジネスパーソンにも必要だ。
西洋では伝統的に「弁論術・雄弁術」のカリキュラムが用意されているが、その基本部分を教えてくれるのがプラトンの初期対話篇である。具体的には『イオン』『メノン』『ラケス』だ。これらを読むといわゆる「ソクラテス・メソッド」のからくりがよく分かる。ソクラテス・メソッドの要点(キモ)は「一文で話すことは一つのこと」に絞ることである。文章でいうと「、」(句点)で話しを続けずに、「。」(読点)で文を完結することだ。つまり、述べる内容をレゴのようなかっちりとしたブロックを積むように構築することだ。それができるには、頭のなかでいうべきことの全体図が見えていないといけない。
この点に関しては、以前のブログ
『外国語会話上達にもつながる弁論術のポイント』
で頭の中の整理法を述べたのでそれを参照して頂きたい。要は、だべり会話をしている限り、頭のなかを整理して話すことはできない。その状況を生き生きと示してくれるのが、上に挙げたプラトンの初期対話篇の数々である。もっとも、これらの対話篇は哲学的観点から言えば、当初設定された問題を解決できず、aporia に陥った失敗作とみなされている。しかし、弁論術の観点からいえば、これら失敗作こそに価値があるのだ。その理由は「論理のからくり」を見せてくれるからである。例えば、手品師が手品をしているところを見ても、そのからくりが分からない。ところが、失敗して道具をポトンと落としてしまったりすると、カラクリが一遍に分かる。または、前から見ていると分からなくても、手品師の背後から見ると、カラクリが簡単に分かる。プラトンの失敗作といわれる『イオン』『メノン』『ラケス』は、舞台裏やカラクリがよく分かる作品である。論理的に話していても、最終的には間違った結論に達することもあるという好例だ。これから逆に、正しい結論に至るにはどうすればいいのかということも見えてくる。
一方、プラトンの初期の力作『プロタゴラス』『ゴルギアス』からは、本格的な弁論の仕方を学ぶことができる。この2つの作品には当時の超一流のソフィストである、プロタゴラスとゴルギアスがそれぞれ登場する。どの程度、本物の弁論かという歴史的詮索はさておき、この作品はあたかも録音の書き起こしのように当時のディベートのライブの興奮をじかに感じることができる。
これらの対話篇にあって、ソクラテスはいつものごとく論理をワンステップ、ワンステップをきちんとチェックしながら話を進める(ソクラテス・メソッド)。それに対して、ソフィストは多少の論理矛盾はあっても滔々とした弁舌で相手を言葉で酔わせてしまう。しかし、その場の雰囲気の中では納得できても、後で冷静になって振り返って見ると納得できないことが多々見つかる。これから、本当の意味の論理(ロジカル・シンキング)とは、必ずソクラテスのように、短答式の問いを重ねる方法しかないことが分かる。
このように私はプラトンから話し方、つまり弁論術の学ぶという観点で勧めるのだが、そのような意見は今まであまり言った人はいないだろう。なぜ、今までこういうことをが言われなかったのかといえば、プラトンを哲学的観点、つまり倫理、政治、形而上学、認識論の観点からしか見なかったからだ。哲学的観点からは、上に挙げた『イオン』『メノン』『ラケス』などの失敗作はほとんど評価されず、もっぱら重厚感のある『国家』やソクラテスの倫理観の結晶である『ソクラテスの弁明』を畏敬して取り上げる、という姿勢であった。
私は、活き活きとした弁論術の実例を、それも人類の歴史上で最高傑作ともいえる実例を知ることのできる書としてプラトンの対話篇を読むことを強く勧める。
【参照ブログ】
想溢筆翔:(第21回目)『粘土言語とレンガ言語』
想溢筆翔:(第14回目)『外国語会話上達にもつながる弁論術のポイント』
(続く。。。)
〇「プラトンとセネカに魅了される」(『教養を極める読書術』 P.22)
プラトンの対話篇を読むことの重要性については前回のブログだけでなくすでに何度も取り上げているが、再度(懲りもせず)なぜそれほどまでプラトンに魅了されたかについて述べよう。
よく「学生時代によむ100冊」「古典的名著」など、名著を紹介した特集でプラトンが言及されるときは、決まって『ソクラテスの弁明』『パイドン』『饗宴』『国家』が挙がる。確かに最初の2作、『ソクラテスの弁明』『パイドン』にはソクラテスの高い倫理観が凝縮されているのでヨーロッパの徳の理想を知るには最適の書といえよう。次に『饗宴』はシェークスピアの喜劇『十二夜』『お気に召すまま』のようなエンターテイメント・ドラマとして楽しめる傑作であるといえる。最後の『国家』はギリシャの教育や行政のあり方(現実と理想)がよくわかる、充実した内容だ。

しかし、私がプラトンに魅了されたのは別の観点だ。
プラトンから大いなる刺激を受けたのは話し方、学術的にいうと、レトリックである。レトリックはたいていは修辞学と訳されるが、ここでは「弁論術・雄弁術」という意味だ。人は訓練を受けなくともしゃべることはできるが、それは単なる「だべり」に過ぎない。あるいは、歩くことは誰でもできるが、競歩のように「速く、長く」歩けるには訓練が必要だ。それと同じく「だべり」ではなく、「聞かせる話し方」ができるようになるには訓練が必要だ。話し方の訓練といえば、アナウンサーや落語家のような特殊な職業に就く人だけに必要だと考えるかもしれないが、一般の社会人・ビジネスパーソンにも必要だ。
西洋では伝統的に「弁論術・雄弁術」のカリキュラムが用意されているが、その基本部分を教えてくれるのがプラトンの初期対話篇である。具体的には『イオン』『メノン』『ラケス』だ。これらを読むといわゆる「ソクラテス・メソッド」のからくりがよく分かる。ソクラテス・メソッドの要点(キモ)は「一文で話すことは一つのこと」に絞ることである。文章でいうと「、」(句点)で話しを続けずに、「。」(読点)で文を完結することだ。つまり、述べる内容をレゴのようなかっちりとしたブロックを積むように構築することだ。それができるには、頭のなかでいうべきことの全体図が見えていないといけない。
この点に関しては、以前のブログ
『外国語会話上達にもつながる弁論術のポイント』
で頭の中の整理法を述べたのでそれを参照して頂きたい。要は、だべり会話をしている限り、頭のなかを整理して話すことはできない。その状況を生き生きと示してくれるのが、上に挙げたプラトンの初期対話篇の数々である。もっとも、これらの対話篇は哲学的観点から言えば、当初設定された問題を解決できず、aporia に陥った失敗作とみなされている。しかし、弁論術の観点からいえば、これら失敗作こそに価値があるのだ。その理由は「論理のからくり」を見せてくれるからである。例えば、手品師が手品をしているところを見ても、そのからくりが分からない。ところが、失敗して道具をポトンと落としてしまったりすると、カラクリが一遍に分かる。または、前から見ていると分からなくても、手品師の背後から見ると、カラクリが簡単に分かる。プラトンの失敗作といわれる『イオン』『メノン』『ラケス』は、舞台裏やカラクリがよく分かる作品である。論理的に話していても、最終的には間違った結論に達することもあるという好例だ。これから逆に、正しい結論に至るにはどうすればいいのかということも見えてくる。
一方、プラトンの初期の力作『プロタゴラス』『ゴルギアス』からは、本格的な弁論の仕方を学ぶことができる。この2つの作品には当時の超一流のソフィストである、プロタゴラスとゴルギアスがそれぞれ登場する。どの程度、本物の弁論かという歴史的詮索はさておき、この作品はあたかも録音の書き起こしのように当時のディベートのライブの興奮をじかに感じることができる。
これらの対話篇にあって、ソクラテスはいつものごとく論理をワンステップ、ワンステップをきちんとチェックしながら話を進める(ソクラテス・メソッド)。それに対して、ソフィストは多少の論理矛盾はあっても滔々とした弁舌で相手を言葉で酔わせてしまう。しかし、その場の雰囲気の中では納得できても、後で冷静になって振り返って見ると納得できないことが多々見つかる。これから、本当の意味の論理(ロジカル・シンキング)とは、必ずソクラテスのように、短答式の問いを重ねる方法しかないことが分かる。
このように私はプラトンから話し方、つまり弁論術の学ぶという観点で勧めるのだが、そのような意見は今まであまり言った人はいないだろう。なぜ、今までこういうことをが言われなかったのかといえば、プラトンを哲学的観点、つまり倫理、政治、形而上学、認識論の観点からしか見なかったからだ。哲学的観点からは、上に挙げた『イオン』『メノン』『ラケス』などの失敗作はほとんど評価されず、もっぱら重厚感のある『国家』やソクラテスの倫理観の結晶である『ソクラテスの弁明』を畏敬して取り上げる、という姿勢であった。
私は、活き活きとした弁論術の実例を、それも人類の歴史上で最高傑作ともいえる実例を知ることのできる書としてプラトンの対話篇を読むことを強く勧める。
【参照ブログ】
想溢筆翔:(第21回目)『粘土言語とレンガ言語』
想溢筆翔:(第14回目)『外国語会話上達にもつながる弁論術のポイント』
(続く。。。)