(前回)
本シリーズ《軟財就計》の第2回目からこれまで Britannica 第11版(11th edition)を表示するためのシステムを説明した。つまり、 Web 上に提供されるアクセス方法では、望む形式で表示できないが、自作のプログラムを組むことで、容易に「わがまま」を押し通すことができる実例を示した。このように自分でプログラムを組むことによって随分見やすい表示でBritannica 11th を読むことができ、大変うれしく思っている。
ところで、Britannica には11th 以外にも学術的に高く評価されている版がある。Wikipediaの記載によると、 11thの直前の 9th 版で"high point of scholarship"と高く評価されている。(10th 版は9thのSupplement)

この情報を目にしてから、私の持っているインディアンペーパーの11th 版の使いにくさもあって、9th版を見てみたいという欲求が高まった。そして、遂に格安で購入できた。その顛末については以前のブログ
沂風詠録:(第339回目)『良質の情報源を手にいれるには?(その 44)』
で述べた通りだ。
9th を使ってみると予想どおり、私の関心である「ギリシャ・ローマに関する知識」に関して他に見られないほど詳細に記述されていた。それまで、ギリシャ・ローマの事物に関してはドイツ語の Kleine Pauly や Artemisの Lexikon der Alten Welt で調べていたり、英語では The Oxford Classical Dictionary を参照していたことは、以前のブログ
沂風詠録:(第314回目)『良質の情報源を手にいれるには?(その 19)』
で紹介した。ただ、残念ながら英語のThe Oxford Classical Dictionary は記述内容が大いに不足しているため、参照することは稀だ。ドイツ語の2冊にはいつも満足しているが、たまに違った角度からもう少し別の情報が欲しいと思う時がある。しかし、いつもそれ以上情報がなく、立ち止まってしまわなければならないことに歯がゆかい思いをすることは一度や二度ではなかった。それで、Britannica 9th を入手した時にこの点の改善を期待したのだが、その期待は裏切られることはなかった。9thのギリシャ・ローマに関連する記述は、11th以上に幅広くかつ専門的なのが、ドンピシャ私が求めていたものであった。
例えば、古代ギリシャの政治家・弁論家であるAeschines(アイスキネス、BC 389 - 314)の項目を見てみよう。当時、アテネの政治的なパワーは落ち、マケドニアのアレクサンドリア大王が昇天の勢いでギリシャ世界を席巻していた。その勢いに呼応してアテネでは、親マケドニア派(アイスキネス)と反マケドニア派(デモステネス、Demosthenes)に別れて激しく争っていた。最終的には、デモステネスの弁論に破れたアイスキネスはロドス島に亡命し、生計のため弁論学校を開いて、弁論術を教えることとなった。 Britannica 9th にはその時の様子を次のように紹介する。
【要約】ロドス島に弁論術の学校を開いた開講の冒頭でアイスキネスは生徒たちに向かって、自分の弁論とデモステネスの弁論の2つを演じてみせた。アイスキネスの弁論に生徒たちは感嘆し、拍手をしたが、アイスキネスがデモステネスの弁論を演じると、生徒たちは総立ちになって拍手した。生徒たちの反応に、アイスキネスは内心、自尊心を傷つけられていたが平静を装い「もし君たちが、その場にいてデモステネスの弁論を聞いたらとても今の興奮どころではないだろうね」とつぶやいた。
Aeschines, after staying some years in Asia Minor, opened aschool of eloquence at Rhodes. He is said to have commenced his lectures by reading to his audience the two orations which had been the cause of his banishment. His own oration received great praise, but that of Demosthenes was heard with boundless applause. In so trying a moment, when vanity must be supposed to have been deeply wounded, he is reported to have said, with a noble generosity of sentiment, "What would you have thought if you had heard him thunder out the words himself !"
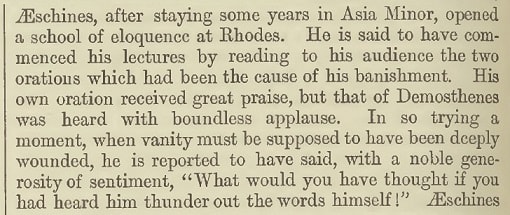
Britannica 9thはこのように、デモステネスの弁論の迫力をアイスキネス自身の言葉で表現しているが、残念なことに 11th やそれ以降の版にはこの部分がカットされている。確かに、わざわざアイスキネスの言葉を引用せずともデモステネスの雄弁さを表現することは可能だ。しかし、アッティカの10大弁論家の内の一人のアイスキネスがデモステネスの弁論がダントツであることを実演したこのエピソードこそデモステネスの雄弁さを証拠立てる歴史的価値があると私には思える。ところで、この部分の記述は、その後ローマで弁論術の教師をしていたクインティリアヌス( Quintilianus、Quintilian)が書いた、弁論術の教科書『弁論家の教育』にも引用されている(巻11、7節)。
このように、今回紹介した、アイスキネスの項目に限らず、 Britannica 9th には他の情報源からは知ることができない内容が多く含まれている。それでは、私がこの9thをどのようにして読むことができたかについて次回、説明しよう。
(続く。。。)
本シリーズ《軟財就計》の第2回目からこれまで Britannica 第11版(11th edition)を表示するためのシステムを説明した。つまり、 Web 上に提供されるアクセス方法では、望む形式で表示できないが、自作のプログラムを組むことで、容易に「わがまま」を押し通すことができる実例を示した。このように自分でプログラムを組むことによって随分見やすい表示でBritannica 11th を読むことができ、大変うれしく思っている。
ところで、Britannica には11th 以外にも学術的に高く評価されている版がある。Wikipediaの記載によると、 11thの直前の 9th 版で"high point of scholarship"と高く評価されている。(10th 版は9thのSupplement)

この情報を目にしてから、私の持っているインディアンペーパーの11th 版の使いにくさもあって、9th版を見てみたいという欲求が高まった。そして、遂に格安で購入できた。その顛末については以前のブログ
沂風詠録:(第339回目)『良質の情報源を手にいれるには?(その 44)』
で述べた通りだ。
9th を使ってみると予想どおり、私の関心である「ギリシャ・ローマに関する知識」に関して他に見られないほど詳細に記述されていた。それまで、ギリシャ・ローマの事物に関してはドイツ語の Kleine Pauly や Artemisの Lexikon der Alten Welt で調べていたり、英語では The Oxford Classical Dictionary を参照していたことは、以前のブログ
沂風詠録:(第314回目)『良質の情報源を手にいれるには?(その 19)』
で紹介した。ただ、残念ながら英語のThe Oxford Classical Dictionary は記述内容が大いに不足しているため、参照することは稀だ。ドイツ語の2冊にはいつも満足しているが、たまに違った角度からもう少し別の情報が欲しいと思う時がある。しかし、いつもそれ以上情報がなく、立ち止まってしまわなければならないことに歯がゆかい思いをすることは一度や二度ではなかった。それで、Britannica 9th を入手した時にこの点の改善を期待したのだが、その期待は裏切られることはなかった。9thのギリシャ・ローマに関連する記述は、11th以上に幅広くかつ専門的なのが、ドンピシャ私が求めていたものであった。
例えば、古代ギリシャの政治家・弁論家であるAeschines(アイスキネス、BC 389 - 314)の項目を見てみよう。当時、アテネの政治的なパワーは落ち、マケドニアのアレクサンドリア大王が昇天の勢いでギリシャ世界を席巻していた。その勢いに呼応してアテネでは、親マケドニア派(アイスキネス)と反マケドニア派(デモステネス、Demosthenes)に別れて激しく争っていた。最終的には、デモステネスの弁論に破れたアイスキネスはロドス島に亡命し、生計のため弁論学校を開いて、弁論術を教えることとなった。 Britannica 9th にはその時の様子を次のように紹介する。
【要約】ロドス島に弁論術の学校を開いた開講の冒頭でアイスキネスは生徒たちに向かって、自分の弁論とデモステネスの弁論の2つを演じてみせた。アイスキネスの弁論に生徒たちは感嘆し、拍手をしたが、アイスキネスがデモステネスの弁論を演じると、生徒たちは総立ちになって拍手した。生徒たちの反応に、アイスキネスは内心、自尊心を傷つけられていたが平静を装い「もし君たちが、その場にいてデモステネスの弁論を聞いたらとても今の興奮どころではないだろうね」とつぶやいた。
Aeschines, after staying some years in Asia Minor, opened aschool of eloquence at Rhodes. He is said to have commenced his lectures by reading to his audience the two orations which had been the cause of his banishment. His own oration received great praise, but that of Demosthenes was heard with boundless applause. In so trying a moment, when vanity must be supposed to have been deeply wounded, he is reported to have said, with a noble generosity of sentiment, "What would you have thought if you had heard him thunder out the words himself !"
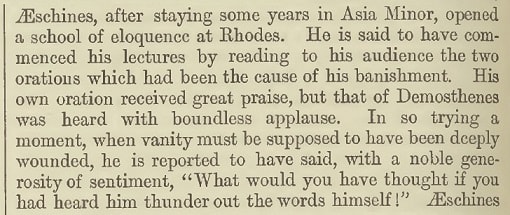
Britannica 9thはこのように、デモステネスの弁論の迫力をアイスキネス自身の言葉で表現しているが、残念なことに 11th やそれ以降の版にはこの部分がカットされている。確かに、わざわざアイスキネスの言葉を引用せずともデモステネスの雄弁さを表現することは可能だ。しかし、アッティカの10大弁論家の内の一人のアイスキネスがデモステネスの弁論がダントツであることを実演したこのエピソードこそデモステネスの雄弁さを証拠立てる歴史的価値があると私には思える。ところで、この部分の記述は、その後ローマで弁論術の教師をしていたクインティリアヌス( Quintilianus、Quintilian)が書いた、弁論術の教科書『弁論家の教育』にも引用されている(巻11、7節)。
このように、今回紹介した、アイスキネスの項目に限らず、 Britannica 9th には他の情報源からは知ることができない内容が多く含まれている。それでは、私がこの9thをどのようにして読むことができたかについて次回、説明しよう。
(続く。。。)



















