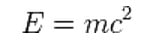このブログでも既に何度か紹介しているが、
Encyclopedia Britannicaは英語でかかれた最高の百科事典であるが、その中でもとりわけ第9版(9th)と第11版(11th)が頭抜けている。
Wikipediaの項には9thには"high point of scholarship"(学識の極点)という名辞が献ぜられている。また、11thには "Another high point of scholarship and writing" と称されている。つまり、9thと11thは、内容の素晴らしさは甲乙つけ難い、ということだ。ただ、11thには "more articles than the 9th, but shorter and simpler" との語句が続く。つまり、11thは意図的に説明を簡潔にしたという。その意図は、推察するに全体のページ数を増加させることなく、9thより、多くの項目を掲載したということだろう。
この点は、中国の24史の『旧唐書』と『新唐書』の関係を彷彿とさせる。というのは、新唐書は、旧唐書の古い文体(四六駢儷体)を欧陽脩が主導する古文で書き換えたのであるが、『新唐書』には「記述は旧唐書より増やして充実させたが、一方では文章簡略にして読みやすくした」(其事則増于前、其文則省于旧)と誇らしげに述べている。(曾公亮の『進唐書表』)ただ、私の好みからいうと、新唐書の記述は、素っ気なく平板な感じがする一方、旧唐書の文章は情緒豊かであると感じる。

具体的な例を挙げてみよう。
ギリシャにディノクラティスという建築家がいた。アレクサンドロスの命で、エジプトのアレクサンドリアに碁盤目状の都市を計画したことで有名だ。ディノクラティスの行状をBritannicaの9thと11thのそれぞれの記述を比べてみよう。先ず、11thでは次のように書かれている。
********** Britannica 11th、8巻 P. 277 **********
DINOCRATES, a great and original Greek architect, of the age of Alexander theGreat. He tried to captivate the ambitious fancy of that king with a designfor carving Mount Athos into a gigantic seated statue. This plan was notcarried out, but Dinocrates designed for Alexander the plan of the new city ofAlexandria, and constructed the vast funeral pyre of Hephaestion. Alexandriawas, like Peiraeus and Rhodes (see Hippodamus), built on a regular plan;
【大意】ディノクラティスはギリシャの建築家で、アレクサンドロス大王の時代に生きた。アトス山の彫刻を大王に勧めたが、実現せず。ピレウスやロドスのような計画都市のアレクサンドリアを設計した。
****************************************
ここにはディノクラティスの建築家としての業績は十分に説明されているものの、人物像が彷彿としない。一方9thの記述はまるで講談話聴いているようだ。
********** Britannica 9th、7巻 P.243 **********
DINOCRATES (called by Pliny Dinochares), a Greek architect, who lived in the reign of Alexander the Great.
He applied to that king's courtiers for an introduction to the Macedonian king, but was put off from time to time with vain promises. Impatient at the delay, he is said to have laid aside his usual dress, besmeared his body with oil in the manner of an athlete, thrown a lion's skin over his shoulders, and, with his head adorned with a wreath of palm branches, and a club in his hand, made his way through a dense crowd which surrounded the royal tribunal to the place where the king was dispensing justice.
【大意】ディノクラティスはギリシャの建築家、アレクサンドロス大王の時代に生きた。何度も大王へのお目通りを願ったがかなえられず。とうとう、待ちきれず作業服を脱ぎ捨て、拳闘家のように全身をオリーブオイルで塗りたくり、ライオンの皮を身に着け、棍棒を手にしたて派手な格好で大王の面前に進みでた。
Amazed at the strange sight, Alexander asked him who he was. He replied that he had come into the royal presence to make known a scheme which would be worthy of the consideration of the greatest monarch in the world. Out of Mount Athos, a mountain rising like a pyramid to a height of 6780 feet topped with a cone of white limestone, he proposed to construct the gigantic figure of a man, holding a large city in his right hand, while in his left he held a gigantic tank large enough to contain all the water from the brooks in the peninsula.
大王は、その奇妙な姿に驚いて、誰だと問うた。ディノクラティスは、大王に相応しい計画たあると言って、アトス山の削ってピラミッド並みの巨大な像を作ることを提案した。
The story goes that the king was not displeased with the idea, but, as he thought it chimerical, it came to nothing. Alexander, however, was so delighted with the man, and with his bold and daring conceptions, that he carried Dinocrates with him when he went on his campaigns against Darius. He was employed by the king to design and lay out the city of Alexandria.
大王はまんざらでもない案だと誉めたものの、絵空事とみなしたが、ディノクラティスの大胆な気性を気に入り、ペルシャ侵攻に伴っていった。そして、アレクサンドリアの都市計画を任じた。
****************************************
ディノクラティスは、長い間アレクサンドロス大王に近づく機会が得られず、しびれをきらした。そこで、一計を案じてわざと奇抜な恰好をして現れたので、大王の目で止まった。それで、早速、大王の派手好みに合わせたアトス山の大改造のホラ話で、見事、大王の琴線を掴んだ、ということだ。確かにこのような話は、無くとも別段ディノクラティスの歴史上の業績の評価には無関係であるが、それでもこのような話を載せておくことが必要と9thの編者は考えた。
歴史書では、司馬遷の『史記』にはこのようなあっても無かってもよいような話がふんだんに盛り込まれている。歴史から、人の生き方とか、言動のパターンを知るにはこのような話は欠くべからざる要素と私は考える。この意味で、11thは世評では学術的には9thより優れているかもしれないが、私個人としては、素っ気ない記述の11thより、文化的な馥郁とした香りが漂う、一見、冗長な記述を厭わない9thの方を一層高く評価するのである。
=================
【参考】DeepLによる和訳を下に掲げる。現在の機械翻訳(AI翻訳)は普通の人間より遥かに上手に翻訳できる。
【11th】ディノクラテス(DINOCRATES)は、アレクサンドロス大王の時代の、偉大で独創的なギリシャの建築家である。彼は、アトス山を巨大な座像に彫り上げる設計で、その王の野心的な心を魅了しようとした。この計画は実現しなかったが、ディノクラテスはアレクサンダーのためにアレクサンドリアの新都市の設計を行い、ヘファエスティオンの巨大な葬儀用の火葬場を建設した。アレクサンドリアは、ペイラエウスやロードス島(ヒッポダマスの項を参照)と同様、規則正しい計画に基づいて建設された;
【9th】ディノクラテス(プリニウスはディノチャレスと呼んだ)は、アレクサンダー大王の治世に生きたギリシャの建築家。
アレクサンドロス大王の廷臣たちにマケドニア王への紹介を申し込んだが、何度も約束を反故にされた。その遅れに業を煮やしたアレクサンドロスは、普段の服装を脱ぎ捨て、スポーツ選手のように体に油を塗り、ライオンの皮を肩にかけ、頭には椰子の枝の花輪を飾り、手には棍棒を持って、王が裁きを下している場所まで、王宮を取り囲む群衆の中を進んだと言われている。
その異様な光景に驚いたアレクサンダーは、彼に何者かと尋ねた。彼は、世界で最も偉大な君主の検討に値するであろう計画を知らせるために、王の前に現れたと答えた。彼は、白い石灰岩の円錐形の頂上にピラミッドのようにそびえ立つ高さ6780フィートのアトス山から、右手に大きな都市を持ち、左手には半島の小川の水がすべて入るほどの巨大な水槽を持った人間の巨大な姿を建造することを提案した。
国王はその考えを快く思わなかったが、空想的なものだと考えたため、実現しなかったという話である。しかし、アレクサンダーはディノクラテスの大胆な構想を気に入り、ダリウスとの戦いに赴く際にはディノクラテスを同行させた。ディノクラテスは王に雇われ、アレクサンドリアの都市を設計した。