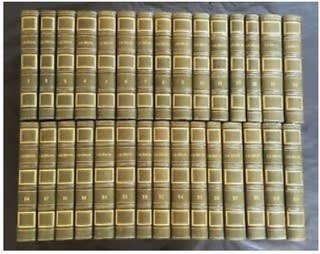(前回)
【365.研鑽・鑽研 】P.4653、AD519年
『研鑽』とは「学問などを深く究めること」。一字づつはそれぞれ「研」は「みがく」、「鑽」は「(きりで)穴をあける」という意味がある。つまり「研鑽」は元来「職人が宝石に穴をあけて、丁寧に磨く」ことを意味した。その物理的な意味から抽象的な意味になった。意味は同じであるものの、漢文の文脈では「研鑽」よりも逆順の「鑽研」の方が多く使われている。中国の辞書には「研鑽」は載っていないが「鑽研」は載っている。辞海(1978年版)には「鑽研」を「謂精究其義也」(その義を精究する也)と説明する。また辞源(1987年版)では「鑽堅研微」の句を見だしとして挙げ、出典は晋書・《虞喜伝》という。、その意味は「研究事理、深入底細」であると説明する。
「研鑽」と「鑽研」を二十四史(+資治通鑑+続資治通鑑)で検索する次の表のようになる。

この表からわかるように、「研鑽」も「鑽研」も中国ではほとんど使われていない単語であるが、強いて言えば、「鑽研」の方が多く使われていることが分かる。(もっとも「鑽研」の4回のカウントは、同じ個所の記事が別の史書に載せられているため、実質2回ということではある。)
さて、資治通鑑で「鑽研」が使われている唯一の場面を見てみよう。資治通鑑は、普通の歴史書のように政治・経済だけでなく、文化から庶民生活に至るまで余すところなく記述されていて、まさしく大著という名に恥じない名著である。今回取り上げた記事はそのことがよくわかる部分である。
+++++++++++++++++++++++++++
北魏の陳仲儒が前漢の京房が策定した音階に従って八音を調整したいと願い出た。官僚がいうには「確かに京房が制定した音律は、今その其器は伝来しているが、音律に関する理論を知っている者はほとんどいない。お前は一体誰に学んだというのだ?根拠とする典籍は何だ?」と詰問した。それに対して、陳仲儒が答えていうには「私は幼いころから琴が大好きでした。それに又、司馬彪が編纂した続漢書を読んでそこに書かれている京房の準の理論を読みました。そしてそれを尽く理解しました。それから自分自身で熟考し、長らく研鑽(鑽研)を積み、納得するに至りました。
魏人陳仲儒請依京房立準以調八音。有司詰仲儒:「京房律準、今雖有其器、暁之者鮮。仲儒所受何師、出何典籍?」仲儒対言:「性頗愛琴、又嘗読司馬彪続漢書、見京房準術、成数昞然。遂竭愚思、鑽研甚久、頗有所得。
+++++++++++++++++++++++++++
この部分は、北魏の孝明帝の時代に、陳仲儒が宮廷音楽の音律を整理しなおした、という記事である。上に紹介した部分に継いで、約 1ページにもわたり、それぞれの調で曲の雰囲気どのように異なるのかについて説明している。
ここで感心するのは、司馬光の本文はわずか 1ページ足らずなのに対して、胡三省の注はびっしり5ページも細字で埋め尽くされている。字数もさることながら、引用文献も多いことに驚かされる。私には分からないが、胡三省は引用すべき箇所を正確に理解していたのであろうと思われる。司馬光に負けず劣らず、博学な人だ。
資治通鑑は元の史書の10パーセント程度しか引用していない。つまり、司馬光が重要でないと判断した部分はカットされている。音楽に関するこの部分が収録されていることから考えると、当時の知識人(文人・士大夫)にとって、音楽に関する情報は文化を理解するうえで重要であったことが逆算できる。
(続く。。。)
【365.研鑽・鑽研 】P.4653、AD519年
『研鑽』とは「学問などを深く究めること」。一字づつはそれぞれ「研」は「みがく」、「鑽」は「(きりで)穴をあける」という意味がある。つまり「研鑽」は元来「職人が宝石に穴をあけて、丁寧に磨く」ことを意味した。その物理的な意味から抽象的な意味になった。意味は同じであるものの、漢文の文脈では「研鑽」よりも逆順の「鑽研」の方が多く使われている。中国の辞書には「研鑽」は載っていないが「鑽研」は載っている。辞海(1978年版)には「鑽研」を「謂精究其義也」(その義を精究する也)と説明する。また辞源(1987年版)では「鑽堅研微」の句を見だしとして挙げ、出典は晋書・《虞喜伝》という。、その意味は「研究事理、深入底細」であると説明する。
「研鑽」と「鑽研」を二十四史(+資治通鑑+続資治通鑑)で検索する次の表のようになる。

この表からわかるように、「研鑽」も「鑽研」も中国ではほとんど使われていない単語であるが、強いて言えば、「鑽研」の方が多く使われていることが分かる。(もっとも「鑽研」の4回のカウントは、同じ個所の記事が別の史書に載せられているため、実質2回ということではある。)
さて、資治通鑑で「鑽研」が使われている唯一の場面を見てみよう。資治通鑑は、普通の歴史書のように政治・経済だけでなく、文化から庶民生活に至るまで余すところなく記述されていて、まさしく大著という名に恥じない名著である。今回取り上げた記事はそのことがよくわかる部分である。
+++++++++++++++++++++++++++
北魏の陳仲儒が前漢の京房が策定した音階に従って八音を調整したいと願い出た。官僚がいうには「確かに京房が制定した音律は、今その其器は伝来しているが、音律に関する理論を知っている者はほとんどいない。お前は一体誰に学んだというのだ?根拠とする典籍は何だ?」と詰問した。それに対して、陳仲儒が答えていうには「私は幼いころから琴が大好きでした。それに又、司馬彪が編纂した続漢書を読んでそこに書かれている京房の準の理論を読みました。そしてそれを尽く理解しました。それから自分自身で熟考し、長らく研鑽(鑽研)を積み、納得するに至りました。
魏人陳仲儒請依京房立準以調八音。有司詰仲儒:「京房律準、今雖有其器、暁之者鮮。仲儒所受何師、出何典籍?」仲儒対言:「性頗愛琴、又嘗読司馬彪続漢書、見京房準術、成数昞然。遂竭愚思、鑽研甚久、頗有所得。
+++++++++++++++++++++++++++
この部分は、北魏の孝明帝の時代に、陳仲儒が宮廷音楽の音律を整理しなおした、という記事である。上に紹介した部分に継いで、約 1ページにもわたり、それぞれの調で曲の雰囲気どのように異なるのかについて説明している。
ここで感心するのは、司馬光の本文はわずか 1ページ足らずなのに対して、胡三省の注はびっしり5ページも細字で埋め尽くされている。字数もさることながら、引用文献も多いことに驚かされる。私には分からないが、胡三省は引用すべき箇所を正確に理解していたのであろうと思われる。司馬光に負けず劣らず、博学な人だ。
資治通鑑は元の史書の10パーセント程度しか引用していない。つまり、司馬光が重要でないと判断した部分はカットされている。音楽に関するこの部分が収録されていることから考えると、当時の知識人(文人・士大夫)にとって、音楽に関する情報は文化を理解するうえで重要であったことが逆算できる。
(続く。。。)