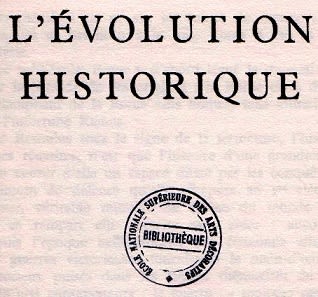(前回)
【7】庶民の食事(1-1、P.243)
現在では、フランス料理は中華料理と並んで世界の2大料理であることに誰も異論はないであろう。しかし、歴史的に見ると、フランス料理が自慢できるようになったのはつい最近、つまりフランス革命(1789年)以降のこと、である。フランス革命で王政が倒されたので宮廷の料理人たちも宮廷から街中へ放り出された。しかたなく、銘々が料理店を開店したので、フランス料理なるものが一般化したという。そもそも、フランス料理の濫觴は1533年、イタリアのカトリーヌ・ド・メディシスがアンリ2世に輿入れした時に、フランスの不味い料理など我慢できないと、フィレンツェから料理人を連れてきた時にある。フランス王室では、材料や調理法に贅と工夫をこらしてた。その結果、当時の料理本に載せられているように種々の洗練された料理が作られたがはたして一般庶民はどのような食事をしていたのであろうか?
+++++++++++++++++++++++++++
【要旨】ヨーロッパでは、15世紀、16世紀以前においては本格的に贅沢な食事(洗練された食事)などなかった。この点においてヨーロッパは中東や中国などより遅れていた。フランスの地方料理の500年にわたる伝統をほめる人がいるが、はたしてどれほどの人がその恩恵に浴していたのだろうか?
+++++++++++++++++++++++++++
ここに見るように、ブローデルの指摘は、現在みられるフランス料理の伝統は確かに否定できないものの、それは社会の極一部の上流特権階級の伝統でしかなかったということだ。ブローデルの基本理念は社会の一部にしか見られない特殊事象を麗々しく記述することではなく、社会全体を通貫している大きな流れを記述することである。それ故、フランス料理についても、この点を強調する。
+++++++++++++++++++++++++++
[農民は]粟かとうもろこし( le paysan se nourrit de millet ou de maïs)を食べて、小麦を売っていた。週に一回塩漬けの豚肉を食べるだけで、家禽・卵・小山羊・仔牛・仔羊……などは市へ持ってゆくのであった。… 農民の、すなわち人口中の絶対多数の食品は、特権人士向きの料理書にある食品とはなんの関わりもなかった。
+++++++++++++++++++++++++++

この部分を読んで思い出したことがある。以前、京都大学で留学生向けの英語の授業『日本の工芸技術と社会』(Craftsmanship in Japanese Society)のテストでオランダの女子学生が料理について次のように記述したことで、日本の料理文化との差を思い知らされた。
+++++++++++++++++++++++++++
例えば、今回の回答の一つにオランダの学生が料理について書いていた文章の中に『日本では、料理が一つの文化となっている。しかし、オランダでは料理が文化だ、というと皆、笑いこけてしまうに違いない。なぜならオランダでは料理というのは、単にジャガイモを腹いっぱいに食べて、栄養をとるもの、というのが伝統的な理解だ。』という趣旨の文章があった。オランダでは、ありふれた料理でも色や形の異なった皿にいれ、盛り付けを工夫して見た目を考えて出すという我々日本人なら当たり前の感覚が存在していなかったのである。
+++++++++++++++++++++++++++
オランダだけでなく、ゲルマン系の国々の料理に対する国際評価はラテン系に比べて高くない。私の実感として、これらの国々の料理は、掛け値なしに質素で、栄養が偏っているとの印象がある。この原因は寒冷な気候のために洗練された料理文化を構築するという条件に恵まれなかったからではないかと思う。南欧のように種々の植物が豊富に取れる条件がなく、とにかく生き延びることがやっと、のような低い生産性では、食べられるだけでも幸福だと思ったことであろう。この点からすれば、中国南部から東南アジア・インドにかけての植生の豊かさは、うらやましいほどの多彩な食文化を形成した。
【参照ブログ】
沂風詠録:(第126回目)『英語講義:日本の工芸技術と社会・テスト』
(続く。。。)
【7】庶民の食事(1-1、P.243)
現在では、フランス料理は中華料理と並んで世界の2大料理であることに誰も異論はないであろう。しかし、歴史的に見ると、フランス料理が自慢できるようになったのはつい最近、つまりフランス革命(1789年)以降のこと、である。フランス革命で王政が倒されたので宮廷の料理人たちも宮廷から街中へ放り出された。しかたなく、銘々が料理店を開店したので、フランス料理なるものが一般化したという。そもそも、フランス料理の濫觴は1533年、イタリアのカトリーヌ・ド・メディシスがアンリ2世に輿入れした時に、フランスの不味い料理など我慢できないと、フィレンツェから料理人を連れてきた時にある。フランス王室では、材料や調理法に贅と工夫をこらしてた。その結果、当時の料理本に載せられているように種々の洗練された料理が作られたがはたして一般庶民はどのような食事をしていたのであろうか?
+++++++++++++++++++++++++++
【要旨】ヨーロッパでは、15世紀、16世紀以前においては本格的に贅沢な食事(洗練された食事)などなかった。この点においてヨーロッパは中東や中国などより遅れていた。フランスの地方料理の500年にわたる伝統をほめる人がいるが、はたしてどれほどの人がその恩恵に浴していたのだろうか?
+++++++++++++++++++++++++++
ここに見るように、ブローデルの指摘は、現在みられるフランス料理の伝統は確かに否定できないものの、それは社会の極一部の上流特権階級の伝統でしかなかったということだ。ブローデルの基本理念は社会の一部にしか見られない特殊事象を麗々しく記述することではなく、社会全体を通貫している大きな流れを記述することである。それ故、フランス料理についても、この点を強調する。
+++++++++++++++++++++++++++
[農民は]粟かとうもろこし( le paysan se nourrit de millet ou de maïs)を食べて、小麦を売っていた。週に一回塩漬けの豚肉を食べるだけで、家禽・卵・小山羊・仔牛・仔羊……などは市へ持ってゆくのであった。… 農民の、すなわち人口中の絶対多数の食品は、特権人士向きの料理書にある食品とはなんの関わりもなかった。
+++++++++++++++++++++++++++

この部分を読んで思い出したことがある。以前、京都大学で留学生向けの英語の授業『日本の工芸技術と社会』(Craftsmanship in Japanese Society)のテストでオランダの女子学生が料理について次のように記述したことで、日本の料理文化との差を思い知らされた。
+++++++++++++++++++++++++++
例えば、今回の回答の一つにオランダの学生が料理について書いていた文章の中に『日本では、料理が一つの文化となっている。しかし、オランダでは料理が文化だ、というと皆、笑いこけてしまうに違いない。なぜならオランダでは料理というのは、単にジャガイモを腹いっぱいに食べて、栄養をとるもの、というのが伝統的な理解だ。』という趣旨の文章があった。オランダでは、ありふれた料理でも色や形の異なった皿にいれ、盛り付けを工夫して見た目を考えて出すという我々日本人なら当たり前の感覚が存在していなかったのである。
+++++++++++++++++++++++++++
オランダだけでなく、ゲルマン系の国々の料理に対する国際評価はラテン系に比べて高くない。私の実感として、これらの国々の料理は、掛け値なしに質素で、栄養が偏っているとの印象がある。この原因は寒冷な気候のために洗練された料理文化を構築するという条件に恵まれなかったからではないかと思う。南欧のように種々の植物が豊富に取れる条件がなく、とにかく生き延びることがやっと、のような低い生産性では、食べられるだけでも幸福だと思ったことであろう。この点からすれば、中国南部から東南アジア・インドにかけての植生の豊かさは、うらやましいほどの多彩な食文化を形成した。
【参照ブログ】
沂風詠録:(第126回目)『英語講義:日本の工芸技術と社会・テスト』
(続く。。。)