山田正亮の絵画 -<静物>から<Work>…そして<Color>へ
2005年6月18日(土)~8月14日(日)
府中市美術館
山田正亮が1950年代に記憶の力だけによって静物を描いたように、私も記憶の中に残るものを手がかりにこの文章を書いてみようと思う。
まず、この展覧会では、山田の初期の作品<Still Life>が多く展示されている。通常なら、彼の代表作である<Work>シリーズを中心とするところだ。だが、この展覧会では、初期の<Still Life>シリーズに多くを割いている。これら静物を描いた作品を見て感じることがある。それは、ものが存在することとは、その印象を把握することなのではないか、ということだ。私たちは通常、ものがそこにある、と認識するのにどのように記憶しているだろうか。例えば、コップがテーブルにある。ただ、コップがテーブルにあるというだけで、記憶できるだろうか。そのコップの色、かたち、見る位置、光の加減による影、周りにあるもの(本、鉛筆、携帯電話、パソコン、テレビのリモコンetcノ)などのさまざまな空間、物質的存在感を一度に見てそこにコップがあると認識しているはずだ。つまり、それらコップ自身とコップのまわりにあるものたちが作り出す空気、空間、雰囲気を記憶に留めているからこそ、そこにコップがあると認識しているのではないだろうか。それら、コップの周りのものたちがなければ、コップをコップと認識し、記憶できないだろう。
突然だが、小林古径や村上華岳の静物画を見たとき、そこに牡丹や柿や椿が「存在」していると感じた。植物だけでなく、小鉢に入った果物などの静物も同様である。あまり日本画の作品について知識があるわけではないが、これらの静物画では背景が描かれていない。コップがコップとして認識されるためのまわりのものたちが描かれていないのだ。だが、そこに描かれているものは、確かに「存在」している。この違いはなんだろうか。洋画と日本画の素材、技法による違いだろうか。それもあるだろうが、それだけではない気がする。小林や村上は、描く対象以外のもの(背景など)を描かないことによって、そのもののもつ空間の広がりを表現しようとした。対して、山田は、ものとものとの関係を描くことによってものを描こうとしたのだ。つまり、小林や村上の絵画は描かないことによってまわりにものが存在しているが、描かれている対象のものしか見えないという状況を作り出している。山田の絵画は、ものとそれが置かれている空間、関係を描くことによって、ものの「存在」を描こうとした。
だが、山田の絵は、小林古径の絵のように写実的な描写による絵ではないではないか。そう、山田はものとものとの関係を描くことによって、絵画が「存在」することに向かうのである。断っておくが、小林古径の絵がただの表面的な写実絵画なのではない。小林古径もまた、絵画が「絵画」として存在する絶対的地点に至ろうとした画家である。ただ、2人の画家が、乗り越えるべき対象、地点が違っただけである。極論するなら、2人の作品からは、同じ香りさえ漂っているといってもいい。話を戻そう。山田の絵画は、静物を描きつづけていく内に、線と色彩、造型が溶け合い、抽象度を増していく。線や面による構造体へと徐々にそのかたちを変えていくのだ。ゆるやかにトーンが変わっていくように、山田の絵画に構造からリズムが生まれてくる。具象から抽象への進展は息を飲む。かたちを持っていたものたち、ものとものとの関係から残っていくのは色彩だった。色彩はリズムを生む。リズム&カラー。リズム&ベース。色彩のストライブという構造を獲得した<Work>シリーズ、その果てに生まれるミニマルリズム<Color>シリーズ。徐々に構造を振りほどきながら、色彩を露にしていく。その美しさに絵画の「存在」を思う。
テーブルにコップがある。その構造、色彩、光と影、空気…。ものの印象をつかむことによって、対象を描くこと。ものを存在するように描く、ということは写実的に描くことだけではない。絵画を描くということは、具象的に描くことだけではない。山田正亮の絵画は、静止している<静物>から出発して、リズムを持った<Color>へと進展した。その流れは現実との対応関係から成り立つ絵画から、自立した絵画という<存在>への道のりだった。
<絵画>が<静物>になる、そんな印象を持った。
2005年6月18日(土)~8月14日(日)
府中市美術館
山田正亮が1950年代に記憶の力だけによって静物を描いたように、私も記憶の中に残るものを手がかりにこの文章を書いてみようと思う。
まず、この展覧会では、山田の初期の作品<Still Life>が多く展示されている。通常なら、彼の代表作である<Work>シリーズを中心とするところだ。だが、この展覧会では、初期の<Still Life>シリーズに多くを割いている。これら静物を描いた作品を見て感じることがある。それは、ものが存在することとは、その印象を把握することなのではないか、ということだ。私たちは通常、ものがそこにある、と認識するのにどのように記憶しているだろうか。例えば、コップがテーブルにある。ただ、コップがテーブルにあるというだけで、記憶できるだろうか。そのコップの色、かたち、見る位置、光の加減による影、周りにあるもの(本、鉛筆、携帯電話、パソコン、テレビのリモコンetcノ)などのさまざまな空間、物質的存在感を一度に見てそこにコップがあると認識しているはずだ。つまり、それらコップ自身とコップのまわりにあるものたちが作り出す空気、空間、雰囲気を記憶に留めているからこそ、そこにコップがあると認識しているのではないだろうか。それら、コップの周りのものたちがなければ、コップをコップと認識し、記憶できないだろう。
突然だが、小林古径や村上華岳の静物画を見たとき、そこに牡丹や柿や椿が「存在」していると感じた。植物だけでなく、小鉢に入った果物などの静物も同様である。あまり日本画の作品について知識があるわけではないが、これらの静物画では背景が描かれていない。コップがコップとして認識されるためのまわりのものたちが描かれていないのだ。だが、そこに描かれているものは、確かに「存在」している。この違いはなんだろうか。洋画と日本画の素材、技法による違いだろうか。それもあるだろうが、それだけではない気がする。小林や村上は、描く対象以外のもの(背景など)を描かないことによって、そのもののもつ空間の広がりを表現しようとした。対して、山田は、ものとものとの関係を描くことによってものを描こうとしたのだ。つまり、小林や村上の絵画は描かないことによってまわりにものが存在しているが、描かれている対象のものしか見えないという状況を作り出している。山田の絵画は、ものとそれが置かれている空間、関係を描くことによって、ものの「存在」を描こうとした。
だが、山田の絵は、小林古径の絵のように写実的な描写による絵ではないではないか。そう、山田はものとものとの関係を描くことによって、絵画が「存在」することに向かうのである。断っておくが、小林古径の絵がただの表面的な写実絵画なのではない。小林古径もまた、絵画が「絵画」として存在する絶対的地点に至ろうとした画家である。ただ、2人の画家が、乗り越えるべき対象、地点が違っただけである。極論するなら、2人の作品からは、同じ香りさえ漂っているといってもいい。話を戻そう。山田の絵画は、静物を描きつづけていく内に、線と色彩、造型が溶け合い、抽象度を増していく。線や面による構造体へと徐々にそのかたちを変えていくのだ。ゆるやかにトーンが変わっていくように、山田の絵画に構造からリズムが生まれてくる。具象から抽象への進展は息を飲む。かたちを持っていたものたち、ものとものとの関係から残っていくのは色彩だった。色彩はリズムを生む。リズム&カラー。リズム&ベース。色彩のストライブという構造を獲得した<Work>シリーズ、その果てに生まれるミニマルリズム<Color>シリーズ。徐々に構造を振りほどきながら、色彩を露にしていく。その美しさに絵画の「存在」を思う。
テーブルにコップがある。その構造、色彩、光と影、空気…。ものの印象をつかむことによって、対象を描くこと。ものを存在するように描く、ということは写実的に描くことだけではない。絵画を描くということは、具象的に描くことだけではない。山田正亮の絵画は、静止している<静物>から出発して、リズムを持った<Color>へと進展した。その流れは現実との対応関係から成り立つ絵画から、自立した絵画という<存在>への道のりだった。
<絵画>が<静物>になる、そんな印象を持った。











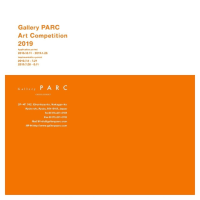

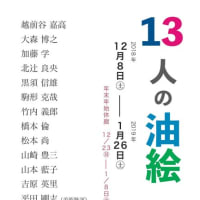




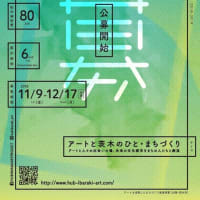

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます