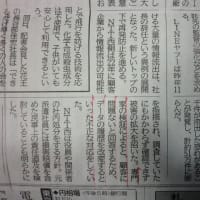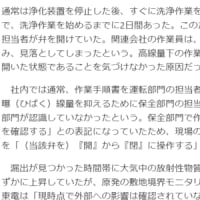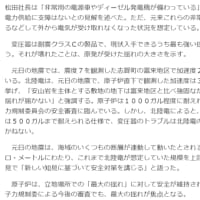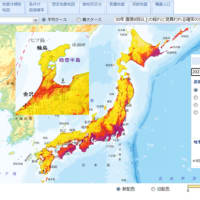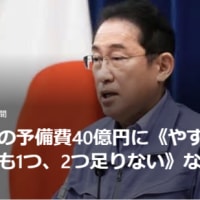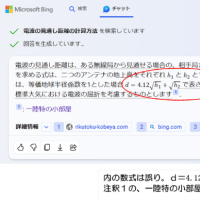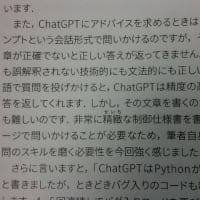例えば、強制空冷の発電機を運転した際に、引いてもドアが空き難い、ドア下から空気が勢いよく吸い込まれている、やたらと室内に塵埃が目立つ等々は、吸排気のフローに問題があるから、、、当然であるが、必要な風量(㎥)は発電機の許容温度上昇から決まる。
、、、で、イメージし易くする為に窒息?状態の実例から;水冷型の40kVA、、、自動車様のラジエータ方式冷却の例。
建屋のコンクリート壁の開口部の面積は必要風量に対応していたが、開口部には所謂ところのフードを付ける。通常そのフードの開口部には、ガラリや防犯上と虫除けも兼ねたパンチングメタルなどを取り付ける、、、ここで、最初の空気抵抗が生じる(フードの形状も影響していた)。
次に、機械室であるから塵埃対策としての防塵フィルターを設ける、、、ここで、次の空気抵抗が生じる。ここまでで、開口部の面積は、実質的に10%程度に小さくなっていたのだ、、、従って、空気の時間当たりの通過量を大きくするために、結果として風速が上がることになる、、、偶々、この施設の吸気は室内開放型(空気圧を平衡させる空気チャンバーの説明は省く)なのでダクトは無いが、ダクトがあればさらに空気抵抗が増えることになる。
おまけに言えば、寒冷地での水冷型は水の管理も重要となるし、小型の発電装置には空冷型もあるが発生する騒音は大きくなる、、、
後発で発電機を設置する時には、業者から「あーそうですか、それでは〇△kVAの発電機、、、建屋工事を除いての発電機回りは**円です」などで、発注とはならない様に、しっかりとした打ち合わせをすることをお勧めする、、、
特に、自家用発電設備として届出が必要な大きさの発電機を設置する時には、適用される法律面や保守性も含めてくれぐれも慎重に、、、
今日は、ここまで晴れたり曇ったりで、風ややあり、、、福寿草の芽の頂部が黄色く色付いていた、、、
、、、で、イメージし易くする為に窒息?状態の実例から;水冷型の40kVA、、、自動車様のラジエータ方式冷却の例。
建屋のコンクリート壁の開口部の面積は必要風量に対応していたが、開口部には所謂ところのフードを付ける。通常そのフードの開口部には、ガラリや防犯上と虫除けも兼ねたパンチングメタルなどを取り付ける、、、ここで、最初の空気抵抗が生じる(フードの形状も影響していた)。
次に、機械室であるから塵埃対策としての防塵フィルターを設ける、、、ここで、次の空気抵抗が生じる。ここまでで、開口部の面積は、実質的に10%程度に小さくなっていたのだ、、、従って、空気の時間当たりの通過量を大きくするために、結果として風速が上がることになる、、、偶々、この施設の吸気は室内開放型(空気圧を平衡させる空気チャンバーの説明は省く)なのでダクトは無いが、ダクトがあればさらに空気抵抗が増えることになる。
おまけに言えば、寒冷地での水冷型は水の管理も重要となるし、小型の発電装置には空冷型もあるが発生する騒音は大きくなる、、、
後発で発電機を設置する時には、業者から「あーそうですか、それでは〇△kVAの発電機、、、建屋工事を除いての発電機回りは**円です」などで、発注とはならない様に、しっかりとした打ち合わせをすることをお勧めする、、、
特に、自家用発電設備として届出が必要な大きさの発電機を設置する時には、適用される法律面や保守性も含めてくれぐれも慎重に、、、
今日は、ここまで晴れたり曇ったりで、風ややあり、、、福寿草の芽の頂部が黄色く色付いていた、、、