スウェーデン中央銀行がさらなる利下げを行った。歴史的に見ても最低水準だった1%から0.5%に下げ、記録をさらに更新することになった。経済の悪化が予想を大きく上回っていたことは間違いない。

しかし一方で、スウェーデン経済は不況に突入する直前の昨年9月の段階で4.75%という高金利であったおかげで、わずか7ヶ月ほどの間に合計4.25%ポイント減という大規模な金融政策を講じることができた。これは、ある意味「ショック療法」として大きな効果を持っているのではないか、と私は思う。スウェーデンの家計の半分が住宅ローンを持っているというが、そのうちの平均的な家庭の場合、これまでの利下げのおかげで月々のローン返済額が数万円も少なくなったという。これが消費につながる可能性は大きい。また、利下げが住宅投資や企業の設備投資に与える効果も一定程度あるだろう。

記者会見で利下げを発表する中央銀行総裁
――――――――――
これまでこのブログには、スウェーデン経済に関する様々な懸念を書いてきた。細かい問題はたくさんある。しかし、全体としてみた場合、実は私はそこまで悲観的ではない。
4月に入ってから株価が上昇し始めている。このまま持続的に上昇していくかというと、そこまで楽観的にはなれないが、少なくとも今年の終わりか来年の頭までにはスウェーデンの経済は上向きに転じているのではないかと予想する。
今のスウェーデン経済にとってプラスの要素は、クローナ安だ。自国の通貨が安くなったおかげで、今年の夏休みは多くのスウェーデン人が国外旅行を諦め、国内でバカンスを過ごす傾向にあるという調査結果がでている。国内のキャンピング場やサマーハウスなどは、既に予約が殺到しているとか。クローナが安いおかげで、ドイツなどの大陸ヨーロッパやユーロ圏をはじめとする国外からの旅行客が、今年はスウェーデンに例年以上に押し寄せてくるだろうと見られている。
スウェーデンの製造業も今でこそ真っ暗闇だが、世界的な景気がひとたび持ち直せば、輸出産業はクローナ安のおかげで大いに潤うだろう。状況は1992-93年頃のスウェーデンに似ている。バブル崩壊に苦しんでいた当時のスウェーデンは固定相場を維持していたが、通貨攻撃を受けて変動相場制に移行した結果、クローナは1年ほどのうちに主要通貨に対して4割も下落した。そして、ちょうどそれと時を同じくして、輸出高が急激に上向きになっていき、これがその後の景気回復と経済成長への引き金になったと言える。
もう一つは失業者が置かれた状況。現在の政権になってから、確かに失業保険の給付水準の抑制や保険料の大幅な引き上げなどの変化があった。その結果、失業保険から離脱する人も増えたことも確かだ。
しかし、日本で3月に「スウェーデンの経済と雇用情勢」について講演させてもらった時にも説明したように、日本とスウェーデンの失業者が置かれた状況を比較すると、スウェーデンの社会保障がいかに充実しているかが良く分かる。現在の厳しい経済状況は、世界中どこの先進国も似たようなものだろう。この苦境から一国だけが逃れる術はない。しかし、スウェーデンにはこの厳しい「冬」を乗り切る体勢が比較的整っているといえるだろう。失業者や苦境に陥った人々を社会全体で一定期間、保護し、来るべき「春」に備える。
保護する手段としては、比較的手厚い失業保険給付に加えて、最近書いた積極的労働市場政策や、家賃の支払いが困難な家庭に支払われる家賃支払い補助金、そして最後の頼みの綱としての生活保護などだ。また、授業料が無料であり生活費の支給もある大学教育や成人高校なども、失業者(特に若者の失業者)を吸収する一種のバッファーとなっている。ちょうど今、今年の秋学期の大学課程の応募の締め切りが近づいているが、今年は応募者が急増している。
だから、今年をどうにか乗り切れば、スウェーデンの将来は明るいだろう。GDPも来年はプラスに転じるだろう。輸出産業も今年末あたりから、大きく業績を伸ばしてくれるだろう(ただし、雇用が回復するには2、3年はかかるかもしれない)。スウェーデンの新聞各紙は、毎日のように暗いニュースを大きく書いてはいるが、その行間に実は記者や解説者のオプティミズムを感じるのは私だけだろうか?
――――――――――

中央銀行総裁Stefan Ingves(ステファン・イングヴェス)の顔を見るたびに、何かに似ているといつも思うのだけど・・・

もしかして、これかな?

しかし一方で、スウェーデン経済は不況に突入する直前の昨年9月の段階で4.75%という高金利であったおかげで、わずか7ヶ月ほどの間に合計4.25%ポイント減という大規模な金融政策を講じることができた。これは、ある意味「ショック療法」として大きな効果を持っているのではないか、と私は思う。スウェーデンの家計の半分が住宅ローンを持っているというが、そのうちの平均的な家庭の場合、これまでの利下げのおかげで月々のローン返済額が数万円も少なくなったという。これが消費につながる可能性は大きい。また、利下げが住宅投資や企業の設備投資に与える効果も一定程度あるだろう。

記者会見で利下げを発表する中央銀行総裁
これまでこのブログには、スウェーデン経済に関する様々な懸念を書いてきた。細かい問題はたくさんある。しかし、全体としてみた場合、実は私はそこまで悲観的ではない。
4月に入ってから株価が上昇し始めている。このまま持続的に上昇していくかというと、そこまで楽観的にはなれないが、少なくとも今年の終わりか来年の頭までにはスウェーデンの経済は上向きに転じているのではないかと予想する。
今のスウェーデン経済にとってプラスの要素は、クローナ安だ。自国の通貨が安くなったおかげで、今年の夏休みは多くのスウェーデン人が国外旅行を諦め、国内でバカンスを過ごす傾向にあるという調査結果がでている。国内のキャンピング場やサマーハウスなどは、既に予約が殺到しているとか。クローナが安いおかげで、ドイツなどの大陸ヨーロッパやユーロ圏をはじめとする国外からの旅行客が、今年はスウェーデンに例年以上に押し寄せてくるだろうと見られている。
スウェーデンの製造業も今でこそ真っ暗闇だが、世界的な景気がひとたび持ち直せば、輸出産業はクローナ安のおかげで大いに潤うだろう。状況は1992-93年頃のスウェーデンに似ている。バブル崩壊に苦しんでいた当時のスウェーデンは固定相場を維持していたが、通貨攻撃を受けて変動相場制に移行した結果、クローナは1年ほどのうちに主要通貨に対して4割も下落した。そして、ちょうどそれと時を同じくして、輸出高が急激に上向きになっていき、これがその後の景気回復と経済成長への引き金になったと言える。
もう一つは失業者が置かれた状況。現在の政権になってから、確かに失業保険の給付水準の抑制や保険料の大幅な引き上げなどの変化があった。その結果、失業保険から離脱する人も増えたことも確かだ。
しかし、日本で3月に「スウェーデンの経済と雇用情勢」について講演させてもらった時にも説明したように、日本とスウェーデンの失業者が置かれた状況を比較すると、スウェーデンの社会保障がいかに充実しているかが良く分かる。現在の厳しい経済状況は、世界中どこの先進国も似たようなものだろう。この苦境から一国だけが逃れる術はない。しかし、スウェーデンにはこの厳しい「冬」を乗り切る体勢が比較的整っているといえるだろう。失業者や苦境に陥った人々を社会全体で一定期間、保護し、来るべき「春」に備える。
保護する手段としては、比較的手厚い失業保険給付に加えて、最近書いた積極的労働市場政策や、家賃の支払いが困難な家庭に支払われる家賃支払い補助金、そして最後の頼みの綱としての生活保護などだ。また、授業料が無料であり生活費の支給もある大学教育や成人高校なども、失業者(特に若者の失業者)を吸収する一種のバッファーとなっている。ちょうど今、今年の秋学期の大学課程の応募の締め切りが近づいているが、今年は応募者が急増している。
だから、今年をどうにか乗り切れば、スウェーデンの将来は明るいだろう。GDPも来年はプラスに転じるだろう。輸出産業も今年末あたりから、大きく業績を伸ばしてくれるだろう(ただし、雇用が回復するには2、3年はかかるかもしれない)。スウェーデンの新聞各紙は、毎日のように暗いニュースを大きく書いてはいるが、その行間に実は記者や解説者のオプティミズムを感じるのは私だけだろうか?

中央銀行総裁Stefan Ingves(ステファン・イングヴェス)の顔を見るたびに、何かに似ているといつも思うのだけど・・・

もしかして、これかな?










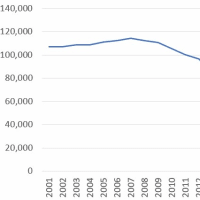
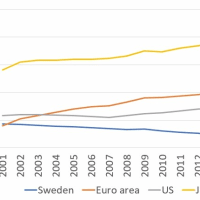
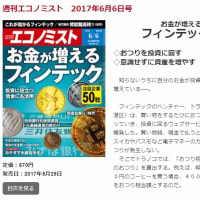
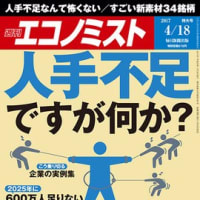






あ、こういうことを考える私は、もしかして共産主義者かな。
私自身も、不況のおかげで人々が無駄なものを買わず、無駄な生産活動が減ること自体はいいと思うんですよ。環境問題・温暖化問題は経済問題と同じくらい、私にとっての関心ごとであります。
ただし、スウェーデンの社会保障を支えているのは、潤沢な税収であり、それをi sin tur支えているのは、国際市場で競争力をつけている、生産性の高い輸出産業であることを考えると、大きな矛盾を正直感じるところです。
無駄な大量消費をなくし、人々が自分に本当に必要な、しかも質にこだわった物だけを消費するようになった場合、経済が全体としてどうなるのか? 税収は?輸出入は?雇用は?
そんなシミュレーションにも近いうちに必ず手をつけて、そのような可能性を探ってみたいものです。
消費しないと経済が発達しないなら、人間の生活に必須な産業(食料とかエネルギー)から重点的に消費を増やしていけば、と思っても限度があるし、使いようによっては長持ちする衣服や家電、車にしても消費があるから技術革新やすぐれたデザインができて、さらなる消費心をくすぐる、と。なんでもかゆいところに手がとどくサービスが得意な日本にいると本当にこんなものが必要なのか?と思うものが多すぎるのも事実。購買よりもっとサービスでお金がまわる仕組みをつくるにはどうしたらよいのか?はたしてそういうことが可能なのか?もんもんと考える日々です。シュミレーション楽しみにしています!